お金が足りない、貯金なしで子育てするための節約方法
子育てには非常にお金がかかるという漠然としたイメージはあるものの、生活費が優先になってしまいますので、子供のための貯金というのをしにくいもので。
しかし子供が大きくなるにつれ、まとまった大金が必要になるケースもあるため、貯金がないと苦しくなることもあります。
上手に貯金ができる方法を紹介します。
「給料日前でどうしてもお金がない」という場合、消費者金融カードローンを一時的に利用する人も多くいます。
5万円をカードローンの最大金利年18.0%で30日間借入した場合をシミュレーションすると、利息は750円未満です。また、無利息サービスを利用すれば一定期間利息0円なので、ちょっと借りてすぐに完済すれば無駄な出費も防げます(SMBCモビットは無利息サービスなし)。
まずは以下から公式サイトをチェックしてみてください。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
- 1 世間の子育て世代の貯金の実態とは
- 2 子供の教育にかかるお金は1,000万円以上?貯金ゼロでは無理?
- 3 育児のお金がなくて不安!みんなどうしてる?
- 4 1ヶ月の赤ちゃんに必要なお金は?
- 5 出産前後は出産手当金で乗り切る
- 6 出産育児一時金で出産費用を賄う
- 7 出産後は育児休業給付と児童手当
- 8 今スグできる!少しでも貯金するための4つの鉄則
- 9 子育てに必要なお金をラクラク貯める3つの方法
- 10 子育てのお金を捻出する方法
- 11 子育て世代がもらえる手当についても理解しておこう!
- 12 子供の将来のために必要な貯金額
- 13 育児ストレス?お金がないストレス?
- 14 育児ノイローゼになる前に!ストレス発散を
- 15 離婚してお金が足りないならどうする?
- 16 貯金ゼロの子育て・・・まとめ
世間の子育て世代の貯金の実態とは
よく雑誌などのメディアでも、「子育て世代の平均貯蓄額は○○万円」と特集されています。
しかしその金額は飽くまで平均であって、必ずしも全員同じ金額を貯金できている訳ではありません。
家族構成も収支バランスも異なるのですから、1,000万円貯金できている家庭もあれば、貯金ゼロの家庭だって当たり前に存在します。
しかし子育てには思った以上にお金がかかるのは確かです。実際どの程度の金額が必要になってくるのか見てみましょう。
子育て世代の4割は、生活が苦しい!と訴えている
子供のための貯金をしたほうがいいと分かっていても、世の中には貯金できないという家庭が実は多いものではないでしょうか。
貯金ができない要因は様々ですが、収入に対し支出が大きいというポイントがあります。
総務省統計局による「平成26年全国消費実態調査」を見てみると、20万円以上の負債をかかえている家庭は全国平均で41.9%と記されています。
つまり10人中4人は20万円以上の借入を行い、返済をしているのです。
返済日は毎月固定されていますから、やはり給与もその支払いに充てなくてはなりません。
そのためなかなか貯金がすすまないという家庭も、珍しくはありません。
◆参考:総務省統計局
平均貯蓄額を信用してはダメ!実際の貯蓄額は?
厚生労働省が子育て世代の平均貯蓄額を発表しています。
そのグラフによると、まず子育て世代で貯蓄している世帯は82%で、約8割の家庭が金額問わず貯蓄を行っているという内容でした。
また、全世帯併せての平均貯蓄額は、1,221万円となっています。
しかし、この数字を見てびっくりする家庭が、ほとんどではないでしょうか。
実はこの平均貯蓄額というものは余り参考になりません。
それは、貯蓄が50万円以下の家庭もあれば、3,000万円以上の貯蓄がある家庭もあるからです。
それらを平均した結果が1,221万円という高額な貯蓄額となってでてきているため、余り参考にしないほうがいいでしょう。
このようになると気になってくるのが、実際いくら貯めている家庭が多いのかという点です。
同じ厚生労働省が発表した数字によると、50万円未満は5.3%、最も多かったのが500万円~700万円の10.9%です。
◆参照:平成28年国民生活基礎調査
上を見ればキリはありませんが、貯金額が50万円未満の家庭だって普通に存在するのです。
子供の教育にかかるお金は1,000万円以上?貯金ゼロでは無理?
貯金の有無を問わず、子供はどんどん大きく成長します。成長すれば手は離れますが、その分金額が大きくなってくるものです。
ある程度「いくらお金が必要になる」と事前に知っておくのと、そうではないのとでは大きく気持ちも異なってきます。
手初めに、子育てにはどれくらいのお金がかかるのかを知っておきましょう。
小学校から大学までかかるお金は最低でも2,000万円
AIU保険「AIUの現代子育て経済考2005」によれば、出産から大学卒業までの22年間における「養育費」は、以下の表のとおり約1,640万円となっています。
「養育」とはその名のとおり養い育てていくのみのお金ですから、これに学費などの「教育費」は含まれていません。
| 費用内容 | 金額 |
|---|---|
| 出産・育児費用 | 約91万円 |
| 食 費 | 約91万円 |
| 衣料費 | 約141万円 |
| 保健医療・理美容費 | 約193万円 |
| おこづかい | 約451万円 |
| 子供の私的所有物 | 約93万円 |
| 合 計 | 約1,640万円 |
子供が自立できるまでには平均1,640万円が必要になってきます。
| 項目 | 進学先 | |
|---|---|---|
| 国立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 63万円 | 149万円 |
| 小学校 | 192万円 | 921万円 |
| 中学校 | 145万円 | 402万円 |
| 高校 | 123万円 | 297万円 |
| 大学 | 国立:269万円 公立:273万円 | 528万円 |
| 合計 | 大学が国立の場合:792万円 大学が公立の場合:796万円 | 2,297万円 |
養育費にプラスして必要となるのが、学費や塾代などの「教育費」です。
公立高校であれば平均123万円、私立高校は平均297万円が必要だと言われています。
高校卒業後、大学進学先が私立だとなおのことです。
ひとり暮らしをするのであれば、敷金礼金や引っ越し費用、新居での家具家電もそろえなくてはいけません。
単純計算をしても大学進学までとなれば最低でも2,000万円は、出ていくものだと認識しておくといいでしょう。
子供に奨学金を借りさせるのも悩みが…
義務教育の間はまだ、学費の支払金額は大きいものではありません。
しかし問題は高校以上です。義務教育から外れますので、今までとは桁違いな金額が必要になってきます。
子供が高校生以上で、貯金がゼロという家庭の人は、奨学資金制度の利用を検討する家庭もあるでしょう。
奨学資金制度は、基本的に在学中であれば返済義務がありません。
返済は、高校若しくは大学を卒業した後ですが、返済が厳しいようであれば子供に返済を任せるという方法をとることも可能です。
ただ、奨学金は、借金であるということを忘れないようにしてください。
近年は、奨学金の返済ができなくて、自己破産をしてしまう若者もいますので、奨学資金制度を利用する場合は、必ず子供に奨学金を受けることのデメリットを話しておくことが必要です。
返済をどちらがしていくのか、など具体的に話をしておくとより安心でしょう。
なお、有名な奨学資金制度には、「日本学生支援機構」が実施している奨学資金制度がありますが、その他にも各都道府県や大学独自の奨学資金制度があります。
特に、私立の大学では、奨学資金制度が充実している場所も多くあるので、事前に相談だけでもしておくことをおすすめします。
育児のお金がなくて不安!みんなどうしてる?
育児のお金について不安を抱えているのは、決して少数の人だけではありません。
若いときに子供を産むと、「こんな少ない収入で本当に育てられるのか?」と不安になることもあるでしょう。
反対に、収入に余裕ができてから子供を産むと、「この子が学校を卒業するまで元気に働けるのだろうか?」「子育てしながら老後資金を貯められるのか?」という不安が生じます。
子育てはお金がかかって当然
例えば子供が1人生まれると年間18万円(出生時~3歳未満)の児童手当は受け取れますが、育児休暇を取得するのなら収入は減りますし、育児関連の支出は増えますので、年間トータルではかなりのマイナスになりそうです。
保険や外食費、親自身の活動費(スポーツクラブの会費や友人との飲み会費用、趣味に費やすお金等)などを削減する必要に迫られることもあるでしょう。
子供を産み育てるにあたって、どの程度の節約が必要になるのかを知るために、まずは産休取得時の収入と出産補助金、児童手当の手続き方法について紹介します。
1ヶ月の赤ちゃんに必要なお金は?
まず最初に、赤ちゃんにかかる1ヶ月の費用について、いくつかの項目に分けて見ていく事にしましょう。
食費
授乳を全てミルクでまかなった場合には、おおよそ1ヶ月のミルク代は1万円前後と考えておけばいいでしょう。
また、ミルクで育てる場合、哺乳瓶・電動ケトル・殺菌用の器具など、付属用品の購入も必要です。
ただ、これらの商品については最初に買っておくだけなので、初期費用として1万円前後用意しておけば大丈夫です。
衣類・おむつ
次に必要なお金は、おむつと衣類にかかる費用です。
まず、おむつですが、1パックあたり60枚~70枚の商品で、おおよそ1,000円~1,300円前後といった値段になります。
一日に何回おむつを替えるか…という点については、赤ちゃんにより様々ですが、おおよそ1ヶ月に必要なおむつ代は、5,000円~8,000円前後と考えておけば大丈夫です。
また、成長の早い赤ちゃんには、衣類代もかかってきます。
子供にどれくらいの衣料費をかけるかどうかも、親の考え方一つですが、安価なもので済ませる事ができれば、毎月3,000円~5,000円程度で済む場合もあります。
医療費
子供が生まれると、何かと病院にお世話になる事も多くなりますが、その時に心配になるのが「医療費」です。
ただ、乳幼児の場合は「医療費助成制度」というものがありますので、一般的な通院医療費・入院医療費・薬代などは、自治体からの援助により、無料になるケースがほとんどです。
ただ、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド代、食事代等は、実費負担が必要となります。
詳しくは居住地域の自治体ホームページなどを、よくチェックするようにして下さい。
出産前後は出産手当金で乗り切る
普段、労働をして給料を受け取っている人に限られますが、出産予定日の42日前~出産後56日の98日間は、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。
出産手当金の計算方法は次の通りです。
ただし、標準月額報酬の上限は28万円となりますので、月平均28万円以上の給料を受け取っている人は、出産手当金の金額が実際の給料の3分の2で計算した額よりも少なくなります。
|
妊娠中に連続4日以上仕事を休んだとき
妊娠悪阻等の理由で、妊娠中に連続4日以上仕事を休み、その間の給料が十分に支払われない場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されることもあります。
1日当たりの傷病手当金の計算方法は、1日当たりの出産手当金の計算方法と同じです。
妊娠中の傷病手当金は、本当はもらえるのに申告せずに受け取っていない人が多い手当金ですので、ぜひ該当する人は手続きをしてくださいね。
出産育児一時金で出産費用を賄う
出産費用は施設やサービスによって差はあるものの、一般的に30~70万円が相場となっています。
とはいっても健康保険から「出産育児一時金」(1児当たり42万円、産科医療補償制度の対象外となる施設での出産の場合は1児当たり40.4万円)が支給されますので、実際に支払う額は0~30万円ほどです。
助産院等の出産費用が低い施設を利用する
出産育児一時金は、出産だけでなく育児にも活用できるお金ですので、出産費用が42万円(産科医療補償制度の対象外となる施設での出産では40.4万円)を超えない場合は、差額を育児資金として受け取ることができます。
出産前後は出産費用以外にも、「妊婦健診費用」「赤ちゃんの日常品」「お母さんのマタニティウェア」「ベビーカーやチャイルドシート」と何かと出費がかさみますから、育児資金を受け取れると助かりますよね。
また、施設によっても差はありますが、一般的には出産費用は助産院が低いとされています。
出産施設を決めるときに、産婦人科クリニックや総合病院だけでなく、助産院などの個人施設も回って、比較検討してみるようにしましょう。
助産院を利用できない場合もある
助産院は助産師だけの施設ですので、医療行為が行えず、次の条件に合致するケースでは利用することができません。
助産院を利用できないときは、早めに他の病院・クリニックを受診してくださいね。
|
帝王切開等の医療行為には医療保険が適用される
出産は病気やけがではありませんので、医療費とはみなされず、医療保険も適用されません。
そのため、妊娠中の検診(妊婦検診)もすべて自費負担ですから、1回あたり7,000~15,000円と高額になってしまいます。
また、出産育児一時金は支給されますが、出産育児一時金で賄えない出産費については全額自費負担となります。
ですが、帝王切開や吸引分娩等の医療行為が必要になった場合には、医療保険が適用されます。
例えば帝王切開の手術は20万円ほどかかりますが、3割負担となりますので、実際に支払う金額は7万円ほどとなります。
高額療養費制度が適用されることも!
<高額療養費自己負担限度額(被保険者が70歳未満の場合)>
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
|---|---|---|
| 報酬月額81万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 報酬月額51.5万円以上81万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 報酬月額27万円以上51.5万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 報酬月額27万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
| 市区町村税非課税者 | 35,400円 | 26,400円 |
収入によって異なりますが、支払う医療費の額が一定以上になると「高額療養費制度」が適用され、上限額以上は支払う必要がなくなります。
万が一、産婦さんや赤ちゃんの体調が悪く、入院が長引いたとしても、一定額以上は免除されますので安心して下さいね。
尚、表中の「多数該当」は、高額療養費制度が適用される月は4ヶ月を超えるときに適用される上限額です。
例えば報酬月額27万円未満の人が長期にわたって療養生活を送らなくてはいけない場合、1~3ヶ月目は月額57,600円が支払う医療費の上限額となりますが、4ヶ月目以降は支払う医療費の上限額は44,400円とさらに低くなります。
帝王切開が民間医療保険の適用内になることも!
加入している民間の医療保険によっては、帝王切開等の出産時に受けた医療行為が保険適用の範囲内になることもあります。
手術費用は出るけれど入院費用は出ない等の制約があることもありますので、気になる人は、加入している医療保険のコールセンターに電話をかけて確認しておきましょう。
出産後は育児休業給付と児童手当
子供が1歳もしくは1歳半になるまでは、専業主婦として育児に専念しようと考えているママも多いのではないでしょうか。
産後56日目までは健康保険から「出産手当金」が支給されますが、その後は子供が1歳(場合によっては1歳6ヶ月)になるまでは雇用保険から「育児休業給付」が支給されますので、安心して育児に専念することができます。
ただし、育児休業開始から6ヶ月間は休業前の賃金の67%を「育児休業給付」として受け取れますが、育児休業開始から6ヶ月経過した後は休業前の賃金の50%しか「育児休業給付」として受け取れなくなるため、給付金の額が減ってしまいます。
生活費や保育費、支給される育児休業給付金を計算し、もっとも良いタイミングで仕事を再開するようにしましょう。
就職活動を開始したら雇用保険の基本手当を申請しよう
出産や育児のために休業しているのではなく、出産や育児のために勤めていた会社を退職した人もいるでしょう。
このような人の場合は、再就職のための活動を開始してから「雇用保険の基本手当」を受け取ることも可能です。
次の記事でも雇用保険の基本手当や再就業のための保活対策を詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
児童手当の手続きをしよう
<児童手当の支給額>
| 収入区分 | 子どもの年齢と学齢 | 1ヶ月の支給額 |
|---|---|---|
| 所得制限額未満 | 0歳~3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校卒業までの長子あるいは第2子 | 10,000円 | |
| 3歳以上小学校卒業までの第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | |
| 所得制限額以上 | 中学校卒業までの子ども | 5,000円 |
子供が産まれたら15日以内に児童手当の受給手続きを実施します。
所得額と扶養親族人数によって受給できる額が異なりますが、扶養親族が1人いる世帯でも前年所得額が660万円(給与としての目安は年間875.6万円)と制限額が高く設定されていますので、多くの世帯で子ども1人当たり10,000円~15,000円を受け取ることができます。
印鑑と請求者の口座が分かる書類(通帳など)、本人確認書類(運転免許証など)、健康保険証、マイナンバーが分かる書類(請求者と配偶者の両方)を持って、お住まいの市区町村役場で手続きをしてください。
今スグできる!少しでも貯金するための4つの鉄則
紹介してきたように、子育てには、決して低くはないお金が必要となります。
いざという時に慌てない、また、お金が原因で子供に何かを諦めさせることがないように、今のうちから、計画的な貯蓄を考える必要があります。
貯金をするには、まず、収支の見直しが重要です。
具体的にどのような行動をしていけばいいのか細かく具体例を挙げながら見ていきましょう。
①まずは収入と支出を把握しよう
今月の給与はいくらなのかと、どうしても収入金額ばかりに目を向けてしまいますが、重要なのは出ていく支出金額の把握です。
自分では節約していると思っていても、実際は無駄な出費も多いものです。
しっかりと、家計簿アプリなどを活用し支出を客観的に見る癖をつけましょう。
また支払って当然と思ってしまう固定費も見直しの対象です。
携帯電話を格安スマホに変更したり、住宅ローンの借り換えを検討したりすれば、一気に数万円カットすることも可能です。
②外食NG!弁当持参で食費を節約
外勤している夫婦の場合、職場の人とのお付き合いでランチは毎回外食になったり、休日家族で遊びに行った結果に疲れたから外食したりと、気が付けば週の何回かは外食になってはいないでしょうか。
まだ「ここのご飯を絶対に食べたい」という目的があればいいのですが、何となく、面倒だからとつい外食にしてしまうのはとてももったいないことです。
可能であればランチの回数を減らしてお弁当を持参したり、家族で出かける場合には疲れて帰宅しても無理なく作れる時短メニューの開発などをしたり、心掛けると節約につながります。
③クレジットカードは使わないほうが貯金できる
最近主婦の間で話題なのが、クレジットカードを活用しお得に買い物をする「ポイ活」です。
しかし、現金での支払いではない分、どうしても金銭感覚がおかしくなってしまいます。
確かに現金で支払うよりも、クレジットカードで支払ったほうがポイントは貯まり、結果的に節約になることも多いので、一概に「クレジットカードはダメ」とは言えません。
しかし現金支払いよりも、購入するときのハードルが低くなってしまうのも事実です。
そのため、節約でクレジットカードを使うのであれば、必ず使った分の金額は、即座に引き落とし口座に入れておきましょう。
手元の現金を動かすことによって、無駄使いを避けることができます。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
④副業で収入をアップさせることも大切
支出をある程度絞ることができたならば、次に行うことは収入を増やすことです。
子供が小さくて外勤が難しい場合でも、在宅で行える仕事であれば問題ありません。
例えば、サイズアウトしてしまった子供服や、使わなくなったおもちゃ類を中古販売サイトで売れば、多少なりとも収入源になります。
また副業としてハンドメイドで、アクセサリーを販売する主婦も多いものです。
費用対効果をしっかりと考え、限られた時間でいかに効率よく稼ぐための副業は何かを模索しておくといいでしょう。
子育てに必要なお金をラクラク貯める3つの方法
いくら「今後は貯金することがいかに大切なのか」を声高に言っても、これから先長きに渡る子育て人生ですので無理は続きません。
「ちょっと無理すれば頑張れる」という節約の仕方をしていると、子育てが終了するまでずっと「ちょっと無理をする」状況が続きます。
このようになると、いつかどこかで無理した分のしわ寄せがやってきます。
子育てに必要なお金は、無理をして貯められるものではありません。
長く続けるためには無理をしないラクラク貯めが必要不可欠なのです。
ここからはお金をどのようにして楽に貯めるかを解説していきます。
①児童手当は生活費として使わず貯金する
前年度の所得が800万円未満であれば、満額支給を受けられるのが児童手当です。
金額は子供の年齢や数によって異なりますが、年齢が上がれば徐々に金額が下がりますので、幼いうちから児童手当は貯金に回しておくことをおすすめします。
預金先は、普通預金ではなく出金しにくく普通預金よりも金利が高い、定期預金にしておくと金利で残高も増えていくことが期待できます。
②学資保険は無理ない範囲でコツコツと
「分かってはいるけれども、なかなか貯金に回せない」という人であれば、強制的に口座から引かれる学資保険もひとつの選択肢です。
毎月掛金が引き落とされ、満期になれば利息込みで掛金よりも、大きな金額が戻ってくることも魅力です。
しかし加入する子供の年齢が上がれば、月の掛金も高くなりますし、途中解約した場合には元本割れしてしまうリスクがあります。
またどこの学資保険に加入するかによっても、サービス内容や金利に差がでてきます。
ハイリターンな商品を求めると掛金も高くなってしまいますので、生活に支障がでない金額にどのような商品があるのか調べてみましょう。
③生活費と貯金用の口座は分けておく
生活費と貯金の口座を一緒にしておくと、流動が大きいので結果的にいくら貯金できているのか分かりにくいものです。
また、「まあいいか」とつい貯金分に手をつけてしまいます。
口座を分けることで、明確に住み分けができ、管理もしやすくなります。
貯蓄用だけ定期預金口座にしておくのもひとつの方法ですが、少しでもモチベーションを上げるため「目的別貯蓄」を行っているネット銀行に口座を開設するのもいいでしょう。
事前に目的別で金額設定しておけば、仮に1万円入金すると自動的に「養育費〇千円」「家族旅行代〇千円」と振り分けをしてくれます。
ダラダラ貯めるよりも目の前に目標があったほうが頑張れるという人は、検討してもいいかも知れません。
子育てのお金を捻出する方法
子育てはお金がかかるものです。
子供がいないときと同じような調子で生活していると、必要最低限のお金すら支払えなくなることもあるでしょう。
子育てのお金を捻出するために考慮すべきことを3つ紹介します。
毎月の生活費を節約
毎月の支出を減らせば、子育てに使うお金を増やすことができます。
次の3つのポイントに注意することで、生活費の無駄を省いていきましょう。
無駄な月額料金をなくす
新聞や雑誌、牛乳配達など、毎月定額で支払っているサービスは本当に価値のあるものなのでしょうか。
例えば「ネット新聞なら、いつでも好きな時に読めるだろう」と契約しても、月に1度か2度しか閲覧していないなら、月額料金を支払うのは無駄ですよね。
他にも、滅多に行かないスポーツクラブ、滅多に視聴しないネットテレビサービス、最近では開封すらしない子供の通信教育、補償内容がいまいち分からない保険等々、無駄な月額料金をたくさん支払っている可能性がありますよね。
充分に利用していないと思えるものは早めに解約し、毎月の固定費を節約していきましょう。
まとめ買いがお得とは限らない
まとめて買うのはお得なことだと考えている人も多いです。
しかし、実際には消費期限内に食べ切れずに捨ててしまったり、「たくさん買い置きがあるから」と気持ちが大きくなって、ティッシュペーパーや洗剤類を必要量以上に浪費することもあります。
本当にまとめ買いすることがお得なのか吟味してから買い物をするようにしてくださいね。
無駄なものを保有していないか見直す
例えば車。
毎日乗っているのなら良いのですが、たまの週末にしか使わないのなら、いっそ手放してみてはいかがでしょうか。
駐車場代や自動車税、自動車保険料、車検代が節約できますよ。
また、滅多に行かない別荘や山荘を所有している人、趣味用品が入らなくてレンタル倉庫を借りている人も、本当に年に数十万円以上ものお金をかけて保有する価値があるのか見直してください。
専業主婦なら仕事を探す
無駄な支出を省くことも大切なことですが、収入を増やすことも大切なことです。
余っている時間がある場合は、仕事を探してみてはいかがでしょうか。
例えば子供が幼稚園や小学校に行っている間の数時間でも、働くことができます。
急ぎの支払いがある場合
節約やパートの経済的効果が表れるまでには、少々時間がかかります。
急な支払いがあるときには、銀行や消費者金融のカードローンを利用してお金を準備してみてはいかがでしょうか。
「消費者金融のカードローンなんて利用したら、利息が高いんじゃないの?」と考えている方も多いと思われますが、一概にはそうとは言い切れないのです。
例えばほとんどの大手消費者金融では「初回は30日間無利息で融資するサービス」を実施していますので、30日以内に返済すれば利息は0円、60日以内に返済するなら通常金利の半分の金利(銀行の金利以下になることが多いです)で借りられ、非常にお得なのです(SMBCモビットは無利息サービスなし)。
賢く借りて早期完済すれば、とても便利な融資手段と言えるでしょう。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
子育て世代がもらえる手当についても理解しておこう!
繰り返しになりますが、子育て世代はお金がかかります。
節約も重要ですが、もらえる手当についても正しく理解していくことで、もしもの場合は困らずに済むこともあります。
それでは、子育て世代にはどのような手当が該当するのかを見ていきましょう。
①児童手当の支給条件と注意したいこと
中学生までの児童を育てる保護者に対して、4か月に1度行政から支給されるのが「児童手当」です。
この児童手当を利用すれば、以下のように零歳から中学校修了までの児童ひとりにつき、月額1万5,000円又は1万円が支給されます。
| 支給対象児童 | ひとりあたり月額 |
|---|---|
| 零~3歳未満 | 15,000円 (一律) |
| 3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 (一律) |
児童手当は基本的に中学生以下の子供がいる家庭なら、どの家庭でも利用できる制度ですが、以下のように所得制限限度額があります。
| 扶養親族等の数 | 所得額 (給与所得排除後の金額) | 収入額 (年収) |
|---|---|---|
| 0人 | 622万円 | 約833万円 |
| 1人 | 660万円 | 約875万円 |
| 2人 | 698万円 | 約917万円 |
| 3人 | 736万円 | 約960万円 |
| 4人 | 774万円 | 約1,002万円 |
| 5人 | 812万円 | 約1,042万円 |
この所得制限をオーバーする場合は「特例給付」となり、児童の年齢に関係なくひとりあたり月額5,000円となってしまいます。
児童手当を受けるには、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。
子供が生まれ名前を決め出生届をだしたら、そのまま児童手当の手続きを促されますので、指示に従い申請をしましょう。
なお、申請場所は居住する地域の、市区町村の役所です。
②母子手当(児童扶養手当)とは?
母子家庭であれば、「母子手当(児童扶養手当)」や「母子福祉貸付金」などと言った利用できる支援制度があります。
それらを利用して子育て費用の足しにするという人もいるでしょう。
母子手当(児童扶養手当)とは、両親の離婚や死亡・失踪などによって片親となってしまった子供を支援するための制度です。
この制度を利用すれば、児童の人数や所得等によって決まったお金が支給されることになります。
支給対象となるのは、年齢が零歳から18歳まで(18歳の誕生日を過ぎ最初に迎える3月まで)の母子家庭の子供です。
また、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
|
|
母子手当てには「所得制限」もあります。
所得制限は以下のように子供の人数によって異なり、その所得をオーバーしている人は支給を受けられません。
| 扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 |
例えば、子供の人数が3人の人なら、年収が1,330,000円までなら全額支給、3,060,000円までであれば一部支給が受けられます。
もし、3,060,000円を超えてしまう場合は母子手当て(児童扶養手当)の利用ができません。
母子手当て(児童扶養手当)の支給額は以下のように、全額支給と一部支給のどちらになるかや、子供の数によっても異なります。
| 児童数 | 全額支給 (月額) | 一部支給 (月額) |
|---|---|---|
| 1人 | 42,290円 | 42,280円~9,980円 |
| 2人 | 9,990円を加算 | 9,980円~5,000円を加算 |
| 3人以上 | 5,990円を加算 | 5,980円~3,000円を加算 |
少々分かりにくいのですが、子供ひとりに対しての支給額が基本となり、ふたり目以降はその金額に加算されます。
例えば、子供ひとりで全額支給なら42,290円となります。
これがふたりなら42,290円に9,990円が加算され、「42,290円+9,990円=52,280円」といった形になるのです。
母子手当て(児童扶養手当)を受けるには、お住まいの地域の区役所内にある「こども家庭支援課」の窓口で申請する必要があります。
③生活が厳しいなら母子福祉貸付金
母子福祉貸付金とは、「母子(父子)家庭」や「寡婦(かふ)の人(夫を失って独身の人)」に対して、経済的自立を目的に貸付けをする制度です。
この制度を利用すれば、修学資金や生活資金、医療介護資金などを無利子又は年1.0%という低金利で借り入れができます。
母子手当(児童扶養手当)との違いは、飽くまで貸付すなわち借金であるということです。
従って母子福祉貸付金を活用したら、必ず返済を行わなければなりません。
母子福祉貸付金が利用できる人は以下のような人です。
- 母子家庭の母(父子家庭の父)又は寡婦(かふ)の人、その扶養する子
- 父母のない児童(法定代理人の同意が必要)
母子福祉貸付金は以下の12種類のいずれかを目的として利用する必要があります。
|
|
|
また母子福祉貸付金で借り入れできる金額は資金使途によって異なります。
例えば、神奈川県の場合の「就学支度資金(学校の授業料等に必要な資金)」の場合は以下のようになっています。
| 学校形態 | 貸付限度額 (月額) |
|---|---|
| 高校(公立) | 150,000円 |
| 高校(私立) | 410,000円 |
| 高等専門学校(私立) | 410,000円 |
| 短期大学・専修学校(私立) | 580,000円 |
| 大学(公立) | 370,000円 |
| 大学(私立) | 580,000円 |
母子福祉貸付金は貸付けですから審査があります。
母子家庭なら誰でも利用できるという訳ではありません。
審査で重視されるのは「返済できるか」という点です。
そのため、基本的に返済の見込みがない人は審査にとおりません。
申し込むときは返済できる見込みがあることを証明するために、給与明細など現在の収支状況等が分かるものをしっかりと用意しておく必要があります。
この母子福祉貸付金の申込先は市域にお住まいの場合は「各市児童福祉所管課」、町村域の場合は「県保健福祉事務所」が相談窓口となります。
子供の将来のために必要な貯金額
家計に余裕が出たら、子供の将来のために貯金を始めていきましょう。
子供の将来の中でも、特に教育費は気になりますよね。
教育費はいくら準備しておく必要があるのか、また、目標額を貯めるために毎月いくらほど貯金すれば良いのかについて探っていきましょう。
進学に必要なのは最低783万円
文部科学省の調査によりますと、幼稚園から4年制大学まですべて公立(大学は国立で計算)に通うなら、教育費は約783万円となります。
反対に、幼稚園から4年制大学まですべて私立に通ったとすると、教育費の総額は約2,221万円となります。
もちろん、一括で支払うわけではありませんし、お稽古ごとや塾、学部によっても誤差はありますが、私立に通わせる場合は公立校よりほぼ3倍の教育費がかかるということは覚えておきましょう。
1ヶ月に1~2万円の貯金で貯まる
教育費に1,000~2,000万円も必要だときくと、「そんなに準備できない」と考えるかもしれません。
しかし、全額をまとめて支払うわけではありませんから、幼少中高の教育費は生活費から捻出し、もっともお金がかかる大学(平成28年度の時点では大学4年間で国立約243万円、私立約451万円)進学までに大学の費用を貯金しておくようにしましょう。
生まれてすぐに学資保険を始めるなら毎月10,000円を積み立てれば18年後には約225万円(返戻率103.8%で計算)は受け取れますし、毎月20,000円を積み立てれば18年後には約450万円を受け取れます。
少ない負担で子供の学資を貯めることは可能ですので、妊娠が分かったら早めに学資保険についても検討してみてください。
育児ストレス?お金がないストレス?
ところで、あなたのストレスは、本当に育児におけるストレスですか?
子供の世話に追われて自分自身のための時間を取ることができず、睡眠不足や過労に陥っているのなら、それは育児ストレスと言えます。
しかしながら、「保育園の保育料が高い」「子供たちに新しい洋服を買ってあげられない」「すぐに熱を出すから、頻繁に病院に行かなくてはならないのが苦痛」などがストレスの原因なら、育児ストレスではなくお金がないことによるストレスと考えられます。
次の記事でもストレスとノイローゼの関係について解説していますので、ぜひご覧になって下さい。
育児ではなく旦那がストレス因子?
また、ストレスの原因が育児ではなく「夫」にある可能性もあります。
育児と家事でクタクタに疲れているのに、何の手伝いもしてくれない夫。
子供が生まれて色々とお金がかかるようになったのに、出産前と同じように自分の趣味や服飾にばかりお金を遣う夫。
そのような夫の存在が、あなたのストレスの本当の原因なのかもしれません。
育児ではなく旦那ストレスによって日々苦しみ、娘や息子が可愛く思えないようになってきている人は、離婚することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
社会から取り残されるという不安がストレスに?
育児に専念するために、子育て期間だけ専業主婦になっている人も多いでしょう。
「早く会社に復帰したい」「このままではキャリアに傷が付く」などと日々焦った気持ちでいると、子どもと過ごすことが苦痛になり、ただ義務感で子どもに接してしまうことにもなりかねません。
そのような人は、育児ストレスというよりは「社会から取り残されるという焦り」によるストレスを抱えていると言えるでしょう。
育児ノイローゼになる前に!ストレス発散を
ストレスを上手に発散できていれば、育児ノイローゼにならなくても済みます。
ただし、ストレスの発散にお金をかけてしまうと、「無駄遣いをしてしまった…」という罪悪感からさらにストレスが強まってしまいます。
子育ての途中でも実施可能なお金をかけないストレス発散方法を3つ紹介します。
自分のための時間を1時間確保する
1日のすべての時間を子育てと家事に使ってしまうと、自分のことを考えるゆとりがなくなってしまい、ノイローゼ状態に陥りやすくなります。
1日に1時間でも良いですので、ネイルケアをしたり本を読んだり好きなお茶を飲んだりする時間を取りましょう。
「1日に1時間の自由時間があるなら、本を読んだりするより寝たい!」と考える寝不足のママたちもいるでしょう。
もちろん、睡眠不足が続くことは望ましいことではありませんので、どうしても寝たいときは「自分のための睡眠」を取るのも良いですね。
子育てに目標を定めて達成感を得る
子育てがストレスフルなのは、子育てにおいて達成感が得られにくいことにも原因があると考えられます。
毎日のお風呂や食事・トイレの世話、どんなに教えても手づかみで食事をする子ども、決して終わることがない子供の遊びの付き合い等、すべてにおいてゴールがなく、いつまでも同じことを繰り返すだけだと感じる母親も多いのではないでしょうか。
ですが、育児においても「目標」を定めれば達成感を得ることができます。
離乳食を残さず食べること、1日に1回でもトイレを汚さずに使うことなどの子供の行動を目標にすることもできますし、絵本を3冊読むこと、夜11時までに寝ることなどの自分の行動を目標にすることもできますよ。
日記をつける
毎日同じような日々が過ぎていくと感じているママたちは、日記をつけてみるのはいかがでしょうか。
1日に5分程度の時間を日記のための時間と決め、日々の気付きを書き留めていきましょう。
日記をつけることで日々の変化が感じられるようになりますし、自分がどれほどの事柄を成し遂げたのか実感できるようにもなりますよ。
離婚してお金が足りないならどうする?
離婚によって1ヶ月に使えるお金が減り、育児のお金が足りなくなってしまうこともありますよね。
例えば専業主婦や扶養の範囲内でパートをしていた方なら、離婚することでいきなり生活苦になってしまう可能性があります。
中には、離婚する前から経済的DVを受け、充分な生活費を確保できない場合もあります。
離婚したときはすぐにお住まいの市区町村役場の子育て課(母子課など、役場によって名称が変わります)に行き、次の公的手当を受けられないか窓口に相談してみてください。
児童扶養手当
子供を養育する側の親は、所得によって児童扶養手当を受け取ることができます。
2018年4月以降は、子供1人の場合は1ヶ月あたり10,030~42,500円、子供が2人のときは月額5,020~10,040円の加算、子供が3人のときはさらに月額3,010~6,020円加算されます。
以下の書類を準備して、お住まいの市区町村役場で手続きをしてください。
|
児童育成手当
児童扶養手当はひとり親家庭に対する国の支援制度ですが、児童育成手当は自治体ごとに実施しているひとり親家庭の支援制度です。
すべての自治体で実施しているわけではありませんので、かならずお住まいの自治体役場に問い合わせてください。
なお、児童育成手当制度は、自治体によって給付額や所得制限の基準も異なります。
現在お住まいの地域で児童育成手当が受給できなくても、他の地域に引っ越せば児童育成手当が受給できるというケースもありますので、かならず引っ越したときは役場窓口で相談してください。
江戸川区と町田市の児童育成手当の支給額と所得制限は以下の通りです。
| 東京都江戸川区 | 東京都町田市 | |
|---|---|---|
| 児童育成手当額 (子供1人あたり) | 13,000円 | 13,500円 |
| 扶養人数0人の時の所得制限 | 年3,604,000円未満 | 年3,684,000円未満 |
| 扶養人数1人の時の所得制限 | 年3,984,000円未満 | 年4,064,000円未満 |
| 扶養人数2人の時の所得制限 | 年4,364,000円未満 | 年4,444,000円未満 |
| 扶養人数3人の時の所得制限 | 年4,744,000円未満 | 年4,824,000円未満 |
※いずれも、平成30年度の支給額と所得制限の基準です。所得制限は、各種控除後の年間所得で判断します。
住宅手当
自治体によっては、ひとり親家庭に対して住宅手当を支給していることもあります。
いずれも所得制限がありますので、お住まいの市区町村の役場で尋ねてみてください。
| ひとり親家庭に対して住宅手当を実施している自治体 | 住宅手当額 (月額) |
|---|---|
| 東京都武蔵野市 | 10,000円 |
| 東京都東久留米市 | 3,500円 |
| 千葉県浦安市 | 15,000円 |
| 千葉県君津市 | 5,000円 |
| 兵庫県神戸市 | 15,000円、 家賃債務保証料として60,000円 |
| 神奈川県大和市 | 10,000円 |
貯金ゼロの子育て・・・まとめ
子育てには思った以上のお金がかかり、多額の費用が必要になるものだと事前に認識しておきましょう。
子育てに関する費用を工面するにはローンという手段もありますが、金利が毎月発生してしまいます。
そのため、貯金をしておき、なるべくならそのお金で費用をまかないたいところです。
無理なく貯金を行うコツは、無理をしないこと・ストレスを感じないことです。
ただでさえ子供が大きくなると、お金とは異なる悩みも増えてきます。
そのうえお金のことも考えるとなると、心理的にも疲れて生活が続きません。
今回紹介した対処法を実行してもらえれば、貯金を楽して貯めることができる可能性が期待できます。
まずは収支の意識改革から始めてみてはいかがでしょうか。
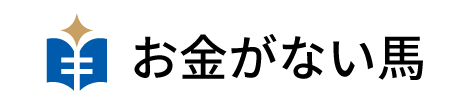





























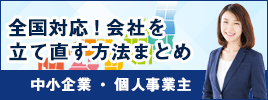

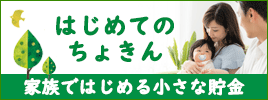


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。