奨学金だけで学費は賄える?足りない時の対処法とは
今や、子供の大学進学費用を稼ぐために、夫婦で共働きをしたり、子供が小さな頃から学資保険などで備えをしたりするのは当たり前の時代になっています。
また、進学する子供たちも、親が蓄えたお金だけでは授業料が賄えず、学生全体の約40%は奨学金を利用しています。
そこで今回は、改めて大学進学に必要な費用と、奨学金で借りられる費用を比較し、実際のところ奨学金だけで学費を賄えるのか検証してみました。
「どうしてもお金が足りない」「急ぎの支払いなのに…」という場合は、消費者金融カードローンがおすすめです。
5万円をカードローン最大金利年18.0%で30日間借りた場合、利息は750円以下。さらに無利息サービスがあるカードローンを利用すれば、一定期間利息はかからず、一括返済できれば利息は0円です(SMBCモビットは無利息期間なし)。
以下に今すぐ申し込めるカードローンをまとめたので、まずは公式サイトを確認してみてください。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
日本学生支援機構の奨学金だけで学費は賄える?
現在、最も多くの学生が利用しているのが「日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金です。
日本学生支援機構は2004年に設立された独立行政法人で、それまで国による奨学金を運営してきた日本育英会が廃止された後に、奨学金事業を引き継いだ形となっています。
日本学生支援機構の奨学金には、無利子の「第1種奨学金」と有利子の「第2種奨学金」があり、どちらが利用できるのかは、「世帯収入」と「子供の成績」を基に判断されます。
公的な奨学金を利用できるのは非常に有り難いことですが、果たして奨学金だけで学費が賄えるのかは疑問です。
実際に、ネット上でも「奨学金だけじゃ足りない!」という声を多く目にします。
まずは、第1種奨学金と第2種奨学金の内容について確認しておきましょう。
第1種奨学金
第1種奨学金とは、利息が付かないタイプの奨学金となりますが、この奨学金を受けるためには、ある程度の学力が必要となります。
必要とされる学力は次の通りです。
| 成績基準 | |
|---|---|
| 予約採用 | 高校1年生から申込時までの成績が3.5以上 |
| 在学採用 |
|
なお、この奨学金の貸与額には上限が決められており、以下のように金額設定されています。
| 国公立・自宅通学の場合 | 月額30,000円又は45,000円 |
|---|---|
| 国公立・自宅外通学の場合 | 月額30,000円又は51,000円 ※自宅通学の月額も選択可能 |
| 私立・自宅通学の場合 | 月額30,000円又は54,000円 |
| 私立・自宅外通学の場合 | 月額30,000円又は64,000円 ※自宅通学の月額も選択可能 |
◆日本学生支援機構公式サイト:「奨学金第1種(利息のないタイプ)」
第2種奨学金
次は、利息が付くタイプの奨学金「第2種奨学金」です。
第2種奨学金は、日本学生支援機構の予算の7割以上を占めています。
上限利息は3%とされていますが、実際の返済利率は返済時の経済情勢により決められます。
この奨学金の場合は、月額30,000円、50,000円、80,000円、100,000円又は120,000円の中から選択することが可能です。
さらに、私立の医学部や歯学部の場合、最高額の120,000円に40,000円の増額が可能となっています。
◆日本学生支援機構公式サイト:「奨学金第二種(利息が付くタイプ)」
こちらも第1種と同様に成績基準が定められています。
| 成績基準 |
|---|
次の3つのいずれかに該当する人
|
また、この他にも非課税世帯(生活保護世帯など)の子供が受給できる「給付型奨学金」などの制度もありますが、こちらは国公立の大学で月額2万円が支給されます。
さらに、以上の奨学金には所得制限があり、親が高所得者である場合、奨学金は利用できません。
例えば、4人家族で親の所得が11,000,000円を超えると、有利子タイプの第2種奨学金も利用できないことになっています。
■奨学金を借りられない人は親が関係している?審査基準は厳しいの?
結局のところ奨学金だけでは賄えないケースも!
以上で紹介した内容から、「奨学金には上限がある」さらに「親の所得にも制限がかかる」ということを考えると、世帯によって奨学金だけでは授業料は賄えないことがわかります。
また、第1種奨学金と第2種奨学金を併用することも可能ですが、この場合でも親の所得制限があり、4人家族の場合、所得が686万円を超えると、併用で利用することもできません。
1種と2種は併用可能
実は奨学金の第1種と第2種は併用が可能です。
第1種、第2種併用の場合、奨学金貸与の学力基準は第1種と同等とされていますが、収入基準は第1種よりも厳しく定められています。
3人世帯の場合を例に挙げると第1種、第2種併用時の収入基準は給与所得者が599万円以下、給与所得者以外の場合は245万円以下です。
第1種の場合は給与所得者が657万円以下、給与所得者以外が286万円以下なのでさらに基準が厳しくなっているのがお分かりいただけると思います。
給与所得に関しては手取りではなく控除前の金額です。
また給与所得者以外というのは自営業者などを指します。
給与所得者よりもまたさらに収入基準が低いですが、この場合は収入から経費を差し引いた所得金額になります。
このように、まず第1種、第2種併用は借りるハードルも高いですし、もし借りられた場合でもしっかりとした返済計画が必要となります。
申請方法と返済例
申請方法は主に予約採用と在学採用あります。
予約採用
予約採用については学校を通じて手続きを行いますので学校に問い合わせてみると良いでしょう。
また高等学校卒業程度認定試験合格者や大学入学資格検定合格者に関しては日本学生支援機構への直接申し込みを行うようになります。
流れとしては以下のようになります。
|
このように予約採用に関しては全て学校を通じて手続きするようになります。
在学採用
在学採用は在学中の学校を通して手続きを行います。
流れとしては以下のようになります。
|
第1種と第2種を併用して申し込みしたい場合は申込時にコースを選択できるようになっていますのでそちらを選択するようにしてください。
では第1種と第2種を併用した場合どのような返済計画になるのでしょうか。
実際にシミュレーションしてみましょう。
- 学校種類:4年制私立大学・自宅外
- 奨学金の種類:第1種、第2種併用
- 返還方式:定額返還方式
- 機関保証制度:利用する
2019年4月から2022年3月まで第1種は月額64,000円、第2種は貸与利率0.25%で月額40,000円をそれぞれ借りたとすると、合計3,744,000円の貸与総額となりました。
返済は2022年の10月から始まり、第1種、第2種合わせて月々16,000円の支払いで2042年の9月に完済予定となります。
もちろん繰り上げ返済も可能ですが、個人のライフプランによっては多額のお金を一度に支払うのは難しいのではないでしょうか。
22歳から返済が始まり、返済が終わるころには40歳を超えています。
そのような事実も念頭にいれて奨学金を検討すべきでしょう。
入学金特別増額貸与奨学金も合わせてチェック
入学金特別増額貸与奨学金をご存知でしょうか。
これは入学月の基本月額にプラスして貸与が受けられる制度です。
貸与金額は10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択します。
第1種または第2種を申し込んでいる人で、なおかつ2つの条件のうちいずれかを満たす人です。
- 学生本人の収入(定職、仕送り、アルバイト、奨学金などの1年間に得た収入)と配偶者(いれば)の定職収入の合計が120万円以下
- 1番の条件以外の人で日本政策金融公庫の「国の教育ローン」受けられなかったことを所定の書類にて申告した人
ただしこの奨学金は入学前に受けられるわけではないので入学前に必要な諸費用に利用することはできません。
奨学金では足りない分を借りる5つの方法
奨学金で全ての学費を賄うのは難しいため、足りない分をどうにかして補う必要があります。
学費が払えないから中退せざるを得ないというのは非常にもったいないです。
公的な貸付制度や支援金、教育ローンなど、教育資金として利用できるものはたくさんありますので、それらをフル活用するためにも、しっかりと理解しておきましょう。
①生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、一定の条件を満たす人に貸付をする制度で、市町村の社会福祉協議会が窓口となっています。
| 利息 | 連帯保証人ありの場合「無利子」 なしの場合1.5% |
|---|---|
| 貸付額 | 数万円~580万円 |
審査は厳しいですが、連帯保証人を付けることができれば、無利子でお金を借りることが可能です。
生活福祉資金貸付制度には、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」の3種類があり、学費が足りない場合に利用できるのが教育支援資金となります。
そして、教育支援資金は「就学支援金」と「教育支援金」のふたつがあります。
就学支援金
就学支援金の貸付額、利用目的や使途例は次の通りです。
| 貸付額 | 利用目的 | 使途例 |
|---|---|---|
| 50万円以内を一括貸付 | 高校、大学、高等専門学校等の入学時に必要な準備費用 (ただし日本学生支援機構などの奨学金を受けられなかった場合のみ) | 入学金、教科書代、制服代など |
教育支援金
教育支援金の貸付額、利用目的や使途例は次の通りです。
| 貸付額 | 利用目的 | 使途例 |
|---|---|---|
| 高校:月額3.5万円以内を分割貸付 高専:月6万円以内を分割貸付 短大:月6万円以内を分割貸付 大学:月6.5万円以内を分割貸付 (これら上限額の1.5倍まで借入可能) | 高校、大学、高等専門学校等の授業料 (ただし日本学生支援機構などの奨学金を受けられなかった場合のみ) |
|
②民間の奨学金
公的な奨学金だけでなく、財団法人、社団法人、株式会社などの多くの団体が奨学金制度を実施しています。
中には、団体から大学に案内が届いていることがありますので、大学に問い合わせてみるといいでしょう。
民間の奨学金の一例を紹介します。
| 団体名 | 対象者 | 支給額 |
|---|---|---|
| 一般財団法人キーエンス財団 | 4年制大学に通う大学新1年生 (20歳以下) | 月額8万円を4年間支給 |
| 交易材残法人電通育英会 | 指定公立高校から指定の大学・大学院に進学した大学生と大学院生 |
|
| 公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団 | 大学への進学予定の高校生 | 月額1.5万円を在学期間中 |
| 公益財団法人帝人奨学会 | 医学・薬学系・バイオ学系・理工学系・工学系・情報学系の大学院生 | 月額8万~10万円 (外国人の場合は月5万~6万円) |
| 公益財団法人アイザワ記念育英財団 | 指定大学の大学生・大学院生 | 月額3万~4.5万円 |
③労働型の奨学金
労働型の奨学金は、在学中に労働することにより学費を融資してもらえる制度を言い、よく知られたものでは「新聞奨学生」があります。
新聞社の多くにはそれぞれ奨学金制度があり、在学生が新聞配達をすれば、新聞社に学費を負担してもらえます。
貸与型の奨学金は卒業後に返済していかなければなりませんが、新聞奨学生は卒業後に借金が残らないため、学生にとって大きなメリットがあるのです。
さらに学費を負担してもらえるだけでなく、毎月の給料ももらえ、新聞社によっては食事や住居も援助してもらえるところもあります。
朝日新聞の「朝日奨学会」を例にとって見てみましょう。
| コース名 | 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | 仕事内容・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | 440万~ 520万円 | 330万~ 390万円 | 220万~ 270万円 | 110万~ 130万円 | 朝夕刊の配達、集金、附帯業務など、1日6時間程度勤務 |
| Bコース | 440万円 | 330万円 | 220万円 | 110万円 | 朝夕刊の配達、チラシ落ち込み、附帯業務など1日5時間程度勤務 |
④国の教育ローン
教育ローンは、銀行、信託会社、消費者金融などでも提供されていますが、金利や返済期間などで最もお得なのは、国の教育ローンです。
正式には日本政策金融公庫の「教育一般貸付」と言います。
教育一般貸付の内容は次の通りです。
| 利用限度額 | 350万円以内 (ただし、海外留学資金の場合は450万円) |
|---|---|
| 利息 | 年1.76% (固定金利・保証料は別途必要) (平成29年11月10日現在) |
| 返済期間 | 15年以内 |
| 入金までのスピード | 20日程度 |
また、教育一般貸付を利用するには、保護者の世帯年収が次表の金額以内であることが条件になります。
| 子供の人数 | ひとり | ふたり | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯年収の上限額、 ()内は事業所得者の場合の上限額 | 790万円 (590万円) | 890万円 (680万円) | 990万円 (770万円) | 1,090万円 (870万円) | 1,190万円 (970万円) |
| 特定の要件を満たせば、上限が990万円(770万円)まで緩和される | |||||
【上限が990万円(770万円)になる要件】
次の8つのうちのいずれかひとつに該当する場合です。
- 勤続(営業)年数が3年未満
- 居住年数が1年未満
- 世帯のいずれかの人が自宅外通学(予定)者
- 借入申込人又はその配偶者が単身赴任
- 融資目的が海外留学資金
- 借入申込人の年収に占める借入返済金負担率が30%超
- 親族に「要介護(要支援)認定」を受けている人がいて、その介護費用を負担している
- 大規模な災害で被災した
⑤民間の教育ローン
一般的な銀行などの教育ローンを利用する方法もあります。
金融機関の教育ローンの場合、所得の最低条件(三井住友銀行の場合は、年収200万円以上が条件)はあるものの、上限の条件はありません。
したがって、所得が多くて奨学金が利用できないと言う場合でも、借りることは可能です。
■大学費用(入学金や学費)を借りるには|奨学金?教育ローン?
ひとり親家庭なら母子父子寡婦貸付制度も使える
母子家庭又は父子家庭といったひとり親家庭の場合、「母子父子寡婦貸付制度」を利用できます。
利用できるのは、「20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子又は男子、寡婦等」とされており、申請や問合せは最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口になります。
母子父子寡婦貸付制度を利用して学費を賄う場合は、「就学支度資金」と「就学資金」があります。
就学支度資金
就業支度資金の内容は次の通りです。
【貸付対象】
- 母子家庭の母が扶養する児童
- 父子家庭の父が扶養する児童
- 父母のない児童
- 寡婦が扶養する子
| 貸付限度額 | 国公立大学・短大等:38万円 私立大学・短大等:59万円 |
|---|---|
| 据置期間 | 6か月 |
| 償還期間 | 20年以内 |
就学資金
就学資金の内容は次の通りです。
【貸付対象】
就業支度資金と同じ。
| 貸付限度額 | 短期大学、専修学校(専門課程):月額9万円 大学:月額9.6万円 ※私立の自宅外通学の場合の限度額 |
|---|---|
| 貸付期間 | 修学期間中 |
| 据置期間 | 当該学校卒業後6か月 |
| 償還期間 | 20年以内(専修学校の一般過程は5年以内) |
同時に借りられないものもあるので注意して
奨学金ひとつだけだと全ての学費を賄うには足りないので、奨学金や国の教育ローン等を併用すればほとんどの学費がカバーできると考える人もいるでしょう。
ちなみに、日本学生支援機構の第1種と第2種は併用して利用できます。
基本的に、日本学生支援機構の奨学金は、国の教育ローン等のような他の制度と併用ができますが、例外もあるので注意が必要です。
日本学生支援機構の「入学時特別増額貸与奨学金」と日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は併用不可となっています。
併用する際には、よく確認の上利用するようにしましょう。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
大学・専門学校の学費の目安
大学や専門学校に進学した場合、どれくらいのお金がかかるのか見ていきます。
年間の費用はおおよそ80万円~120万円程度
進学する学校が私立か国公立かによって異なりますが、先に結論から申し上げると、私立の場合なら年間の授業料で約80万円~120万円のお金が必要となります。
おおまかに分けると、文系の大学が費用としては比較的安く、薬剤師や医師などを目指す学部の場合は、授業料は非常に高くなり、例えば日本薬科大学の薬学科の年間授業料は220万円となっています。
一方専門学校についても、費用は様々です。
例えば美容系の専門学校なら、年間の授業料はおおよそ60万円~80万円程度で済みますが、同じく医療系の専門学校になると120万円~150万円が必要となります。
入学金
大学に必要なお金はもちろん授業料だけではありません。
大学入学時には、入学金が必要となります。
例えば、私立の名門、早稲田大学の入学金は、どの学部でも一律で20万円と決められていて、他の私立大学でも、おおよその入学金は20万円~40万円の間が多いようです。
一方、これが国公立になると入学金が安くなるのかと言うと、実はそうでもありません。
例えば、京都大学のホームページを見ると、入学金は28万2,000円となっていますので、私立よりも高いケースがあることがわかります。
学校協力費・教材費など
入学金や授業料以外にも必要な費用があります。
基本的には「任意…」としていながらも、学校協力費を求められる大学もあり、もちろん教材費なども必要になってきます。
また、最近では大学でレポートを提出するために、パソコンを購入するのは当たり前の時代になってきていますから、生徒専用のパソコンの購入を義務付ける大学も増えています。
お金がかかるのは学費だけじゃない
また、大学でも専門学校でも、必要な費用は入学金や授業料だけではありません。
もちろん通学に必要な交通費もかかってきますし、遠方の大学に進学する場合には、ひとり暮らしのための「家賃」「食費」などが必要になってきます。
これらを考えると、自宅以外から通う場合、上記でご紹介した授業料の他に、毎月8万円~10万円程度の費用が別に必要になることがわかります。
最後に、大学の入学料や、月の授業料、年間の授業料、4年間にかかる学費の合計をまとめてみました。
| 学校区分 | 入学料 | 月の授業料 | 年間授業料 | 年間設備費 | 4年間の学費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 282,000円 | 44,650円 | 535,800円 | - | 2,425,200円 |
| 公立大学 | 393,426円 | 44,817円 | 537,809円 | - | 2,544,662円 |
| 私立大文系 | 242,579円 | 62,177円 | 746,123円 | 158,118円 | 3,859,543円 |
| 私立大理系 | 262,436円 | 87,397円 | 1,048,763円 | 190,034円 | 5,217,624円 |
| 私立大医科歯科系 | 1,038,128円 | 228,086円 | 2,737,037円 | 831,722円 | 15,313,164円 |
学費が足りずに未納が続く時の対処法
では、奨学金だけでは学費を賄えない場合、どのような対処をすればいいのでしょうか?幾つか考えてみます。
学費の延納・分納
ほとんどの大学では、年間の授業料を年2回に分けて支払うようになっています。
ただ、年間100万円の授業料と仮定すると、1回の授業料納付は50万円となりますので、奨学金で賄えない場合は支払えないこともあり得ます。
そのような場合は、大学に「延納」や「分納」が可能かどうか、相談されることがおすすめです。
延納の場合、大学にもよりますが最大で半年間程度は猶予されるケースもありますし、分納の場合は年二回の支払いをさらに分割してもらうことも可能です。
ただ、このあたりの条件は大学が個々に決めることですので、統一のルールはありません。
学費の減額や免除
学費の減額や免除を申請するという方法もあります。
国立大学の場合、授業料免除は「学力基準」と「所得基準」のふたつの基準を満たしている必要があります。
| 学力基準 |
|
|---|---|
| 所得基準 | 以下の算式で家計評価額が0円以下になる場合。 家計評価額=総所得金額-特別控除額-収入基準額 |
学力基準については、大学ごとに異なるので、進学先で確認する必要があります。
所得基準も特別な算式に当てはめて計算することになるため、詳しくは文部科学省の授業料免除選考基準を参考にしてみてください。
アルバイトを増やす
以上のような対策が取れない場合は、学生自らがアルバイトなどをして稼ぐしか方法はありません。
ただ、これも考え方次第となりますが、必要以上に奨学金を借りて、実際に就職してから長い間返済に苦しむより、必要最小限の奨学金を借りて、足らない分はアルバイトで稼ぎ、卒業後は早期に完済する…というのもひとつの手段かも知れません。
学費が払えないとどうなるの?
学費がどうしても払えないと「この先どうなるの?」と不安でいっぱいになります。
納入日には間に合わないけれど少し期間があれば払えるという場合は、「延納」という方法があります。
学校によって猶予期間が異なり、必要書類もありますので、納入日に間に合わないことが明らかな場合は大学に早めに相談しておきましょう。
いつまでも学費を支払わないと、中退や除籍になってしまうかも知れません。
間に合わない場合に延納できる期間
学費の支払いが間に合わない学生のために、大学では学費の「延納期間」が設けられています。
ただし延期ができる期間は大学によって異なり、自分の都合で指定ができません。
大学によっては数週間ほどしか認められないところもあれば、数か月待ってくれるところもあります。
実際に延納を希望する場合には「延納願」などの書類を提出する必要があるため、どのような書類が必要になるのか大学に問い合わせてみましょう。
注意点としては、大学によっては延納に伴う延滞金がかかることや、延納すると次の学費納入日までの期間が短くなることがあります。
最悪、中退や除籍が待っている
大学の学費が払えないままにしておくと、自主退学という道を選ばない限り、中退や除籍といった扱いになってしまいます。
なお、大学によっては除籍ではなく退学、抹籍(まっせき)といった呼び名になりますが、どれも大学の学生としての籍がなくなることを意味します。
苦しい受験勉強を乗り越えてやっと合格した大学なのに、中退や除籍になってしまっては本当にもったいないです。
ちなみに、除籍された場合に大学から発行される証明書は「除籍証明書」になりますが、自主退学すれば「大学中退証明書」が発行されます。
除籍証明書だとマイナスイメージを持たれることがありますので、除籍される前に自主退学する方がいいかも知れません。
授業料が払えない理由は考慮される?
授業料が払えなくなってしまう理由は、一言で言えば「経済的な理由」で片付けられてしまいますが、細かな事情は学生(又は家庭)によってそれぞれ異なります。
学費を自分で稼いでいる学生の中には、毎日アルバイトをしてお金を稼いでいたけれども、納入日までに学費を貯めることができなかったという人もいるでしょう。
また、親が学費を出してくれていた学生の場合、これまでは親が学費を払っていたけれども、リストラなどの影響で収入が減ってしまったり、病気で休業せざるを得なかったりといった事情があるかも知れません。
しかし、このような様々な事情があって学費が支払えなくなり、大学を中退せざるを得ない学生が年々増えていることを考えると、学費が払えない理由はそれほど考慮されているわけではないと言わざるを得ません。
卒業後の返済計画
奨学金や支援制度を活用して無事に卒業した後は、返還生活が始まります。
日本学生支援機構の奨学金を利用した学生は、大学や専門学校等を卒業後7か月目から返還が始まります。
月々の返済額や返済回数(年数)は借りた金額によって異なるので、自分はどのような返還をしていくのか返済計画を立て見ましょう。
奨学金の返済は、口座振替によって行われ、奨学金の借入が終了したときに返済用口座「リレー口座」の加入手続きをします。
返済方法は、毎月定額が引き落とされる「月賦返還」と、毎月定額プラス半年に1度まとまった金額が引き落とされる「併用返還」のふたつがあります。
まとまった資金ができたときは、繰上げ返済もできます。
なお、日本学生支援機構の公式サイトでは、「奨学金の返還シミュレーション」ができますので、返済計画を立てる上での参考にしてください。
奨学金や支援制度は申し込み時期に注意
奨学金や各支援制度には申込期間が設けられており、その期間を過ぎてしまうと受け付けてもらえなくなってしまします。
例えば、日本学生支援機構の奨学金の場合で見てみましょう。
【予約採用】
高校3年生の時点で進学後の奨学金を予約してください。
- 1回目:5月~6月頃募集し、10月下旬に決定通知送付
- 2回目:10月~11月頃収支、2月下旬に決定通知送付
【在学採用】
大学や専門学校への進学後に申請してください。
- 原則1回のみの募集で、毎年春に募集
奨学金の申請期間は各高校、大学・専門学校でそれぞれ決められていますので、期間厳守で手続きするようにしましょう。
支援制度を利用する場合も、申請期限が決められているものはしっかりと確認し、余裕を持って提出しましょう。
親が学費を払えなくなったら
これまで親に学費を払ってもらっていた学生が、家庭の経済状況の変化で親が学費を払えなくなってしまうこともあるでしょう。
「大学をやめなくちゃならないの?」と暗い気持ちになってしまうかも知れませんが、まだまだ諦めるのは早いです。
奨学金に申し込んだり、休学して学費を稼いだりと、学費を工面する方法はあります。
在学中でも奨学金などに申し込める
最も多く利用されている日本学生支援機構の奨学金には、高校3年生の時点で申し込む「予約採用」だけでなく、大学入学後に申し込める「在学採用」があります。
在学採用の場合は、大学ごとに日本学生支援機構から与えられている枠数が異なりますが、在学中に奨学金をもらい始めることができるので、経済状況に変化のあった学生にとっては有り難い制度です。
第1種、第2種共に申請することができますが、募集は毎年1回春のみとなりますので、申請期間に間に合うように手続きをしてください。
なお、申請時期になると大学で説明会を行うところが多いので参加してみましょう。
休学して学費を稼ぐのもあり
どうしても学費が払えない場合は、思い切って休学し学費を稼ぐという方法もあります。
休学なので大学に在籍したままとなり、休学期間が明ければ復学できます。
大学の休学は、病気や経済的な理由など、やむを得ない事情がある場合に認められている制度で、「休学の理由の証明書」を用意したり、教授の許可が必要な場合があったりするため、手続きもれのないよう大学に確認してみましょう。
ただし、休業をするに当たっては注意点があります。
休学期間は大学によって異なり、2年~4年となっている大学が多いようです。
また、休学中であっても、全く費用がかからないわけではなく、半期ごとに数万円の費用を支払わなければなりません。
どうしてもお金が必要な時は
この記事を読まれているのは、学生ご本人だったり親御さんだったり…ということになると思いますが、そのどちらの場合でも、「お金が工面できなく大学に在学することさえも危うい…」というケースも想定されます。
ここからは、そんな急場をしのぐ方法についても幾つか紹介します。
カードローン
最もスピーディーにお金を用意するには、消費者金融などのカードローンを利用する方法があります。
カードローンには消費者金融系・銀行系・信販系の3つがありますが、銀行系カードローンは2018年から即日融資が不可となっています。
急ぎでお金を用意するならアコムやプロミスなどの消費者金融、そしてオリックスクレジットなどの信販系カードローンのみということになります。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
クレジットカードのキャッシング
少額、かつ短期で返済できるなら、クレジットカードのキャッシングも利用できます。
ただ、先ほどの消費者金融カードローンと同じく、クレジットカードのキャッシングでは実質年率で15%~18%の利息が発生しますので、できるだけ早期に完済することがポイントとなります。
不要品を売る
1万円~5万円程度のお金を用意するなら、不要品を売る方法もあります。
ブランド物のバッグや貴金属を持っている場合はそれなりの金額を用意することも可能です。
また、「そんな高価なものはない…」という場合でも、メルカリなどでコツコツと出品を続ければ、2~3万円くらいならすぐに用意することも可能です。
親に頼る
学生が自分の親に…、親が自分の親に…という感じで、身近な人にお金の援助をお願いすることもできると思います。
ただ、忘れてほしくないのは「大学は義務教育ではない」と言う点です。
したがって、たとえ親からの援助であっても、返済できるようになったら、少しずつでも返済されることをおすすめします。
奨学金に関するみんなの疑問
晴れて奨学金の貸与を受けることができた場合でも、当初申請した金額では足りなくなるといったことも考えられます。
実際Yahoo!知恵袋でもこんな質問が投稿されています。
ベストアンサーや他の回答にもあるように第1種の選考に通ることはなかなか厳しいため、まずこちらを残すことを前提に、奨学金の増額を検討すべきでしょう。
しかし奨学金は借金です。
そのため卒業後の自分の生活や人生をしっかりと考え具体的な返済計画が必要です。
「卒業後は働きだすから何とかなる」ではなく、現代の平均年収や生きていくために必要なお金を具体的に考えれば、奨学金の返済は大きな足かせとなることが分かります。
今のことだけではなく将来もしっかり見据え、奨学金を借りるようにしましょう。
まとめ
今回は、進学に必要な学費、そして利用可能な奨学金について幾つかの情報をお届けしました。
奨学金については、利用できる金額がいくらか…?ということも気になりますが、一方で奨学金が返済できなくなった若者が貧困化している実態等、闇に隠れた問題もたくさんあるようです。
いずれにせよ、今回の記事でもご紹介した通り、大学は義務教育ではありません。
本当に自分が行きたい大学なのか?目標を達成するために必要な勉強なのか?ということを自問自答して、必要なお金を必要なだけ借りる…というのが最善の選択と言えるのかも知れません。
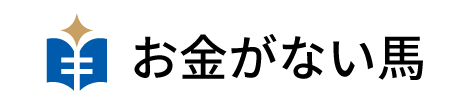

























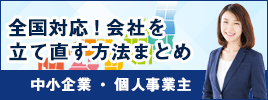

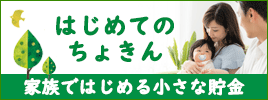


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。