障害年金の請求における問題点
世の中では、年金は将来支給されないのではないだろうかという漠然とした不安があります。
また、今回、出ました5年に一度の財政検証は厳しい結果が出ています。
しかし、給付額の半分は税金でまかなわれていますし、事務処理費用は全額国庫負担です。
また、年金積立金が全体で約160兆6000億円(2019年6月末現在)あります。
たとえ所得代替率が50パーセントを下回ることとなったとしても、今後も変わらず年金は生活保障の柱となることは間違いありません(国家財政が破綻すれば別です)。
さて、年金には大きく分けて老齢年金、遺族年金。
障害年金の3つがあります。
老齢年金は、加齢により労働能力が失われた場合の生活保障です。
遺族厚生年金は、一家の働き手を失った場合にその収入で生活を維持していた遺族の生活保障です。
遺族基礎年金は、18歳までの(障害を有する場合には20歳までの)子の福祉に配慮した年金です。
そして障害年金は、病気やけがで労働能力を失った場合の生活保障になります。
今回は、障害年金の社会保障法の中での位置づけと、請求する際の注意点について考えてみたいと思います。
障害年金の社会保障法の中での位置づけ
日本国憲法27条1項では、「すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う」、と規定します。
これは、労働能力があるのならば働いて生活を成り立たせ、労働の意思も能力もあるのに仕事が見つからない場合には、国家が助力しようとする趣旨です。
これを実現するために、雇用保険法があります。
では、労働能力が病気やけがで失われている場合にはどうするのでしょうか。
日本国憲法25条2項では、国に対して社会保障の向上及び増進をする努力義務を課しています。
それを受けて制定された健康保険法・国民健康保険法を使って病気やけがを治すことが第1です。
この間、労務不能の状態になっている場合には傷病手当金が支給されることとなります。
ただし、傷病手当金は、国民健康保険法では任意規定となっておりますので保証されない場合が多くあります。
傷病手当金は、短期の生活保障として支給開始から1年6ヶ月支給されることとなります。
厳密に言えば違うのですが、障害年金はこの1年6ヶ月を超えて労働能力が失われた状態である場合が守備範囲となります。
すなわち障害年金は、長期の生活保障となります。
このように見てきますと日本国憲法の下では自助自立を基本とし、労働能力が失われた場合に少しのお金を出し合って助け合う保険の方式を利用した健康保険法・年金保険法(共助)があり、それで生活が成り立たない場合に日本国憲法25条1項に基づく最後のセーフティネットである生活保護法(公序)があります。
したがって、障害年金で生活が成り立たない場合には生活保護を併給することとなります。
障害年金には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)があります。
これに加えて、障害基礎年金には子の加算が、障害厚生年金(1級・2級)には配偶者加算がつきます。
また、障害厚生年金(1級・2級)が支給される場合には、同時に障害基礎年金も支給されます。
障害厚生年金は報酬比例の年金のため、加入期間が300月に満たない場合には300月加算され、3級の場合には最低保障もあります。
提出書類についての問題点
次に、障害年金を請求する際の問題点について考えてみます。
通常、請求する際には請求書、診断書、病歴就労状況等申立書の3点を提出します。
この3つの書類は、障害年金受給要件である初診日要件・保険料納付要件、障害等級要件を判断するための基礎資料となります。
これは、障害年金の受給要件を知らない人でも請求できるように工夫されたものです。
しかしその意味をよく理解していないがために障害年金は、健康保険・遺族年金・老齢年金よりも多くの紛争が発生しています(平成29年度(再)審査請求受付状況では、総計1457件のうち障害年金は1106件に及びます)。
この3つの提出資料について考えてみますと、請求書はいかなる病気やけが(請求傷病)で、いかなる請求をするのか(請求方法)を明らかにする役割を持ちます。
障害年金受給要件の審査は、請求書に記載された請求傷病と請求方法に対して行われます。
そして、診断書は請求書に書かれた請求傷病の初診日と障害等級を判断するための重要な資料となります。
初診日証明のためには、このほか受信状況等証明書や第三者証明などを使うことがあります。
保険料納付要件は保険者のもつ保険料納付記録で判断することとなりますので、保険料納付要件を満たせない場合には初診日を見直すか、保険料納付記録に誤りがないかを確認することとなります。
さて、病歴就労状況等申立書ですが、これは請求人が書いたものですので信用性がありません。
障害年金受給要件を判断するための客観的な資料ではないからです。
それゆえに診断書が障害認定日と請求日現在の障害の状態を表すことからこの時点との間に病歴就労状況等申立書と論理的整合性が認められるのならば、発病時からの線全体に信用性を認めることとなります。
請求書の請求傷病、診断書に記載された内容、病歴就労状況等申立書に記載された内容の論理的整合性は厳しく問われます。
例えば、医師の判断として日常生活は一人ではできないとされていても、同居者なしの一人暮らしをしている場合には日常生活は一人でできると判断されます。
請求書・診断書・病歴就労状況等申立書は記載内容を単独で見た場合には問題がなくても、それぞれを読み比べてみると論理矛盾を来すことがよくあります。
細心の注意を払って作成するようにしてください。
障害年金の受給要件を証明する上での問題点
次に、障害年金受給要件について少し考えてみます。
初診日要件は、障害基礎年金が支給されるのか障害厚生年金が支給されるのか、初診日の前日においてその前々月までに保険料納付要件を満たすのか、初診日から1年6月経過後を障害認定日として障害等級を判断することから非常に重要です。
そのため初診日がいつかは激しく争われることとなります。
保険料納付要件は被保険者期間の3分の2以上を保険料納付済期間・保険料免除期間で満たすことができるのか、初診日の直近1年間を保険料納付済期間・保険料免除期間で満たすことができるのか判断されます。
保険料納付要件は、保険料を納付したのか、納付できないときは免除申請しているのかで決まりますので納付できないときには必ず年金事務所に相談するようにしてください。
最後に障害等級要件に関連して、請求件数の多い精神の障害ではよく「働いていたら障害年金はもらえない」と言われることについて考えてみます。
障害等級要件は障害等級1級・2級は労働能力が失われた状態、3級は労働能力が著しく制限されている状態とされています。
労働能力の有無を判断する1つの資料として厚生年金被保険者としての資格と標準報酬額があります。
すなわち、給料が出ている状態には労働能力があると判断されるのが原則となります。
しかし、働けることと、労働能力があることとは全く別個の問題となります。
国民年金法にも厚生年金保険法にも障害年金を受給したら働いてはいけないとは書いてありません。
労働能力の判断は、一人で行動できるのか否かを見ます。
そして、回りの手助けをかりて働いているとしてもその手助けがなくなれば働けないのならば労働能力はないことになります。
障害年金の請求は書面審査であることから証明資料とともになぜ働けるのかを示す書面を提出しなければ労働能力はあると判断されてしまうこととなります。
これが、働いていたら障害年金はもらえないといわれていることの核心になります。
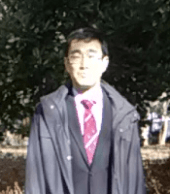
社会保険労務士
深山元幸(みやま もとゆき)
現在、障害年金の裁定請求・審査請求・再審査請求を専門にお手伝いさせていただいております。
元々は社会保険労務士になるつもりはありませんでした。私は、旧司法試験を自力で、20年間最後までやり抜いてきました。学問は衣食住たりて初めて成り立つ高価なものです。そのため、試験勉強と仕事との両立を図るために様々な仕事に就きました。花屋、法律事務所、団体職員、警備員などです。しかし、論文試験を最後の最後まで突破できず試験制度はなくなりました。試験制度がなくなった当初、しばし呆然としましたが何もしなければ転落するのみです。そのため、短期でとれる資格を取れるだけ取り西浦和障害年金OFFICEを立ち上げました。
障害年金を専門に行うメリットは、毎日障害年金を勉強し仕事を行っているので業務をスムーズに行うことができることにあります。そして、法律の勉強とは法律を覚えることではなく、法律の使い方を学ぶことにあります。
法律の使い方とは、問題点を法律要件にあてはめ、法律効果の有無をもって結論を導くという法的三段論法を使いこなすことにあります。障害年金も国民年金法・厚生年金保険法という法律に定められています。これまで行ってきた法律の勉強は全く無駄にはなっていません。
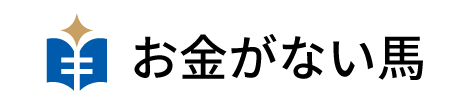























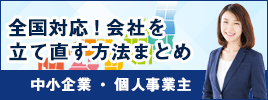

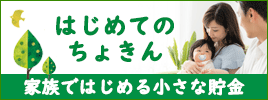


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。