貸金業者とは?リースや銀行とは違う?
貸金業者と銀行の違いはどこにあるのか、急に質問されても出てくる答えは預金業務を行えるかどうかの違いじゃないの?となるのが精一杯ですよね。
しかし貸金業者と銀行の違いは預金関係だけでなく、貸金業者も銀行も「金貸し屋」であることは同じでも、業務形態が全く異なっているのです。
貸金業者について詳しく解説していきたいと思います。
こんなかたに役に立つ記事です
この記事はこんな人に役立ちます。
- 銀行と貸金業者の違いを知りたいかた
- 貸金業者の業務内容を知りたいかた
- 貸金業者の法律による縛りを知りたいかた
これらの人には役に立つ記事になっていますので、ぜひご覧ください。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
貸金業者とは
貸金業者とは、貸金業を営む業者のことを言います。
貸金業者の目的や定義および事業内容など詳細を定めているのは、貸金業法です。
貸金業法が初めて成立したのは、昭和58年のことです。
それ以前は貸金業を営むにおいて特別な登録が必要なく、また事業内容もある意味制限がありませんでした。
しかしそれでは違法な貸付や取り立てが横行してしまうということで、貸金業全体を適正に運営するため各都道府県に貸金業協会を設立し、貸金業を営む業者に対して登録制度を設けるようにしました。
当時の名称は「貸金業の規則等に関する法律」という長い法律の名称でしたが、貸金業法が改正されるちょっと前、2007年12月に法律の名称を「貸金業法」と定めてあります。
それと同時に、各都道府県にあった貸金業協会を一本化し、日本貸金業協会として設立しました。
また、信用情報機関も各都道府県にあったのですが、それも統合しJICCとして設立してあります。
平易な言葉で言い表せば、貸金業者は反復継続の意思を持ってお金を貸す業者及び人のことを言い、貸付の相手が不特定多数である必要はありません。
業態が法人なのか個人なのか、またお客さんが多い、少ないで判断するものではないということですね。
しかし、特定の人に対してお金を貸すことを反復継続して行うと、その相手がたとえ親戚であろうとも貸金業を営んでいると判断されてしまいます。
貸金業法における貸金業とは
貸金業法第2条によると、貸金業とは次のようなことを業としていることを言います。
- 単純にお金を貸し付ける
- 金銭貸付の媒介
- 手形の割引
- 売渡担保などによってお金を貸し付ける
法律というのはわかりにくい用語を使いますよね。
一見難しい用語でも、簡単に説明すれば次のように言い換えることもできるでしょう。
- 他人にお金を貸すこと
- お金を貸す際に仲介をすること
- 手形割引による貸付
- 譲渡担保による貸付
※売渡担保と譲渡担保は同じ意味で、具体例を挙げると自動車を担保にお金を借りる際、先に所有者を貸金業者に異動してからお金を貸すことを言います。
なぜそのようなことをするかと言うと、先に名義を変えてしまえば相手がお金を返さない場合に面倒な手続きをとることなく、担保を処分できるからです。
基本的に貸金業とは以上のような方法を以って、お金を他人に貸すことを事業内容とする業者のことを言います。
貸金業者ってたとえばどんな業者?
貸金業者とは、簡単に言えば、銀行や信用金庫など預金業務を行わずに融資をすることを商売にしている業者です。
具体的には、消費者金融や信販会社などが挙げられます。
これらの業者は、預金を融資によって運用している銀行などの金融機関と異なり、自己資金や借り入れによって資金調達を行い、それらの資金を融資によって運用しています。
そのため、顧客の預金を返還する義務がある銀行と比較して、リスクの高い融資を行うことができてしまいます。
このため、無理な貸付を行うことがないよう、貸金業法という法律によって、業務内容が詳細に定められているのです。
クレジットカード会社は貸金業者?
クレジットカード会社は、貸金業者の登録をしているのが普通です。
ただし、クレジットカードの利用方法によって、貸金業法に該当する行為かどうかは異なりますので、クレジットカード会社の行為が全て貸金業法に適用するのかと言えば、そんなことはありません。
一体どういうことなのでしょうか?
詳しく解説していきたいと思います。
カード決済とキャッシングの違いがある
クレジットカードには、一般的にお買い物に利用するショッピング枠があります。
こちらは、実際にお金を借りているわけではありませんよね?
買い物代金をカード会社に立て替えてもらっているだけですので、ショッピング枠の利用は貸金業法対象外です。
このため、クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象ではないので、年収の3分の1を超える枠の作成も可能です。
ショッピング枠だけのクレジットカードを販売するのであれば、その業者は割賦販売法という法律に則って業務を行うことになります。
したがって、これだけであれば貸金業者として国や都道府県に登録をする必要はないのです。
また、ショッピング枠の管轄は経済産業省であり、金融庁管轄の登録貸金業者には当たりません。
しかし、ほとんどのクレジットカードでは買い物ができる枠の他に、ATMやCDから現金を借りられるキャッシング枠を付帯できます。
キャッシング枠は、モノを購入するのではなく、実際に現金を借りるための機能です。
つまり、カードローンと同じになります。
このため、キャッシング枠も作成できるクレジットカードを発行する会社は、国や都道府県に登録貸金業者として登録をしなければならないのです。
そして、ほとんどすべてのクレジットカードにはキャッシング枠を付けられるようになっていますので、クレジットカード会社は貸金業者として登録をしていることが一般的なのです。
貸付業務をしても貸金業者でない者
貸金業務を行っていたとしても、貸金業者とならないケースがあります。
公共機関がお金を貸付する社会福祉協議会がありますね。
または国が行う奨学金貸付など、他人に対してお金は貸すものの、貸金業者ではないと認められることがあります。
貸金業法第2条によれば、貸金業者から外れる貸金業務は次のようになります。
- 国や地方公共団体がお金を貸すこと
- お金を貸し付けしていても他の法律に規定があるもの
- 商品の売買や運送、保管に対して付随してお金を貸すこと
- 会社内で社員に対してお金を貸すことなど
銀行や信金・JAなどがお金を貸すことは、銀行法や信用金庫法が適用されることから、貸金業法が適用されません。
また保険会社が契約者貸付として行う事業は、付随してお金を貸すことになりますので、貸金業者とは言いません。
同じように、会社内で従業員が給料の前借りと言ってお金を借りることも貸金業法は適用されず、お金を貸した会社も貸金業者とはなりません。
貸金業者と認められる者
貸金業法が適用される貸金業者は、ノンバンクと言われる業者が該当します。
たとえば以下のような業者のことを言います。
- 消費者金融業者
- クレジットカード会社(キャッシング部門)
- 一部のリース業者
- 抵当証券業者
- NPOバンク
- クラウドファンディング
消費者金融業者が貸金業法の適用を受けることは、ご存知の人も多いかもしれません。
また、クレジットカード会社のキャッシングについても貸金業法が適用されることから、総量規制の対象になることも次第に浸透しつつありますね。
意外なのは、ファイナンスリースのようなリース商品を取り扱っているリース業者が、貸金業法の適用を受けるということです。
すべてのリース会社が貸金業者となるわけではなく、一部のリース会社に限定され、企業へ融資することを事業内容として行なっていると、貸金業法の適用を受けます。
抵当証券業者とは、不動産を担保にお金を貸す業者のことを言います。
最近では、非営利目的のNPO法人が低金利で社会貢献活動を行っている企業に対して融資していることがありますね。
これも貸金業者です。
またクラウドファンディングと称し、ソーシャルサービスの一環でクラウドファンディングを商品化している企業が、ベンチャー企業などに対してお金を融資することがあります。
これらの場合も貸金業者として貸金業法の適用を受けますので、注意が必要ですね。
ただし、NPOバンクやクラウドファンディングは個人に対して融資することはありません。
企業に対して事業資金を融資することになるため、総量規制の対象とはなりません。
同じようにリース会社が企業を融資することも、総量規制に該当する貸付にはなりません。
不動産担保にしても同じことが言えます。
総量規制の対象となるのは、消費者金融業者及びクレジットカードのキャッシングに限定して考えても差し支えはないでしょう。
銀行は貸金業者ではない
ちょっとここで、法律を引っ張り出してきましょう。
実は貸金業法には貸金業者の定義があって、貸金業者とは金銭を貸し付けするまたは金銭貸付の媒介をすることを生業としている業者のことを言うのです。
じゃあそれなら銀行も同じじゃないの?となりますが、貸金業法第2条には貸付を生業として行うについて、他の法律の規定が定められている者は貸金業者ではない、とというようなことが書いてあります。
うーむ、ちょっと難しすぎる、という人のために要約してみましょう。
つまり銀行はお金を貸すことについては同じでも、銀行は銀行で銀行法という法律によって営業が規定されているため、お金を貸すことを生業としていても貸金業者とは言わない、と言うのですね。
貸金業者は貸金業法によって営業が規制され、銀行は銀行法によって営業が規制されているために、貸金業者というくくりには入らないのです。
貸金業者は基本的にお金を貸すことを主目的としているため、お金を貸し付けることについての法律はかなり厳しいものです。
貸金業法第21条では、借金を取り立てるにしても時間帯が8時から21時までと決まっていますし、多人数で自宅に取り立てに行ってはならない、家族に借主本人に代わって借金を返済してほしいとの強要もできません。
借主の生活の平穏を見出すような言動や態度をとってはいけない、乱暴な言動や態度によって相手を怖がらせてはいけないなど、徹底して借主を保護しなければならないことを、貸金業法では定めています。
「貸金業者は金利が高い」「銀行カードローンは金利が低い」とは限りませんから、金利の高い低いで貸金業者と銀行を比べるのは間違っています。
ポイントは誰を保護するか、ということです。
貸金業者は借主の利益を保護しなければならないのに対して、銀行は銀行法第1条によって預金者を保護し、金融の円滑と共に国民経済の健全な発展を主目的としているのです。
預金者を保護する観点にたてば、受信行為を行っている銀行は、リスクの高い融資を行って預金者の預金を棄損するわけにはいきません。
このため、銀行は銀行法という法律によって、貸金業法の規制を受けなくても、厳しく審査を行うように定められているのです。
借主を保護するか預金者を保護するかで、貸金業者と銀行の違いが出てくるわけですね。
◆電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法
◆電子政府の総合窓口e-GOV 銀行法
銀行カードローンも貸金業法の対象外
上述したように、銀行は銀行法のもとで事業を行っているため貸金業法の影響を受けないので、銀行が取り扱っているカードローンも、当然貸金業法の対象外となります。
貸金業法の対象外ということは、総量規制を気にせずに融資を行えるということなので、銀行カードローンでは理論上年収の3分の1を超す金額での融資も可能です。
「理論上」という表現をしたのは、近年銀行に対して過剰融資を行っているとの意見が多く、銀行でも融資に関して自主規制を行っているためです。
自主規制の内容は総量規制に基づいたものになっているので、銀行カードローンも総量規制の対象となっていると考えておいたほうがいいかもしれません。
とは言え、総量規制とは異なり法的拘束力のある規制ではないので、融資対象者として的確であると認められた場合は、年収の3分の1を超す金額で融資を受けられる可能性はもちろんあります。
貸金業者と銀行はお金を貸すことは同じ
貸金業者と銀行の違いを法律云々でご説明する前に、金貸し屋として貸金業者と銀行には何か違いがあるのでしょうか。
カードローンでお金を借りる立場からすれば、貸金業者も銀行も同じに見えますね。
お金を借りるには申し込まなければならないし、審査を受けなければならないことは同じです。
もちろん、審査に通らなければお金を貸してくれないのも一緒ですね。
貸付金利は違っていたとしても利息をつけて返済しなければならない、返済期日に遅れれば遅延損害金を支払わなければならない。
支払期日に遅れると督促の電話がかかってくるし、長期間滞納すれば金融事故として信用情報機関に登録されるなど、お金を借りる点については、はっきりとした違いを見いだすことは難しいですね。
返済能力がなければ貸してもらえない、金融事故歴があっても貸してもらえないなども含めて、お金を貸すことについての違いはそれほどありませんよね。
お金を借りるとなったら、銀行カードローンに申し込むか消費者金融に申し込むかどちらかになるのが普通ですね。
一部報道によると銀行は消費者金融になったのではないか、と記事まで出るくらいですから、世間的な目で見れば貸金業者と銀行は同じではないか思われているのかもしれません。
◆Yahooニュース 銀行の皮をかぶった消費者金融
貸金業者と銀行の決定的な違い
貸金業者の貸付は総量規制対象ですが、銀行による貸付は総量規制の対象ではないというのが、お金を借りる点で大きな違いですね。
それはなぜかと言うと、銀行の貸付金利が低く過剰融資にはならないからというのが理由ですが、今頃になって銀行の過剰貸付が問題になるとは思ってもみなかったことでしょう。
◆産経ニュース 銀行カードローン調査へ 金融庁、過剰融資の実態把握
銀行カードローンは、銀行が顧客の預金を簡単には棄損できないため、総量規制の適応外となっています。
しかし、消費者金融への総量規制適用以降、消費者金融でお金を借りられなくなった人に対して銀行が過剰に融資を行い、社会問題になってしまったのです。
銀行は顧客の預金を簡単には棄損できないため、保証会社の保証を付けてカードローン融資を実行します。
そして、保証会社は消費者金融やローン会社などの貸金業者です。
貸金業者は、銀行で融資を受けることができなくなった代わりに、銀行カードローンの保証によって収益を確保するようになりました。
「消費者金融の迂回融資」などという批判が強まり、今は銀行も自主規制によって、年収の3分の1を超える融資を行っていません。
また、2018年から銀行カードローンの融資前には、警察庁の反社会的勢力データベースへの照会が必要になりました。
この確認には最短でも1営業日は必要になるので、銀行カードローンは即日融資も不可能になりました。
総量規制対象か否かという法律上の違いは今は実質的にはなくなり、銀行と貸金業者の決定的な違いは、金利と融資スピードという2点に絞られたと言ってもよいでしょう。
貸金業者の知っておきたい4つの豆知識
貸金業者に関して理解をしておきたい知識について、ご説明します。
貸金業者の変遷や、ヤクザや闇金との違いについて、しっかりと理解をしておきましょう。
ここを理解しておくことで、間違って違法業者からお金を借りてしまうというリスクを軽減できます。
①貸金業者はむかしは高利貸しと言われた
貸金業者は貸金業法が改正される前は世間から、「サラ金」や「高利貸し」と差別的な扱いを受けていました。
確かに金利は、銀行に比べて高かったことは間違いありません。
出資法改正直前の上限金利は年29.2%と高く、その前は40.004%や54.75%などかなりの暴利を貪っていたことも否定できません。
借金の取り立てにしても借主を精神的に追い込み、自殺させることによって生命保険から借金を回収するということも平然と行なっていました。
そのため、当時の行政監督庁は貸金業法を制定し、貸金業者の営業を規制することを始めたのです。
当時の銀行は個人向け貸付カードローンを扱っていませんでしたので、なおのこと貸金業者に対して悪いイメージを持つ人も多かったですね。
そのために貸金業法はいくどとなく改正され、出資法も上限金利を段階的に引き下げ、貸金業業界全体の引き締めを図ったのです。
これらの法律改正の結果として、今は貸金業者は合法の金利の範囲内で業務を行っていますし、暴力的な取り立てを行うことができないようになりました。
②貸金業を営むには登録が必要
貸金業法第3条により、貸金業を営むには登録をしなければなりません。
貸金業者の規模によって内閣総理大臣から登録を受ける、または事業所を置いてある都道府県の知事によって登録を受けなければなりません。
登録を行わずに貸金業を営むことは許されていませんので、正規の貸金業者とは登録業者のことを指し、無登録業者はいわゆる闇金業者になります。
また登録は1回行えばそれで良いというわけではなく、3年ごとに更新を受ける必要があります。
更新を受けなければ、貸金業者とは言えません。
うっかりして更新申請を行わなければ、たちまち無登録業者となってしまい、世間でいうところの闇金業者になってしまいます。
登録を行った貸金業者は管轄官庁の厳しい監督を受けることになり、法律遵守で業務を行うことを監督されています。
法律を犯して業務を行っている貸金業者は、登録取り消しとなることもあります。
その場合は、5年間は貸金業者として登録を受けることはできなくなり、貸金業者にとっては死活問題になりますので、登録貸金業者は金融庁の監督で処分を受けないように、法律に則って業務を行っています。
つまり、登録貸金業者からお金を借りる場合には、安全にお金を借りられると言えるでしょう。
昔のように膨大な高金利を設定されることも、脅迫に近い取り立てを受ける心配もありません。
③反社会組織は貸金業を営業できない
貸金業者の登録の申請にあたっては細かな取り決めがあり、登録申請を行えば誰でも貸金業者になれるというわけではありません。
法律を抜粋すれば、貸金業法に違反し登録業者として取り消され、取り消しの日から5年以上経過しないと申請ができません。
また犯罪などを起こし禁固刑以上の罪を負い、刑の執行終了から5年を経過しないと、同じように貸金業者としての登録はできません。
重要なことは貸金業者に反社会組織、たとえば暴力団員関係者が貸金業を行うことは認められておらず、貸金業登録業者として申請するためには、暴力団員でなくなった日から5年を経過しなければならないということです。
もちろん登録する人が一般人だとしても、従業員に暴力団員を雇うことや、貸金業務の補助をさせること、または従事させるおそれのある場合があると認められる場合は、貸金業は営めません。
したがって、正規の貸金業者が反社会組織であることはありえず、暴力団関係者が関与することはありませんので、消費者金融業者からお金を借りることに恐れを持つ必要はまったくありません。
④無登録業者は厳しい罰則がある
貸金業法第11条により、無登録による貸金業の営業は固く禁止されています。
また、名義を他人に貸すことも許されていません。
もし無登録で貸金業務を営んでいたことがわかってしまうと、刑事罰として摘発を受け、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、およびその両方を刑として受けなければなりません。
逮捕要件は現行犯でなくてもよく、貸付の実態が認められれば無登録業者は即罪を負うことになります。
また広告の表示や勧誘も行なってはいけないため、インターネットで宣伝広告しているような無登録業者は、十分に逮捕される要件を満たしていることになりますね。
さらに、広告の内容についても規制があるので、インターネットや街中の看板で「審査なしで融資可能」などと、審査結果という不確定な問題を確定的に伝えているような広告は、その時点で違法になります。
このような広告を行っている業者は高い確率で闇金ですので、絶対に取引をしないようにしてください。
銀行の知っておきたい2つの豆知識
銀行はカードローン融資をここ数年強化してきましたが、今はその銀行の方向性について批判の声が大きくなっています。
結果的に、銀行のカードローン融資は縮小傾向にならざるを得なくなっています。
銀行がカードローン融資を推進した背景について、少し詳しく解説して行きたいと思います。
①銀行カードローンの自主規制
以前は、銀行の貸付金利は貸金業者に比べればかなり低いものでした。
個人向け小口融資に力を入れることはなく、主に住宅ローンや教育ローンなどの目的ローン、および事業者向け融資に熱心で、不動産などを担保に取ることや連帯保証人を立てての融資がメインでした。
昭和時代のバブル景気の記憶のある人ならおわかりかと思いますが、銀行は大企業だけではなく中小企業にもどんどん融資を行い、設備投資資金として事業拡大をさせたのです。
しかしバブル景気が終わると、経済状況は一変し大企業を中心として海外へ拠点を移すなど、大企業の下請けを行っていた中小企業は仕事を失い、借金を抱えたまま途方に暮れていたのです。
銀行は預金者保護をしなければならない立場にあったため、借金を支払うことのできない企業に対して、貸し渋りや貸し剥がしを行うようになりました。
中小企業が仕事を失って倒産する前にできるだけ借金を回収しておこうと、多くの銀行が容赦ない取り立てを行ったのです。
もちろん銀行は担保を取って融資する、連帯保証人をとって融資する契約を結んでいました。
そのため、返済できない企業は不動産を競売にかけられ、設備投資した機械類も持ち出され、連帯保証人に対しても裁判を起こすなど、結構えげつない取り立てをしていたのです。
貸し剥がし問題や銀行の取り立て問題は一時的にニュースにはなりました。
しかし、借金は返さないほうが悪いのだ、計画性もなくお金を借りたほうが悪いのだとの流れになるに従って、銀行の責任は問われることなく、会社は倒産し自殺に追い込まれた人も多かったことでしょう。
銀行の貸付業務は適正だったのかと言うと、無担保無保証で貸していた消費者金融と比べると、同じ穴の狢ではなかったかの気持ちが強いですね。
企業向け融資が伸びなくなってしまったので、銀行は個人ローンを拡大させる方向性に梶を切ります。
しかし、バブル期の経験から、銀行は極度に不良債権を恐れるようになり、個人向け融資には保証会社の保証をつけるのが一般的でした。
そこで登場したのが、今のような銀行カードローンです。
折しも、貸金業法が改正されたタイミングだったため、銀行は貸金業者の保証をつけたカードローン融資をどんどん拡大します。
しかし、実質的に審査を行っているのは保証会社である貸金業者ですので、銀行は営業して案件を取るだけが仕事になります。
銀行員に審査能力がなくなったと言われるのは、このくらいのタイミングからです。
先ほど述べたように、今は銀行カードローンの過剰融資への批判が強まったことによってカードローン融資は自主規制を行っているので、今後、銀行はカードローンなどの高金利商品で利益を出すことは難しくなっています。
銀行経営が厳しいと言われるのは、まさに、このような流れの中で企業に対しても個人に対しても融資をする先がなくなってしまったためで、今後の銀行経営は岐路に立っていると言えるでしょう。
②銀行の参入要件はハードルが高い
細かい話にはなりますが貸金業を営むには現在の法律で、純資産が5,000万円以上なければならないのに対し、銀行は参入するのに純資産が10億円を下回ってはならないと、かなりハードルは高いです。
銀行は簡単には参入できない業種ですので、楽天やSBIなどの大手企業しか新しい銀行を作ることが難しいのです。
一方、貸金業者は参入障壁が低いので、名前を聞いたことがないような中小の消費者金融が無数に存在するのです。
貸金業者の主な義務について
それでは、貸金業者へ話を戻しましょう。
貸金業者の業務内容は、貸金業法によって詳細に規定されています。
具体的にどのようなことが法律によって定められているのでしょうか?
具体的には以下のようなことが定められており、この決まりにしたがって、貸金業者は業務運営を行っています。
- 審査
- 取立行為
- 貸金業務取扱主任者
- 適用金利
これらが法律によって定められているため、昔と比べて今は貸金業者からお金を借りても安全だと言えます。
それぞれについて具体的に解説していきます。
貸金業者は返済能力の調査を行う
正規の貸金業者はお金を貸し出しする際に審査を行いますが、その際に必ず行わなければならないのは、信用情報機関からデータを取得することです。
カードローンの借り入れ希望者が単に借り入れ申し込み書に書いただけでは、書いてある内容が正しいのかどうか判断できません。
そのため貸金業者は、信用情報機関へ照会し総量規制に抵触していないか、返済状況はどうか、金融事故情報はないかなど審査を行うわけです。
無登録業者は、信用情報機関に加入できません。
そのため闇金業者からお金を借りたとしても、信用情報を取得できないのです。
だから誰にでもお金を貸す代わりに、金利がべらぼうに高いのです。
正規の貸金業者は、資金需要者の保護をしなければならない義務を負っていますので、過剰な貸付はしてはならないことになっています。
また資金需要者から助言を求められた場合は適切に対応しなければならず、場合によっては借金の相談を行うことができる団体、たとえば法テラスなどを紹介することもあります。
貸金業法によって取立て行為が規制
貸金業法が改正になってからより厳しくなったのが、貸金業者による取り立て行為です。
相手が返済しないからと言って定められた時間以外に、正当な理由なく電話することや、訪問をすることは固く禁じられています。
また近隣住民に対して聞き込みを行うことも禁止され、お金を借りた相手の生活を乱すようなこともしてはいけません。
2人以上で訪問することも、相手が貸金業者に畏怖を感じさせることから、慎重に行うことが求められています。
もちろん契約者本人以外に貸借関係があることを他人に言いふらすことは、法律違反となるため行うことはありません。
借金が返せないからと言って、他社からお金を借りて返済しろ、のようなことは強要できませんし、大声を出すことも暴言を吐くことも許されていません。
貸金業者が自宅に訪問した際に、相手からすぐこの場を立ち去るように求められた場合は、即刻応じなければなりません。
お金を返さないからと言って玄関などに張り紙、立て看板を建てることも禁止されています。
借り入れ本人以外の家族に対して債務の弁済を求めることも、してはいけない行為です。
以上のように正規の貸金業者は厳しい貸金業法によって、事業内容や行動内容が定められています。
昔のテレビであったような怖い取立ては、登録貸金業者は絶対に行いません。
このような取り立てを行って金融庁へ垂れ込みがあった場合には、貸金業者は金融庁から厳しい行政処分を受ける可能性があり、貸金業者としてはそちらのほうがリスクが高いので、法律遵守で取り立てを行っているのです。
貸金業務取扱主任者の設置
貸金業務を営む場合は、事業者ごとに従業員50人に対して最低1人の割合で、貸金業務取扱主任者を設置しなければなりません。
貸金業務取扱主任者は貸金業に関する必要な知識を持ち、他の従業員に対して指導する立場にあります。
万が一従業員が貸金業法に違反するようなことをしてしまうと、貸金業務取扱主任者の責任問題に発展する可能性もあり、その役割は重要です。
試験は全国で年に1回程度行われ、合格率は30%未満と決して高い数字ではありません。
資格を持った主任者は、貸金業業務を適正に行えるよう、従業員に対して社内講習会を開くこともあります。
適正に信用調査を行っているのか、書面をきちんと交付しているのか、顧客台帳を正しく記載しているのかなど、細かく管理しなければならないのも貸金業務取扱主任者の使命です。
貸金業務取扱主任者資格は国家資格ですので、国家資格を持った人が必ず設置されていると考えれば、貸金業者からお金を借りることも安心ではないでしょうか。
貸付金利は利息制限法に則る
以前の貸金業業者は貸付金利を出資法に準じて行なっていましたが、貸金業法が改正になってから、利息制限法に則って貸付金利を定めなければならなくなりました。
出資法で定められている上限金利は年20.0%ですが、利息制限法の金利は貸付金額によって細かく分けられています。
- 10万円以下の貸付:金利年20.0%
- 10万円超100万円未満の貸付:金利年18.0%
- 100万円以上の貸付:金利年15.0%
以上のように上限金利が設定されています。
貸金業法が改正される直前の上限金利は、出資法により年29.2%でした。
貸金業者は、出資法の金利によって金銭消費貸借契約書を結ぶことが許されていました。
ほとんどの貸金業者が、利息制限法上の上限金利以上出資法以下のいわゆる「グレーゾーン金利」で融資を行っていました。
しかし、貸金業法改正によってグレーゾーン金利は廃止され、貸金業者の貸付利率は利息制限法の上限金利とされました。
これまでグレーゾーン金利による利息を支払っていた場合には、その利息は過払い金となり、過払い金請求が活発に行われるようになったことはご存知の通りです。
銀行カードローンの金利が低いといっても、銀行によっては金利が年18.0%に設定されているところもあります。
標準的な銀行カードローンの金利は年14.6%前後であることを考えると、それほど消費者金融カードローンの金利が高いとは言えません。
また金利が低いからといって多くの金額を借りてしまっては、支払う利息は多くなってしまいます。
消費者金融カードローンにしても銀行カードローンにしても重要なのは、計画的に無理のない範囲でお金を借りるということですね。
貸金業者についての気になるQ&A
では最後に、貸金業者についてよくある質問に、Q&A形式でまとめてお答えしていきましょう。
①金融業と貸金業の違いとは?
A.融資のみを行うのかどうかと考えると分かりやすいでしょう
金融業は、融資だけでなく預金や積金など金融に関わる様々な事業を行います。
一方貸金業は、その名の通り「貸金」、つまり融資事業のみを行います。
法律を用いて説明すれば、より細かなことまで説明が可能ですが、実際に利用する際にはそこまでしっかりと理解する必要はないので、これぐらいのイメージで考えておくといいでしょう。
②貸金業者の資本金はどこから?
A.自己資金や借り入れによって調達しています
事業者自身の自己資金で用意している場合もありますし、借り入れを利用して調達している場合もあります。
大手の貸金業者ともなると、かなりの金額を動かしていますので、借り入れによって調達している金額の割合が大半を占めるでしょう。
③貸金業者になるのに必要な資格とは?
A.貸金業務取扱主任者の資格が必要です
貸金業を営むためには、従業員50人に対して最低1人の割合で貸金業務取扱主任者が必要になります。
これは、マンション管理業者で管理業務主任者が必要なように、法律で決められていることです。
自分自身が貸金業者で働く場合には、必ずしも貸金業務取扱主任者の資格を持っていなければならないというわけではありませんが、持っていたほうが何かと有利には働くでしょう。
④個人貸しが商行為とみなされるのはどんな時?
A.お金を貸すという行為を反復・継続して行っている時です
友人同士の「今月ちょっとピンチだから1万円だけ貸して」という形でのお金の貸し借りは、商行為には当たらないと判断されるでしょう。
しかしそれが何度も定期的に行われるようだと、商行為と見なされてしまう可能性があります。
たとえ個人間のやり取りであれ、お金の貸し借りには注意したいですね。
⑤SMBCモビットは銀行系カードローンだから貸金業法の適用外?
A.SMBCモビットは消費者金融のカードローンなので貸金業法が適用されます
確かにSMBCモビットは、「銀行系カードローン」と表現されることがあります。
しかしそれは、「銀行と同系列のグループに属している」ということでそう表現されているだけであり、SMBCモビット自体は消費者金融のカードローンなのです。
そのため、SMBCモビットでの融資にはもちろん貸金業法が適用され、年収の3分の1を超える金額の融資は受けられません。
まとめ
貸金業者とは、消費者金融や信販会社などの業者を指します。
銀行や信用金庫などは銀行法や信用金庫法の規制を受けているため、貸金業者ではありません。
2010年の改正貸金業法完全施行以降は、貸金業者の業務内容について、審査や、金利や取り立てや総量規制について詳細な規制が行われるようになりました。
これまで、貸金業者は実質的には国の細かな管理をほとんど受けてきませんでしたが、改正貸金業法によって、銀行並みの厳しい監督を受けることになりました。
貸金業法改正によって貸金業者が苦しむ中、一時、銀行カードローンは融資を拡大しましたが、今は銀行カードローンも年収の3分の1までしか融資を行っていません。
銀行カードローンと貸金業者のカードローンの違いは、以下の違いしかないように思います。
- 銀行は金利が低いが融資までに時間がかかる
- 貸金業者は金利が高いが即日融資も可能
どちらがよいということは一概には言えません。
自分がカードローンに何を求めるかによって、銀行か貸金業者を選択するのがよいでしょう。
取り立てなどの対応は、銀行も貸金業者もどちらも安全です。
タグ:お金の知識


















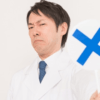

















































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。