貸金業法とは?違反にはどうやったらなるの?
消費者金融などの貸金業者は融資のプロでも、貸金業法法令関係をすべて正しく理解しているとは限りません。勝手な思い込みや誤解によって知らずしらずのうちに貸金業法違反をしているケースも少なくないのです。
今回は誤解や認識不足によって貸金業者が犯しやすい貸金業法違反の例を挙げながら、どのような場合に貸金業法違反となるのかご説明していきたいと思います。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
貸金業法とは
そもそも貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者に対して定められた法律です。
増え続ける多重債務者問題を解決して利用者が安心して借入れができるように平成22年に改正され、総量規制などの新たな法律が定められました。
貸金業法とはどのような法律で、何を目的として制定されたものなのか見ていきましょう。
貸金業法は貸金業者が業務を行うときに守らなければならない法律
貸金業者はお金を貸す際に、一定のルールに基づいてお金を貸さなければなりません。
ルールがないとお金を貸す際に消費者が膨大な金利や取立てに苦しむ可能性があるため、貸金業者の業務について詳細に様々な取決めをしたものが貸金業法です。
貸金業者は金融庁に登録を行い、貸金業法にのっとった貸金業務を行う必要があります。
平成22年に全面改正された貸金業法が全面施行
以前の貸金業法は悪質な取立て、収入に見合わない貸付が合法化されていました。
これによって、お金の借り過ぎによる自殺や家庭崩壊、悪質な取立てや督促などに精神的に追い込まれる人が多発して社会問題となりました。
そこで、これらの問題点を改善するために貸金業法が全面改正され、収入に見合った貸付と法律を遵守した金利、非常識な取立てなどの問題は解決することができました。
貸金業法の対象となる貸金業者とは
貸金業法が適用される業種は銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫以外の預金の取扱いをしていない貸金業社でお金を貸す業務を行っている金融機関すべてです。
具体的には預金業務と貸金業務の双方を取り扱っていない、ノンバンクのことを指します。
そもそも貸金業者とは
貸金業者と聞いてもどのような業者のことを言っているのか分からないという人もいるでしょう。
貸金業者とは消費者金融や、クレジットカードを扱う信販会社なども貸金業に入ります。
貸金業者とは具体的に以下の業種となりますので、参考にしてください。
・消費者金融
個人を対象とした貸金業者です。
アコムやプロミス、アイフルが該当します。
・クレジットカード会社
クレジットカードを発行する会社です。ショッピングのほかに、キャッシングサービスも行っています。
信販会社や銀行系や流通系のクレジットカード会社などが含まれます。
ただし、キャッシング利用ができずショッピング利用のみのカードを発行している企業は、貸金業に登録する必要がありません。
代表的なクレジットカード発行会社は株式会社オリエント・コーポレーションや三菱UFJニコス株式会社などが挙げられます。
・リース会社
利用者が欲しいと思うものをリース会社が購入して、貸し出す会社です。
商品代金はリース会社へ支払うことになります。
リース会社は企業へ融資を行うこともあるので、貸金業者の登録をしている場合もあります。
貸金業者として例を挙げると、昭和リース株式会社や三菱UFJリース株式会社などがあります。
・事業者金融
いわゆるビジネスローンを専門とする事業者向けの融資を行う業者です。
商工ローンと呼ばれることもあります。
事業性資金を扱うため総量規制の対象外です。
ライフティ株式会社やAGビジネスサポート株式会社、株式会社ビジネスパートナーなどが該当します。
・ソーシャルレンディング会社
クラウド・ファウンディングの一種で、お金を借りたい人に対して貸してくれる人をマッチングさせるサービスをする業者です。
SBIソーシャルレンディング、アクシュなどがあります。
・NPOバンク
非営利やボランティアに近い形で、地域の社会福祉のために融資を行う団体です。
未来バンク事業組合、NPO夢バンクなどはNPOバンクと言われています。
銀行貸付は対象外
お金を借りることができる金融機関と聞くと銀行を思い浮かべる人もいますが、銀行は銀行法に基づいて運営されているため貸金業法の対象外です。
しかし総量規制対象外であるため、消費者金融で借入れができない人が、銀行カードローンを利用するようになりました。
その結果、銀行カードローンの過剰融資が問題となり、平成29年より総量規制に準じた自主規制を各銀行で取り入れているようになりました。
自動車ローンや住宅ローンは総量規制の対象外
総量規制には、除外と例外と言った総量規制の対象にならない貸付があります。
その中に自動車ローンや住宅ローンが入ります。
自動車を購入する際には優遇金利のついたクレジットなどがあります。
総量規制が自動車ローンまでを対象とすると、このクレジットも年収の3分の1までしか組むことができなくなってしまいます。
また、信販系の住宅ローンなども存在しますが、自動車も住宅も高額商品ですので年収の3分の1までしか借りることができなくなってしまうと、自動車や住宅を購入できる人が著しく少なくなってしまうことになります。
そのため、いかにノンバンクの貸金業者からの貸付けであっても自動車や住宅ローンの借入れは総量規制の対象外となっており、年収の3分の1を超える借入れも可能です。
また、利用者にメリットがある貸金業法に基づくおまとめローンも総量規制の対象外です。
銀行「系」は貸金業法の対象になる
総量規制やグレーゾーンの撤廃など、2010年の改正によって大きく変わった貸金業法ですが、この法律が適用されるかどうかは対象となる業種が関係します。
貸金業法が適用される業種は法律の名前からもわかるように貸金業者が対象となります。
貸金業者とは、消費者金融、クレジット会社、信販会社などの貸金業者として登録している業者のことをいい、これらの業者は貸金業法が適用されます。
これに対し、銀行の業種は金融業となりますので、金融業者となります。
金融業者ですので、貸金業法が適用されることはなく、銀行は銀行法という法律が適用されます。
このことを踏まえたうえで銀行系カードローンが貸金業法の対象となるのかということについて考えていきます。
銀行系カードローンとは、銀行のグループ会社となっている消費者金融が取扱っているカードローンのことをいい、貸付は消費者金融が行っていることから銀行系カードローンは貸金業法が適用されます。
あくまでも銀行と関係がある消費者金融が取扱うカードローンということで「銀行系」となっているだけとなります。
銀行カードローンは貸金業法の対象外
貸金業法によって消費者金融やクレジットのキャッシングなどは年収の1/3を超える借り入れをすることができなくなっていますが、銀行法には総量規制のような年収に対する借り入れの上限は規制されていません。
ですので、銀行からの借り入れは年収の1/3を超える借り入れであったとしても貸付することができ、銀行が融資可能さえすればカードローンであっても年収以上の借入をすることが可能です。
従って、銀行が直接貸付をする「銀行カードローン」には法的な規制はないということになりますが、自主規制という形で銀行それぞれが自主的な規制のルールに乗っ取って貸し付けをしています。
しかし、実際には銀行カードローンで年収の1/2程度まで借り入れしているという人は多く、自主規制していないのではと疑問視する声も上がっています。
主な銀行・銀行系カードローン
「銀行カードローン」は銀行が直接貸付を行うカードローンで、「銀行系カードローン」は銀行のグループ会社の消費者金融が貸付を行うカードローンであると解説しましたが、それぞれのカードローンにはどのようなものがあるかを見てみましょう。
| 銀行カードローン | 銀行系カードローン |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行「バンクイック」 | アコム |
| 三井住友銀行カードローン | プロミス |
| みずほ銀行カードローン | SMBCモビット |
主な銀行カードローンと銀行系カードローンにはこれらのカードローンがあり、どのカードローンも知名度や人気が非常に高いカードローンです。
アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループ、プロミスという商品名でカードローンを提供しているのはSMBCコンシューマーファイナンスであり、SMBCグループの会社です。
SMBCモビットもプロミスと同様にSMBCグループのカードローンです。
このように、大手消費者金融のほとんどは大手銀行のグループ会社となっており、銀行系カードローンといえば「アコム」「プロミス」「SMBCモビット」が主なものといえます。
アイフルは銀行系カードローンではない
大手消費者金融のカードローンといえば銀行系カードローンでも挙げられた「アコム」「プロミス」「SMBCモビット」ですが、この3つのカードローンの他にも「アイフル」も大手消費者金融のカードローンといわれています。
ですが、アイフルはどこの銀行のグループにも属していませんので銀行系カードローンではありません。
大抵が銀行のグループ会社となっている消費者金融の中でアイフルは唯一消費者金融として単体で営業をしており、アイフルが提供するカードローンは「消費者金融系カードローン」といいます。
消費者金融系カードローンはその呼び名からもわかるように、貸金業法が適用されます。
貸金業法はなぜ改正された?
貸金業法がなぜ改正されることになったかと言うと、グレーゾーン金利と呼ばれる金利にて貸付されたものに対して、返済困難となる人が続出して社会問題化したことがきっかけとなっています。
またどこが改正されたのかを確認して、今後貸金業者からお金を借りるときに知っておくといいでしょう。
グレーゾーン金利と多重債務問題が社会問題化したため
貸金業法が改正される以前の平成19年2月末では、借入件数が5件以上の多重債務者が全国で見ると180万人で平均借入額は240万円となり、借金苦による自殺者も多く社会問題となりました。
多くの多重債務者を増やす原因となったのが「グレーゾーン金利」です。
利息制限法では、元本が10万円未満の借入時は年20.0%まで、10万円以上100万円未満の借入時の金利は年18.0%まで、100万円以上の借入時の金利は年15.0%までと定められています。
なお、出資法では年29.2%を超える利息を課した場合には罰則規定が設けられていました。
貸金業法が改正される前までは、貸金業者が利息制限法で定められた金利を超えて貸付をしても特に罰則もなく、出資法の上限である年29.2%以内であれば罰則規定に抵触しないという状況でした。
このため、多くの業者が利息制限法の上限金利を超えて出資法の上限金利未満の金利帯でお金を貸し出していました。
この利息制限法の上限金利を超えた、出資法の上限金利年29.2%未満の金利帯を、法律違反ではあるが罰則のない金利帯であることから「グレーゾーン金利」と呼びます。
貸金業法の改正により、出資法の上限金利も年20.0%と規定し、貸金業法には法定金利を違反した業者は違反として行政処分とする旨が定められたため、グレーゾーン金利は根絶され金利は法定金利へ統一されました。
グレーゾーン金利帯で支払った利息を過払い金と呼び、最後の返済日から10年以内であれば過払い金を取り戻せる可能性が高くなります。
総量規制によって、すべての消費者金融は年収の3分の1までしかお金を貸せないことに加えて、過払い金の支払いにも追われ、これらの理由から近年消費者金融の経営が苦しくなっていると言われています。
法律改正によって大きく変わった条文はなに?
改正された貸金業法によって大きく変わった内容は、次の通りです。
- みなし弁済の廃止
- 貸金業者の規制強化
- 出資法の上限金利引下げ
- 総量規制の制定
貸金業者からの借入れが、利用者にとって利益のあるものとなるために改正されました。
それぞれの条例を詳しく紹介します。
みなし弁済が廃止された(旧43条)
貸金業規制法(旧貸金業法)の43条に一定の要件を満たすと、利息制限法の上限金利を超える利息の支払いであっても有効とするという規定があります。
これが、みなし弁済と呼ばれるものです。
このみなし弁済によって利息制限法を超えて、出資法の上限金利である年29.2%で取引されることがありました。
グレーゾーン金利は高い金利のため、返済するために他社から新たに借り入れをするするという、多重債務者を増やす要因になったのです。
しかし、貸金業法の改正によりみなし弁済は廃止されました。
貸金業法の第十二条の八でみなし弁済が廃止されて、グレーゾーン金利もなくなり利息制限法の上限金利を超える取引は違法となりました。
貸金業者の参入規制強化
貸金業法の第三条及び第四条にて、貸金業者は最低純資産が5,000万円以上の会社でなければ営業できなくなりました。
また貸金業務取扱い責任者の資格試験に合格したものが、営業所ごとに配置するよう義務化されました。
そのため、新たに貸金業を営む業者を規制して、違法業者の参入を阻止するようになったのです。
利息制限法に基づいた貸付金利
貸金業法の改正によって、利息制限法によって定められた利息を超える契約をしてはいけないという項目が新たにつくられました。
貸金業法の「第十二条の八の3」で利息制限法の金利を、超えてはいけないように規定されています。
なお、利息制限法で定められた貸付金利は、下記のようなものとなります。
- 元本額が10万円未満の借入は年20.0%まで
- 元本額が10万円以上100万円未満の借入は年18.0%まで
- 元本額が100万円以上の借入は年15.0%まで
総量規制の導入
貸金業法の改正によって総量規制が導入されましたが、貸金業法第十三条に、貸金業者は顧客に対して年収の3分の1以上の金額を貸付けしてはならないという内容が記載されています。
総量規制は利用者が借り過ぎを防ぐために設けられたほか、貸金業者が貸しすぎないためとしての意味もあるのです。
法律に違反した場合の罰則規定が強化された
年収の3分の1を超える貸付を行った場合には、利用者へは罰則はありません。
しかし、業者には罰則があります。
年収は毎年変動するものですので、利用者が年収の3分の1を超える貸付を行わないように、大手消費者金融では利用者に特典を用意して収入証明書の提出を促しています。
◇法定金利
金利の上限は利息制限法という法律によって決められています。
ところが、この法律には罰則がありませんでした。
多くの貸金業者が罰則のない利息制限法の上限金利を守ってこなかったのですが、貸金業法改正によって、法定利息を超過した場合に罰則を設け、利息の上限は利息制限法の法定金利以内ということが定められました。
また、過剰貸付や高金利での貸付をした場合にも、罰則が科せられます。
過剰貸付の禁止
貸金業法では利用者の返済能力を超える過剰貸付の禁止を定めていますが、具体的な金額については規定されていません。
ただし、金融庁のガイドラインには「無担保・無保証で行う貸付には1業者につき50万円、または当該資金需要者の年収額の10%」とあります。
また総量規制から年収3分の1以上の貸付は禁止されていることも忘れてはいけません。
高金利貸付の禁止
貸金業法の改正に伴い、法定利息に違反した業者は行政処分の対象となるという罰則が設けられました。
高金利貸付による罰則は5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金が科せられます。
法律改正によって消費者にメリットはあるの?
法律が改正されて具体的に消費者にとって、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
大きくは「金利が下がった」「闇金業者が減った」ことが挙げられます。
金利が下がった
利息制限法では金利の上限は借入金額に応じて決まっています。
貸金業法改正以前は、プロミスやアコムなどの大手消費者金融でも、出資法の年29.2%以下という高い金利で貸付を行っていたため、現在の上限金利は最大年20%となっているため、かなり低くなったと言えるでしょう。
貸金業者を許可制としたことで闇金業者が減った
ヤミ金融対策法として、悪質な貸金業者や暴力団等への資金融資を排除するために、貸金業登録制度を強化しました。
貸金業者として登録するときには本人確認書類を義務化するとともに財産的要件を確認したり、各営業所に主任者の設置をしたり、厳格な審査が行われることになったことが大きなポイントです。
貸金業法第41条の38の違反:目的外使用の禁止
貸金業者は指定信用情報機関が提供する個人信用情報を返済能力などの調査以外に使用してはならない、と定められています。
簡単に言えば個人信用情報は、消費者金融などの金融機関に借入申し込みをした時点で初めて調査するものであってそれ以外の目的で使用してはならないという意味です。
もちろん個人信用情報を取得するには借入申込者の同意が必要でなければならず、本人の同意なしで消費者金融が勝手に個人信用情報を照会することが禁止されています。
ただし貸金業法第13条の3によって、極度方式基本契約(いわゆるカードローン契約)の借入残高が総量規制を超過していないかどうか調査する途上与信については、本人の同意がなくても個人信用情報の取得が許されています。
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法
個人信用情報目的外使用の違反事例
消費者金融の担当部署が顧客に対して利用限度額の増額を案内するにあたって、途上与信調査した際に取得した個人信用情報を基にDMや電話、メールなどの方法により利用限度額の増額勧誘を行うケースが多いようです。
途上与信は総量規制超過や返済能力の調査などの以外には利用することができません。したがって個人信用情報の目的外使用の禁止に違反します。
消費者金融から増額勧誘メールが来たら審査に通ったのも同じではなく、顧客が利用限度額の増額を申し込みしてから個人信用情報を取得することになりますので増額案内や勧誘があったとしても必ず増額審査に通るわけではありません。
貸金業法第21条の違反:取立行為の規制
貸金業法第21条は取立行為の規制を定めたものです。
返済期日に遅れている借主へ督促する場合は威迫する行為や言動、私生活または業務の平穏を害する言動や態度はしてはならないと定めてあります。
正当な理由がないのに21時から翌日8時までの時間帯に借主に電話をかけることやFAXを利用して送信すること、並びに借主の自宅を訪問することは禁止されています。
貸金業法が改正されて以来消費者金融は徹底した法令遵守のもとに督促業務を行なっていますが、なかなか連絡が取れない借主がいた場合は知らずしらずのうちに貸金業法違反を犯してしまうケースがあります。
取立行為の規制違反事例
消費者金融の従業員が返済期日に遅れている借主に対して、8時から21時までの間に自宅へ電話したものの本人は留守でした。
家族に聞いたところ借主本人は毎朝8時前には自宅を出かけ、帰宅時間は21時を過ぎることが判明しました。
そこで消費者金融の従業員は21時30分頃電話をかけ、返済期日の約束を取り付けることに成功しました。借主からも苦情を言われることがなくスムーズに電話連絡ができてよかったと督促担当者はほっと胸をなでおろしたところです。
一見すると電話をかける時間として正当な理由であるかのように見えますが、借主が携帯電話を持っているかどうか確認していないこと、携帯電話を持っているなら日中に電話連絡することは可能であったことの確認ができていません。
正当な理由とは借主からの自発的な承諾がある場合や、他に連絡を取るための合理的な方法がない場合が該当するため、借主が携帯電話を持っていることがわかっている場合は21時以降の電話督促は違法です。
貸金業法第16条の違反:誇大広告の禁止
貸金業者は広告または勧誘するときに、貸付の利率その他貸付条件について著しく事実と異なる表示または実際のものよりも有利であると誤認させるような誇大広告は禁止されています。
消費者金融は競争が激しく、顧客獲得のために興味を引くようなキャッチコピーを使っている場合が少なくありません。単なるキャンペーン実施と言うなら問題はなくても、事実誤認させるような誇大広告は行なってはいけないのです。
誇大広告の禁止違反
消費者金融A社は公式サイト及び新聞やチラシなどの広告に「他社借入件数が多くても融資可能」や「ブラックでもご相談ください」と記載した広告を行いました。
A社は中小消費者金融のため、集客能力が低く全国的にあまり名前が知られていないということから、なんとか顧客を獲得するための方法として、目を引くキャッチコピーを掲載しましたが、これは誇大広告の禁止にあたり行なってはいけません。
そもそも消費者金融は、借入希望者が適正な判断ができるように事実と相違する表示をすることは禁止されており、他の業者よりも著しく有利であると誤認させるような表示を行うことは法律に違反します。
借入意欲をそそるような表示として、以下のような表示も監督指針として適切ではないと判断されています。返済能力がなくても借りれるような宣伝文句、借入方法が簡単であることを強調する宣伝文句を使用することはできません。
- 今月に限り極甘審査
- 面倒な手続き一切不要
- ブラックでも融資可能
- 諦めずに相談してください
- 他店で断られたかたも大歓迎
- 他社借入〇件以上でも融資OK
以上のような宣伝文句は闇金だけではなく中小消費者金融にもよく見られます。たとえ正規の貸金業者だとしても、以上のようなキャッチコピーを使っているところはあまり信用できませんね。
貸金業法第13条の3、4の違反:総量規制超過の措置
貸金業者は借主と極度方式基本契約(カードローン契約)を締結する場合は、個人信用情報の調査に基づいて総量規制の範囲内であることを確認するとともに、総量規制を超過している場合は利用限度額の減額及び貸付停止をしなければなりません。
総量規制とは個人が無担保無保証で消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用する場合に、貸付上限額を年収の1/3までと定めたものです。
例えば年収が300万円なら100万円まで、年収が600万円なら200万円までの範囲内で消費者金融などが個人に貸しても良い上限額となります。
途上与信によって総量規制を超過していることがわかった場合は、利用限度額の減額や貸付停止を行う義務が課せられています。
総量規制超過の措置を怠った
消費者金融A社は年収300万円の借主に対して、個人信用情報を調査した結果他社借入がないことから70万円の利用限度額を設定し貸付を行いました。
その後借主から利用限度額の増額申請を受け、個人信用情報調査したところ他社借入が増えておりその借入残高が40万円あることが判明しました。
A社は他社借入金額との合計が110万円となり、総量規制を超過することがわかったため利用限度額の増額はできないと借主に通知しましたが、他には何も行なっていません。
しかし、単に利用限度額の増額はできないと通知するだけではなく、A社は総量規制の範囲内に収まるように利用限度額を減額すること、並びに貸付停止の措置をとらなければなりません。
明らかに総量規制の範囲を超えていることをわかっているのに、適切な措置をとらないのは貸金業違反です。
貸金業法第13条の違反:返済能力の調査
貸金業者が個人と金銭貸借契約を締結する場合において、返済能力があることを調査しなければならないことが定められています。
借入希望金額が一定金額以上の場合や、個人信用情報に登録されている他社借入金額との合計が一定金額以上になった場合は返済能力や資力があることを証明できる収入証明書を求める必要があります。
収入証明書を徴求していなかった
消費者金融A社は長年の取引ということもあって、借主への貸付金額が50万円を超えたにもかかわらず、毎月きちんと返済してくれる信用力がある顧客と判断し収入証明書の提出を求めない場合があります。
ヘタに収入証明書の提出を求めてしまったら全額返済されてしまうのではないか、他の消費者金融に借入先を変更されてしまうのではないかとの不安があったようです。
しかしながら貸金業法では、借入金額が50万円を超える場合や他社借入金額との合計金額が100万円を超える場合は、収入証明書の提出を求めなければならないことが義務付けられています。
たとえ借主がA社の信用力を得ていたとしても、個人信用情報は他の金融機関も利用するデータであるため信用力を裏付ける収入証明書類の徴求をしなければなりません。
貸金業法第22条の違反:債権証書の返還
消費者金融などの貸金業者が借主から借金の全額の返済を受けた場合は債権の証書を変換しなければならないことが義務付けられています。
簡単に言えば借金を全額返済したら借用書(契約書)を返してもらうという意味です。それも遅滞なく返還しなければなりません。
債権証書の返還義務違反
消費者金融A社は顧客からの借金の全額を返済を受けたところ、顧客から郵送されるのは家族にバレるから困ると言われ保管している場合があります。
しかし貸金業法第22条によって借用書の返還はしなければなりませんので、A社の判断で保管することは許されません。
消費者金融側で処分してくれないかと頼まれても、明らかな顧客からの要請であるとの客観的な証拠もないため、借主が希望する自宅以外の住所へ郵送するなど対策をとらなければなりません。
その他貸金業法違反による罰則の内容
貸金業法違反による内容は行政処分の対象となるだけでなく、内容によって刑事罰の対象となります。
主な業務区分と違反行為、適用される罰則についてご紹介したいと思います。
◆無登録営業及び登録名義貸し
道府県知事又は財務支局長の登録を得ることなく貸金業務を営んだ場合、及び貸金業者の名義貸しを行った場合は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます。
◆貸金業務取扱主任者の不適切な設置
業務取扱主任者は営業所ごと、及び従業員50人に対して1名設置することが義務付けられています。これに違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます。
◆取立て制限者と知りながら行った債権譲渡
貸金業者が持っている債権は自由に譲渡することができますが、債権譲渡先が暴力団及び反社会勢力との繋がりがある、または本人である、会社または団体であることを知っていながら債権譲渡を行った場合は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。
◆従業員に暴力団員を使用した場合
暴力団員と知りながら貸金業者が従業員として雇った、または借金取立てに暴力団員に依頼した場合は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。
両罰規定
貸金業法第51条によって法人及び個人の貸金業者が処罰されるだけでなく、法人の役員や従業員に対しても厳しい罰が下される両罰規定があります。
消費者金融などの貸金業者の従業員が携わることとして、督促や利用限度額の増額の勧誘、借用書の返還などには担当者にも刑事罰が処されますので注意が必要です。
法律改正のデメリットはあるの?
貸金業法改正によって貸付金利が下がり、違法な取立て行為がなくなるなどのメリットがある一方で、デメリットもあります。
貸金業法改正によるデメリットはなにか、確認していきましょう。
年収の3分の1を超える借入れは行うことはできない
改正貸金業法は年収の3分の1を超える借入れを行うことを禁止しています。
貸金業者全体から年収の3分の1を超えることはできません。
そのため、例えば年収が300万円の人は貸金業者全体から100万円までしか借入れを行うことができません。
他社から既に50万円の借入れがある場合には残り50万円までしか借入れを行うことができないということになります。
なお銀行カードローンは貸金業法外(銀行は銀行法が適用)なため、総量規制対象外となり年収の3分の1以上借りることができます。
ただし、銀行の自主規制により、都市銀行を中心に総量規制に準ずる貸付制限を行う銀行が増えているのが現状です。
50万円を超える場合は収入証明の提出が必須
改正された貸金業法では、借入額が一定の条件下で収入証明書の提出が義務付けられました。
収入証明書の提出が必要な場合とは以下の条件のときです。
- 1度に50万円を超える借入れを行う場合
- 他社との借入額の合計が100万円を超える借入れを行う場合
収入と見られるものには、「給与所得」「年金」「不動産収入」「個人事業の事業所得」などがあります。
なお、宝くじや競馬などの当選金や、保険金、投資による収入などは含まれません。
また、収入確認資料とは、源泉徴収票、給与明細、所得証明書、確定申告書などが該当します。
提出方法は郵送、FAX、インターネット、自動契約機等様々な方法での受付を行っています。
怪しい業者は金融庁に登録しているか確認
中小の消費者金融は銀行系カードローンや大手消費者金融の審査に落ちた人の受皿として一定の存在がありますが、名前を聞いたことがない企業であることが大多数です。
中には闇金の可能性がありますので、金融庁へ登録された貸金業者であるかどうかを確認することが絶対に必要です。
闇金のホームページの中には「闇金に注意してください」という旨の文言をうたって、あたかも合法企業のように擬装しているような企業もありますので、確認は必須です。
貸金業を営むには金融庁への登録が必須
貸金業を営もうとする場合は、財務局または各都道府県で登録を受けなければなりません。(貸金業法第3条)
登録を受けるためには法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付して提出することで審査を受けられます。
合法的に貸金業を営むには金融庁の貸金業法としての基準を満たし、金融庁に貸金業法に違反していないかどうかの監督を受ける必要があります。
つまり、金融庁へ登録している業者はすべて法律遵守の企業であると判断することができます。
反対に、金融庁へ登録していない貸金業者はすべて闇金であると判断したほうがよいでしょう。
登録番号が設定されるので違法な業者か調べられる
金融庁のホームページには登録貸金業者の一覧が掲載されています。
一覧表には所管財務局、登録番号、登録年月日、貸金業者名、郵便番号、本店等所在地、代表等電話番号が記載されていますので、これらの情報から取引を行おうとしている業者が金融庁に登録している業者なのかどうかを慎重に判断しましょう。
将来的に銀行も法で規制される!?
銀行もそれぞれ自主的なルールによって規制をしていますが、2010年の貸金業法の改正以降カードローンなどの無担保ローンの融資残高は飛躍的に伸びています。
それまで個人の借り入れといえば消費者金融であったものが貸金業法の改正によって銀行カードローンを申し込む人が増え、さらに銀行も法的な規制がないために融資をしてきました。
これにより、現在では貸金業界が保有する融資残高よりも多い融資残高を保有しています。
こうなると多重債務者を減少させるという貸金業法改正が意味を成さないとして、2017年3月に全国の銀行が加盟する全国銀行協会は自主規制の強化をすると公表しました。
そして同年4月以降に順次各銀行が強化した自主規制のルールに乗っ取ってカードローン事業を行っています。
しかし、あくまでも自主的なルールで法的な規制はありませんので、今後もこれまでと同様に契約件数や融資残高が伸び続ければ貸金業法の総量規制と同じような規制が導入される可能性があります。
可能性があるというだけで本当に規制されるかはまだわかりませんが、導入されるかどうかは今後の銀行の動向次第であるといえます。
各銀行の自主規制の内容
自主規制の強化を迫られている銀行は、これまで簡易化していたカードローンの審査を厳格にするために、収入証明が必要となる融資額の引き下げや融資上限額の引き下げなどを実施することを公表しました。
以下は大手銀行が規制を強化すると公表したもので、現在では強化された自主規制のルールでカードローン事業を行っています。
| 銀行名 | 自主規制前 | 自主規制後 |
|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 融資額300万円超から収入証明が必要 | 50万円を超える申し込みから収入証明が必要 |
| 三菱UFJ銀行 | 融資額200万円超から収入証明が必要 | 融資額50万円超から収入証明が必要 |
| みずほ銀行 | ・融資上限:年収の1/2 ・融資額200万円超から収入証明が必要 | ・利用限度額が50万円以上の場合 ・原則収入証明が必要 |
| りそな銀行 | 100万円超や300万円超など融資種類によって収入証明が必要となる融資額が違う | 収入証明が必要となる融資額を引き下げる |
これらの大手銀行が規制を強化をしたのに伴って、地方銀行でもそれぞれのカードローン内容を精査したうえで順次自主規制を強化しています。
さらに銀行業界では、融資スピードを重視することによって審査が曖昧になっているということで即日融資を行わない方向に向かっており、今後はさらに自主規制を強化していくことで法的な規制の導入を避けようとしています。
貸金業界は総量規制の撤廃を求める
銀行業界に総量規制が導入される可能性がある一方で、貸金業界では同じカードローン(キャッシング)という商品で、商品内容も類似しているにもかかわらず貸金業者には規制があり、銀行には規制がないのは不公平だということで総量規制の撤廃を求めています。
そもそも同じような形式でお金を借りるものを借りる場所(業者)が違うだけで、規制されるものと規制されないものがあれば利用する側も混乱してしまいます。
現にインターネットなどで総量規制について検索すると、よく規制の対象となる借り入れとなるのかを解説しているサイトが多くあります。
それだけ利用する側も分からなくなっている人も多いですし、不公平だとする貸金業界の言い分も一理あります。
しかし、貸金業法で総量規制が導入された経緯が多重債務者対策というところからすると、撤廃を求めるのは単に融資残高が伸びず、収入減が減っているからなのではと考えてしまいます。
タグ:お金の知識






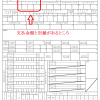




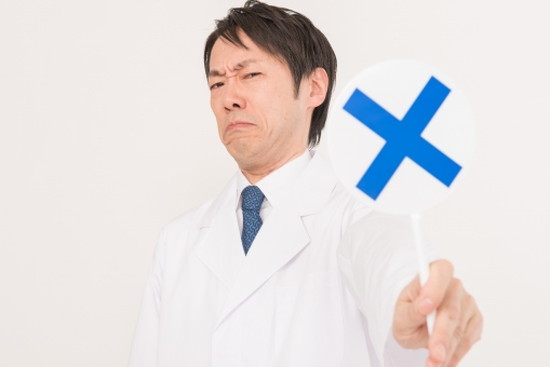














































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。