生活福祉資金貸付制度でお金を借りる方法と借りれない原因や対処法
今得ている収入では、どうしても生活していくことができない。
しかし、今の状態では金融機関に融資を申し込んでも、審査に通る見込みがないでしょう。
そんな時に利用検討してもらいたいのが、生活福祉金貸付制度です。
生活福祉金貸付制度とは民間の金融機関からお金を借りられない方を対象に、無利子または民間の金融機関では考えられない低金利で必要資金を貸付けし、一般的な社会生活が送れるように促すために用意された制度です。
よって、一般的には低所得者層がこの制度の利用対象者となってきますが、申請を行った方の中からは下記のような非難も多く、実際に利用するには難しい点が多々あることは否めません。
- 審査が厳しすぎる
- 誰のための貸付制度か分からない
そこで、今回はこの生活福祉金貸付制度の概要を、確認しながら借りれない原因を解明し、その際の対応策を紹介していくことにします。
- 執筆者の情報
- 名前:馬井実
年齢:49歳
性別:男性
職歴:1992年~2008年まで地方銀行で貸付業務に従事
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
この記事はこんな人におすすめ
今回紹介する記事は、以下の悩みを抱えている人におすすめです。
- 金融機関等から借入ができない人
- 失業等で所得が大幅に減ってしまった人
- 日常的な生活が困窮している人
生活福祉資金制度とは?
一口に生活福祉金と言っても、その内容は大きく分けると下記の4つに分類され、更にその中でも細かく分類されています。
- 総合支援資金 生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
- 福祉資金 福祉費、緊急小口資金
- 教育支援資金 教育支援費、就学支度費
- 不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
資金使途に応じて、最適な生活福祉資金制度を利用するというわけです。
生活社会福祉金制度は低所得者や高齢者、障害者で社会的生活が金銭的に困難な人の生活を経済的に支えることと、対象者の在宅福祉と社会参加の促進を図る目的を持った制度です。
都道府県社会福祉協議会を実施主体とし、各自治体の社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
就労支援、技術習得にかかる費用や、高校・大学などへの進学費用、また介護サービスにかかる費用の貸付が行われている他に、各自治体の社会福祉協議会が行う相談会や、相談支援班が、低所得世帯などの経済的自立を図るための相談支援を行っています。
また、生活福祉資金制度は、生活困窮者自立支援制度と連携して貸付を行っています。
就職する予定のない人で総合支援資金と緊急小口資金の貸付を必要とする人の条件は、経済的自立を目指すために、自立相談支援機関で行われる自立相談支援事業の利用が貸付の前提となっています。
自立相談機関では、相談者の状況から自立支援プランの検討や、生活福祉資金の借入額や償還計画について相談を行っており、相談のうえで生活福祉金制度の手続きを行います。
生活福祉資金制度の概要
各生活福祉金貸付制度の概要は、下記の通りとなっています。
①総合支援資金
- 生活支援費
金利 連帯保証人アリの場合0%、ナシの場合1.50%
据置期間 最長6か月
借入限度額 15万円/月(同居人が2人以上の場合20万円/月)
資金使途 生活の建て直し - 住宅入居費
金利 連帯保証人アリの場合0%、ナシの場合1.50%
据置期間 最長6か月
借入限度額 40万円
資金使途 賃貸契約にかかる費用 - 一時生活再建費
金利 連帯保証人アリの場合0%、ナシの場合1.50%
据置期間 最長6か月
借入限度額 60万円
資金使途 生活支援費よりも大きな出費(就労のために必要な技術取得費用、滞納等への穴埋め、債務整理の経費など)
総合支援資金は原則的に住居がある人が対象ですが、地方自治体で実施している住居確保給付金に申請をしていて、今後住居の確保が確実にできる人であれば利用可能です
申し込みは住まいのある、自治体へする必要があります。
また、貸付には自立相談支援事業の利用が条件となっていますので、離職中の人はハローワークへの求職申込みと職業相談が必要となります。
生活支援金と一時生活再建費については申込者の口座へ、住居入居費については家主や不動産業者などの口座へ振り込みされます。
②福祉資金
- 福祉費
金利 連帯保証人アリの場合0%、ナシの場合1.50%
据置期間 最長6か月
借入限度額 580万円
資金使途 生活費やその他福祉関連など、(生業を営むため、住宅の増改築や補修、就職や就職のための技能取得、冠婚葬祭、日常生活をするうえでの一時的に必要な経費、けがや病気による療養、福祉用具などの購入、介護サービスや障害者サービスを受けるため、被災やり災のための臨時経費など) - 緊急小口資金
金利 0%
据置期間 最長2か月
借入限度額 10万円
資金使途 緊急出費
③教育支援資金
- 教育支援費
金利 0%
据置期間 最長6か月(卒業後)
借入限度額 高校3.5万円/月、高専6万円/月、短大6万円/月、大学6.5万円/月
資金使途 義務教育外の就学にかかる教育費 - 就学支度費
金利 0%
据置期間 最長6か月(卒業後)
借入限度額 50万円
資金使途 義務教育外の入学にかかる教育費
④不動産担保型生活資金
- 不動産担保型生活資金
金利3%または長期プライムレートのいずれか低い方
据置期間 最長3か月
借入限度額 土地評価額の70%程度、または30万円/月
資金使途 不動産を持つ高齢者世帯の生活資金
*推定相続人による保証人が必要 - 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
金利3%または長期プライムレートのいずれか低い方
据置期間 最長3か月
借入限度額 土地評価額の70%程度(集合住宅は50%)、または生活扶助学の1.5倍
資金使途 不動産を持つ要保護高齢者世帯の生活資金
生活費として利用するのであれば総合支援資金、または福祉資金となり、進学のための資金調達ならば教育支援資金、高齢者が住宅を担保として生活資金を受けるならば、不動産担保型生活資金といったように、資金使途によって利用できる生活福祉資金制度が違ってきます。
また総合支援資金と福祉資金は誰でも利用することができますが、教育支援資金と不動産担保型生活資金は利用者が限定されてくるので、この点はよく理解しておきましょう。
- 臨時特例つなぎ資金貸付制度
金利0%
借入限度額 10万円以内(一括口座振込)
資金使途 離職者支援のための当面の生活費
臨時特例つなぎ制度は失業等で住居がない離職者に対し、申請した失業給付や住居確保給付金などが下りるまでの間の生活費として貸付が行われます。
また、自治体によってはこの制度の他に、特例の貸付制度がある場合があります。
東京都では自然災害で被災した都内避難世帯への緊急小口資金貸付を行っており、通常は貸付対象ではない都の住民以外でも申込むことができます。
この制度は据置期間や、償還期間も通常より長く設定されています。
また、各福祉事務所によって避難世帯が利用できる制度があり、西東京市では「生活つなぎ資金」と称し、急な出費やけがや病気などで一時的にかかる費用を、2万円までを限度とする貸付を行っています。
西東京市の「生活つなぎ資金」の申し込みは原則として、西東京市に住民票を置いてあることが条件となっていますが、避難世帯の場合は世帯主以外の申請が可能な場合があります。
どんな人が利用できるの?
この制度が利用できるのは前の項で軽く触れたように、以下のいずれかに当てはまる人です。
| 低所得者世帯 | 目安として市町村民税が非課税となる程度(自治体により基準が異なる) |
|---|---|
| 高齢者世帯 | 介護が必要となる65歳以上の高齢者がいる |
| 障害者世帯 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかが交付されている人がいる |
| 失業者世帯 | 失業により生活が困難となった |
基本的な貸付条件は上記のものになりますが、各種の貸付の利用にはそれぞれ条件が異なり、各自治体によっても条件が異なる場合があります。
東京都の例を見てみましょう。
| 総合支援金 | 失業等で日常生活全般に困難を抱えている 生活の立て直しのために継続な相談支援と生活費一時的な資金を要している 自立支援事業への利用かつ貸付後継続的な支援を受けることに同意している |
|---|---|
| 福祉資金 | 日常生活以外の具体的利用目的でまとまった資金が必要 返済見込みを立てられる 東京都内に住居があり、住民票と住所が一致している 暴力団がいない世帯 |
| 教育支援金 | 福祉金と同条件であること 保護者の世帯収入が収入基準を超えない世帯 貸付以外で学校卒業までの生計維持が可能 公的給付金や奨学金を受けられる場合はそちらを優先 |
| 不動産担保型生活資金 | 高齢者世帯 単独で所有している不動産に住んでいる 世帯構成が原則65歳以上 単身または夫婦のみの世帯と同居している親 対象不動産を所有している |
借りられる条件
制度の対象となる人は大まかに言えば表にあげた通りですが、更に細かく幾つかの条件があります。
主な条件は以下の通りです。
- 同制度による連帯保証人になっていない。
- 住民票の所在地に申し込んでいる。
- 他の公的な給付や貸付を受けることができない。
- 返済できる見込みがある。
生活福祉資金貸付制度は、自分の住民票があるところでないと申し込めません。
そのため、住民票と異なる場所に住んでいる場合は、住民票を移したりする必要があります。
また、この制度以外に他の制度を利用することで、現状を改善できる場合はそちらの制度を利用することになります。
生活保護などの他の制度を利用している場合は、基本的にはこの制度を利用できませんが、事情によっては利用できることがあるようです。
特に臨時特例つなぎ資金貸付は、失業等で住居がない離職者に対し、申請した失業給付や住居確保給付金が下りるまでの間、連帯保証人が必要なく無利子で10万円まで貸付を行っています。
これは社会福祉協議会の判断によりますので、他の制度を利用しているけれどもこの制度も使いたいという人は一度相談してみるのがいいかもしれません。
他にも、返済できる見込みがあるかどうかというのは、大事なポイントになってきます。
この制度はお金を給付しているわけではなく、貸し付けているだけなので返せなさそうな人には貸してくれません。
無職で就職の見込みがなかったり、多重債務を背負っていたりといった場合は制度の利用が厳しくなるでしょう。
どうやったら使えるの?
ここまでどのような条件があれば、制度を利用できるのか制度の細かい説明を見てきました。
ここからは実際にどうやったら制度を、利用することができるのかを説明していきたいと思います。
必要書類
まずは用意する書類についてです。
必要な書類は申請する自治体によって異なりますが、
基本的に必要な書類は申込書、収入証明書類、住民票、健康保険証などの本人確認書類、連帯保証人の収入証明書類や住民票などです。
これに加えて制度を利用する事情や、制度の種類によって自立計画書・雇用施策利用状況確認票・債務状況の分かる書類などが必要になってきます。
具体的にどの書類が必要かは、各県の社会福祉協議会のホームページで確認することができます。
手続き
手続きとしては、各市区町村にある社会福祉協議会に行って相談し、必要な書類を揃えて申し込みます。
この際に、社会福祉協議会の代わりに、地域の民生委員の人に相談することもできます。
申込書類は都道府県の社会福祉協議会で審査され、制度を利用できるかどうか判断されます。
審査の結果が送られてきて、無事に審査が可決されていれば、あとは借用書を提出すればお金を借りることができます。
この審査は時間がかかることが多いため、もし急ぎでお金が必要な場合は緊急小口資金に申し込みましょう。
こちらであれば一週間程度で借りることができます。
また、審査の過程で、実際にどういう生活をしているのか、確認するために民生委員の人が家に来て確認することもあります。
返せなかったらどうなる?
借りたはいいものの想定外の出費などで返済が遅れたり、返済期間内に返しきれなかったりした場合はどうなるのでしょうか。
この制度を行っている社会福祉協議会は公的機関であるため、非常識な取立てなどはありません。
また、この制度の利用や延滞は信用情報に影響しないので、その点に関しては大丈夫です。
ただ、支払いが遅れたりすると、電話や手紙などで督促されます。
他にも、延滞した期間分はペナルティとして、通常の利子に加えて延滞利子というものがかかることもあります。
このようなことになる前に支払が厳しそうであれば、社会福祉協議会に行って相談することも大切です。
相談すれば、事情によって返済期間を延ばしたり、返済頻度を変えたりと行ったことも柔軟に対応してくれます。
余りに返済しないでいると所持している、財産を差し押さえられる可能性もあります。
返済できない事情があれば、早めに相談に行きましょう。
返済が難しい場合は償還免除してもらえる
生活福祉資金の交付は原則として借主の指定口座へ振り込まれますが、社会福祉協議会窓口で直接現金を受け取ることも可能です。
借入金の償還中は3か月に一度の割合で借入残高のお知らせが発行され、返済の延滞が発生すると社会福祉協議会の担当者が借受人の督促を行います。
返済が厳しい場合通常は償還猶予として、1年間の支払猶予をしてもらえます。
しかし生活福祉資金を借りる人は、ほとんどの場合生活困窮者であることから、督促を行うことが妥当でないと判断した場合、償還免除されることがあります。
もちろん返済可能な状況にあるにも関わらず、返済することに対して誠意が見られない場合は、最終的に法的措置によって回収されることになりますが、返済困難な状況が以下に該当する場合は生活福祉資金貸付金償還免除となります。
- 借受人が死亡
- 借受人の返済困難
- 借受人の行方不明
- 借受金の返済困難
- 償還期限を2年延長しても返済困難な場合
- 返済困難のまま時効が成立した場合
ただし上記に該当する場合でも、借受人がいる世帯が生活の見直しに対して、努力を行っていることが条件となり、生活福祉資金貸付金によって浪費をしていると認められた場合は償還免除にはなりません。
なお償還免除については、都道府県知事の承認を得て決定を行います。
いくら努力しても返済できないという場合は、悩むことなく直接社会福祉協議会に連絡するか、民生委員を通じて相談を行いましょう。
生活保護受給者でも借りられるの?
生活福祉資金貸付には様々な貸付制度があり、生活保護受給者及び生活保護受給世帯でも借入併用が可能です。
ただし生活保護を受けている場合は、総合支援金の借り入れはできません。
生活保護は生活扶助など生活に関わる支援を、既に受けてもらっているためです。
総合支援金以外の福祉資金と教育支援金は、生活保護の各種扶助と二重にならないため生活福祉資金でお金を借りることもできます。
ここで問題になるのが生活福祉資金は、返済しなければならない義務があることです。
生活保護を受けている状況でお金を、借りてはいけないという法律はないとしても、支援を既に受けている状況で、たとえ生活福祉資金だとしてもお金を借りるのに難色を示す自治体も少なくありません。
生活福祉資金でお金を借りても返済可能かどうか、返済できる見込みがあることが条件となることから生活保護を受けている状況で返済する能力があるかどうかということと、現実的に考えるとたとえ借りれたとしても少額になるようです。
自治体によって異なる
総合支援金は例外として、基本的に福祉事務所が借入れの必要性を認めている、生活保護受給者は同制度を利用することが可能としています。
ただし、同制度の返済のように、対応は各自治体によって制限や判断が異なる場合があります。
例えば、生活保護者が借入を行った場合、生活保護費での返済は認められないとしている自治体がある一方、生活保護が支給されるまでの貸付を生活保護費で返済を認める自治体もあり、対応は様々です。
貸付金制度の問題点
生活困窮世帯に対する支援は生活保護と生活福祉資金の二つがあり、共通点や類似点も幾つか見受けることもできます。
生活福祉資金貸付制度は生活保護と同じように世帯単位で貸し付けられて、民生委員が協力する体制も同じです。
また生活に関わる借入が民間の金融機関ではできない状況に置かれる世帯に対して、支援を行う目的も同じですね。
生活の安定を図るとともに支援活動を行う民生委員の役割についても、生活福祉資金貸付制度の目的は生活保護制度が反映されたものと言えるでしょう。
しかし経済的困窮者を援助するための生活福祉資金貸付制度は、生活保護制度とは違い自治体ではなく、社会福祉協議会に委託されていることが、貸付制度の運用や考え方がねじれている可能性が否定できません。
生活保護を申請する人は自治体の役場で手続きできるものの、生活福祉資金の貸付は社会福祉協議会が行い、貸付を行うかどうかの判断が社会福祉協議会の相談担当者の裁量によって違いが出てくる危険性があります。
そのためせっかく生活福祉資金の借入相談に行っても、生活困窮状態をうまく説明することができずに借りることができないまま放置されるケースも目立っています。
つまり生活福祉資金貸付の審査を自治体が行うのか、社会福祉協議会が行うのかで貸付制度を利用できるかできないかが決まってしまうのは問題と言えるでしょう。
役場の生活保護担当者と社会福祉協議会の相談担当者が密に連絡を取り合い、誰が生活福祉資金の借入を申し込んできたのか、どのような状態で申し込んできたのかフィードバック体制が求められるところです。
民生委員にしても生活福祉資金についてどこまで踏み込んで良いのか曖昧な点が多く、場合によってはプライバシー侵害にも当たってしまいます。
以上のような問題点を解決するには、社会福祉協議会と民生委員、役場の生活福祉担当者がチームを結成し、きめ細かな相談や、状況によっては福祉施設を案内するなどのサービスが必要ですね。
生活福祉資金が借りれない原因は?
生活福祉資金制度の概要についてご理解いただけたかと思いますが、冒頭で申しましたようにこの制度は基本的には低所得世帯への貸付けとなります。
その低所得世帯と定義されているのは下記の3世帯です。
- 低所得者世帯 民間から借り入れができない世帯
- 高齢者世帯 65歳以上の高齢者世帯
- 障害者世帯 障害者手帳や養育手帳を交付された人の世帯
この中でも判断が曖昧になるのが低所得者世帯ですが、厚生労働省の国民健康・栄養調査では世帯所得が200万円未満を低所得者層と定義しており、その他にも市町村民税が非課税、つまり住民税が課税されない世帯を低所得者層とする定義もあります。
しかし、生活福祉資金制度の定義する低所得者層は、主に下記の条件がその定義となります。
- 前年度所得が125万円以下、または前年度収入が204万円以下
- 障害者
- 未成年者
- 寡婦、寡夫(配偶者と死別、生死が明らかでない、または離婚し、現在婚姻をしておらず、扶養親族がいる人)
しかし、これは飽くまで貸付対象者に該当であるという話であって、ここに該当するから必ず貸付けが行われるというわけではありません。
冒頭でも紹介した申込者からの避難があるのも、申し込んだはいいが却下されたという方が少なくないからです。
生活福祉資金制度は給付でなく貸付!
生活福祉資金制度で借りれなかった原因で一番多いのが、返済能力が認められなかったという理由です。
生活福祉資金制度自体が民間の金融機関から借りれない世帯に貸付けし、一般的な社会生活が送れるように促すためのものですから、申込者に高い返済能力を求めるのは酷な話でしょう。
返済能力がないから貸し付けできないでは、「誰のための貸付制度か分からない!」と憤慨する方の気持ちも分かります。
しかし、生活福祉資金制度は給付制度ではなく、貸付制度ですから、返済できる見込みがあることが貸付条件となってくるのです。
この制度は決して高いとは言えない貸付額からも分かるように、この制度による貸付によって生活を軌道修正し、一般的な社会生活を送れる基盤づくりを行うことが最大の目的です。
そのため、総合支援資金や緊急小口資金の申込者は社会的自立をするために、自立支援機関で支援プランの相談などを行うことが前提となっており、据置期間後に返済が可能な計画を立てる必要があります。
「お金ないなら貸してあげますよ」といった、一時救済のための制度ではありません。
この貸付けによって生活を立てなおし、返済できる状態になると判断されなければ、貸付けが行われることはないのです。
よって、下記のような返済能力なしと判断される条件に当てはまる場合には、返済できないと判断されて借り入れすることはできません。
- 無所得、もしくは所得収入があってもかなり低い
- 多重債務者(債務整理をする場合を除く)
- 住宅確保ができていない、もしくはできる見込みがない
- 以前に借りた生活福祉金が返済されていない
ここまでの実情を見て、「民間の金融機関から、借りれない人の救済制度なのに」と思われた方は少なくないでしょう。
事実、民間の金融機関から借りれないけれど、返済能力には問題ないなんて人が一体どれだけいるのだろうかと、事実この制度には首をかしげる点があるのは事実です。
しかし、明確な審査基準が公表されているわけではありませんし、国の制度と言っても担当窓口となるのは市役所等の各自治体となってくるので、その審査基準にも違いが出てきます。
特に障害というハンデがあれば、審査通過率が高くなることも予測されます。
各自治体によってサービスに違いはあるものの、障害者支援法によるサービスを受けているのであれば、給付金をもらっている世帯でも利用できる場合や、連帯借受人を立てれば利用できる場合があります。
ですが最終的には返済能力が決め手となってくるので、返済能力がなければ生活福祉資金制度を利用することができないことはよく理解しておきましょう。
生活福祉資金は低所得者を対象とした制度
何度も言いますが生活福祉資金は、低所得世帯を対象とした制度です。
よって、低所得者でないという事実が確認される場合には、絶対に審査に通ることはありません。
下記のようなことが確認されれば、借り入れできることはないでしょう。
- 他の貸付制度が利用できる
- 他の金融機関から借り入れできる可能性がある
- 生活保護や失業保険給付を受給している
ただし、一時生活再建費に関しては、債務整理の手続きに必要な費用の貸付が認められているので、本来対象外である低所得者ではない場合でも、多重債務に陥っていて債務整理が必要と判断される人は利用できる可能性があります。
生活福祉資金制度は他から借りれない時の最終とりで
生活福祉金制度は民間の金融機関から、借りれない場合の借入先です。
金利が安いから利用したいという理由で利用することはできませんから、他の金融機関から借り入れできる可能性がある方が審査に通ることはありません。
また生活福祉資金制度は他の公的支援制度が受けられない場合に利用する、最後のとりで的な側面を持つので、他の公的支援制度を受けられるのであればそちらを優先してくださいと言うことになり、これもまた借りれない原因となってきます。
よって、他の公的支援制度が利用できる場合だけでなく、既に利用している場合も借りることはできません。
生活福祉資金制度は生活保護や、失業保険給付を受けられなかった方のための制度だと認識しておきましょう。
つまり、この生活福祉資金制度は民間、公共ともにどこもお金を貸してくれるところがないという場合に、最終的に利用することになる最後のとりでとも言える、公的支援制度という性質を持っているのです。
その割には審査が厳しいと言われる方もいるでしょうが、この点はよく理解しておいてください。
生活福祉資金に通りやすい人の特徴
それでは生活福祉資金制度が借りれない原因について理解してもらったところで、この話の締めとして生活福祉資金に通りやすい人の特徴をあげておきましょう。
ここまでの話で一体どんな人が審査に通るんだと思われた方もいることでしょうから、その特徴を見て自分に当てはまるかどうかを確認するのも1つの方法でしょう。
その特徴は下記の通りです。
- 家計簿等(明細やレシート)の提出で家計の実態を明確にしている
- 税金の滞納がない
- 緊急度が高い
- 困窮度が高い
- 連帯保証人を付けている
- 第三者の生活福祉資金貸付制度の保証人になっていない
- 他の公的支援制度が受けられない
基本的に借り入れ申込者本人が返済可能かどうかを判断していると言えますが、返済見込みが疑わしい場合でも、連帯保証人を付けることで審査に通りやすくなる可能性があります。
生活福祉資金貸付制度は原則的に連帯保証人を立てる必要がありますが、立てない場合でも貸付が可能です。
しかし、連帯保証人を立てることは、債務者となる申込者には連帯保証人を付ければ、金利がかからないという大きなメリットがありますが、それとともに債権者には貸倒れとならない保証を付けられるメリットが生まれます。
よって、返済能力に多少問題があったとしても、連帯保証人の審査評価が高ければ、それを補って審査通過となる可能性は大いに考えられるのです。
国の制度利用による借り入れと言っても借金であることには違いなく、申込者が返済不能となれば連帯保証人に返済が求められることになるので、依頼できる人は限られてくるでしょう。
しかし、なってくれる当てがあるのならば、連帯保証人を付けた方が審査に通る確率は間違いなく高くなってくるでしょう。
生活福祉金が借りれない場合はどうすればいいの?
ここまでの説明で生活福祉資金制度は誰でも、簡単に借りれるといった類のものではないことはお分かりいただけたでしょう。
となれば最後の頼みで申し込んで、審査に落ちた場合はどうすればいいのでしょうか。
これは全ての方の救済法とはなりませんが、その場合には下記のような対応策が考えられます。
- 病気や障害などの理由で返済能力がないのなら生活保護を検討
- 職業訓練受講給付金を活用
病気や障害などの理由で返済能力がないのなら生活保護を検討
病気や障害などの理由で返済能力がないと判断されたのならば、生活福祉資金制度の利用は諦めて方がいいでしょう。
返済義務が課せられた生活福祉資金制度では、返済能力なしで審査に通ることはないからです。
しかし、それが原因で生活が困窮しているのならば、生活福祉資金制度よりも生活保護の方が断然おススメですし、生活保護はそういう方のいる世帯を、金銭的に助けるための制度ですから、こちらの方が審査通過もしやすいでしょう。
しかも生活保護なら貸付けではなく、給付となるので返済義務はありません。
まずは福祉事務所等に訪れて、相談してみることをおススメします。
職業訓練受講給付金を活用
失業保険が受けられない、生活福祉資金制度もダメだったという場合に、おススメなのが職業訓練受講給付金です。
職業訓練受講給付金は失業保険が受けられない求職者に対して、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講することを条件に、その期間中の生活支援を目的として給付を行う制度で下記の給付を受けることができます。
- 職業訓練受講手当 10万円/月
- 通所手当 職業訓練機関までの交通費で上限設定あり
- 寄宿手当 10,700円/月
利用するには下記条件を全て満たす必要がありますが、まずは受付先となるハローワークに相談してみることにしましょう。
- 本人収入が8万円以下/月
- 世帯の全体収入が25万円以下/月
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在の居住地以外に不動産を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している
(理由がある場合でも支給単位期間ごとに8割以上の出席率が必要) - 世帯にこの給付金を受給している人がいない
- 過去3年以内に虚偽、不正による特定の給付金支給を受けていない
まとめ
借りられる条件について見てきましたが、審査に通りやすくなる条件はあるのでしょうか。
審査に通りやすくなる条件は、本当にこの制度を必要としていて、しっかりと計画を立てて返していける人かどうかです。
具体的に書くと下のようになります。
- 困窮していて緊急にお金が必要
- 家計の状態をきちんと家計簿やレシートと行った形で記録・保管している
- 連帯保証人がいる
- 余計なことにあまりお金を割いていない
これらに当てはまったり、同様の事情があったりすると審査に通りやすくなるようです。
タグ:お金の知識








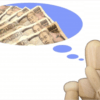










































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。