親や身内から借金をしたときに確定申告で気を付けたいこと【贈与税】
親からお金を借りるときは、確定申告のときに贈与税がかからないように注意しないと、親からの借金が自分への贈与とみなされて税金がかかってしまうのです。
親から借りたお金がなぜ贈与になるのでしょうか?借りているお金に贈与税がかかってしまう原因やそうならないための対策を紹介します。
贈与税って何?
贈与税とは、個人が個人から財産をもらった時にかかる税金です。
親でなくても、個人から財産をもらうと贈与税は発生します。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかり、亡くなった人の保険金を受け取った場合は、場合によって贈与税、相続税、所得税のいずれかを支払わなくてはいけません。
なぜ身内からの借金は贈与ではなく借入なのに、課税対象になるのでしょうか?
それは税務署の目が光っていて、借りる方法によっては身内のローンや親からの借金も贈与とみなされて税金を納めなくてはならない可能性があるからです。
贈与税の未納はバレないのではという疑問をもつ人もいると思いますが、結論からいうと贈与税の未納はバレます。
贈与税を無申告で確定申告をしたときはバレないかもしれませんが、その後の税務調査やマイナンバーの照会などで必ずバレます。
バレた場合は申告しなかった年分の延滞税や加算税が請求され、はじめから贈与税を払っていたほうが結果としてお金が掛からないのです。
親からの借金を贈与だと疑われる4つのケース
親子間の借り入れで、父親が「子供に貸した」と主張したけれど、税務署の判断は贈与となって贈与税がかかったというケースがあります。
税務署から親や身内からの借金を贈与とみなされず、税金がかからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
まずは、親からの借金を贈与だと疑われる4つのケースを紹介します。
返済不能な高額借金
親から借り入れた額が高額で、自分の収入から返せない場合は贈与が前提の貸借であると判断されます。
最初から返す気もなく、返してもらう気もなく貸借したお金は贈与ですので借金ではありません。
この場合は、贈与税がかかってしまいます。
そして、返済額を毎月きめておかないと借入とは言えませんので、借り入れる額は返済できる金額である必要があります。
契約書がない
借入の時に、親子間でも契約書を交わすことは必須です。
お金の貸し借りを書面に残さないと、後になってから返済額や返済期限のトラブルが発生する確率が高くなります。
そして、契約書がない場合は借りたお金は親からもらったことになってしまい、金額によりますが、この場合も贈与税がかかってしまいます。
親子間だからこそ、あとになってトラブルがないようにお金の貸し借りはきちんと行いましょう。
無利子で借りた
借入に対する利息相当額が贈与とみなされるケースがあります。
お金を借りた時に払わなければいけないものに利子があり、親からお金を無利子で借りた場合は、本来なら支払わなければいけない利子分の金額を、親が子供に贈与したと判断されてしまう場合があります。
返済期限が無い
個人から借り入れた借金の返済期間が無いということは、お金は借入に当たらず贈与だと判断されます。
いつでも返せて、返す期限も決まっていないというお金は借金とは認められません。
親から贈与では無く借金という形でお金を借りて、返す時期も決まっておらず「返すのはいつでもいいよ。」といわれたら要注意です。
親から借金するときに行うこと
身内からの借金でも贈与税として税金がかからないようにするには、お金の貸し借りをしたという証拠が必要です。
贈与税がかからないお金の作り方、お金の貸し借りの証拠を作る方法を紹介します。
親子間でも契約書を作成する
お金を借りるときはどのような借用書を書けばいいのでしょうか?
親子間でもお金の貸し借りをするときでも契約書として金銭消費貸借契約書をつくりましょう。
金銭貸借契約書を記載するときの注意点と、金銭消費貸借契約書はどのように書くのか解説します。
親子間で、利息付・連帯保証人なしの場合は、
|
|
以上を記載すれば、金銭消費貸借契約書は完成です。
期限の利益の損失は借金の支払いがされず利息が払われなかったときは、どのようなものがあるのかを記載します。
なお、金銭消費貸借契約書は課税文書として収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は契約金額によって違い、1万円未満は必要ありません。
| 契約金額のないもの 10万円以下 | 200円 |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超え1000万円以下 | 10,000円 |
| 1000万円超え5000万円以下 | 20,000円 |
| 5000万円超え1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超え5億円以下 | 100,000円 |
収入印紙を貼付した借用書の原本は貸した人が保管し、借りた人は写しを保管しておきましょう。
返済の証拠を残す
証拠の残る形で返済を行うことも大切です。
毎月きちんと返済されていない場合は、贈与とみなされてしまい贈与税の支払いを求められる可能性があります。
毎月、銀行振り込みで親の口座に毎月の返済額を入金すれば、通帳に記帳することで返済の証拠が残ります。
毎月の返済の証拠を通帳で残せば、税務署から疑われた場合に通帳を提示すれば問題ありません。
金利を払う
親からの借金でも無利子だったり、極端に利息が低かったりすると贈与とみなされる可能性があります。
利息は何%にすればよいのかという疑問があると思いますが、親から借りる場合は利息は消費者金融や銀行よりも安い金利で問題ありません。
1%~5%程度の金利に設定しておくことをオススメします。
親と子が別生計の場合は、親は子供から受け取った利子を雑取得として確定申告をしなくかてはいけませんので注意しましょう。
返済が出来る額を借りる
返済が出来る額を借りることも、贈与とみなされないために重要なことの一つです。
自分の収入を考えた場合に、とても返済できないような高額な借金は、贈与を前提として渡ししたとみなされる可能性があります。
親から借りる時でも、返済可能な額にするようにしましょう。
受け取った利息は確定申告
注意しなければならないのは借りる側が支払った利息の確定申告です。
例えば親からお金を借りたとしても、親が利息を受け取れば利子所得として確定申告しなければなりません。
利子所得は受取利息に税率15.315%と地方税5%を支払うことが決められていますので、確定申告期間内にきちんと申告するようにしてください。
返済不要の時の対策は贈与税の非課税枠をつかう
親から借金したときに返済を求められないときは、贈与となるケースが多いです。
制度をうまく利用して贈与税の対策を練りましょう。
暦年贈与にする
1月1日~12月31日の暦年毎に贈与する場合は、一人当たり110万円までなら非課税です。
年間110万円以下であれば数年にわたって贈与を受けても、贈与税はかかりません。
これを暦年贈与と言います。
暦年贈与の注意点は以下の3点です。
- 贈与契約書を作成する
- お金の受け渡しは銀行口座に限定する
- 受け取る金額を年間110万円以下にする
もし年間の受け取り額が110万円を超えた場合は、その超えた分に贈与税がかかります。
さらに毎年、同じ時期に同じ金額を贈与すると、連年贈与とみなされて贈与税が課税されてしまいます。
そこで暦年贈与を行う場合は、時期をずらしたり110万円以内で金額を変えたりするようにしましょう。
借金扱いなら非課税
お金の貸し借りは目的や金額にかかわらずに非課税となります。
しかし、親子間のお金の貸し借りの場合はお金のある時に返す、出世払いするなど返済方法が明確ではない取引が行われることが多いでしょう。
贈与税の支払いを防ぐためには、きちんとお金の貸し借りをしたという証拠が必要になりますので、注意をしましょう。
不動産は持ち分を分けて、残りの財産を相続
不動産の名義は、出した資金の額によって、所有割合を分けることが出来ます。
そこで、可能であれば自宅を買う時に資金の一部を親に出してもらいましょう。
例えば現金1000万円を贈与としてもらうより、不動産の購入資金として出してもらい、いずれ親の所有割合(持ち分)を相続するほうが税金は下がります。
親にも不動産取得税や固定資産税が掛かったり、他に相続人がいる場合は、相続時に財産分配の相談をする必要があったりしますが、相続人がほかにいない場合などは節税対策になるでしょう。
相続時精算課税を活用
両親が60歳以上の場合は相続時精算課税を利用することができます。
相続時精算課税は60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して財産を贈与したときに選択できる贈与税の制度のことで、この制度を利用すると2,500万円までなら複数年にわたって贈与を受けた場合でも贈与税はかかりません。
ただし、贈与してくれていた人が亡くなり相続が発生した場合、先に受けていた贈与分も相続対象の遺産に上乗せされて相続税が計算されます。
つまり、贈与税は掛からなくても、場合によっては相続税が発生する可能性があるわけです。
また相続時精算課税は一度選択すると、110万円の非課税枠を使用することはできず、また併用することもできないので注意が必要です。
相続時精算課税を利用するかどうかは、よく検討することをおすすめします。
なお相続時精算課税を使用して2,500万円を超えて贈与された場合は、その超えた金額に一律20%の贈与税がかかります。
贈与税が発生しない例
贈与になっても贈与税がかからない金額や発生しない特例をチェックしましょう。
なお、贈与税を非課税にするためには税務署への申告が必要です。
住宅取得金は贈与税非課税枠がある
親からの贈与で自分の家を建てる資金や増築の資金などを取得した場合は、一定の要件を満たす場合は贈与税が非課税になります。
住宅取得資金は贈与税非課税枠が増えるのです。
非課税限度額は適用を受ける住宅の新築などの契約の締結日に応じた金額です。
◆ 非課税限度額
| 住宅用家屋の新築などにかかる契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外 |
|---|---|---|
| ~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月1日 ~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 2020年4月1日 ~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 2021年4月1日 ~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅取得等資金なら、最低でも700万円は非課税です。(2018年11月現在)
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間で親から資金援助によって住宅の取得資金とした場合一定の要件を満たすと非課税となる金額が定められています。
消費税が8%の場合と10%の場合で非課税となる金額に違いがありますが、将来消費税が10%になることを考えて両方を併記しておきましょう。
また省エネ住宅か省エネ住宅でないかによっても金額が異なってきますのでご注意ください。
◆消費税8%の場合
・平成32年3月31日まで
:省エネ住宅1,200万円
:省エネ住宅以外700万円
◆消費税10%の場合
・平成32年3月31日まで
:省エネ住宅3,000万円
:省エネ住宅以外2,500万円
なお平成33年12月31日に近くなるほど段階的に非課税金額が減少されますので、住宅資金の援助受けることを考えている場合は平成32年3月31日までの手続きがお得です。
◆国税庁 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅の共用で贈与が発生しない
結婚している期間が20年以上の夫婦で住宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで非課税にできます。
親と子の間で共同で住宅を購入する場合でも適用され、支払った金額に応じて登記を済ませることで贈与税がかからないというものです。
必ずしも同居する必要がないためメリットがありますが、持分に応じて固定資産税がかかるなど負担金が増える場合があります。
ただし相続のこともありますのでしっかり話し合いをしましょう。共有登記が親になっていると持分に応じて相続をすることになりますので相続税が発生します。
◆国税庁 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
結婚や子育てに関するする資金は非課税
2019年3月31日までの間に個人が結婚や子育ての資金を親からもらった場合は、そのお金に贈与税は掛かりません。
しかし適用をうけるためには、お金をもらう人が結婚・子育て資金非課税申告書を、資金を受け取る口座のある銀行などの金融機関を通して預入等期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
生活費や教育費は非課税
生活費や教育費として必要と認められるものは金額にかかわらず非課税です。
生活費とは通常の日常生活に必要な費用を言い、教育費とは学費や教材費、文具費をいいます。
贈与税がかからないお金は直接これらに充てる場合を言い、もし貯金や株式や不動産を購入資金に充てた場合は贈与税が掛かります。
親にお金を借りるときは
親からお金を借りた理由として多いのは、「子供の授業料」「車や住宅購入の頭金」「引っ越し費用」「冠婚葬祭」などが上げられます。
親からお金を借りるとなると情けないという気持ちになり、つい嘘をついてしまうかもしれませんが、バレた時に親や身内を怒らせ、貸してもらえない可能性があります。
素直にお金が必要な理由を説明し、返済方法や返済期限などを明確にし、また約束通りに返済していくことが、のちのちの親子関係にも影響してくるため大切です。
結婚費用を親から借りる
結婚費用を親から借りることについては地方独特の習慣、双方の親の考え方によって違いがあるでしょう。
まだ若いのだから結婚費用を親から借りるのは仕方がないと言う考えもあれば、そもそも結婚によって独立するのだから、結婚費用は当人同士の貯金やブライダルローンを使ってやるべきという考えもあります。
一概に結婚費用を親から借りることは良いとも悪いとも言えませんが、基本的な考え方としては、結婚するお互いが持っているお金を持ち寄って、その範囲内の予算で結婚式を挙げることではないでしょうか。
結婚式には必ずご祝儀があります。ご祝儀も結婚費用の予算に組み込み、どうしても足りない分だけを親に頼むのが良さそうです。
結婚した後でも新婚旅行や出産などにもお金がかかります。
結婚をするということは自立するということですから、何から何まで親に頼るのはあまり感心しませんね。
車購入資金を親から借りる
車の購入資金はまとまった金額が必要です。新車で買うのか中古車で買うのかによっても違ってきますが数十万円から数百万円かかることも珍しくありません。
数十万円の金額なら親から借りることができたとしても、さすがに数百万円となると親から借りるのは無理がありそうです。
仮に車の購入資金を親から借りることができたとしても、年額110万円以上の借入は贈与税とみなされてしまう可能性があるために、必ず借用書を作って利息を支払うようにしたいですね。
また車を購入するには何も全額を現金で支払うばかりではありません。比較的金利の安いディーラーローン利用するか、または残価設定方式で車を購入すればかなりローン返済額を少なくすることもできます。
基本的には給料に見合った車を購入することですね。身の丈に合った車を購入する、これが一番ではないでしょうか。
生活費を親から借りる
親から生活費を借りる金額が1万円2万円なら問題ないとしても、失業してしまった挙句生活費がないとなると、次の仕事が見つかるまでの期間を考えると3カ月分くらいのまとまった金額が必要になることがありますね。
1か月当たりの生活費が20万円だとすれば、3カ月分で60万円です。
60万円の大金を借りる場合は、たとえ親子の関係でも社会人の常識として借用書を書くことは当然のことです。
借用書の雛形はインターネットからダウンロードすることもできれば、市販されているものをそのまま流用することもできます。
親が「親子の関係なんだから借用書なんていらないよ」と言ったとしても、社会人である以上は責務を果たさなければなりませんね。
借りる相手がたとえ親でも、民間の金融機関からお金を借りているのと同じように金利を定めて毎月返済するようにしましょう。
親だから借りたお金を返さなくても良い考えは甘すぎます。
親に迷惑をかけないためにも毎月きちんと支払うことを心がけてください。
親から借りるには返済能力が必要
いくら借用書を作成して親からお金を借りた事実を証明しても、毎月利息を支払っているとしても子供に十分な返済能力がないと税務署は贈与税を課税してくることがあります。
民間の金融機関からお金を借りるのと同じように、親から借りる金額によって返済能力が確かにあることを証明しなければなりません。
身内からお金借りるときの言い訳
もちろん、祖父母や親が認めてくれた場合に限りますが、親子間等の直径親族なら、かなりの額まで非課税でお金をもらうことも可能です。
ですが、単に「お金を貸して」「お金をちょうだい」と祖父母や親、その他の親戚に言うのはちょっと幼稚ですよね。
どのような言い訳をすると、快くお金を貸してくれたり、お金をもらったりすることができるでしょうか。
子どもの授業料が払えない
子どもには厳しくても、孫のこととなると突然甘くなるおじいちゃん・おばあちゃんは少なくありません。
お父さんやお母さんからお金を借りたいときは、自分に使うのではなく子どもに使うのだということをアピールして下さい。
教育ローンを借りるよりも低金利で借りられるかもしれませんよ。
きちんと利息を払うから貸して
銀行の金利はますます低くなっています。
ほとんどの都市銀行では、普通預金の金利は0.001%。
100万円預けても利息は10円。
そこから税金が20.315%差し引かれますので、受け取る利息はわずか8円ほどになってしまいます。
そのような超低金利状態ですから、「年に1万円の利息を支払うから」と言えば、100万円くらいは貸してもらえるかもしれません。
取り立てに追われていて・・・
すでにお金を金融会社から借りていて、取り立てに追われて大変だということを伝えてみるのも悪くないアイデアです。
「もしかしたら親戚(家族)ということで、うちにまで取り立てが来るかも・・・」と不安になって、急いでお金を工面してくれるかもしれません。
現実の取り立て行為については、次の記事で詳しく説明しています。
理由を聞かずにお金を貸して!
特別な理由を言わずに「黙ってお金を貸してほしい」と訴えることで、親戚縁者からの同情を得られる可能性があります。
ただし、親戚内であなたの評判が良いことが前提です。
普段から素行が悪く鼻つまみ者として知られているなら、お金を貸すどころか、本気で縁を切られてしまうかもしれませんよ。
おカネを借りるときのNG言い訳集
では、お金を借りるときに絶対に言ってはいけない理由や言い訳とは何でしょうか。
保証人になってしまった
「友人の保証人になってしまい、借金を背負ってしまった」「賃貸契約の連帯保証人になったら、知人が家賃を払わずに雲隠れした」等の保証人関係の言い訳は、例え事実であってもNGです。
兄弟姉妹や祖父母等の親族は、あなたというかわいい家族を守るためなら、多少損をしてもお金を貸してくれるかもしれません。
ですが、あなたの知人やあなたの友人は、いわば縁もゆかりもない人ですので、そのような他人のために一肌脱ごうとはしてくれないでしょう。
また、そのようなろくでもない人間関係を持っていること自体、あなたの評価を下げる原因となってしまいます。
もし、あなたに今後本当に困ったことが起こっても、誰も助けようとはしてくれなくなるかもしれませんよ。
保証人になってくれと頼まれたときの断り方については、次の記事でも詳しく説明しています。
生活費を貸してほしい
生活費に困っているというと、困難な状態が長く続くようなイメージを持ちます。
今月お金を貸してあげても、また翌月になったら「今月も生活費が足りなくて・・・」と言われる可能性もありますので、いくら身内であっても関わりたくないと思わせてしまうでしょう。
「急に入院費用が必要になって」「私立高校しか受からなくて入学金が足りない」などと、1回きりの急な出費のためにお金がなくなったということをアピールして下さい。
配偶者の借金のために・・・
既婚男性や既婚女性が使いがちな言い訳として、「夫(妻)が借金を作ってしまい、返済に追われている」というものがあります。
本当のところは自分が作った借金であっても、ストレートに言うことが恥ずかしいために、「夫(妻)が・・・」と嘘をつくこともあるでしょう。
ですが、融資を申し込まれた親族側の立場になって考えてみますと、「なんで旦那さん(奥さん)の借金を、こっち側で面倒見なきゃならないの?」となりますよね。
徒に親族間の不和を招くだけですので、配偶者の借金を(たとえ本当のことであっても)お金を借りるときの言い訳に使わないでくださいね。
住宅ローンの返済が多すぎて
住宅ローンも、お金を借りるときの言い訳に使うことは勧められません。
ほとんどの住宅ローンは何十年も続くものですから、今後も何度も「貸してくれ!」と言われてしまうかもと、相手に不安を抱かせるからです。
また、支払い能力以上の住宅ローンを組んでいるということも、親族へ悪い心証を与えてしまいます。
身の丈に合わない生活をしようとしていると捉えられるかもしれませんし、「うちは賃貸なのに、なんであなたが持ち家に住むためにお金を貸さなくてはいけないの?」と反感を与えてしまうかもしれません。
親族に貸したお金が返ってこない時は
反対に、あなたが身内にお金を貸したのに、なかなか返してもらえないときはどうすることができるでしょうか。
お金を貸すときに借用書や金銭消費貸借契約書を作っておくなら、訴訟を起こすときの有力な証拠となります。
ですが、裁判所であなたに有利な判決が出たとしても、借りた側に本当にお金がないときは返済してもらうことは不可能です。
弁護士費用や裁判費用だけかかって、結局は損失が大きくなっただけ・・・ということもありますので、「返済してもらえなくても諦められる金額」だけを貸すようにしましょう。
【借金回収】個人間で貸したお金を自力で返済してもらう労力と物的証拠
相続税と贈与税の違い
そもそも相続税と贈与税は一体何が違うのかという所からですが、相続税とは親族が他界したときに、残された家族が故人の財産を相続した場合に発生する税金です。
相続したからといってすべての財産に相続税が発生する訳ではありません。
贈与税とは1年間のうちにもらった財産に対して、発生する税金のことです。
相続税と贈与税の両方に共通するのは、基礎控除額より財産が下回っていれば税金は発生しませんし、上回っていれば発生するという仕組みです。
借入金を相続するとは?
借入金といった負債は、資産と同じように相続財産となります。
ただし、銀行からの借入金は一般的な相続財産と異なる点がありますのでこれから話すことを覚えておきましょう。
遺産分割協議ってなに?
相続は、法定割合といって相続人に引き継がれる資産や負債の割合が決まっています。
ただし、法定割合よる分割に納得しない相続人もよく見かけます。
そこで遺産分割協議といって、法定割合によらず、遺言や相続人同士での話合いで分割割合を決める方法が認められています。
この方法によって特定の資産や負債を相続人に引継ぎすることが可能となります。
しかし、ここで注意したいのが銀行借入は遺産分割協議の対象とならないという点です。
債権者と相続人の関係
先ほど話ししたとおり、銀行からの借入金は遺産分割協議の対象とはなりません。
それは、債権者である銀行が保護しているためです。
例えば相続人が2人いて、遺産分割協議によって片方に資産を全て相続し、もう片方に借金を全て相続したとしましょう。
その場合、銀行としては亡くなった被相続人の資産も、勘案した上で融資をしたにもかかわらず、資産のない相続人に融資を引き継ぐ形になります。
すると返済が滞る可能性も出てきますし、資産がないからといって相続人に自己破産をされかねません。
このようなことを防ぐためにも、銀行は遺産分割協議にしたがう必要がなく、相続人全てに法定割合分の返済を主張することができるのです。
言い換えると、借入をしている人は相続人みんなに返済の負担を負わすことにもなりかねませんので、これから話しする対策方法を覚えておきましょう。
相続より多額の返済!そのときの対応策
先ほど話ししたとおり、銀行借入は財産と同じように相続される上に、引受人を指名して相続することができません。
また、場合によっては相続人が財産以上の借金を引き継ぎ、多額の返済に苦しむことになりかねません。
そこで借入の相続対策についてまとめましたので紹介します。
借入れは生前に整理するのが理想
銀行借入金の相続対策として、生前に完済して整理しておくことが好ましいでしょう。
しかし、借入が多額になると一括返済するのが難しいかもしれません。
そこで、生命保険の利用を検討しましょう。
これは死亡保険金で借入残高を返済するという方法であり、掛け捨てタイプでしたら保険料も少なくなる可能性があります。
また、そもそも住宅ローンには団体信用生命といった生命保険が付いているケースが多いので、一度は確認しておくことをおすすめします。
銀行と交渉してみる
銀行借入は、遺産分割協議は適用されずに法定相続されるという話をしました。
ただし、相続人が銀行と交渉する余地はあります。
それは、銀行にとっても借入を案分して法定相続するより、返済が見込める人に全て相続してほしいからです。
このように、相続人のひとりが他の相続人の借入金を全て背負うことを、免責的債務引受け(めんせきてきさいむひきうけ)といいます。
ただし、借入を引き受ける相続人は銀行審査を受けるほか、場合によっては追加担保を差し入れするケースもありますので注意しましょう。
相続放棄という選択もあり?
借入金の相続対策として、資産も負債も含めて相続自体を放棄する方法も考えられます。
それは、相続する資産がなかったり、あったとしても換金性の低い同族会社の株式であったり、価値の低い不動産であれば、そもそも相続をするメリットが少ないからです。
ただし、相続放棄は被相続人が亡くなった3か月以内に手続きをする必要があり、それを超えると単純承認といって相続を認めることとなりますので注意が必要です。
生前贈与とは?
限られたケースになりますが、相続対策として借入金を生前贈与する方法も考えられます。
これは、アパートローンなど不動産の借入であれば、その不動産と一緒に借入も生前贈与できるといった負担付贈与を利用するものです。
この方法により、生前に特定の相続人に借入を引き継ぐことが可能となります。
ただし、債権者である銀行の同意が必要であるほか、贈与税や譲渡による所得税や住民税といった税金が発生する可能性がありますので注意しましょう。
借入金は相続財産から差し引くことができる
個人が残した財産がすべて、自身の財産にプラスとなるようなものばかりだとは限りません。
仮に借金をしていたとするならば、その借金も相続することになってしまいます。
銀行などの金融機関での借入金があった場合は、その分を差引きした金額を相続することができます。
金融機関としてもお金を貸していた契約者が他界したことが分かったときには、まず誰が相続したのかを確認し、その相続者に今後請求をかけてきます。
そのため、単純にその借金の金額分を引いた預金額が実質手元に残る財産となる訳です。
分かりやすく家族が知っている借金であればいいのですが、誰も知らなかったり後々になって借金が判明したりする場合は金銭トラブルのきっかけとなる場合もあります。
したがって、他界後は故人の持ち物を確認し、「借金などなかったのか」をまず確認しておくと安心でしょう。
分からないようであれば「信用情報機関」に問い合わせをして、「本人死亡の開示手続き」を行ってください。
そうすることで「この人は既に他界された」という番号が記載されますので、該当する金融機関から連絡が入り現状いくら借金をしているかも分かります。
貸手が親族でも遺産相続から控除することが可能
貸手が親族であったとしても、銀行などと同じ条件で相続されます。
例えば親から借金を500万円していたとしましょう。
親が他界し相続した金額が2,000万円だった場合には、本来相続すべき金額2,000万円―借入金500万円=1,500万円を相続することになります。
債務と確実に認められることがポイント
借金の分を差し引けるということは、その分相続する財産が少なくなり、税金の控除に該当する可能性が高くなってきます。
しかしここでのポイントは、「これは間違いなく債務であります」と税務署に認められることです。
これが不明確になってしまうと、税務署から「いやこれは単なる贈与でしょう」と突っ込まれてしまう可能性が出てきます。
贈与とみなされれば差引きもできませんし、その金額が多きければ基礎控除額を超える可能性が出てきて贈与税が発生してしまいます。
相続税の基礎控除をしっかりとおさえよう
相続税は個人の資産を相続したら必ず発生する税ですが、控除されるべきものもありますのでまずはそこをしっかりとおさえていきましょう。
相続税基礎控除の計算方法は、3,000万円+(法定相続人×600万円)です。
仮に法定相続人が2人だとしたら、「3,000万円+2人×600万円=4,200万円」となります。
そして、相続した金額が4,200万円以上であれば相続税が発生するという内容になります。
基礎控除内であれば申告手続きは不要
計算で基礎控除内になったならば申告の義務がありませんので、特に申告手続きも必要ありません。
ただし「優遇措置」を使って基礎控除内になった場合には、申告をする必要がでてきますので注意が必要です。
相続税で認められている優遇措置とは
優遇措置も細かく規定がありますが、一番身近になるのは配偶者の税減処置でしょう。
これは夫婦どちらかが他界し、配偶者が財産を相続しても税金が発生しないように認められた優遇措置です。
この優遇措置は申告しないと、税金がそのまま発生してしまいますので、注意が必要になります。
借入金は控除可能?
他界した人に借入金があった場合には差引き控除が可能です。
ただし「これは確実に借入金である」と認められることが大前提になります。
身内間で口約束などの方法で行う借入金は、証明するのが少し難しくなりますので、注意が必要になります。
また借入金とは少し意味合いが異なりますが、未納の税金があった場合も控除は可能です。
住宅ローンは控除不可?
住宅ローンは同じ「借入金」という仲間に感じますが、実は控除対象ではありません。
しかし、「控除もできないならば、そのまま負の遺産として相続するしか方法はないのか?」と思う人もいるでしょうが、安心をしてください。
ポイントは住宅ローンを組むときに、団体信用生命保険に加入していたかどうかです。
もし、加入をしていなければ、そのまま控除されず相続人に住宅ローンは引き継がれます。
金額によっては財産放棄の手続きを取る必要がでてくるかもしれません。
しかし団体信用生命保険に加入していたならば、契約者が他界したときの残高に応じて生命保険会社が受取人に保険金を支払い、そのお金を持って住宅ローンを完済させることができます。
保証債務は債務と認められない
では、故人に直接的な借入金はない場合で、保証人になっていたときはどうなるのでしょうか。
基本的に保証債務は控除としては認められません。
あくまで「保証していた」だけですので、個人が主として借入をしていた訳ではないという判断になります。
しかしどうしても保証していた人が支払い困難になり、代わりに支払うしかない場合や、保証をしていた人にその分を返還するように求めても応じられない場合には、相続税の控除対象となります。
◆国税庁公式サイト:「相続税基本通達 14-3(保証債務及び連帯債務)」
相続開始前3年以内に贈与を受けたときのポイント
何かしらの財産を贈与してもらって3年以内に相続すべき人が他界した場合には、以前に贈与した分も相続税に加算されてしまいます。
いつ他界するかなんて誰にも分かりませんので、万が一3年以内に贈与してもらった人は注意が必要です。
贈与を受けた財産は相続財産になる?
3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産とみなされます。
「既に故人の財産ではないのに」となりますが、相続税節税対策として生前贈与とされないように、3年以内という年数で縛っています。
また、贈与税控除額のラインである110万円以下の財産でも加算されるますし、相続税にプラスされる金額は贈与された当時の評価額となります。
また形あるものばかりが贈与される訳ではありません。
大金が動くことが多い住宅取得時に資金の贈与を行っていた場合には、金額が非課税であれば加算されませんが課税対象ならばプラスされます(非課税金額は年度によって変動するので確認しておいた方がいいでしょう)。
過去3年以内の贈与税は相続税で控除?
単純に過去3年以内に贈与された場合でも、贈与されたときに支払った「贈与税」と言う税金もありますし、そのうえ相続税に加算されるとなると税金の二重払いになってしまいます。
そのため相続税控除の優遇措置として、「贈与税控除」という控除ができるようになっています。
気をつけておきたい「借金の時効」
いくら形式上色々な書類がそろっていたとしても、そもそも全く返済をしていなければ借金があったと認められる可能性が低くなってきます。
個人間の借金の時効は10年です。
もちろん途中で支払い督促を簡易裁判所に提出し、書面が債務者に届いた時点で時効は中断しますが、何もしなかった場合は時効が成立してしまいますので注意をしてください。
まとめ
親からの借金を確定申告するときに、贈与税として税金がかからないようにする方法を紹介しました。
贈与税の課税対象外という贈与も理解して、対策をしっかり行えば贈与税がかからない方法は意外と多くあります。
なにより親子間でもお金のやり取りはきちんと契約書を交わすようにしましょう。
タグ:借金・お金の悩み















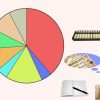










































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。