借入金で税金の節約ができる?借入金の有効活用方法を解説
「税金対策のために借金をする」というようなことを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
いったいなぜ借金が税金対策のなるのでしょう?
今回は税金と借金の関係についてご説明します。
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
この記事はこんなひとにおすすめ
今回の記事は以下の人におすすめの内容です。
- 借入金と税金の関係を知りたい
- 借入金で贈与税の支払いが必要になるケースが気になる
- なぜ借入金に税金がかかるかを知りたい
借入金に税金がかかる!?
借入金と税金対策をする関係を説明する前に、借入金に税金が必要かどうかを紹介します。
借入金は経費にならないことは、広く知られていますが、所得税などの税金に関してはどのような扱いになるか知らない人もいます。
そこで、借入金と税金に関する情報を詳しく解説します。
借入金に所得税はかからない
結論から先に言わせてもらうと、借入金には所得税や法人税などの法律がかかることはありません。
したがって、借入金は所得税が非課税となるため、基本的には税金を気にする必要はないです。
他にも住民税など税金も非課税となっているため、借入金を行ったときに支払う税金としては、契約書の印紙税程度となっています。
借入金は収入か?
借入金は自分の通帳内にお金が入ってくるため、収入として考えてしまいやすいですが、会計や財務上では負債として考えるため収入には含まれません。
したがって、収入や所得に対して支払わなければならない税金に関しても、支払いをする必要はないのです。
贈与とみなされると贈与税がかかる
これまでに、借入金は税金が必要ないと紹介してきましたが、一部のケースでは贈与税が必要となる可能性があります。
借入金として契約を結ぶ場合には、贈与ではないため贈与税ではありませんが、家族や知人間での取引きの場合には、一定期間返済を行っていなかったり、利息の支払いが行われていない場合には、贈与として判断されるケースがあります。
110万円を超える金額から贈与税の対象となるため、贈与税と税務署から判断された場合は税務署から督促がくる可能性があるのです。
贈与とみなされ税金がかかるケースとは
借入金の中には贈与と判断されるケースがあると紹介しましたが、具体的にはどのような状況が当てはまるか気になります。
そこで、どのような状況で税金が必要になるかを紹介します。
利息なしの借入金の場合
一般的にはお金の貸付を行った場合には、取立てのコストを考えると利息を徴収しないということはありえないです。
したがって、借入を行うときに無利子で貸し付けを行っている時点で、「回収する意思がないのでは」と税務署に疑われるため、贈与とみなされる可能性があります。
親子間の貸し借り
親子間の貸し借りを行うときには、特に贈与税として疑われる可能性が高いです。
親子間では最初はお金の貸し借りと思って行ったとしても、途中で返済が難しくなり返済を行わないという例が良くあります。
したがって、親子間の取引きを行うときには借入金と判断してもらえるように、特に気を付けなければなりません。
兄弟間のお金の貸し借りに贈与税はかかる?
兄弟間の貸し借りであったとしても、親子間での貸し借りと同じように贈与税がかかるケースはあります。
借入金額や利息の金額、返済の有無などから借入金と判断されなければ、贈与と判断されて贈与税が必要となる可能性があります。
借入金を贈与と判断されないためには
借入金を贈与と判断される可能性は複数あるため、対策を立てなければ贈与税の督促がくる可能性があります。
そこで、借入金を贈与と判断されないために、どのような対策を行えるか紹介します。
少しだけでも利息を払う
贈与税と判断されてしまう項目として、利息の支払いがないことが理由としてあるため、少額の利息でも良いため利息の支払いを行うことがおすすめです。
利息の支払いも金融機関の様に「借入金額に対して〇%」と、毎月変動する金額を設定しなくても良く、毎月定額の金額を少しずつ返済すれば贈与とは思われにくいです。
定期的に返済する
無期限で貸付を行っていると、借入金ではなく贈与と思われやすいため、毎月定期的に返済を行うことも大切です。
先ほどの利息と同じで、金額が少額であっても問題なく、最終的に返済ができれば良いため、毎月の支払い額は一定でも大丈夫です。
契約書を用意する
家族間や知人との借入金でも、贈与と判断されないように契約書を準備することも重要です。
契約書に「貸付を行った」と記入されていれば、贈与ではないと主張が行いやすいため、面倒であったとしても契約書を準備することが大切です。
ただし、契約書と言っても金融機関で使われているような、厳粛な長い文言の書いた書類である必要はなく、手書きでも良いので必要事項を記入した内容のものを用意してください。
返済できる範囲の金額を借りる
貸付する金額が高額すぎて、とても返済の目途が付かない様な金額である場合には、贈与と判断されやすいので気を付けてください。
例えば、20代の子供に対して1,000万円以上のお金を貸した場合には、常識的に考えて返済をする意思がないのではと疑われます。
貸付金額も常識的範囲内で納めるようにして、返済が可能である金額にとどめることで貸付と判断されやすいです。
借入金を返済しても節税にはならない
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、借金の返済自体には全く節税効果はありません。
借入金は負債になりますので、借入を行い、負債を背負うことによって、現金という資産を手に入れています。
返済時には、資産である現金から負債を減少させていくだけとなります。
バランスシート上で借方と貸方が動くだけですので、借金をしても、借金を返済しても費用にはならないため、税金を節税するために利益を圧縮するという効果は全くありません。
個人事業主の確定申告
個人事業主は毎年3月15日までに確定申告を行わなければなりませんが、このときには借金がいくらあるかで、税金の額が変わるようなことは全くありません。
あくまでも、税金の計算は所得に対して行われるため、借入金の金額がいくらであるかは関係ないのです。
また、個人の所得税の税率は累進課税という所得に比例して税率が上がっていく仕組みで、以下のようになっています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得が200万円であれば200万円×10%-97,500=102,500円が納税額となります。
この所得の計算に必要なのは、売上と経費を計上した損益計算書だけで、資産や負債を計上した貸借対照表は必ずしも必要ありせん。
青色申告で借入金を計上
青色申告は複式簿記によって毎日の取引を記録し、それに基づいて確定申告を行う制度です。
税務署の承認を受ける必要がありますが、税務署のホームページなどで確定申告を行う場合には青色申告書を作成するのは非常に簡単です。
青色申告には特別控除というメリットがあります、資産と負債を計上した貸借対照表(バランスシート)の作成があれば65万円が、損益計算書だけであれば10万円が所得から差し引かれます。
先ほどの事例で貸借対照表ありで青色申告を行った場合には、(200万円-65万円)×10%-97,500円=37,500円となり、6万円以上の節税効果があります。
貸借対照表には借入金も記載されますが、ここに借入金があるかどうか、いくらあるかでは納税額は全く変わりません。
法人税率
ちなみに法人の場合には税率は個人と異なり、所得によって税率が段階的に変動することはありません。
法人税は法人所得税、法人住民税、法人事業税という3つの税率がありますが、これらの実質的な負担税率を法人実効税率と言います。
現在の法人実効税率は34.62%となっています。
所得税だけで見ると所得が800万円以下で15.0%、800万円超の中小法人が23.4%、それ以外の法人は23.4%となっています。
利益が一定以上出てくると税率は個人の所得税よりも法人税のほうが低くなるため、ある程度事業が軌道に乗った個人事業主は法人成りするのです。
ここでも、借入金があるかないかでは所得は変動しませんし、借入金の返済を経費に算入することもできません。
経費には参入できない
ここまで説明したように、税金は所得に対して発生するものです。このため、節税を行うのであれば、所得を少なくするのが最も基本的な考え方です。
借入金はあくまでも借りたときはバランスシートが借方も貸方も同時に増加する、返済したときにはバランスシートが貸借双方とも減少するだけです。
資産と負債が動くだけですので、損益には全く影響しません。
借入金の返済を行う人は現金が実際に出ていってしまうため費用のように感じてしまいますが、これはあくまでも借りたお金を返しているだけです。
借入金の返済そのものは人件費や光熱費のように、経費に算入して利益を圧縮できるものではありません。
借入金に関する仕訳
ちなみに借入金に関する仕訳は以下のようになっています。
100万円を借りたとき
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金100万円(資産の増加) | 借入金100万円(負債の増加) |
100万円を返済したとき
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 借入金100万円(負債の減少) | 現金100万円(資産の減少) |
このように、お金を借りても返しても、動くのは資産と負債だけです。
では利息をつけて返済した場合はどうなるでしょうか?
借入金100万円を利息2万円とともに返済したとき
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 借入金100万円(負債の減少) | 現金102万円(資産の減少) |
| 支払利息2万円(費用) |
支払利息は費用として損金算入できる項目です。
ここで初めて2万円分だけを経費として所得を圧縮できることとなりました。
このように、借入金において所得を圧縮する効果があるのは支払利息だけで、利息部分に関しては節税効果があります。
借入金で税金対策ってどういうこと?
では、借入金で税金対策を行うとはどういうことなのでしょうか?
相続税を節約できる
借入金によって税金対策を行うケースとして最も多いのが相続税です。
相続のときには資産と負債の両方を相続します。
このとき、例えば資産が1億円、借入金が5,000万円あった場合には、相続税の課税対象となるのは1億円-5,000万円=5,000万円となります。
これが借入金による最も大きな税金対策です。
債務控除できる借入金には以下のような借入金があります。
- 住宅ローンの借入金
- 事業の売掛金
- 金融機関からの借入金
- 事業の未払金
- 医療費の未払金
- アパートローンの借入金
大地主の高齢者が借金をしてアパートを建設する場合がよくあります。
現在、社会問題化していますが、これはまさに債務控除により税金対策を行う目的から行われています。
さらに家賃収入から借入金の返済可能という甘い言葉に乗って大変な思いをしている地主さんも少なくないようですが、いずれにせよ、アパートローンの借入金は債務控除の対象となります。
ただし、注意しなければならないのは、建築したアパートも資産としてカウントされてしまうということです。
借金をした金額が○○債務控除できるわけではなく、債務控除できるのはあくまでも借入金-建築によって増加した資産の差額だけですので注意してください。
現在相続税は以下の基礎控除額を超えた分だけは課税対象となります。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
子供が2人、配偶者が1人いる場合には3,000万円+600万円×3=4,800万円
この場合には4,800万円を超える部分だけが相続税の課税対象になります。
仮に、資産が5,000万円あった場合には200万円だけ債務控除を行うだけで、すべての相続税は非課税となります。
利息部分を損金算入できる
先ほど仕訳のときに説明したように、借入金の返済金そのものは費用ではないため、所得の圧縮効果も節税効果も全くありません。
経費に算入できるのは支払利息だけです。
高金利の借入を行って多くの利息を払ったほうが当然ながら節税効果は大きいですが、この場合には一般的には納税額のほうが大きくなります。
ポイントとなるのは所得によって税率が変わる境目です。
個人事業主であれば所得900万円と901万円で税率が10%も異なります。
法人も所得800万円以下と800万円超で税率8%以上も変わります。
このため、借入金の支払利息を経費計上することで、税率が低くなる所得の範囲内に抑えることができれば節税効果があります。
住宅ローン減税
住宅ローンを組むと、住宅ローンの残高に応じた所得税の控除を受けることができます。
借入金で減税を行う方法として個人に最も身近な減税がこの住宅ローン減税です。
住宅ローン減税は住宅ローンの年末残高の1%を所得税から税額控除を受けることができるという制度です。
例えば住宅ローンの年末残高が3,000万円であれば1%の30万円を所得税から控除できます。
所得からの控除ではなく、税額からの控除ですので、他の税金対策よりも大きな節税効果があります。
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年だけは自分で税務署に行って確定申告を受ける必要があるのです。
2年目以降は銀行から送付されてくる住宅ローンの年末残高証明書を年末調整時に会社に提出することで、源泉徴収された所得税が還付されてくるという流れになります。
Q&A:借入金と税金に関する5つの質問
借入金と税金に関する情報を解説してきましたが、まだまだ伝えきれていない情報がいくつかあります。
そこで、借入金と税金に関する質問の中で、良く疑問にあげられるものに5つ回答しているので、知らない内容がないかを確認してください。
遺産相続時に相続税が多めに取られる危険性があるので気を付けてください。
また、友人間であったとしても金額が110万円以下の場合には贈与税の対象とならないため、税金がかかる心配はないため、借入金額が少額の場合には税金の心配はいりません。
しかし、お金の返済とともに利息を受け取った場合には、雑所得として計上しなければならないため、確定申告で記入する必要があります。
住民税の計算に用いられる金額も、収入や所得を使うため所得税と同じように、利息の受け取りがなければ関係ないです。
したがって、繰越欠損金などと相殺して税金がかからないように調整することもあります。
まとめ
借金で所得税、相続税などは節税できます。
ただし、借金には利息がつきものです。税金対策と考えて借入を行ったけど、実際には利息の負担のほうがが大きくなってしまったというような可能性も排除できません。
このため、借金で税金対策を考える場合には、税理士などへ相談をしたうえで、借金をすることが得なのか損なのかをよくよく勘案したうえで判断するようにしましょう。
タグ:その他金融業者




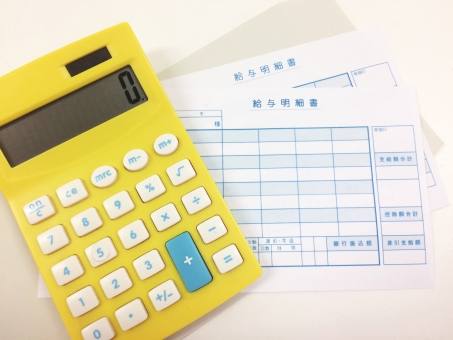

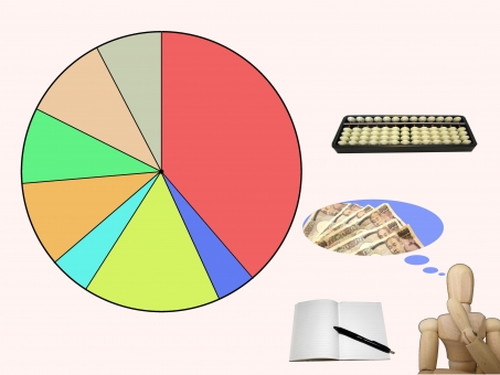








































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。