借入者、債務者とは?
○○資金の借入者、○○ローンの借入者といった言葉を見かけることがありますが、それと共に債務者という言い回しが使われるケースも少なくありません。
では、借入者と債務者とははどういった意味なのでしょうか。
実は、この2つは言い方こそ違えど、まったく同じ意味を持つ言葉です。
金融機関との契約においては、借入者よりも債務者という言葉が使われるのが一般的です。
契約内容には連帯債務者や第三債務者といった、類似した呼び名もよく出てきます。
そこで今回は借入者と債務者が持つ意味について掘り下げ、関連するワードについても説明していくことにします。
金融機関との付き合いが必要になる年齢となれば、知っておくべき言葉となるので、最後まで目を通し、金融用語の基礎知識として身に着けるようにしてください。
この記事はこんな人におすすめ
- 借入者と債務者との違い、使用用途を知りたい
- 関連するワードとの関係性を知りたい
借入者とは借入している人のこと
一言で説明すると借入者とは「借入」を行う、あるいはその手続きを行っている人のことです。
何かに出場する人が「出場者」、申込を行う人を「申込者」と呼ぶように、これは読むがごとしで、クドクドとその内容を説明する必要はないでしょう。
借入金とは借金のこと
では借入とは何なのかというと、お金や物を借りることを意味します。
しかし、個人や会社が金融機関から、お金を借りることを指す際に、利用されるのが一般的です。
物を借りるのに使用しても間違いではありませんが、友人からゲームを借りることを借入と表現することはあまりありませんよね。
個人間の物の貸し借りではなく、銀行・消費者金融などの金融機関でカードローンや住宅ローンを利用して、お金を借りることを借入と表現するという認識でいいでしょう。
ローンとの違いは?
カードローン会社のカードローンや、銀行の住宅ローンのように、金融商品にはローンと銘打った金融商品が数多く見られます。
この「ローン」も金融機関からお金を借りることを意味しますが、借入とローンはどう違うのでしょうか。
ローンというのは一部の例外を除いて、お金の使用目的が決まった状態でお金を借り、あらかじめ決められた返済方法に則って、分割で支払いを行う金融商品のことを指します。
よって、契約方法を明確にした借入の、別呼称であると認識してもらえばいいでしょう。
これに対して借入は、金融機関からの借入全てが、それに相当します。
そのためローンは借入の1つの表現方法であり、借入の中にローンが含まれるというわけです。
借入者と債務者は同じ意味
借入者に似た言葉に、債務者があります。
債務というのは簡単に言えば借金のことで、債務者と借入者は共にお金を借りている人を指します。
つまり、銀行とカードローン利用者の関係で言えば、カードローン利用者のことを債務者と言い、借入者と債務者の両者は、全く同じ意味の言葉というわけです。
ただし、法律上では債務者という言葉を使いますので、借入者よりも債務者の方がより正式な言葉であり、借入者は少し砕けた言葉という違いがあります。
つまり、利用する場面によって、この両者が使い分けられているというわけです。
金融機関が借入者に対しての連絡をする場合に「○○借入者の皆様へ」という言い方をすることがありますよね。
これは債務者という表現をすると借金というイメージが強いため、利用者への配慮された結果でしょう。
このように使う側の意図が込められている場合もあり、使用されるシーンは様々です。
連帯債務者にも返済義務がある
借入を行う際、連帯債務者を設定することがありますが、連帯債務者は債務者と同様に、借金の返済義務を負う人を指します。
いい例が夫婦で収入合算して住宅ローンを組むペアローンです。
このペアローンは連帯債務ローンとも呼ばれ、2人の収入合算金額でローンが組めるため、借入できる額を大きくできるメリットがあります。
しかし、連帯債務ローンで注意してもらいたのは、支払い義務を課せられる割合です。
連帯債務ローンは収入割合に応じて、支払い義務を負うのではなく、500万円のローンならば、夫婦両者がそれぞれ500万円の支払い義務を負うことになります。
実際は住宅ローンの持ち分割合を夫婦間で自由に決定することができ、大抵の場合は、年収の高い夫が(主)債務者、低い妻が連帯債務者となるパターンが一般的です。
連帯債務者という名前からは、その人自身が直接お金を借りているようなイメージは湧きませんが、債務者と同額の借金をしている立場であることを理解しておきましょう。
連帯保証人との違い
連帯債務者と似た言葉に連帯保証人という言葉があります。
おそらく、この連帯保証人の方が認知度は高いのではないでしょうか。
中には両者を同じように考えている人もいるようですが、この両者では債務に対する返済義務が全く違ってくるので、注意が必要です。
連帯債務者は常に借金の返済義務を負いますが、連帯保証人の場合は、債務者が返済不能となった場合に限り、借金の返済義務を負うことになります。
つまり、連帯債務者は債務者と同様に、借金をしている当人となりますが、連帯保証人は、債務者が返済不能に陥った場合に、返済を保証する人のことです。
よって、連帯保証人自身が直接借金をしているわけではありません。
収入合算のペアローンには、連帯債務者のタイプもあれば、この連帯保証人を用いたタイプもあります。
この場合は連帯債務者の場合とは違い、住宅ローン債務を直接追うことにはなりません。
よって、債務者という立場にはならないため、住宅ローン控除も受けられませんし、団体信用生命保険への加入もできません。
夫婦合算で返済を行うのであれば、連帯債務者としてのペアローンの方が、メリットは高くなってくるでしょう。
この違いは誤解のないように、よく理解しておきましょう。
連帯保証人について、詳しくはこちらをご覧ください。
第三債務者という関係性
「第三債務者とは?」
そう聞かれても、ちゃんと説明できる人は多くないでしょう。
普通の人にとっては、まったく聞きなれない呼び方でしょうし、中には初めて耳にするという人も多いのではないでしょうか。
実はこの第三債務者は、債務者が返済問題により、裁判所から財産の差し押さえが執行された際に登場します。
財産の差し押さえの対象となるのは、大きく分けると下記の3つです。
- 動産:現金や換価できる宝石や高級腕時計など
- 不動産:土地、不動産
- 債権:債務者が第三者に対して持っている請求権
ここで注目してもらいたいのが3つ目の債権です。
債権には下記のようなものがあり、差し押さえする動産、不動産がない場合、債権の存在が明らかになれば、債権者は債権執行によって、債務者が持つ債権を差し押さえすることができます。
- 預金債権:銀行にある預貯金
- 賃金債権:雇用主が従業員に対して支払う賃金
- 売掛債権:取引先への売掛金
- 保険金請求権:保険会社に対する解約返戻金
- 敷金返還請求権:貸主に預けた敷金
これら債権金額を抱えている対象は、債務者から見れば、債務者が債権者となり、相手が債務者というスタンスになります。
そのため、これら債務者をひっくるめて、全てを第三債務者と呼ぶのです。
これら第三債務者に対する債権を差し押さえする場合は、裁判所から債権差し押さえ命令が通達され、弁済期間内に差し押さえ額に相当する債権額が差し押さえされます。
よって、中には下記のように苦情が出るケースも出てくるので、相手への配慮が必要になってくることもあるでしょう。
- いきなり債務者扱いされて迷惑だ
- 無駄な業務が増えてしまった
- 第三者の尻ぬぐいなんてしたくない
事実、いきなり差し押さえ通達が届くのですから、第三債務者に当たる人たちに、迷惑を掛けることに違いはありません。
しかし、いざ差し押さえとなれば、こういったケースも出てくるので、自分だけの問題では済まないことをよく覚えておきましょう。
対義語は債権者、貸付者
借入者や債務者の対義語には「貸付者」、「債権者」などが挙げられます。
貸付というのは人にお金を貸すこと、債権は貸したお金の返済を要求する権利のことです。
借入者の反対ということなので、「貸付者」、「債権者」は、もちろんどちらもお金を貸している人という意味となります。
先ほどの銀行とカードローン利用者で例えると、銀行が債権者、あるいは貸付者です。
よって、堅苦しい言い方で言えば、弁済期間で発生している借入額は、債権金額、または債権額といった呼び方となるでしょう。
借入の反対は返済と考えることもできますが、借入者や債務者の対になる存在は貸付者と債権者になります。
債権者と貸付者も同じ意味と考えてもらって問題ありませんが、債権者の方がより正式な言葉として覚えておくようにしてください。
債権者が持つ債務者への効力は
債権者は貸したお金の返済を要求できる権利を有する人を指しますが、果たしてその権利はどこまでの権限があるのでしょうか。
債権者が債務者に返済を求めて、すんなりと返済される場合は問題ありませんが、いつもそうすんなりと事が進むわけではありません。
中にはお金がないなどの理由で、返済を渋る債務者も出てくるでしょう。
そこで押さえておいて欲しいのが、債権者が持つ、下記5つの効力です。
- 給付保持力
- 訴求力
- 執行力
- 貫徹力
- 掴取力
それではこれら権限について、分かりやすく説明しておきましょう。
給付保持力とは
少し難しい言い回しになりますが、給付保持力とは債務の履行によって、給付を受けた場合、それを保持し続けても違法に当たらない効力を指します。
かみ砕いて説明すれば、10万円のテレビの売買契約ならば、売主は買主から受け取った10万円を自分の物にできるということです。
訴求力とは
訴求力とは、先に話した返済を求めても応じてもらえない、債務不履行となった場合に効力を発揮する権利です。
裁判所に下記申し立てをすることで、強制的に債務者の財産を差し押さえできる権利を取得することができます。
- 支払督促
- 民事調停
- 訴訟
裁判所へ債権の存在があることを、訴えることができる効力ということですね。
執行力とは
執行力とは、訴求力で得た判決内容を、そのまま執行できる権利を指します。
裁判所から差し押さえ判決が下れば、債務者の財産を差し押さえることができるというわけです。
また、この執行力には、次の貫徹力と掴取力の2つの効力によって、権利実行を行います。
貫徹力とは
貫徹力とは契約内容をそのまま、強制的に実行させるための効力を指します。
債務者との契約が卵を100個渡すというものであれば、その契約通りの債務を強制実行させるといった具合です。
掴取力とは
そして貫徹力に対して、掴取力は、債務者の財産を差し押さえ、換価することで債務と同との価値がある金銭で弁済させる効力です。
借入者の読み方は「かりいれしゃ」
ここまで借入者という言葉は漢字で書いてきましたが、もしかしたら読み方が分からないという人もいるのではないでしょうか。
借入者は、「かりいれしゃ」というのが正しい読み方です。
借入を「しゃくにゅう」という読み、「しゃくにゅうしゃ」と言う人もいるようですが、「かりいれ」が正式な読み方と決められているので、借入者も「かりいれしゃ」という読み方になります。
辞書には「しゃくにゅう」という読み方も記載されているため、「借り入れ」のように書かれていない限りは、「しゃくにゅう」という読み方でも特に問題はありませんが、人に伝える際は「かりいれ」の方が伝わりやすいです。
また、正式な場面では「かりいれ」と読むようにしましょう。
Q&A
Q.借入者が亡くなったとき、借金はどうなる?
借入者が亡くなった場合は、相続人が死亡者の財産を相続するかどうかで、借金の行方が違ってきます。
相続するものは現金や換価価値のある不動産ばかりではありません。
借金等の負の遺産があれば、それも併せて相続することになるのです。
借金がある場合は相続放棄すれば、連帯債務者や連帯保証人などになっていない限りは、その子供や家族に返済の義務が移ることはありません。
確定債権の方が多く、相続した総額で弁済できないようであれば、最悪、裁判所から強制執行による差し押さえが実行される可能性も出てくるのです。
そのような場合は、相続放棄することをおすすめします。
しかし、相続放棄する際ためには、 家庭裁判所への申述の届出が必要になります。
決められた期間内に届け出を出さなければ、自動的に相続を認めたことになるので注意が必要です。
Q.相続人に支払う能力がない場合はどうすればいい?
相続放棄が遅れ、負の遺産を相続することになったが、相続人に支払う能力がないというケースも少なくありません。
- 少額個人再生
- 特定個人再生
まとめ
借入者や債務者、貸付者、債権者など、言葉だけを聞けば難しそうに思えますが、借入や貸付などの意味を知ればそれぞれの言葉の意味も簡単にわかります。
- 借入者・債務者→お金を借りる側(例:カードローンの利用者)
- 貸付者・債権者→お金を貸す側(例:銀行)
借入者は借金を返済しなければなりませんが、返済中に亡くなった場合でも遺産の相続を拒否すれば返済も免除されます。
タグ:お金の知識



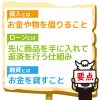









































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。