法人を解散したときの借入金はどうなるの?
企業は後継者がいなかったり、経営悪化で今後の見通しが立たなかったりする場合は、法人を解散させることも考えます。
法人解散時の清算方法を一歩間違えると経営者が借入金の一括返済を求められたり、多額の税金を払うことになったりしますので注意が必要です。
法人の解散時に気になる疑問点を、まとめましたので見ていきましょう。
有限会社の解散手続きは?
有限会社を解散するには所定の手続きが必要です。
解散しますと宣言しただけで簡単に解散することはできません。
具体的には、法務局での解散登記と清算結了登記を行う必要があります。
なお、本社がどこにあるかによって、直轄している法務局が異なるので注意してください。
それでは、有限会社の解散について詳しく見ていきましょう。
会社法により解散理由が定められている
会社法という法律によって有限会社の解散理由は、以下のように定められています。
- 存在期間満了など約款で定めた解散事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 解散命令
- 解散判決
株式会社と有限会社の違い
株式会社と有限会社の解散手続きに大きな違いはありませんが、一部に異なる点が存在します。
違いを知らずに焦ってしまうことがないように、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
有限会社では清算人会を設置できない
株式会社と違って、有限会社は清算人会の設置ができません。
ちなみに清算人とは、会社が解散した後に業務を取り仕切る人のことです。
会社が解散したということは、解散以前の利益を目的とした業務は行っていないため、清算会社として清算業務をメインに行うことになります。
そして、清算人会とは清算人の業務を監督するための機関です。
株式会社よりも特別決議の要件が厳しい
会社を解散するかどうかを株主総会で決定するためには、特別決議を行う必要があります。
この特別決議において株式会社の場合は、株主の半数以上が出席するという条件を満たした上で、さらに3分の2以上の賛成を得る必要があります。
しかし、有限会社の場合は、株主の半数以上という点は同じですが、4分の3以上の賛成が必要です。
株式会社よりも厳しい要件であるため解散になりにくいと言えるでしょう。
有限会社の解散手続きは?
有限会社を解散することが決定したら、まずは清算の手続きを行うことになります。
だたし、合併や破産による解散の場合は清算の手続きはありません。
なお、清算とは債権を取り立てることや、債務を弁済すること、加えて財産を株主に分配するなどもことです。
清算業務が全て終わったとしても株主総会において、決算報告の承認が必要になりますので注意してください。
そして、株主総会において清算の決了をした日から2週間以内に、清算決了の登記を行って解散手続きは終了です。
有限会社を解散する際の注意点
これまでに株式会社との違いなどを確認してきましたが、有限会社を解散するときの注意点は他にもあります。
まだ違いがあるのかと感じるかもしれませんが、残りわずかですからしっかりと確認しておきましょう。
有限会社はみなし解散の適用除外となる
株式会社にはどれだけ期間が空いたとしても10年に1回は、変更登記を行わなければなりません。
しかし、一番最後に登記をしてから12年が経過した場合、廃業していないのであれば登記しなさいという通知が届きます。
この通知が届いてから2か月が経過しても登記を行わなかった場合には、解散したと見なされるため、清算決了の登記を行わなくても解散したことになるというのがみなし解散です。
しかし、有限会社の場合には法律でみなし解散について定められていないため、12年以上が経過してもみなし解散の適用除外となります。
放置しておいても解散したことにはならないので、十分に注意をしてください。
解散時には手数料などの支出が発生する
有限会社を解散するためには、様々な手続きを行うために手数料が必要になります。
業況が悪いことが原因で解散する場合には、手数料を捻出することも厳しい状況である可能性も考えられるでしょう。
しかし、手数料を払わずに解散することはできませんので、資金を準備する必要があります。
なお、必要な手数料で代表的なものを一覧表にまとめておきますので、参考にしてください。
| 解散登記 | 30,000円 |
|---|---|
| 清算人登記 | 9,000円 |
| 清算決了登記 | 2,000円 |
| 官報広告のための費用 | 40,000円程度 |
ここで紹介しているものが全てというわけではなく、会社によって他にも必要となる費用があるでしょう。
最終的にどれくらいかかるかを事前に正確に想定しておくことは難しいと考えられます。
会社を解散登記したら負債はどう処理する?
会社を法務局へ解散登記手続きする前に、負債を清算したいところです。
しかし、多額の借入金が残っていたら、完済できない可能性があります。
そこで、借入金を完済できないときの注意点をまとめましたので確認しましょう。
会社解散時の借入金の返済
会社は解散すると、銀行から借入金の一括返済を求められる可能性があります。
それは、銀行取引約定書という銀行に差し入れた契約書での取決めに、「清算開始の申立てによる期限の利益喪失」ということが明記されているからです。
これは、簡単にいうと「会社をたたんだら、返済日を待たずに一括返済してもらいます」ということを意味しています。
もし会社が一括返済をできない場合は、銀行は連帯保証人に催促をしたり、担保に差し出した土地や建物の処分を検討したりしなければなりません。
また保証協会付融資で、銀行借入が保証協会からの返済によってゼロになった場合でも、今度は保証協会から催促がきますので注意しましょう。
代表者からの貸し付けがあるかはどこを見ればわかる?
もし代表者が亡くなった場合には、相続税の対象となるので、代表者からの貸し付けは、代表者にとっては財産として扱われます。
このため、代表者からの貸し付けを確認するためには、最新の申告書を用意してください。
用意したら「借入金及び支払利子の内訳書」を確認することで、代表者から借りたお金について記載があるはずです。
しかし、借入金としてではなく、未払金として処理されている場合には「未払金の内訳書」という書類に記載されているます。
短期間での借り入れや、目的によっては未払い金として処理されているかのせいもあるため、念のために両方の書類に目を通しておくとよいでしょう。
代表者が会社にお金を貸しているとどうなる?
中小企業の場合、会社の支払いを社長個人の財布から立て替えることも多いでしょう。
ただしこの立替えは、社長が会社にお金を貸したこととなり、会社にとっては役員借入金という負債として残ります。
会社を解散するときの役員借入金の清算方法は、銀行借入と異なりますので、そのポイントについて順番に確認していきましょう。
多額の役員借入金があるときの対策
役員借入金は、社長の立替えが積み重なると膨大な金額となるため、会社が解散するときに返済できない可能性もあります。
そのような場合は、社長が貸付金をもう返さなくてもいいよという債権放棄の手続きをすることで、会社の役員借入金をゼロにすることができます。
しかし、債権放棄をすると多額の税金が発生する可能性がありますので注意しましょう。
それは社長が債権放棄をすると、会社にとっては債務免除益といって、なくなった借金の金額分が会社の利益となり法人税が発生するからです。
ただし、これから話をする方法で法人税をゼロにすることもできますので覚えておきましょう。
債権放棄のタイミングが重要
社長が債権放棄をすると、会社は債務免除益という黒字が発生しますが、債務免除益は会社の繰越欠損金という会社の赤字と相殺することができます。
ただし、繰越欠損金は赤字を繰り越しできる期限が最長で9年しかないため、会社を解散するときには期限切れになっている可能性もあります。
そこで、会社の解散が民事再生等の理由であれば、期限切れの繰越欠損金も債務免除益と相殺することができるということを覚えておきましょう。
これは、会社は解散する理由が、会社更生法またが民事再生法による私的整理であれば、期限切れの繰越欠損金の使用が法律上認められているからです。
ただし、期限切れの繰越欠損を利用するには、実際に再生手続きが開始していなければならないといった一定の要件があります。
この要件はシビアであるため、必ず専門家に相談した上で債権放棄をするタイミングを間違えないように注意しましょう。
繰越欠損金がないときは
債務免除益と相殺できる繰越欠損金がない会社は、機械設備や備品といった固定資産や、在庫等の棚卸資産が残っていないか確認をしましょう。
会社が過去に取得した資産は、解散時に処分をすれば売却損や除却損といった、含み損が発生する可能性があります。
こういった損失も、繰越欠損金同様に債務免除益と相殺することができますので是非覚えておきましょう。
法人解散と役員借入金の資本振替処理
役員借入金の免除益は、繰越欠損金と相殺できますが、役員借入金を免除せずに資本勘定に振り替えて、繰越欠損金と相殺することも可能です。
それは、中小企業は会社と社長の財布の明確な区別がなく、会社が社長から借りた役員借入金は実質的に社長が出資した資本金と見られるからです。
ただし、役員借入金を資本勘定に振り替えるには、現物出資という手続きが必要となり費用がかかります。
したがって、役員借入金が残っている会社は、解散するときに役員借入金を資本に振り替えるのではなく、債務免除益を発生させて繰越欠損と相殺することをおすすめします。
銀行借入が残っていると返済は軽減される?
会社が解散するときに、銀行からの借入金は原則一括返済する必要がありますが、逆に返済額が軽減される可能性も考えられます。
それは、銀行にとっても無理な一括返済を求めるより、少額ずつでも完済してもらう方がいいからです。
また、担保付融資でも銀行は無理に社長の自宅を取ろうとはしませんし、保証協会付融資でも信用保証協会は会社に代わって銀行に代位弁済したいわけでもありません。
したがって、時間はかかっても必ず返済するというスタンスで社長が銀行に相談することで、返済額が軽減される可能性がありますし、担当が今後の解散手続きに協力してくれる可能性もありますので覚えておきましょう。
まとめ
会社は解散するときに銀行借入はもちろんのこと、日ごろから社長が何となく立替えしてできた役員借入も清算する必要があります。
また、中小企業が10年以内に解散する確率は90%を超えるといわれてますので、まだ現役の経営者も今回の話をきっかけに、役員借入金や繰越欠損金について意識してみてはいかがでしょうか。
タグ:その他金融業者


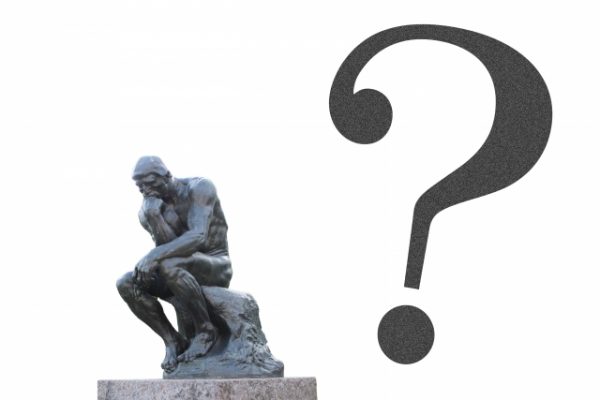














































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。