消費者金融業界は今後どうなると思う?
貸金業法改正以来、消費者金融は冬の時代に入ったと言われていましたが、最近は業績回復の兆候もあり、消費者金融も業界全体として上昇傾向に入ったのではないかと、エコノミストはこぞって発言していますね。
しかし筆者が貸金業務取扱主任者講習で聞いたところによると、消費者金融業界は一旦業績は回復したものの、さらに業界全体の淘汰が進むようで消費者金融の業界地図は大きく変わってきそうです。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
消費者金融業界の今後と銀行カードローン
今回のコラムはあくまでも筆者の考えであって、必ず消費者金融業界の今後が記事の方向に進むことは保証していません。
ただ中小消費者金融として30年以上に渡り営業してきた実績と経験、及び日本貸金業協会との定期的な会議への出席、並びに貸金業務取扱主任者講習会での弁護士による発言などを基に、消費者金融の将来性を推測するにすぎません。
また消費者金融業界を蔑む意向は全く持ち合わせていませんので、先にご了承願いたいと思います。
さて前置きはこのくらいにして、ちょっと前までは銀行カードローンの過剰貸付が社会問題化しつつある、というようなニュースが頻繁に流れていましたが、最近若干鳴りを潜めているようです。
銀行カードローンの過剰貸付で何が問題だったのかと言うと、銀行カードローンとは言いながら、実質的に審査担当行うのはグループ企業の消費者金融や、外部委託のクレジットカード会社が行なっていたことにあります。
以上のことからも銀行カードローンの過剰貸付と消費者金融業界の今後は、密接に関係があると考えた方が良さそうです。
過払い金返還請求がまだ終わっていないことを理由に、消費者金融の本格的な回復はまだ先との見方も否定できません。
しかし過払い金返還請求の時効が借金完済から10年を既に過ぎていることから、過払い金返還請求する人はもうとっくににしていると考えることもできますね。
消費者金融業界の今後を単に数字だけ予想するのではなく、業界全体として新規参入が増えているのか、も予想の材料として使うべきでしょう。
銀行は貸せば貸すほど儲かる
つまり保証会社の存在ですね。
保証会社は銀行カードローンの保証人であり、審査も担当しています。銀行はといえばはっきり言って何もしていないところが多いですね。
保証会社は大手消費者金融をはじめとして、都市銀行や地方銀行カードローンの電話受付やカードローンセンターの設置、返済期日に遅れた人への督促業務まで行なっています。
銀行は潤沢な資金をカードローン会員に貸し出すだけで、何もすることなく利回りよく利ざやを稼ぐことができるわけです。
銀行にとってはまさにノーリスクハイリターンですね。
銀行カードローンの貸付残高は5兆円を軽く超え、消費者金融業界全体の貸付残高よりも多くなっています。
消費者金融は総量規制によって、貸すことのできる金額が年収の1/3までと定められているのに対して、銀行カードローンは総量規制の対象外ですよね。
一部の銀行では自主規制によって貸付額年収の1/3までに定めているとはいえ、返済能力があれば年収の1/2まで貸しているのは以前と変わりがありません。
メガバンクとの提携による収益構造がバレた
メガバンクに至ってはグループ企業に消費者金融業を取り込むことによって、審査を厳しくしてできるだけノーリスクな人にお金を貸せば、保証会社に保証料を支払っても10%近くの利回りで潤沢な資金を運用できるのです。
しかも保証料を5%程度支払ったところで、その収益はグループ企業全体の収益にも繋がるわけですから、利益をまるまるグループ内に溜め込むことができるわけですね。
その収益構造が世間に知れ渡るようになると、金融庁はまるでシナリオ通りに銀行カードローンの貸付自粛を申し入れたのです。
しかし消費者金融のように銀行カードローンにも総量規制を導入する、とまではなっていません。あくまでも自主規制です。
金融庁が強く出ることによって、日本貸金業協会に対してもメンツが立つ、世間一般に対しても金融庁は銀行カードローンを監視していると思わせることができますね。
消費者金融の市場規模は減少傾向にあるが底をついた
日本貸金業協会が発表している貸金業関係資料より数字を引っ張り出してきましょう。
正規に登録している貸金業者数は過払い金問題が多発してきた2006年の1万4,236業者から、2017年3月までの間に1,865業者に大幅に減少しています。
パーセンテージに直すと86.9%もの減少率ですね。
また消費者金融の消費者向け貸付残高は、同じ期間に20.9兆円から6.2兆円まで減少しています。これもパーセンテージに直すと70.3%の大幅な減少ですね。
数字を見る限り消費者金融の市場規模はどん底では、と思わせますが、逆に過払い金で支払うものは支払っての数字と見ることもできるわけです。
まさに今が消費者金融業界全体の底であると前向きに考えることはできないでしょうか。
消費者金融はネットからの申し込みによって借入のハードルが下がっています。
景気が上向いている現在では、お金が足りないなら消費者金融から借りればいいじゃない?、と趣味や旅行などの余暇を楽しむためにお金を借りる人が次第に増えています。
人口のわずか1%でも消費者金融からお金を借りようと考える人が出てくれば、それだけでおよそ1,200万人の新規貸付が増える計算です。
大手消費者金融であるアコムの会員数がおよそ120万人であることを考えると、それだけで大手消費者金融が10社分ですよ。
消費者金融業界は貸金業法改正を望んでいる
金融庁が銀行に対してカードローンによる過剰貸付を自粛するようにと申し出る前から、消費者金融業界は日本貸金業協会を筆頭に貸金業法改正を求めています。
銀行カードローンでお金を借りれなくなった人にでもお金を貸すことができるように、金利は出資法改正前に戻すことで、多少属性が悪い人でもお金が借りれるようにしなければ、自己破産件数はこれからも増え続けていく、という理論です。
確かに銀行カードローンの審査を銀行自体が行い、保証会社を利用しないとなれば、今まで保証会社を務めていた消費者金融は収益のおよそ20%を失ってしまいます。
そもそも消費者金融が保証会社を務めるようになったのは、貸金業法改正によって金利が下がり利息収入が減った分を補うためです。
せっかく保証料と言う収入源があったのに、銀行が保証会社を利用しないとなったらグループ会社に消費者金融を置いておく必要はありませんよね。
使い道のない消費者金融をグループ会社に置いていたって何の得もなければ、あっさりメガバンクグループから切り離されたとしても不思議ではありません。
保証会社が銀行カードローンの保証人として借金を銀行に代位弁済するのは、返済期日から遅れること3カ月経過してのことです。
しかし可能性としては返済期日から1カ月でも遅れたら、保証会社が借金の肩代わりをしなければならない状態になるかもしれません。
さて困ったのがメガバンクグループに入っている大手消費者金融です。
銀行との保証委託契約は銀行と消費者金融の間で取り交わされていることですから、内容を変更することはそれほど難しいわけではありません。
前述したように消費者金融の20%を保証料として収益源としていたのに、保証料が入ってこなくなってしまったら元の木阿弥ですね。
だからこそ貸金業法を改正して、以前の出資法の上限金利29.2%を復活させようと努力しているのです。
アイフルの株価が上がっている
一見関係ないように見えてもアイフルの株価は上がっています。
2006年2月頃に260円の安値をつけたアイフルの株価は、移動平均を見る限り上向き傾向にありつい先日400円を突破しています。
表向きの情報ではアイフルは銀行カードローンの保証業務をあまり積極的にはしていません。
また銀行系グループに入っていないため独自の審査基準によって運営が可能です。決算資料を見ても会員数の伸び率は大手消費者金融のアコムやプロミスを上回っています。
つまり銀行カードローンの保証料に収益を頼っている銀行系消費者金融よりは将来性があるということですね。
それに対してアコムの株価は下がり傾向にあり、2016年5月に650円ほどあった株価は470円台までに落ち込んでいます。
株価は半年先1年先の企業業績を表すと言われている通り、銀行カードローンの過剰貸付と貸金業法改正には何か関連性があるのではないかと考えてもおかしくはありませんね。
消費者金融業界の将来性
筆者が想像するに近く貸金業法は改正されるでしょう。
なぜなら消費者金融と銀行カードローンの垣根がなくなりそうだからです。
例えば消費者金融に借入を申し込んだ場合、今までは総量規制に関係のない銀行カードローンはあまり審査の対象にはなりませんでした。
しかし今後は消費者金融に借入を申し込んでも、審査する際に銀行カードローンでいくらお金を借りているのか、及び銀行貸付による目的ローンや住宅ローンについても、返済能力を判断する上で材料となるらしいのです。
もちろん銀行カードローンに申し込む場合でも、保証会社がいなくなれば審査を厳しくしなければなりません。
そうなってくると住宅ローンの借入がいくらあるのか、目的ローンでいくらお金を借りているのか、消費者金融でいくらお金を借りているのか審査しなければなりません。
銀行は返済負担率によって返済能力を測ると言われているように、収入に対して借金がどのくらいあるのかパーセンテージで客観的に判断し、銀行カードローンの審査に通るかが決まります。
消費者金融の数は微減で推移
日本貸金業協会がまとめた資料によると、2016年4月の登録貸金業者数は1,916社あったものの2017年12月現在で1,796件と120社減少です。減少率にして6.3%減ですが2017年4月と比べてみると減少率が3.1%に低下しています。
つまり貸金業法改正によって過払い金訴訟が全国的に多発し、貸出金利もおよそ30%ほど少なくなった時期から比べれば確かに消費者金融の数は1/10になりました。
これは貸金業を廃業するところはほとんど廃業し、現在残っているところは現状維持しているということです。
しかも特筆すべきは2017年10月現在で登録貸金業者数は1,795社であったのに対し、同年11月の登録貸金業者数は1,800件と一時的に増えているのです。
もちろん貸金業者は消費者金融だけではなく、リース業者やNPO法人、クラウドファンディングも含まれていますので、一概に消費者金融だけが持ち直しているとは言えないものの、少なくとも消費者金融の数は「いまが底」周辺にあるのではないか、と捉えることもできるでしょう。
今後、消費者金融の数が急激に増えて行くことは予想できないにしても、消費者金融業者として残るところは残ったのが今の現状であることは間違いなさそうです。
ここ数カ月の間に在宅ワーク会社やファッション業界が貸金業へ進出していること、及びみずほ銀行とソフトバンクが共同出資して立ち上げたJ.Score(ジェイスコア)を見ると、貸金業界のキャパシティはまだまだ十分に確保できていると考えた方が辻褄が合いますね。
消費者金融の業界地図が大きく変わるかもしれない
消費者金融は貸金業法改正によって貸付金利が上がれば、多少リスクを冒しても顧客獲得に出てくるでしょう。
とくに株価が上がっている消費者金融は顧客獲得のために、様々なサービスを繰り出してくるに違いありません。営業貸付残高もどんどん増えていくと思います。
しかしこれは罠かもしれないのです。
銀行カードローンの滞納で一番困るのは保証会社ですよね。
だって保証会社は借金を回収しなければ大損ですから、裁判を起こすなど強制執行をすることをチラつかせながら借主に迫っていくだろうと考えることができるからです。
逆に借入希望者は消費者金融からもっと多くのお金を借りれる、となったら銀行カードローンの返済に回してくるかもしれませんね。
独立系の消費者金融はいくら借金回収のために奔走しても、自己破産されてしまったらそれで終わりです。貸金業法が改正されたとして思い切って顧客獲得に乗り出しても、水の泡と消える可能性があるのです。
その結果待ち受けているのは、消費者金融の2回目の再編です。
メガバンクに属していない大手消費者金融、または中堅の消費者金融からお金をどんどん借りさせ、メガバンクグループに属している消費者金融に返済させるようにすれば、グループとしてもグループに属している消費者金融としても安泰です。
貸金業法改正は消費者金融業界全体の業界地図が大きく変わるかもしれない転換点となることでしょう。
消費者金融の最終形として、メガバンクに属している消費者金融が残り、優良な属性を持った人はプライム金利で借りれる銀行カードローンまたは、J・SCOREのようなレンディングサービスに移行するでしょう。
属性の良くない人は、サブプライム金利で借りれる消費者金融と区分けされることになりますね。
ところでJ・SCOREはみずほ銀行が半分出資していることをご存じですよね?
みずほ銀行自体銀行カードローンを商品展開しているのに、なぜ今になって消費者金融業界に乗り込んでくるのか、考えれば消費者金融業界の将来性は「明るい」と見えてくるのではないでしょうか。
タグ:お金の知識




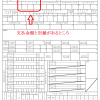















































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。