一般社団法人は銀行からお金を借りること可能?
営利を目的としない一般社団法人でも設立の際には、事務所の費用や備品の費用などで様々な支出が必要になることがあります。
営利を目的とせず、会員の善意で成り立っている一般社団法人ですが、銀行から借入をすることはできないのでしょうか?
銀行からの借入は厳しいですが、借入を行う方法がないわけではありません。
この記事では、一般社団法人が借入によって資金調達をする方法や審査について解説していきます。
この記事はこんな人におすすめ
この記事は以下のような人におすすめの記事になります。
- 銀行などから資金調達したい一般社団法人の方
- 一般社団法人に融資を行う金融機関を探している人
- 一般社団法人に対する審査の基準を知りたい人
一般社団法人の融資について詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
一般社団法人とは
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利の法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。
一般社団法人は次の2点を満たせば非課税となります。
- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
通常ほとんどの一般社団法人では、非営利法人で非課税となっていのが一般的です。
株式会社で言えば代表取締役に該当するのが、一般社団法人で言えば代表理事です。
代表理事は法人を代表して業務を執行し、法人業務に関する裁判上または裁判外の行為をすることができます
また、代表理事の選任は、理事の互選か社員総会の決議によって行うことができます。
代表理事には定期的に法人業務の執行状況に関して、理事会へ報告する義務があり、理事会決議を経なければなりません。
さらに、任意に「副理事長」や「副会長」、「専務理事」、「常務理事」などといった役職理事を設置することも可能です。
また、一般社団法人には評議会というものがあります。
評議員会は,すべての評議員で組織され、規定した事項および定款で定めた事項に限って決議をすることができます。
このように、株式会社などよりもかなり自由に法人内部の決まりを決定することができ、その定款(決まり)に基づいて非営利活動を行うことを目的とした法人が一般社団法人です。
組合活動や交流会などの会員相互の扶助を目的として設立されるのが一般社団法人で、東京商工リサーチの調査によると、2016年時点で新設数が増加しており、過去最多の5996社となっています。
このような背景から、最近では本来非営利目的であることから融資を受けることが難しかった一般社団法人への融資が解禁されつつありますが、この点に関しては詳しく後述していきたいと思います。
事業融資は2種類の融資がある
中小企業や個人事業主などの小規模事業者が借りることができる事業資金は大きく分けて運転資金と設備資金という2種類の資金があります。
さらに、創業のための資金なのか、事業実績がある状態で必要な資金なのかによって創業資金なのか一般の資金なのかによって分かれています。
制度融資とは
制度融資とは、企業経営の事業開始に必要な資金や、事業承継などの地域の企業の維持や発展のために、地方自治体、銀行、信用保証協会が融資を行う制度です。
信用保証協会が保証を行い、銀行が融資をし、地方自治体が助成するという仕組みです。
制度の内容は地方自治体によって異なりますが、基本的には利息や信用保証量の一部を地方自治体が助成金として還付する仕組みとなっています。
詳しくは、会社が所在する自治体の窓口か銀行へ確認しましょう。
新創業融資とは
新創業融資とは、日本政策金融公庫の創業事業の融資制度です。
創業時には一定の条件を満たすと、無担保無保証でお金を借りることができます。
特に、創業後の職業が、これまで会社員として勤務して来た業種と同一業種だと、融資を受けることができる可能性は高くなります。
詳しくは日本政策金融公庫や地元の商工会議所へ確認してみてください。
なお、今は国をあげて創業に対する支援を行なっていますので、国の創業補助金という補助金制度も存在します。
借入などの外部資金調達がある場合には、200万円を限度として補助率1/2で融資を行なっていますので、中小企業庁ホームページなどで概要をチェックしてみてください。
また、会社設立の方法がわからないなどという人は、税理士事務所などの会社設立キャンペーンなどを活用しましょう。
設立に関する手続きを安価で行うことができますよ。
銀行での借入は難しい
非営利の一般社団法人が銀行から融資を受けるのは難しいというのが現状です。
金融機関は基本的に営利企業に対して、利益の拡大を目的として融資を行うものです。
そもそもが非営利活動を目的としている一般社団法人が金融機関から融資を受けることはかなり難易度が高いと考えておいた方がよいかもしれません。
信用保証協会はほぼ期待できない
銀行は新規で融資を行う際には信用保証協会の保証をつけて融資を行います。
しかし、全国にある信用保証協会のうちほとんど全ての信用保証協会が一般社団法人を融資対象とはしていません。
信用保証協会には保証対象事業というものが決まっていますが、一般社団法人は対象外となっています。
理由は「営利ではない」ということはもちろんそうですが、信用保証制度というのは、税支出によって成り立っています。
税収入で成り立っている信用保証協会が非課税である一般社団法人に保証を行うということが難しいのでしょう。
同じような理由で、税金の滞納者に関しても信用保証協会は保証を行っていません。
反対に、営利目的で運営する株式会社や個人事業主なら「創業資金」や「経営力強化資金」「企業活力強化貸付」「中所企業経営力強化資金」などの様々な融資制度で幅広く融資を行なっていますので、信用保証協会や資金の取扱金融機関へ相談してみましょう。
また、信用保証協会は、中小企業の資金繰りをサポートする機関でもあります。「創業支援セミナー」「経営サポート事業」なども行なっていますので、営利目的の事業者の方は、信用保証協会はかなり活用できる機関です。
このように、信用保証協会は、営利目的の事業者であれば活用できるのですが、非営利で非課税の一般社団法人が活用することは非常に難しいのです。
プロパー融資も難しい
信用保証協会の保証付融資で一般社団法人が融資を受けることは不可能です。
では、保証協会の保証をつけないプロパー融資であれば一般社団法人は融資を受けることができるかといえばそれも難しいというのが実情です。
プロパー融資というのは、何も保証をつけずに銀行が自己資金で行う融資です。
金融機関にとっては返済が履行されない場合には、それが丸々損失になってしまうので、よほど安全な企業に対してしか融資をしません。
そのため、資本金が充実している企業や、返済期間が長い長期事業資金を借りるような場合には、起業から継続的に利益を出し続けている収益性の高い企業しかプロパー融資を受けることはできません。
そもそも、営利を目的としていない一般社団法人にそこまで収入があるかどうかは別として、よほど毎年の収益が安定している一般社団法人でないと難しいでしょう。
一般社団法人の中では不動産などの資産を保有している法人も存在しますので、そのような法人であれば融資を受けることも可能かもしれません。
いずれにせよ、銀行の融資のルールの中には「一般社団法人には融資をしない」という決まりはありません。
銀行から一般社団法人が融資を受けようと思った場合にはまずは相談してみましょう。
資産状況によってはプロパーで融資を受けられる可能性はゼロではありません。
銀行は営利企業に融資をするもの
とは言え銀行は基本的に地元に事業所を構える営利企業へ融資を行い、地域経済を拡大し、従業員の生活向上につなげることを主な目的としています。
簡単に言えば融資金を元手にさらに事業規模を大きくして、収益を上げることができる事業者に対して融資を行うのです。
したがって、非営利の一般社団法人はそもそもが銀行の融資の中小企業事業資金融資の価値観からは外れていると考えることができます。
このため、すでに独立して存在し、一定の資産を持っている一般社団法人が銀行から融資を受けることができる可能性はゼロではありませんが、一般社団法人設立の費用を銀行から借入することはほぼ不可能であると考えておいたほうがよいでしょう。
社団法人は日本政策金融公庫へ
先ほど述べたように、銀行から一般社団法人が借入ができる可能性は限りなく低いと言えます。
しかし、日本政策金融公庫であれば一般社団法人でも融資を受けることができる可能性があります。
日本政策金融公庫は一般社団法人に対する融資を株式会社に対するように行っています。
信用保証協会のように「保証対象外」としているわけではありません。
一般社団法人融資の注意点
一般社団法人であろうとなかろうと、日本政策金融公庫から設立に伴う費用の融資を受けようと思った際には事業計画書を策定しなければなりません。
一般社団法人も株式会社のような明確な事業計画書を策定する必要があります。
事業計画書には以下の5点を明確に記入する必要があります。
①会員の会費はいくらなのか(収入)
②事業から得られる収入はいくらなのか(収入)
③事業継続のために必要な経費はいくらなのか
④設立の目的はどこにあるのか
⑤今後数年後の資金繰りはどのようになるのか
特に一般社団法人はなんとなく「このような事業をしたい」という思いから設立はして見たものの、そもそもが会員の善意で成り立っているため、会員の熱意が薄れ、次第に活動実態がなくなってしまうということが珍しくありません。
一般社団法人の審査の際には、この事業の継続性が強く問われることになります。
また、非営利である一般社団法人の借入金の主な返済原資は会員の会費に頼ることが多いと考えられることから、しっかりと事業を継続でき、今の会費が持続可能なのかということが審査の対象になると考えられます。
そのため、一般社団法人設立に至るまでの活動の内容なども審査の対象となり、「この人はこの活動に対して本気なんだ」と思わせる事業計画書が重要です。
なお、代表者は連帯保証人になることが一般的です。
対象事業の中身も審査し、当該事業が継続拡大することが社会一般のためになるのか?ということも審査されます。
ただし、基本的に融資限度額は必要最小限しか適用されませんし、設立間もない一般社団法人が「企業育成貸付」などの融資を受けることも、経営状態が悪化した中小事業者が「企業再生貸付」のような融資制度を借りることもできません。
あくまでも資産状況が充実した、広く事業を行なっている安全な一般社団法人がさらに事業を拡大するような状況に関してしか、融資を受けることができないと考えておきましょう。
融資を決定づける事業計画書
融資に重要書類が「事業計画書」です。
株式会社で言えば創業計画書などととも言います。
事業内容、収支計画、資金計画、などを事業年度ごとにこの先数年間の事業経営全体を予測するための書類です。
ここで、希望する借入期間で「返済には問題ない」とか「十分な利益を見込むことができる」というような判断ができれば、融資を受けることができる可能性が高くなります。
事業実績が何もない状態では、事業計画書が審査に大きな影響を及ぼすほどの重要な書類です。
作成に自信がないという方は、商工会議所や税理士事務所が「事業計画書作成セミナー」などを行なっていますので、まずは相談してみるのがよいでしょう。
今後は銀行も融資対象にする流れ
現在、一般社団法人に対してほとんどの銀行は融資を行っていませんが、今後は銀行も一般社団法人に融資を拡大するような流れができつつあるためご紹介します。
中小企業融資制度
地方自治体、銀行、信用保証協会の3者が共同で商品設計し融資を行う制度資金融資(信用保証協会が保証を行い、銀行が融資し、地方自治体が金利や保証料の補助を行う)は銀行が中小企業へ融資を行う際にもっとも活用する融資の手法です。
制度資金は中小企業融資制度を根拠としています。
この中小企業融資制度では「農林漁業、風俗営業飲食業の一部、公益法人、社会 福祉法人、学校法人等」への融資対象としていません。
一般社団法人は公益法人に含まれますので、中小企業融資制度は一般社団法人には融資対象としていないのです。
これが銀行が一般社団法人には基本的に融資を行わない根拠と言えます。
しかし、今、この流れが変わりつつあります。
社会的問題解決に取り組む法人
平成27年10月に中小企業信用保険法の一部を改正する法律が施行され、中小企業者の定義にNPO法人が追加され、信用保証 の対象となったNPO法人への融資が可能となりました。
しかし、NPO法人と同じように社会的問題の解決に取り組む一般社団法人は中小企業信用保険法に定める中小企業者ではないため、信用保証の対象外となり、融資を利用することができないことが問題視されています。
中小企業保険法の一部を改正する法律では一般社団法人の資金繰りについて以下のように資金繰りの円滑化を図ることとしています。
『社会的課題(保健・福祉・医療、子どもの健全育成、まちづくり、環境等)を解決するため活動する一般社団法人・財団法人を、中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者の定義に追加し、融資を可能とすることで、当該法人の資金調達の円滑化を図る。』
条件として以下の2つを満たしている一般社団法人としています。
- 当該一般社団法人等の主たる事務所が特区の区域内に所在すること
- 当該一般社団法人等の事業目的について、「社会的課題の解決」であることが定款において確認できること
つまり国家戦略特区の区域内に事務所を構え、「社会的課題の解決」に取り組んでいる一般社団法人は中小企業の定義を満たすことができ、信用保証協会を利用できるとしたものです。
今後はこの法律改正に基づいて、銀行でも信用保証協会への融資が拡充して行くものと考えられます。
一般社団法人であっても、創業スクールなどの各種セミナーも受講できるようになる可能性がありますし、地域操業アドバイザーなどの専門家のサポートを受けることができるようになる可能性があります。
つまり、今後は株式会社と一般社団法人の垣根が少しずつなくなっていく可能性があるのです。
など、トラック協会や介護事業などの一定の事業に関しては、専門の融資制度も用意されていますので、詳しくは行政書士や事業が所属する業界団体に聞いて見ましょう、
銀行に融資を受けられなかった場合には
銀行に融資を受けることができない場合には、売掛金などの売上債権を売却するファクタリングや、消費者金融などのノンバンクからの借入や、私募債の発行などの直接融資によって資金調達したり、役員借入をするなどの方法が企業であれば一般的です。
しかし、営利を目的としない一般社団法人では以下の方法も検討しましょう。
- ファイナンス・リース
- セール&リースバック
最後にこれらの方法について詳しく解説していきたいと思います。
ファイナンス・リース
車両や機械などが必要な場合には、ファイナンス・リースという方法で購入する(借りる)ことができます。
ファイナンス・リースとは、指定した備品をリース会社が顧客に代わって購入し、顧客はその使用量を毎月リース会社に支払っていくという方法です。
一般社団法人は、会員の会費によって成り立っている組織ですので、運転資金に困るということはそれほどありません。
借入の需要が発生するタイミングは、コピー機や車などの備品を購入するタイミングであることが一般的です。
備品購入のために銀行の設備資金を活用することができる場合もありますが、審査に通過できない場合には、ファイナンス・リースの活用も検討しましょう、
ファイナンス・リースも審査はありますが、銀行の審査よりも難易度は厳しくないので、一般社団法人でも審査に通過できる可能性がありますよ。
セール&リースバック
セール&リースバックとは、ファイナンスリースとは全く逆の方法です。
顧客が持っている機械設備などをリース会社に売却して、毎月リース会社にリース代金を払っていく方法です。
セールス&リースバックを活用すれば財産を手放すことにはなりますが、設備を利用した資金調達ができる上、設備を保有することによって生じる事務コストや維持コストを削減することができます。
また、追加保証金を入れることで、月々のリース料を下げる事が可能な場合もありますので、社団の資金繰りと合わせて適切に方法で活用しましょう。
まとめ
一般社団法人への融資は今まさに拡大しつつありますが、日本全体でみると、銀行から一般社団法人が融資を受けるとはまだまだ難しい状況です。
どうしても融資によって資金調達をしたいのであれば、日本政策金融公庫へ相談したほうがよいでしょう。
その際には事業計画書の策定が非常に重要です。
一般社団法人の事業計画書は非常にざっくりとしたものが多いようですが、収入と支出の根拠を示し、返済には問題ないと理解させるとともに、事業にかける熱意も重要になります。
なお、非営利の一般社団法人は多くの人の賛同を得られなければ事業の継続は難しくなります。
このため、借入ではなくクラウドファンディングの利用なども1つの方法でしょう。
タグ:その他金融業者



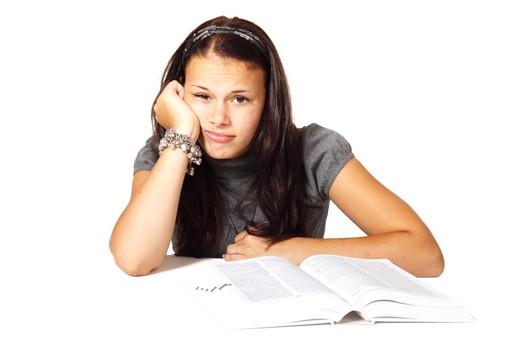
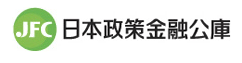








































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。