適切な借入金は業界によって違う
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
自己資本比率と優良企業
会社はお金を借りるとき、銀行へ3期分の決算書を提出します。
その決算書から見ることができる自己資本比率は、銀行にとって会社が優良企業であるかどうかを、判断する目安となります。
しっかりと、その計算方法について確認しおきましょう。
3期分の推移を見ることで、会社が安定しているのか、不安要素をしっかりと把握しながら、経営をしているのかが見ることができます。
自己資本とは?
会社を経営していく上で、必ずどこからかお金を調達してこなければなりません。
その調達する手段として、経営者本人の財布から出すお金を自己資本といい、それに対して銀行などの外部から調達するお金を他人資本といいます。
自己資本は他人資本と違って返済する必要がないため、自己資本の多い会社は、将来的に資金繰りが安定した、体力のある会社であると判断することができます。
自己資本比率とは?
自己資金は多いほど会社にとって良いという話をしましたが、具体的に自己資本比率といった数値で表すことで、会社が良い状態であるかを判断することができます。
自己資本比率は、資本金と負債を足した総資本のうち、自己資本が何%あるかといった指標であり以下の式で計算できます。
自己資本比率=自己資本金/総資本(自己資本金+他人資本金)
会社の自己資金比率は、高いほど経営が安定しているといわれています。
それは、例えば自己資本比率が100%である会社は、手持ちのお金を全て自分自信で賄えている無借金経営であり、資金的な体力があるからです。
逆に、自己資本比率が0%に近い会社は、いくら手持ちにお金があっても、そのほとんどが将来返済する必要がある借金になります。
そしてこれは、将来的には資金繰りが厳しくなる可能性が、高くなることを表していることになります。
金融機関から借入できる企業の特徴
自己資本比率は銀行の格付で重視される指標であり、これが高い企業ほど借入できる可能性が高くなります。
そこで、自己資本比率が具体的に何パーセントであれば、銀行借入が有利になるかについて確認してみましょう。
自己資本比率は何%がいい?
銀行が格付をする指標として、自己資本比率が50%以上であればその会社は優良であり、少なくとも30%以上あることが安全圏のラインとなります。
また、自己資本比率が10%を切る会社は、銀行の格付ランクが下がる可能性がでてきます。
また、そもそも経営上安定していないということになりますので、これから話しする自己資金比率を上げる方法を検討しましょう。
過年度利益で内部留保を高める
自己資本比率が低い会社は、決算を黒字にすることで自己資本比率を増やすことができます。
それは、会社の昨年の黒字は過年度利益といって、内部留保として今期の資本に足されるからです。
できる限り経費を削り、内部にお金を貯めることによって、自己資金を増やすことができます。
逆に、会社の決算が昨年赤字であれば、その分だけ会社の資本から削られるようになり、赤字が続いて資本金がマイナスとなれば、債務超過という状態になります。
債務超過となった会社は、銀行融資を受けるのが極端に難しくなり、経営上破綻する可能性が高くなりますので注意しましょう。
そのほかの自己資本比率を高める方法
会社を黒字にする以外にも、他人資本である銀行借入を減らすことで、自己資本比率を高めることができます。
しかし、銀行借入の繰上げ返済は手持ちの現金がなくなるため、余剰資金や遊休資産の売却代金などでするように気をつけましょう。
また、会社の役員借入金を、資本に振り替えることで自己資金比率を高める方法があります。
この方法は1円もお金を動かすことなく、自己資金比率を上げることができる便利な方法ですので後で詳しく話をします。
役員借入金は他人資本なの?
会社が社長や親族から借入れした役員借入金は、決算書では「負債」として銀行借入金と一緒に記載されています。
しかし、中小・零細企業の場合、会社の財布と社長個人の財布に明確な区別がないため、役員借入金は必ずしも返済する必要がありません。
したがって、中小・零細企業の役員借入金は、負債から資本金に振り替えることが可能です。
これによりお金を動かさずに勘定科目の移動だけで自己資本比率が上げることができますので覚えておきましょう。
業界別自己資本と借入金の比率
一口に自己資本比率とか、財政的に健全かといっても、借金の多い業界もありますし、少ない業界もあります。
業界ごとに、財務の健全性を判断するベンチマークが異なるのが実態です。
業界ごとに自己資本比率の健全性や平均値はどの程度異なるのでしょうか?
製造業
自己資本とは、返済不要の自前の資本のことを示します。
また、自己資本比率とは、返済不要の自前の資本が会社の資産のうち何%を占めるのかを示す指標で、以下のように計算します。
自己資本(自己資本+他人資本)÷総資産×100で計算します。
製造業の自己資本比率は中小企業では24.9%となっています。
これは製造業者の中でも業種によって大きく異なり、化学工業が最も高く毛皮製造業が最も低くなっており、業種での格差は16.8%となっています。
一口に自己資本比率といっても業種によっては設備投資を多くしなければならない業種は借入金によって設備投資を行わなければならないこともあります。
このように、設備に依存する割合が高い製造業はその業種の内容によっても自己資本比率の違いがあります。
卸売業
卸売業の自己資本比率は中小企業で18.8%となっています。
製造業よりは低い値となっていますが、小売業よりは高い自己資本があります。
卸売業の中で最も自己資本比率が高いのが繊維・衣服等卸売業で、最も自己資本比率が低いのは各種商品卸売業となっており、その差は5.3ポイントとなっています。
製造業のように、業務の内容によって依存する設備が異なるというわけではありませんので、業種によって自己資本比率に大きな差が出ないというのが卸売業の特徴です。
小売業
小売業の中小企業での自己資本比率の平均は16.0%となっています。
こちらは業種別の格差はそれほど多くありません。
最も自己資本比率が高い各種商品小売業と最も自己資本比率が低いその他の小売業の差は6.9ポイントとなっています。
小売業は店舗が必要になるため、設備には依存しますが、業種ごとに設備投資の変化はないため、小売業全体では自己資本比率が低く、業種ごとに自己資本比率の違いは小さくなっています。
サービス業
サービス業の自己資本比率の平均は28.7%となっています。
一口にサービス業といっても多種多様なサービスがあり、設備投資や借入が全く必要のない業種もありますが、業種によっては店舗を構え、過大な設備投資を行う必要もあります。
サービス業は、全体で見ると設備に依存する割合が他業種よりも低いことから相対的に他の業種よりも高い自己資本比率となっています。
飲食業
飲食業の平均自己資本比率は10.2%と各種業界の中で最も低い値となっています。
外食に行けばわかるかと思いますが、よほど味に定評がある店でない限りは飲食業の命は店舗設計です。
最初に多大な設備投資を行う業種です。また、設備投資は借入金によって調達するのが当然の業界です。
このため飲食業の自己資本比率は他の業種と比べて最も低いものとなっています。
飲食業を営んでいる方は他の業種と比べて自己資本比率が低いからといってそこまで気にする必要はないかもしれません。
毎日現金での売り上げがある飲食業は自己資本比率よりも収益性のほうが大切になります。
建設業
建設業の自己資本比率の平均は30.8%となっています。
建設業の場合には、長期借入金によって設備投資を行うことも運転資金を長期で借りることもそれほど多くない業種です。
借入金は受注した工事を引き当てにした短期借入金で、工事が完了した都度返済していくのが理想的な経営ですので、基本的に長期借入金が発生する業種ではありません。
逆に言えば、設備投資も行っていないのにも関わらず、長期借入金が増えている状態というのは健全な状態ではないといえます。
一方業界動向の問題から、それほど利益率の高い工事を受注するのは中小企業が受注するもが難しいという側面もあります。
このため、建設業は自資本比率が高いですが、利益率が低い業種であるといえます。
有利子負債依存度も業界によって異なる
有利子負債依存度とは、自己資本に占める、利払いを伴う負債がどの程度を占めるかということを示す指標で、財務内容の健全性を示す指標となっています。
有利子負債依存度が高い企業ほど、自己資本のうち、借入金が占める割合が多いということで、高い企業ほど財務状態が脆弱であるといえます。
倒産企業の平均は71.2%!企業の健全度を見る有利子負債依存度
有利子負債依存度は以下のように計算します。
有利子負債依存度=(有利子負債残高÷総資産)×100
業種によって、平均値は異なり、一概に何%だと経営が危険水域にあるかということは言えません。
以下業種ごとの平均値を示しますので、参考にしてみてください。
製造業
製造業の有利子負債依存度の平均は37.4%となっています。
製造業は業種によって設備投資の割合が異なる業種です。
もっとも依存度が高い木材、木製品製造業では償却期間の長い設備を借入金によって導入している場合が多いため50%を超える依存度となっています。
一方、食料品製造業では、製造業の中で最も依存度が低い割合となっています。
最も高い業種と低い業種の差は10ポイント以上あることから自社の業種平均の有利子負債依存度はどの程度かを把握して、平均程度の有利子負債依存度を目指しましょう。
卸売業
卸売業の有利子負債依存度の平均は35.34%となっています。
飲食品卸売業の平均が最も高く、機械器具卸売業の平均が最も低くなっています。
その差は16ポイント以上の差があり、冷蔵冷凍などの保存の必要性がある飲食品の卸は設備投資のために借入金に依存していることがうかがえます。
小売業
小売業の有利子負債依存度の平均は43.3%となっています。
こちらも業種によって差があり、衣服の小売りは店舗設計等にお金をかける傾向にあり依存度が最も高くなっています。
一方、無店舗の小売業は店舗に設備投資を行う必要がないため有利子負債依存度は26.21%と業界平均よりも大きく低い数値になっています。
サービス業
サービス業の有利子負債依存度は37.41%となっており、他の業界並の水準となっています。
理容美容業などがもっとも高い数値となっており、50%を超えています。美容院は空間が命ですので、多くの美容業が設備投資に力を入れており、有利子負債依存度が高くなっているようです。
飲食業
飲食業の有利子負債依存度は70.22%と他の業種に比べて最も高くなっています。
これは自資本比率と同様に、飲食店は最初に大きな設備投資を行い、長期間かけて売上の中で返済を行っていく業種であるためです。
飲食業の場合には借入金の依存度よりも収益性のほうが大事になります。逆に言えば、自己物件を購入して借金の返済さえ終了すれば飲食業の経営は一気に安定化するともいえる業種です。
建設業
建設業の有利子負債依存度は42.23%と他の業種とそこまで大きくは変わりません。
業種別にみると特別が技術や機械を必要とする職別工事業が最も高い借入金依存度となっており、50%を超えています。
そのほかの業種は30%前後となっており、建設業自体はそれほど設備投資を伴う長期借入金に依存しない業種であるといえるでしょう。
借入金月商倍率の業界別基準
借入金月商倍率とは、単純に借入金が月商の何倍あるかを示す指標で金融機関の融資の判断材料として使われます。
借入金月商倍率 = (短期借入金+長期借入金)÷月平均売上高
借入金月商倍率が低いほど、その企業の借入金が売上規模に比べて少ないと判断することができます。
6か月以内なら大丈夫などといわれることがありますが、借入金の種類によってその借入金が課題なのかどうかの判断は全く異なります。
運転資金としての借入が多ければ企業の業況に不安が生じますし、高額設備資金の借入金であれば高額の借入で借入金月商倍率が大きくなっても仕方ない部分があるためです。
以下業種ごとの平均を参考にしてみましょう。
製造業
製造業の借入金月商倍率は4.04か月となっています。
機械設備によって仕事の効率や内容が変わってくる製造業にとって設備投資は不可欠です。
10年20年と使用する見込みの機械を長期借入金によって購入して、長期間かけて返済していくという業態ですので、借入金月商倍率はそれなりに高い値となっています。
卸売業
卸売業はそこまで大きな設備投資は不要な業界です。
倉庫設備等は必要になりますが、飲食品の卸以外は冷蔵設備などにもそれほどお金は使いません。
このため、借入金の平均は業界の中でも最も低い月商の2.29倍となっています。
設備投資が大きく必要ない、参入しやすい業界であるともいえます。
小売業
小売りには店舗が必要です。
店舗の設備投資の必要性から借入金月商倍率は3.07倍となっています。
小売りは業種によって設備投資の必要性が大きく異なり、たとえばアパレル業などであれば店舗の設備に金をかけるため借入金の規模も大きくなりますが、インターネット販売などの無店舗営業などでは設備投資がありませんので、業界全体の平均を下げている傾向にあります。
サービス業
サービス業の借入金月商倍率は3.31か月となっています。こちらも業界によって大きく異なります。
サービス業は基本的に現金収入があるため運転資金での借入が必要ない業界です。
このため、サービス業の主な借入金は設備投資で美容院などは店舗設計のための多くの設備投資を必要とします。
その代わり、仕入れにかかるコストがないため収益性の高い業種となっています。
このように、借入金が月商に比べていくら多くても、それ以上の収益性で借入金を返済していけている限りは大きな問題にはなりません。
飲食業
やはり飲食業の借入金月商倍率は断トツの7.79か月となっています。
飲食業も毎日を売上が日銭として入ってくるため運転資金の借入が必要ない業種です。
開業時の開業資金での設備投資にお金がかかる業界であるということがよくわかります。
製造業や卸売りなどに比べて利益率が高い業種ではあるものの、開業時には多くの借金をしなければ皆開業できていないということもわかります。
建設業
建設業の借入金依存度も6.06か月と高い割合です。
長期借入金に依存せずに行うことができる業態なのが建設業ですが、いざ、自前に設備機械を購入するとなると決して安い金額ではありません。
結果的に借入金月商倍率は飲食業に次いで大きな値となっています。
なお、建設業は利益率もそれほど高くない業界ですので、建設業は借入金も大きく、利益率も低いと、業種としては相変わらず厳しい業種であることがうかがえます。
Q&A
負債の額が流動資産を上回っているということは、負債で調達した資産が固定資産の購入に回っているということです。
固定資産の割合が多い業界としては飲食業、アパレル業、美容院、製造業などの初期投資で大きな機械や設備や建物の購入が必要になる業種であることが考えられます。
逆に言えばこの業種で借入金による設備が少ない業種の財務状態は非常に堅実であるといえるでしょう。
収益が出ている企業であればどこの業界であっても経営は成り立ちます。
もっとも大切なのは収益性とキャッシュフローです。
まとめ
自己資本比率にしても有利子負債依存度にしても借入金月商倍率にしても、バランスシート上で借入金がどの程度の割合を占めているか、もしくは会社の売上規模に比べて多いか少ないかを判断する指標です。
これらの指標あくまでも会社を判断するための1側面でしかありません。
借入金には返済期間というものがあり、いくら借入金の規模が月商に比べて多くても、返済期間が長ければ、会社の経営には影響を及ぼさないことが多いためです。
自己資本比率や有利子負債依存度などの指標から業界平均より多いか少ないかを判断すると同時に、経常利益率などの収益性を判断する指標も併せて評価しましょう。
例えば自己資本比率が低い飲食業ですが、経常利益率は高い業種ですので、利益さえ出ていれば借金返済に困ることはないですし、長期間にわたって借金を返済していく業種であるいえるのです。
この記事の執筆者
手塚 龍馬
1982年生まれ33歳
成蹊大学卒業後、地方銀行へ就職。
個人、法人への営業担当として8年勤務し、預金業務、融資業務を行い、住宅ローン、自動車ローン、フリーローン、カードローン、事業性ローンなどを7年行う。
保険業務、投資信託販売業務なども多数取り扱いを行う。
現在は飲食店経営の傍ら、金融関係のライター活動も行っている。
タグ:その他金融業者
























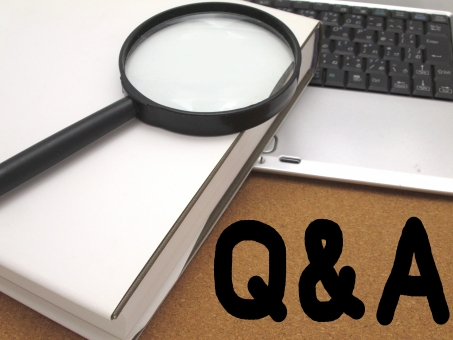









































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。