短期貸付金の利息はどれくらいかかる?計算方法を解説
会社が子会社や従業員へ短期間の貸付けをすることがあります。
そのときは基本的に利息を付けて、返済してもらいます。
その利息をどのくらいの利率にすればいいのか、知りたい人もいるでしょう。
そしてなぜ利息が必要なのか、その理由と一緒に説明していきます。
また利息の計算方法を、解説しますので参考にしてください。
この記事はこんなひとにおすすめ
今回の記事は以下の人におすすめの内容です。
- 短期貸付金の利息設定方法が知りたい人
- 短期貸付金とはそもそもどのようなお金か気になる人
- 短期貸付金の仕訳方法が知りたい人
短期貸付金について確認しておこう!
会社経営を行っていると、取引先や役員に対して短期貸付金を行う可能性がありますが、短期貸付金とはどういう特徴があり、どのような状況で利用されるのかしっかり把握しましょう。
短期貸付金とは
短期貸付金は会社が短期間の貸付けを資金繰りに悩んでいる子会社や、役員または従業員に貸付けするお金のことです。
貸付けをする場合は、役員や従業員が冠婚葬祭または災害時や病気でお金が必要なとき、さらにはマイホームの購入資金に充てるための福利厚生としての目的でのみ認められます。
また子会社や取引先には、経営が苦しいときの運転資金などとして貸付けします。
なお、貸付金は「長期貸付金」と「短期貸付金」に分けられ、貸付期間が1年以上のものを長期貸付金、1年以内のものを短期貸付金と区別しているのです。
したがって短期貸付金は、1年以内に返済される予定のであることが前提です。
法人と個人による貸付利率の違い
短期貸付金は貸す相手が子会社や取引先の場合と、役員や従業員の場合で違いがあるのでしょうか。
個人と法人での貸付の違いとして利息の設定の違いがあります。個人である役員や従業員に貸しつけるときは、「認定利息」がかかります。
ただし借りる人の目的によっては、利息を付けなかったり低い利息にしたりすることが可能です。
法人や個人事業主から利息を取るときは、関係する法令があるので注意をしながら、利率を決めることになります。
なお、法令には次のものがあります。
- 利息制限法
- 出資法
- 法人税基本通達
- 所得税法
また短期貸付金は高い利息を付けたり、極端に低くしたりすると、課税対象となるので覚えておきましょう。
短期貸付金に利息がかかる理由
短期貸付金を設定する場合には、利息を設定するかどうか選べますが、設定する場合も多いです。
なぜ、短期貸付金に利息をかけるのか、利息を設定しなければどうなるのか、具体的な理由を見て行きましょう。
法人による貸付けには利息が付く
会社は営利を目的とした運営をしなければならないので、貸付けにも利息としての利益を作る必要があるのです。
仮に会社から100万円を借りるとした場合、利率が1.9%とすると利息は1年間で19,000円となります。会社は営利団体であるため、本来であればこの19,000円は受け取らなければなりません。
仮にこの利息を会社が受取らずに無利子で貸しつけると、利息は借りたものへ報酬として渡したことになります。
報酬となると給料と同じように所得として計上されるため、所得税を源泉徴収されることになりますので注意してください。
利息を取らなくてもいい場合
短期貸付けをするときには利息を付けなければいけないのですが、例外として利息を付けなくてもいい場合があります。
- 災害や病気などで臨時的に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に、不足する生活資金のために合理的と認められるような金額や、返済期間でお金を貸しつける場合
- 会社が借りている平均調達金利など合理的と判断できる利率を定め、その利率で役員や従業員に貸しつける場合
- 上記以外の場合で、災害や病気などで貸しつけるときの、平均な利息の差が1年間で5,000円以下の場合
なお、平均調達金利とは事業年度の金利合計を、事業年度の各月の借入金残高平均で割ったものです。
このような場合には、個人に対する短期貸付金で利息を設定しなくても、所得として換算されないため、無利息で貸付が可能です。
短期貸付金の適正利息
短期貸付けするときに適正利息を知っておくことが大切です。
国税庁のホームページに、お金を貸したときの利息について次のように記載されています。
役員または従業員にお金を貸した場合、利息相当額は次のような利率となっています。
- 銀行などの金融機関から借り入れて、貸付けをしている場合…その借入利率
- その他の場合…貸付けを行った日の属する年に応じた次の利率
◇借入期間と特例基準割合
| 借入期間 | 特例基準割合 |
|---|---|
| 平成20年中 | 4.7% |
| 平成21年中 | 4.5% |
| 平成22年から25年中 | 4.3% |
| 平成26年中 | 1.9% |
| 平成27年から28年中 | 1.8% |
| 平成29年中 | 1.7% |
| 平成30年中 | 1.6% |
なお役員や従業員にマイホームの購入資金に充てるための住宅資金の貸付けを、平成22年12月31日までに行ったときは年1%を基準とする特例があります。
従業員に短期貸付けする利息の計算方法
利息がかかる理由を見てきたので、これから従業員に短期貸付けを行うときの利息の求め方を紹介します。
利息の求め方
短期貸付金の利息の計算方法は2種類です。
ひとつは貸付けする会社が銀行からの融資を受けて貸しつける場合と、貸付けをした年の特例基準割合を用いて算出する方法です。
◇銀行から借りて融資を行う場合
銀行から100万円の融資を年1.9%の利率で融資を受けた場合は、短期貸付金の利息は銀行から借りた利率をそのまま当てはめます。
100万円を1.9%の利率の場合は次の通りです。
- 100万円×1.9%=19,000円
◇特例基準割合から求める方法
国税庁のホームページに載っている特例基準割合を使って計算します。100万円を1.8%の利率で短期貸付けした場合は次の通りです。
- 100万円×1.8%=18,000円
なお、上記の金額は年率で計算しているため、1年間貸付を行ったときの利息となります。もしも、1年未満の貸付の場合には、借入日数に応じた分だけの利息負担で大丈夫です。
短期貸付金の利息の仕訳
短期貸付金を経理で計上するときには、借方科目に短期貸付金、貸方科目に現金等支払方法の入力を行えば大丈夫です。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 1月31日 | 短期貸付金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
また、その後利息とともに返済を受けた場合には、借方科目に現金、貸方科目に短期貸付金と受取利息の記入を返済日とともに入力しましょう。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 7月31日 | 現金 | 101,900 | 短期貸付金 | 100,000 |
| 受取利息 | 1,900 |
仕訳として帳簿に記入するときには、上記の入力方法で大丈夫ですが、経費などの一時的立て替えの場合には、立替金として入力するため区別をしておきましょう。
短期貸付金の利息に関するQ&A
短期貸付金の利息について紹介してきましたが、短期貸付金についてまだまだ伝えきれていない情報がいくつもあります。
そこで、伝えきれていない代表的な情報をQ&A形式でまとめてみたので、是非知らない情報がないか確認してください。
①貸付金利息を取らない場合は所得税の源泉徴収が必要?
貸付金利息を取らない場合には、基本的には認定利息にあたる分の利息を所得税として源泉徴収しなければなりません。
しかし、利息の支払いが必要ない特別な状況の場合には、所得税の源泉徴収は必要ないです。
②会社が役員からお金を借りた場合の利息は?
個人から法人への貸付を行うことを役員借入金と呼びますが、役員借入金の利息は取締役会の承認のもと決定されます。
役員報酬と同じように、利息を自由に社長などが決定してしまうと、会社の利益を経営者が無断で取得する可能性がでてくるので、役員が独自に決められません。
③短期貸付金が多い会社は融資を受けにくい?
短期貸付金が増えてしまうと、役員や従業員に対して高額なお金を横流ししているのではないかと疑われるため、銀行などの金融機関からの評価が下がり融資を受けにくくなります。
融資を受ける前に不要な短期貸付金は解消しておく方が良いでしょう。
④同族会社への貸付金の適正利息は?
同族会社への貸付金を行うときにも、先ほど紹介した適正利息の求め方をもとに計算しなければなりません。
仮に適正利息を取らなかった場合には、贈与と取られたり、金利分を徴収されたりする可能性があるため気を付けましょう。
⑤短期貸付金や利息と給与は相殺できる?
短期貸付金や利息を給与や役員報酬を利用して相殺ができます。
ただし、給与と相殺する場合には、手取りの金額が減ってしまうというデメリットの他にも、貸付金分役員報酬を増やしてしまうと、税金や社会保険料が増加するため気を付けましょう。
まとめ
短期貸付金には利息が必要ですが、例外として利息を必要としない場合があります。
また貸し付ける相手が役員や社員など個人の場合は、利息を求める計算に金融機関の利率を使ったり特例基準割合を用いたりと状況によって変わります。
短期貸付金の利息は、課税の対象となることもあるので気を付けましょう。
タグ:その他金融業者




























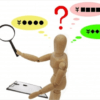













※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。