根担保とは何?抵当権と根抵当権の違いやメリットを徹底解説!
銀行融資で不動産を担保に差し入れることを、抵当権の設定(ていとうけんのせってい)といいます。
また抵当権は、普通抵当権(ふつうていとうけん)と、根抵当権(ねていとうけん)の2種類があります。
根担保を差し入れると思わぬトラブルに巻き込まれたり損をしたりしますので、この違いをしっかり押さえておきましょう。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
そもそも抵当権って何?
抵当権は法律用語ですので詳しく知らない人もいるかも知れません。
しかし意外にも、住宅ローンといった身近な契約でも抵当権は発生しています。
そこで、まずは抵当権について簡単におさらいしましょう。
不動産担保で借入れするときの制度
銀行からお金を借入れするときに、土地や建物などの不動産を担保に差し入れることがあります。
そして担保を差し入れる旨を公(おおやけ)に対して、法務局へ登記することを抵当権の設定といいます。
このとき借入れをした人が抵当権設定者といい、融資をした銀行が抵当権者といいますので覚えておきましょう。
住宅ローンでも土地や建物を差し入れる
抵当権は、事業性融資を受ける商売人だけが関係するのではありません。
それは、担保付のフリーローンや住宅ローンなどでも利用されているからです。
なお一般的なカードローンや自動車ローンといった無担保融資の商品は、抵当権は関係ありません。
融資商品が有担保であるか無担保であるかはあらかじめ確認しておきましょう。
質権(しちけん)や占有権(せんゆうけん)と何が違う?
抵当権と同じように、質権や占有権も担保を差し入れる法律行為です。
しかし質権や占有権で差し入れたものは、抵当権とは異なり自分で使うことができません。
つまり住宅ローンで自宅を質権や占有権の設定をすると、自宅が銀行のものになってしまうため自分がそもそも住めなくなるのです。
所有権を移さずに利用することができる!
抵当権であれば、担保に差し入れた不動産を自分で利用することができます。
質権や占有権と違い、抵当権を設定しても所有権は移らないからです。
さらに銀行が抵当権を行使して不動産を競売にかけられるのは、債務が不履行となった場合、つまり借金を返してもらえない場合に限りますので安心してください。
抵当権と根抵当権は何が違う?
抵当権は普通抵当権といわれる一般的な抵当権と、根抵当権の2種類あります。
これを知らずに借入れをすると、思わぬところで不動産を持っていかれかねません。
そこで、普通抵当権と根抵当権の違いを順番に確認していきましょう。
抵当権では債務が特定されている
普通抵当権では、担保に差し入れた不動産がどの融資のためか特定されています。
つまり住宅ローンであれば、担保に差し入れた自宅は飽くまで住宅ローンのためだけの担保なのです。
したがって住宅ローンを完済して債務がなくなれば、同じように普通抵当権もなくなります。
根抵当権があれば全ての借金を弁済する
普通抵当権に対して根抵当権は、担保に差し入れた不動産が全ての融資のために差し入れたことになります。
すなわち、根抵当権付きの融資とは別に無担保融資を受けた場合でも、その不動産は無担保融資まで担保しなければならないのです。
さらに根抵当権は不特定多数の借金が対象となっていますので、根抵当権を設定したときの融資を完済したとしてもなくなることはありません。
根抵当権で保証する金額は?極度額って何?
根抵当権は、この金額まで借金を肩代わりするという極度額(きょくどがく)があらかじめ設定されています。
例えば極度額が1,000万円の場合、借金の本数に関わらず1,000万円までは不動産を処分してお金を作ってもいいよという契約となります。
また普通抵当権と違い、根抵当権では延滞利息や処分に関わる費用も肩代わりしなければなりませんので注意しましょう。
完済後の根保証に用心!担保を抜こう!
根抵当権が残っていれば、今後受ける融資が無担保であっても担保を差し入れたことと同じになります。
万が一のときに不動産を手元に残しておくためにも、融資が完済したら担保から外す手続をします。
これを抹消登記(まっしょうとうき)といいますが、不動産の数(筆数)×1,000円の登録免許税と司法書士への数千円~10,000円程度の費用がかかります。
なお、普通抵当権の場合でも抹消手続が必要です。
普通抵当権は借金がなくなれば効力を持たないのですが、抵当権付き物件のままだと売買や相続に影響しますので抹消しておくことが望ましいです。
登記簿謄本で確認する方法は?
担保に差し入れた不動産に普通抵当権と根抵当権のどちらが設定されているかは、登記簿謄本に記載されている乙区で判別できます。
普通抵当権であれば登記の目的が「抵当権の設定」となっていますし、権利者の金額が「債権額」と表記されています。
これに対して根抵当権の場合は登記の目的が「根抵当権の設定」なっており、権利者の金額は「極度額」という表記になります。
根担保(根抵当権)で融資を受けるメリットとデメリットは?
ここまで話だけを聞くと、銀行融資で根抵当権を設定するメリットを感じられないかも知れません。
そこで根抵当権を利用する意味やメリットを紹介します。
登記する手間と費用を節約できる
抵当権を設定するときに、物件の価値によっては数10万円という費用がかかります。
人生に一度きりの住宅ローンならまだしも、事業性融資を反復的に受ける場合は幾らお金があっても足りません。
そこで根抵当権であらかじめ極度額を決めておくことで、いちいち抵当権を設定したり抹消したりする手間と費用を節約することができるのです。
事業性担保融資のほとんどが根抵当権
このような理由から、事業性融資で担保を差し入れるほとんどの場合が根抵当権となります。
むしろ銀行にとって根抵当権が当たり前であり、普通抵当権での交渉は難しいでしょう。
もし根抵当権を設定したくなければ、保証会社や連帯保証人などの別の担保で交渉してみてみることもおすすめします。
保証協会で代位弁済(だいいべんさい)ができなくなる?
保証協会付き融資を受けて返済できなくなった場合、代位弁済といって保証会社が代わりに返済してくれます。
ただし、根抵当権が残ったままだと不動産の処分が優先される可能性があります。
したがって、経営者は根抵当権を設定する契約時はもちろんのこと、完済時の抹消手続についても注意しましょう。
実家に根抵当権があった!どうすればいい?
商売をしていない人でも、親や兄弟から不動産の相続を受ける場合は注意が必要です。
それは親や兄弟が事業性融資だけでなく、消費者金融など借入れで根保証を入れている可能性があるからです。
相続される不動産に根保証があれば、自分のクレジットやカードローンの借金とひも付けされる可能性があります。
親族の根抵当権が判明した場合は、司法書士や弁護士などの専門家に一度相談しましょう。
「抵当権」と「質権」の違い
宅建などの資格試験では、担保物権として質権などと比べられることがあります。
抵当権は担保物権の中でも、担保に入れたものの所有権がお金を借りた人にあり、一方質権の場合には、担保に入れたものの所有権はお金を貸した人にあるのです。
例えば、マイカーローンを組むときに車を担保に入れる場合、このときの所有権はマイカーローンを組む人にあるので(なければ車に乗れないことになります)抵当権に分類されます。
逆に、質屋に時計を預けてお金を借りたときには、あなたの時計の所有権は質屋に移ります。このような質入れをするケースは、担保物件の中でも質権にあたります。
住宅ローンは原則、抵当権として住宅を担保物権にされます。
貸出方法の一つとして、質権設定をして住宅ローンを組むこともできますが、住宅を利用できなくなり、現実的な貸出方法ではないので利用されることはありません。
抵当権の手続き「抵当権設定登記」
法律的には抵当権を設定することは口約束でも行なえますが、問題が起こったときに法的根拠が薄くなってしまうため、登記を行って抵当権を設定することが一般的です。
抵当権を設定した不動産は、法務局に『抵当権設定登記』をします。
住宅ローンを組むときには、抵当権設定登記をどのように行われるのでしょうか。また、住宅ローン利用者が行う手続きはあるのでしょうか。
ここでは、抵当権設定登記について詳しく解説します。
抵当権設定登記とは
不動産を購入や相続、所有するときには、不動産の所有状況を証明する不動産登記をします。
抵当権設定登記もこの不動産登記の一部で、不動産が担保に入れられていることを証明しているのです。
通常、住宅ローン設定時に必要な抵当権設定登記は、銀行が紹介する司法書士や弁護士に委任することが一般的です。
申込者本人が行うこともできますが、書類の不備などで書類が受理されないなど、住宅ローン予定日までに抵当権の設定ができないリスクがあるので、銀行側は推奨してきません。
銀行によっては、抵当権の設定登記を申込者自身が行うことを認めておらず、登記を委任しなければローンの契約をしないこともあるため気を付けましょう。
抵当権設定登記の必要書類
抵当権設定登記には、いくつかの書類が必要となります。
- 不動産権利証(登記識別情報[2005年以降の不動産の場合])
- 印鑑証明書
印鑑証明書は、取得してから3か月以内の証明書が有効であるため、直近の証明書を準備しましょう。
司法書士や弁護士に委任をする場合には、委任状を記入すれば上記以外に申込者自身が準備する書類はありません。
上記の他にも、抵当権設定契約書や抵当権設定登記にかかる申請書など必要な書類がありますが、司法書士や銀行側が準備をするため、申込者自身が用意する必要はありません。
司法書士や弁護士への報酬
司法書士や弁護士に登記の依頼をするということは、相応の報酬を支払わなければなりません。司法書士への報酬は、登録免許税と書類の取得費用も含まれています。
抵当権設定に係る費用を表にまとめましたので、以下の表を参考にしてください。
| 経費項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 債権金額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 30,000円~80,000円 |
| 事前調査費用 | 約1,000円(筆数により変動) |
| 設定後書類取得費用 | 約1,000~2,000円(筆数により変動) |
例えば、2,000万円の住宅ローンを組むと仮定すると、合計の依頼料は以下の計算式になります。
(2000万×4÷1000)+2000+(30,000~80,000)=112,000~162,000円
抵当権設定後は返済を経て完済にいたりますが、完済時には抵当権を抹消する必要があります。
これから、抵当権抹消について学んでいきましょう。
抵当権の手続き「抵当権抹消登記」
抵当権の設定を行ったということは、住宅ローンの返済が終わるタイミングで抹消の登記もしなければなりません。
残念ながら抵当権の抹消は、住宅ローンの支払いが完了しても自動的には行われません。
また、銀行が代理で行うことではないため、基本的には自分で抹消登記を行うか、自分で司法書士に抹消登記を依頼しなければなりません。
抵当権の抹消を勧めるか勧めないかは銀行や担当者によって捉え方が違うため、完済と同時に抹消するものであると覚えてください。
近年では、他のサービス業と同様に銀行業務にもサービスの充実・他行との差別化を求める顧客が増加したことから、銀行側から抵当権の抹消を勧めるように変わりつつあります。
抵当権抹消登記を行わなければ、相続や売買などでデメリットが生じる可能性がありますので、住宅ローン完済前に詳しい知識をつけておきましょう。
ここでは、抵当権抹消とは何か、抹消登記の方法について紹介します。
抵当権抹消とは
抵当権抹消登記とは、住宅ローンを組むときに設定した抵当権の登記を抹消する登記となります。
抵当権の抹消を行わなくても、住宅ローンの完済が終わっていれば弁済を強いられることはありません。(根抵当権を除く)
不動産登記簿に抵当権の情報が残ったままだと、リバースモーゲージなど新たに不動産を抵当権に入れてローンを組むときに、金融機関から嫌がられる可能性があります。
しかし、申込審査時には不動産登記簿謄本にて確認しますので、残債があるかないかを聞き取りされ、もし抵当権が残っている場合には設定と同時に抹消を勧めてくれるでしょう。
また、抵当権抹消登記の書類は銀行が発行しますが、有効期限を過ぎてしまうと再発行に手数料を取られることもあるので、完済後早めの手続きをおすすめします。
抵当権抹消登記の方法
抵当権抹消登記は、銀行から受け取る書類と法務局から取得できる「抵当権を抹消する不動産の全部事項証明書」を準備して、法務局に提出することで完了します。
自分で抵当権の抹消を行う場合には、以下の書類が揃っていることを確認してください。
必要書類はこちら
- 解除証書
- 抵当権設定契約証書
- 代表者事項証明書
- 委任状
書類を確認したら、申込書を作成して認印と手数料分のお金を持って法務局の登記相談コーナーにて担当者の進めるとおりに手続きをしてください。
登記相談コーナーでは、登記資料に不備がないかを相談員が丁寧にチェックするため提出後の不備を減らすことができますし、不明な点は相談員から教えてもらえるため、質問を準備してから向かいましょう。
また、「申請書を作成する時間がない」「書類の作成ができるか不安」と言う方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
設定登記と比較すると報酬の相場は低いため、大きく経済的な負担にはならないでしょう。
抵当権抹消に係る費用をまとめましたので、以下の表を参考にしてください。
| 経費項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 筆(棟)数×1,000円 |
| 司法書士報酬 | 5,000円~10,000円 |
| 事前調査費用 | 約1,000円(筆数により変動) |
| 抹消後書類取得費用 | 約1,000~2,000円(筆数により変動) |
ちなみに、住宅ローンの抹消(土地1筆・建物1棟)であれば20,000円程度で済みます。
参考:不動産売却の教科書「抵当権抹消手続きを自分で行う方法・場所・必要書類と注意点」
抹消しないことで起こる弊害は?
抵当権を抹消しない事で起こり得る弊害としてもっとも可能性が高いのは売却時でしょう。
住宅ローンなどの抵当権が付いた債務は、完済と同時に抵当権を抹消するのが一般的です。
売買時に抵当権が残っていることで、リスクのある取引だと認識され取引がなくなる恐れもあります。
また、新たな融資を受ける際にも弊害になり得ます。
抵当権がある事で、まだローン返済中であるという認識を持たれてしまい、希望額で融資されないどころか、審査にとおらない可能性も出てきます。
因みに、金融機関では審査時に担保物件に係る調査をしますので、担保物件に完済したはずの抵当権がまだ付いている場合には事実確認のうえ、設定と同時に抹消を勧めてくれるので安心してください。
抵当権抹消に係る注意点
住宅ローンの完済と同時に抵当権の抹消手続きを行うのが一般的ですが、他の書類などと混ざってしまい書類を紛失してしまうことがありますので注意が必要です。
日常生活に利用する書類ではありませんが、大事な書類ですので保管には気を付けましょう。
万が一必要になった時、紛失してしまうと手続きがスムーズに運びませんので、法務局からの書類は厳重に保管しておくことをおすすめします。
抵当権の「順位」とは
抵当権の権利書には、「1番権利」などと順位が付けられています。
このような抵当権の順位にはどのような意味があるのか、詳しく確認していきましょう。
民法では債権者は平等
まず抵当権を含める民法の前提を紹介します。民法上では、債権者が複数いる場合には特例がない限り、債権者の権利は平等になります。
例えば、A君がB君から50万円、C君から100万円借りていたとします。しかし、A君はお金を全く返すことができなくなったので、A君の所持金15万円をB君とC君で分け合うことになりました。
このときに、B君とC君の分け前はどのようになるのでしょうか。一見すると、C君の方が多くお金を貸しているため、取り分も多くなるように思えます。
しかし、先ほどの債権者の権利は平等であるという原則が働くため、取り分もきっちり半分となり、B君7万5千円、C君7万5千円となります。
抵当権には順位が付く
抵当権は1つの不動産に複数つけることができます。
この場合民法上では、権利は平等とありますが、いつ設定しても平等であれば後から抵当権をつけた人が有利となってしまいます。
このような事態を防ぐために、抵当権には上から順位がつけることができます。
上から1番抵当、2番抵当、3番抵当…と言ったように順位づけなり、上の順位から優先して権利を行使が出来ます。
例えば資産価値3,000万円の土地に1番抵当2,000万円、2番抵当800万円、3番抵当500万円の設定があるとします。
この状態で借主が自己破産したり返済が滞るようなことで、この抵当権が行使された場合、担保となっている土地は差し押さえられ、競売にかけられます。
競売で土地が3,000万円で売れた場合には、1番抵当から優先順位がありますので、1番抵当の2,000万円、2番抵当の800万円の順に回収していくことになります。
担保物件売却額3,000万円-1番抵当2,000万円-2番抵当800万円=200万円となってしまいます。
このため、3番抵当の500万円は満額回収できず300万円は貸し倒れてしまうことになります。
このように抵当権は後順位になればなるほど担保としての価値は薄れてしまいます。
住宅ローンを2社以上から借入れるのは困難
1つの物件を購入するために住宅ローンを2社以上から借入を行うのは現実的に不可能です。
住宅ローンの条件として、抵当権の順位を一番にして抵当権をつけることが一般的となっています。
このため、2社目の抵当権は必ず2番目となってしまいます。
3,000万円の資産価値の土地建物に対してA社2,000万円、B社2,000万円で住宅ローンを組もうと思っても、後順位のB社の抵当権は1,000万円の担保割れとなってしまいます。
住宅ローンは基本的に担保価格までしか融資を行わない上に、抵当権第1位が条件ですので、2つとも条件を満たすことができないため、2社目の住宅ローンを、同一物件を担保にして借りることは不可能です。
土地と建物を別々に抵当に入れることも困難
建物を建てるのであればそれを建築する土地もすべて担保として提供しなければなりません。
土地だけ他の抵当権が設定されてしまった場合には、土地が借主以外の第三者の手にわたってしまい、建物の担保としての価値が著しく低くなるためです。
したがって、土地と建物を別々に抵当権につけることはあまりなく、同一の担保として抵当権をつけることになります。
抵当権つきの不動産を相続した場合
不動産を親や親族から相続するときに抵当権がついているかどうかは非常に重要で、ローンの支払い状況などによっては、相続税の金額にも影響をあたえたり抵当権抹消登記が必要になります。
そこで、抵当権つきの不動産を相続したときの注意点について、詳しく確認していきましょう。
不動産を相続すると抵当権も付いてくる
遺産相続をするときには、親の遺産の中の資産も負債もどちらも相続することとなりますので、残念ながら資産だけを相続することはできません。
また、不動産の場合には、抵当権も資産と共についてきます。
したがって、遺産相続後に住宅ローンの支払いができない場合には、銀行などの抵当権の所有者から不動産を差押えられる危険性があります。
相続後に困ることが無いように、遺産相続前に不動産の抵当や担保関係をしっかりと調査し把握してから相続をしましょう。
抵当権を抹消には借金の完済と手続きが必要
抵当権つきの不動産を相続した後に、相続人が抵当権の抹消を行うことは可能ですが、抹消をするためには、抵当権所有者に対して住宅ローンなどの借金を全額完済しなければなりません。
また、抵当権の抹消を行うためには、先ほど紹介した抵当権抹消登記を相続人自身が行わなければなりません。
住宅ローンの抵当権設定手続きを行った本人ではないことや、書類の受取や名義の変更など専門的な知識が必要になることから、専門家である司法書士に依頼することになるでしょう。
抵当権と相続税の関係
抵当権と共に住宅ローンが残っている場合、相続税が減額になる場合があります。
相続税の計算は、相続する資産から負債を差し引いて算出されます。
そして、住宅ローンは負債として計算されるため、不動産の金額から差し引いて相続税の計算が行われます。
例えば、4000万円の不動産を相続したときに、抵当権と500万円の住宅ローンが残っていたとします。この場合、相続税の対象となる財産は、4000万円-500万円=3500万円となります。
法定相続人1人のときの相続税の基礎控除額(税金対象外の金額)は3600万円(基礎控除額3,000万円+600万円[法定相続人×600万円])なので、他に遺産がなければ相続税はなしとなります。
相続破棄という手段もある
「抵当権と共に高額の住宅ローンや借金を相続してしまい、とても不動産の売却金額だけでは返済ができない」、このような状況の場合、遺産を相続しない相続破棄という方法をとることもできます。
相続破棄をしてしまえば、親の借金であったとしても相続人に支払いの義務は一切ないので、親や親族が高額な借金がある場合には、思い切って相続破棄してしまうのもひとつの手です。
ただし、相続と同じように部分的な破棄をすることはできないので、不動産や預金などの資産も全て相続破棄することになります。
もし不動産を売却すれば借金を完済できそうな場合は、相続破棄しない方が良いでしょう。
大きな融資には抵当権設定が必須
金融機関としては、住宅ローンなどの大きな額の融資は無事に回収されるかが不安であるからこそ抵当権を設定します。
そのためもし、融資金額、返済期間、借入金の使途、返済額、融資金利等などで約束が守れなかった場合には、対象物件の権利は金融機関の元に渡るということです。
契約書には契約の流れがあり、借主と貸主の同意の基に融資契約と抵当権設定に関する契約書を交わすことになります。
それらは主な契約で、購入前にどのプランで家を購入するかそして、いくらで返済するのか、抵当権設定に係る費用がどの程度かかかるのか十分確認してからの契約を組むことをおススメします。
抵当権付きの不動産を担保とした借入は可能?
住宅ローンの返済をしている間にも、何らかのローンを組む必要が出てくることも考えられます。
このときに、不動産を担保に入れることができれば、有利な条件でローンを組むことができます。
しかし、すでに他の債権者の抵当権がついている不動産を担保として借入を行うことは、不可能でしょうか?
担保余力との関連を踏まえて詳しく確認していきましょう。
担保に余力があれば可能
先ほどの例を再び用いて確認していきましょう。
資産価値3,000万円の土地と建物に3,000万円の抵当権がついている物件を担保にして借入を行うことは可能でしょうか?
住宅ローンを借りてすぐに当該物件を担保として借入を行うことは不可能です。
3,000万円の資産に対して3,000万円の借入が残っているためです。
しかし、10年間返済して借入額が2,000万円まで減少していた場合には、資産価値に減少がないと仮定すると資産価値3,000万円-借入残高2,000万円=担保余力1,000万円の枠が空いていることになるため、1,000万円の借入ができる可能性があります。
ただ、この物件には担保価値が認められるというだけで、この物件を担保として借入を必ず行うことができるというわけではありません。
むしろ、個人の借入の際に不動産を担保として借入を行うのは住宅ローンとリバースモーゲージくらいで、ほとんどの借入が不動産担保を取らないというのが現実です。
利用できない可能性が高いときはどんなとき?
先ほど述べたように、不動産の評価額が先順位の抵当権の借入残高を下回っている場合には担保価値が認められないため担保としては利用できません。
例えば、担保評価を行った際に2,000万円しか価値がないにも関わらず、3,000万円の抵当権がついていたような場合には、後順位の抵当権には1円も回収できる見込みがないことからこのような物件は担保として提供することは不可能です。
また、多くの住宅ローンやリバースモーゲージなどの条件である「抵当権1位」のローンは担保の余力がどれほどあろうと、先順位の抵当権がついている時点で申し込み条件を満たしていないことになるため、担保として利用することはできないですし借入を行うことも不可能です。
現実問題として、抵当権つきの不動産を担保にローンを組むことはかなり厳しいと考えておきましょう。
抵当権に関するQ&A
最後に抵当権に関する少し細かい内容を、Q&A形式でまとめてみました。状況が限定されているものも多いですが、気になる内容がないか是非確認してみてください。
Q.動産を抵当に銀行からお金を借りることはできる?
動産を抵当にして銀行からお金を借りるケースは、現実的にいくつかあります。
例えば、車を購入するときにマイカーローンを銀行で組む動産を抵当に入れてお金を借りていることになります。
また、工場を経営する企業の場合、工場内の設備や機械を抵当に入れて融資を受けることもあるでしょう。ただし、どちらも車や設備などの購入費用として、動産を抵当に入れることがほとんどです。
実務として抵当権を設定することはないので、あくまでも借主と貸主の共通意識として「動産を抵当に入れているという考え方」と認識しておくとよいでしょう。
例えば、学資ローンを借りるために車を担保に入れるなど、目的と対象物に関連性が無い借入れはどの銀行も行っていません。
Q.抵当権付きの賃貸物件を借りると、債権者に追い出される可能性がある?
賃貸物件のオーナーが借金を支払えずに、債権者に所有者が移るケースは実際に起こる事例です。
通常の場合には、マンションの経営者が変わるだけで居住者に影響しませんが、マンションやアパートの建て替えや取り壊しをするときには、追い出しを請求されることもあります。
追い出しの請求については、一部の例外を除き基本的には受け入れて出ていかなければなりませんが、即座に退去することは難しいため、マンションを借りている人も所有者が変更してから6か月間引越しの猶予があたえられます。
残念ながら、立ち退きの要求があった場合には、6か月以内に新居を見つけて引越しを行いましょう。
Q.抵当権を実行されるとどうなるの?
抵当権を実行された場合、不動産は競売にかけられることとなります。
抵当権者は裁判所に競売の申立てに行き、その後裁判所主導で競売が開始され、競売で売却された金額は、抵当権者に配当されます。
このときに、抵当権者が複数いる場合には、順位に応じて配当額が変動します。
住宅の所有権は競売で落札された瞬間に、落札者へと移行してしまいます。
もし落札以降に関わらず居住していると、不法占有となるため立退きをしなければなりません。
Q.債務を弁済できず抵当権を実行されても債務が残ることはある?
先ほども紹介したように、抵当権行使後は不動産が競売にかけられ落札金額が、配当として抵当権者へ分配されます。
しかし、落札金額が住宅ローンの残債よりも少なかった場合には、不足した金額はそのまま無担保の借金として残ってしまいます。
残債については借金の返済義務は残るため、抵当権者と交渉をして借金返済の段取りを決める必要があります。
状況によっては、自己破産や個人再生などの債務整理を行う必要もあるので、弁護士などの法律の専門家を交えて交渉することをおすすめします。
まとめ
借入れを利用する人にとって、根抵当権は登記費用以外のメリットがありません。
もし担保付融資を完済したにも関わらず根抵当権が残っている場合は、抹消することが望ましいでしょう。
ただし担保から外すことで、銀行評価が下がる可能性があります。
今後の事業形態や借入れ予定などを考慮した上で、担保抹消をするようにしましょう。
タグ:目的別

































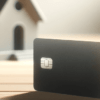











※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。