奨学金は追加融資可能?貸与月額変更手続きを徹底解説
学生のうち半分近くが利用していると言われる奨学金ですが、奨学金の借入は月額〇〇円という形で行われます。
毎月、数万円を借り入れ、学生生活に必要なお金を補填するという制度です。
学生生活の中において、キャンパスの変更などの理由から月額貸与額が不足するという事態になる可能性があります。
そのような場合には奨学金の追加融資を受けるということは可能なのでしょうか?
追加融資を受ける場合には日本学生支援機構の審査に通過する必要があります。
追加融資の審査とはどのような点が重要になるのでしょうか?
この記事では奨学金の増額について徹底解説をしていきます。
この記事はこんな人におすすめ
この記事は以下のような人におすすめの記事となっています。
- 奨学金が足りなくて困っている人
- 奨学金を増額融資してもらいたい人
- 奨学金の手続き方法について知りたい人
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、経済的な理由などで教育費が足りない学生に、進学に必要な費用を無利子または低利子で貸しています。
奨学金は、学費に使われるというイメージがありますが、それだけではなく入学金、教材購入費、下宿・生活費、サークル活動費などを補填するためにも使われます。
ただし、入学金については納付期限が支給開始日に間に合わないため利用できないケースがほとんどです。
日本学生支援機構では、第一種奨学金と第二種奨学金という2つの貸与型奨学金と、平成30年から導入される給付型奨学金とがありますが、どちらも契約者は学生本人となります。
親ではない点に注意が必要です。
また、学力や収入に関する基準が定められており、連帯保証人・保証人を必要とします(ただし、保証料を支払えば不要)。
では、日本学生支援機構の奨学金の申込み方法や手続きの流れ、返済や相談先について説明していきます。
申込方法と手続きの流れは?
奨学金の申込み方法や手続きは増額申込みの場合と新規申し込みの場合で異なります。
増額申込み
奨学金の増額申し込みは、いつでも誰でもできるわけではありません。
第一種の場合は、自宅通学から自宅外通学に変更する場合で、審査にとおる必要があります。
一方、第二種の場合は、「増額したい」と思ったときに必要に応じて増額できます。
ただし、支給額変更は原則として1回のみになりますので注意しましょう。
増額については学生課で「奨学金貸与月額変更願」をもらって申請手続きをします。
新規申込み
新規申し込みは、高校在学中から申込み可能で、もちろん大学入学後の申込みも可能です。
予約採用の場合は、高校を通して申し込む方法と日本学生支援機構に申し込む方法とがあり、高校3年生の5月中旬から7月中旬頃に申し込みが行われます。
一方、在学採用の場合は、大学の学生課を通して申し込むことになり、毎学年4月頃に申込みが行われますが、学校によって申込期限が決められていますので、早めに高校・日本学生支援機構、学生課に相談することをおすすめします。
貸与期間と返済について
奨学金の貸与期間は、大学入学後から卒業までの間となり、第一種・第二種ともに4月~7月の間に貸与が開始されます。
なお、原則として卒業まで貸与されますが、毎年「奨学金継続願」を提出する必要があるのです。
その後、卒業してから返済が開始されますが、返済期間・回数は返済方法によって異なります。
返済方法には、所得連動変換方式(第一種のみ)と定額返還方式がありますが、早期返還を目指すためには繰り上げ返済を行うことがおすすめです。
どこに相談すればいい?
高校在学期間中に予約採用を申込む場合は、学校の担任の先生か、日本学生支援機構に相談してみましょう。
大学に入学してから申込む場合や増額の申込みをする場合は、学生本人が学生課で相談します。
なお、奨学金ではありませんが、国の教育ローンを利用したいという場合は、「教育ローンコールセンター」というものが設けられていますので、そちらで相談しましょう。
奨学金の種類
まずは在学中に利用できる奨学金の種類について解説します。
奨学金には第1種奨学金と第2種奨学金、給付型奨学金の3つの種類が存在しますが、追加融資の基準や追加融資ができるかできないかも、奨学金の種類によって異なります。
それぞれの奨学金の概要や採用基準の違いについてまずは理解をしておくことが重要です。
第1種奨学金
第1種奨学金とは、無利息で貸与される奨学金で、一定以上の成績を収めており、経済的に困窮していて保護者の経済力では学費を賄えないという家庭事情の子供に限られて貸与されるものです。
四年制大学に入学した場合の貸与月額は以下のように決められています。
●国公立・自宅通学の場合:月額20,000円、30,000円または45,000円
●国公立・自宅外通学の場合:月額20,000円、30,000円、40,000円または51,000円
●私立・自宅通学の場合:月額20,000円、30,000円、40,000円または54,000円
●私立・自宅外通学の場合:月額20,000円、30,000円、40,000円、50,000円または64,000円
※日本学生支援機構公式サイトより引用
第2種奨学金
第2種奨学金とは、第1種奨学金よりも緩やかな基準で借りられる奨学金で、こちらは有利子になります。
利率固定方式という、いわば固定金利で借りられますし、利率見直方式という変動金利のような借り方も可能になっています。
平成30年の利率は利率固定方式で0.2%〜0.3%程度、利率見直方式では0.01%と非常に低金利で借りられます。
金利はその時々の金利情勢によって変化しますが3%が上限とされています。
第2種奨学金の貸与月額は、大学の場合は20,000円〜120,000円となっています。
前述したように、第1種奨学金は借りられる月額が最大で64,000円と、それほど多い金額ではありません。
第1種だけでは足りないという学生は第1種と併用して第2種も借りるという手続きを行うことが可能になっています。
給付型奨学金
給付型奨学金とは返済不要の奨学金です。
支給対象者となるのは、住民税非課税世帯や生活保護受給世帯など非常に限られますが、返済が不要という点が最大のメリットです。
支給月額は以下のように決まっています。
- 自宅通学:国公立2万円、私立3万円
- 自宅外通学:国公立3万円、私立4万円
金額はそれほど大きくはありませんが、返済不要ですし他の奨学金との並行利用できるため、該当する人は受給しておいたほうがいいことは間違いありません。
第1種と第2種の併用供与
第一種奨学金と第二種奨学金を併用貸与してもらうこともできます。
片方だけでは充分な学費を賄えないと判断した場合は、どちらも利用することを検討してみましょう。
ただし、家計の収入基準は第一種のものよりも厳しくなっているので、誰でも簡単に利用できるわけではありません。
また、貸与額が多額になるほど返済の負担が大きくなることは覚悟しておかなければなりません。
申込み方法などについては学校で相談してください。
所得連動利子奨学金
所得連動返還型無利子奨学金制度は、貸与を受けた学生が、卒業後に一定の収入を得るまでの間、申請することにより返済期限を猶予してもらえる制度です。
これにより、返還の不安を軽減して勉強に安心して取り組めるようにすることを目的としています。
第一種奨学金を申込んだ人の中から、基準に合った学生を選定し、本人には採用時に通知されます。
追加融資ではなく増額
奨学金の場合、銀行や国の教育ローンの借入のように、融資金が一括で振り込まれる訳ではなく、「月額〇〇円」というように毎月お金を借りるという手続きになります。
このため、追加融資というよりも、貸与月額を増額するという考えになります。
一定の条件を満たせば、受給中でも奨学金は貸与月額を増額することが可能になります。
増額が認められるケース
増額が認められるかどうかは、それぞれの奨学金の種類によって異なりますし、特定のケースのみ増額できることがあります。
奨学金はカードローンのように本人の返済能力に基づいて融資を行なっているわけではありません。
あくまでも学生の学業を支援するための貸付金ですので、一般のローンのように「返済能力さえあれば追加融資や増額が可能」というわけにはいきません。
それぞれの奨学金の増額基準は以下のようになっています。
入学時特別増額貸与奨学金
大学などの入学時というものは、入学金が発生するため2年目以降よりもお金がかかるものです。
そこで、入学時だけ通常の貸与月額に増額してお金を貸与する「入学時特別増額貸与奨学金」という奨学金があります。
通常の奨学金に増額し、10万円、20万円、40万円、50万円のいずれかの貸与を受けられます。
第1種の場合
前述したように、第1種奨学金は「国公立か私立か」「自宅通学か自宅外通学か」などという基準によってあらかじめ貸与月額が定められています。
このため、この基準に基づいて支給額を変更できる場合のみ、貸与月額を増額することが可能になっています。
例えば、自宅通学から自宅外通学へと変更になった場合には増額できます。
一方、自宅外通学から自宅通学へ変更になった場合には減額されてしまいます。
第2種は用途が広い
第2種奨学金は必要に応じて増額と減額を行えます。
ただし、学生生活が継続して必要とする場合に限るとされていますので、私生活で支出が増えてしまったなどの理由の場合には、増額を断られてしまうことになります。
なお、今月だけ増額したいとか、短期間で増額や減額を繰り返すということはできません。
さらに、増額部分については、金利も通常の金利とは異なります。
利率固定方式にしても、利率見直し方式にしても基準金利に0.2%上乗せになります。
このため、増額をするのであれば最初から余裕も持って借りておいたほうが金利的には安くなるため最初の借入時に計画的に申し込みを行うようにしましょう。
返済時のことを考えた利用を
奨学金は大学などを卒業した後に返済をしていく必要があります。
そして卒業後にはその借入内容が信用情報に登録されるため、返済に遅れると信用情報に遅れたという情報が記録されてしまいます。
仮に住宅ローンなどを申込む場合、返済状況に「奨学金延滞」という記録が残されていると、ローンの審査に悪影響が出てしまいます。
さらに、最近は奨学金の返済負担が大きく返済できなくなり、ブラックになったり自己破産に至る人が増えているということも社会問題になっています。
奨学金は第2種であれば比較的簡単に増額できます。
しかし、将来の返済ことを考えて、ある程度借りる金額を少なくするということも重要です。
返済額が収入に見合った返済負担率に収まるように、計画的に利用しましょう。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)は増額融資可能?
教育費用を賄うための借入れは奨学金だけではありません。
公的機関である日本政策金融公庫の「国の教育ローン」も教育資金を確保するための心強い味方です。
国の教育ローンも奨学金同様に増額融資が可能となっています。
増額融資についての説明に入る前に、まずは国の教育ローンの基本情報について確認しておきましょう。
| 借入限度額 | 350万円(海外留学の場合は450万円) |
|---|---|
| 金利 | 年1.78% |
| 返済期間 | 最長15年 |
| 振込みまでのスピード | 20日程度 |
| 申込期間 | 一年中いつでも可 |
(2019年3月現在)
では、国の教育ローンを増額するときの申込み方法や必要書類などについて確認していきましょう。
申込方法と手続きの流れは?
国の教育ローンの追加融資は、子供ひとりにつき350万円を超えない範囲内で増額できます。
このときに気を付けたいのは、すでに借り入れているローンに上乗せするということではなく、追加で新しいローンを組むという形になることです。
増額融資の申し込み方法は次のように進められます。
- インターネットから増額申し込みを行う。
- 審査が行われる。10日前後で結果が郵送される。
- 借用証書、合格確認書類など必要書類を提出する。
- 審査結果の連絡から10日前後に口座に振り込まれる。
基本的には、新規申し込みのときと同じような手続き内容となります。
増額審査は新規融資時よりもハードルが高い?
増額融資を申込んだ場合は、再度審査を受ける必要がありますが、新規融資時よりも審査が厳しく行われる傾向があります。
というのも、借入総額がさらに大きくなるため、その分の返済能力があるかどうかを厳しくチェックされるからです。
そのため、新規融資時にぎりぎり返済可能な金額を借り入れてしまっている場合、追加融資の審査を通過するのは非常に厳しいと言えるでしょう。
増額申込みにかかる必要書類は?
増額融資を申し込むときに必要となる書類は次のとおりです。
- 借入申込書
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 運転免許証またはパスポート
- 源泉徴収票または確定申告書(控)
- 預金通帳(最近6か月分以上
- 在学を確認できる書類
- 使い道を確認できる書類
「世帯年収の上限額緩和」の場合はさらに書類が増える
「世帯年収の上限額緩和措置」は、子供が2人以内の場合で、以下の8つのうちにいずれかひとつに該当する場合、上限額が990万円まで緩和されるというものです。
- 勤務年数(営業年数)が3年未満
- 居住年数が1年未満
- 世帯に自宅外通学者がいる(予定も含む)
- 申込み人かその配偶者が単身赴任
- 借入れ使途が海外留学資金
- 申込人の所得に占める返済負担率が30%を超えている
- 親族に要介護(要支援)認定者がいて介護費用を負担している
- 大規模な災害に被災した
3の場合は自宅外通学を確認できる書類を、4の場合は単身赴任が確認できる書類を、7の場合は地自治の認定通知書などを、8の場合は罹災証明書などの提出が追加で必要になります。
奨学金も国の教育ローンも審査落ちしたら
奨学金も国の教育ローンもお金を借りることなので、利用する前に審査を受けることになります。
審査を受ける以上、審査落ちすることも考えられますので、もしそうなった場合の対応策についても考えておきましょう。
金融機関の教育ローン
国の教育ローンに審査落ちしてしまったら、授業料や教材費、下宿・生活費などを支払えませんよね。
その場合は、銀行教育ローンの利用を検討してみるといいでしょう。
銀行の教育ローンは、国の教育ローンよりも限度額が大きく、1,000万円や銀行によっては2,000万円まで対応しているところもあります。
また、カードローンタイプの教育ローンを提供しているところもあるため、利用限度内であれば何度でも自由に借入れできるので便利です。
但し、極度額を設けている教育ローンの場合には、何にいくら使うのかを申告しなければならない場合もあります。
他にも、保証人が必要かどうかも気になりますが、原則不要ではあるものの申込人の返済能力に応じて必要となる場合があります。
さらに、銀行によっては無担保か有担保を選べ、有担保の場合には所有不動産を担保にすることになりますが、その代わり金利が安くなるなどのメリットがあります。
金額によってはカードローンで
銀行の教育ローンのほかにも、カードローンを利用するという方法もあります。
カードローンには、銀行系と消費者金融系とがあり、銀行系カードローンは低金利で種類が豊富ですが、即日融資はできません。
一方、消費者金融系カードローンは、銀行系に比べて金利が高くなりますが、審査スピードが速いので契約したその日のうちに融資を受けられるところが多いです。
また、教育ローンは基本的に借入れは一度きりですが、カードローンは利用限度額の範囲内であれば自由に借入れできるので、ちょっとお金が足りないときに便利です。
しかし、毎月の返済に加えて臨時返済も行っていかないと、借入期間が長引き利息の負担が大きくなります。
他にも、「借りグセ」がついてしまうこともありますので、利用は必要最小限に抑えるなど計画的に利用することが大切です。
まとめ
奨学金には第1種奨学金と第2種奨学金と返済不要の給付型奨学金があります。
貸与月額を増やす増額という手続きは、学生の通学状況などによって行えます。
また、利息の発生する第2種奨学金に関しては、増額手続きは比較的簡単に行えます。
しかし、給付型奨学金はあくまでも借金で、社会人になった後には返済義務が生じ、返済ができなくなった場合には通常の借金と同じように、厳しいペナルティがあります。
学生は現在の生活が精一杯という人も少なくありませんが、卒業後に返済していくことも考慮した上で適切な金額を借りるようにしてください。
タグ:目的別


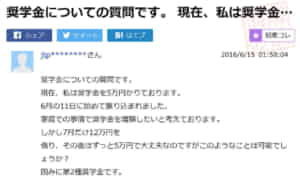
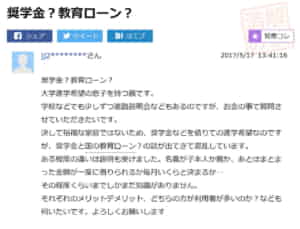







































※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。