事業資金も借入時の長短バランスが大事!
会計士や銀行から「決算書の長短のバランスが悪い」などと言われたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか?
借入金には長期借入金と短期借入金があります。
この借入金の長期と短期をバランスよく、適材適所に利用しないと、会社の資金繰りが悪化してしまうことがあります。
しかし、長期と短期のバランスと言われてもよく分からないという人がほとんどではないでしょうか?
基本的には、長期と短期を正しい使い道に利用すれば長短のバランスが悪くなることはありません。
この記事では、長期資金と短期資金の使い方から、長短のバランスについて解説していきます。
短期借入金と長期借入金
銀行から企業が融資を受ける際には短期借入金と長期借入金という2つの借入金が存在します。
この違いというのは、借入期間の違い以上に、返済方法の違いが企業の資金繰りを左右する、長短のバランスに影響を及ぼすことになります。
1年以内は短期借入金
短期借入金とは、1年以内に返済期限が到来する借入金です。
一般的に短期借入金は、期日に一括で返済される融資です。
1年超は長期借入金
長期借入金とは、1年を超える借入期間がある借入金です。
完済までの期間が長いため、長期借入金は一般的に完済まで毎月均等に返済していく借入金です。
運転資金の考え方
そもそも会社の運転資金とは何なのでしょうか?
まずは、基本的な運転資金の考え方を考察するとともに、運転資金を調達するためにはどのような資金調達を行うべきなのかを考えていきたいと思います。
運転資金の計算方法
会社の運転資金とは、以下の方法で計算します。
「売掛債権+棚卸資産-買入債務」
- 売上債権とは未入金のすでに売り上げた売上です。売掛債権:売掛金、受取手形
- 棚卸資産:在庫
- 買入債務:買掛金、支払手形
また、棚卸資産とは将来の売上で、こちらも将来的には入金されるものです。
一方、買入債務とは未払いの仕入れ資金です。
例えば、売上債権が200万円、棚卸資産が100万円、買入債務が150万円の場合には、200万円+100万円−150万円=150万円。
この会社には150万円の運転資金が手元に必要であるという考えになります。
収支ずれの際に運転資金が必要
現金商売の飲食業やサービス業であれば手元に運転資金がなくても会社は運転することができます。
このような業種は売上が即現金化するためです。
しかし、ほとんどの会社は売上の入金は後になり、先に仕入れなどの買入債務の支払いが必要になります。
上記の事例で言えば、将来的に売上として入金されてくるまでは、運転資金の150万円を手元に持っておかなければ会社を運転していくことは不可能であるという考えになるのです。
仕入債務の支払期限が到来し、売上債権が入ってくるまでの時間的なずれを収支ずれとか資金ギャップと呼びます。
運転資金は短期で返済可能
収支ずれとは、買入債務の支払いと、売上債権の入金までの短期間だけ発生するものです。
例えば買入債務の支払いが翌月末、売上債権の入金が翌々月末という場合には、売上金が入金となるまでの、今月と翌月の2ヶ月分だけ運転資金があればよいことになります。
このため、運転資金の借入は売上が入金になるまでの短期間だけで、売上が入金になったら返済し、そこで必要なら再び借りるというサイクルを辿ればよいことになるのです。
銀行融資の実態
銀行融資では、運転資金は短期という原理原則が実はできていません。
何かといえば長期で融資してしまいますし、銀行も企業も短期的な目線で考えればそちらの方が都合がよいのです。
しかし、そのような行為が結果として企業の長短バランスを崩し、資金繰りを圧迫させる原因となってしまいます。
運転資金も長期で融資する
実際の銀行融資の現場では、運転資金も長期資金で融資してしまっているのが実情です。
理由としては銀行も企業も短絡的に考えれば長期資金の方が都合がよいためです。
銀行は長期の方が安心
銀行にとっては、期日に一括返済が必要になる短期資金よりも、毎月コツコツと返済が行われる長期資金の方が安心です。
短期資金は、期日になった時に「お金がなくて一括返済できない」というリスクがつきものです。
また、信用保証協会の保証も短期資金よりも長期資金の方が得やすいという事情もあります。
筆者も銀行員時代は運転資金融資と言えば長期資金ばかりでした。
手形のコロガシは担保も必要
短期資金は手形貸付によって行われますが、短期で運転資金を融資すると、期日になったら返済し、すぐにまた融資を受けるという状態になるのが一般的です。
手形が期日の都度ずっと更新されていくため、このような融資を手形のコロガシなどと言いますが、手形のコロガシはずっと同一金額を貸しっぱなしの状態になるため、銀行とすれば何らかの担保がないと安心できません。
このため、担保を提供できない会社は短期での運転資金を借りにくいという事情もあります。
さらに、これまでずっと手形が転がっていた取引先に対して、銀行にとってより安全な信用保証協会の保証付長期資金を融資して、手形融資を回収するということも、数年前まで行われていたため、本来短期で融資すべき運転資金は、当たり前のように長期で融資されるようになっています。
企業も長期の方が安心
企業にとっても心理的には短期よりも長期の方が安心です。
短期資金は期日に一括返済の必要があるため「もしも期日に返済できなかったらどうしよう」という心理がどうしても働くのです。
さらに、銀行から突然一括返済を迫られる可能性もゼロではありません。
このため、企業にとっては毎月確実に返済していける長期の方が何となく安心という考えになるのです。
長短バランスの悪さで資金繰りは悪化
先ほど述べたように、本来運転資金は短期で融資されるべきものです。
これを長期で借りてしまうと資金繰りは悪化していきます。
長期には毎月の返済が伴うため、長期で借りた運転資金での融資金が手元から枯渇した後は、毎月の返済だけが残ることになります。
こうなってしまうと、借りる前より借りた後の方が毎月の現金の流出が大きくなってしまい、企業の資金繰りは次第に苦しくなります。
短期であれば必要な期間、必要な金額しか借りないため、このような事態は起こりません。
本来短期で借りる運転資金を、長期で借りてしまっている。
これが長短のバランスが悪いという状態になります。
長短バランスを保つために
長短のバランスを保つためには、適切な期間で借入を行うこと、これに尽きるのです。
運転資金とは売上が入金となるまでの短期間に必要な資金ですので長期で借りてしまったらやはり長期的には資金繰りが苦しくなってしまうのです。
運転資金は短期で
先ほどから述べているように、運転資金とは短期的な資金ギャップを埋めるための資金ですので、短期で融資されるべきものです。
経営に大きな問題がない限りは長期で借りてはいけません。
設備資金は長期で
設備投資とは、投資したお金を設備の償却期間内で長期間かけて回収していくものです。
このため、設備資金で借りたお金も、当該設備投資の利益から返済していくものですので、長期資金で借りる必要があります。
設備資金は購入する設備の償却期間内で長期間かけて返済していきましょう。
長期運転資金は2つのケースのみ
長期で運転資金の融資が行われるのは、2つのケースだけであると考えてください。
どちらのケースも支払と入金の時間的なずれである資金ギャップを埋めるための資金ではありません。
資金ギャップを埋めるためには、その期間だけ短期資金で融資を受けるということがやはり原理原則になります。
創業時
創業から間もなくというのは売上は安定しません。
このため、創業時というのは半年から1年分くらいの運転資金を手元に持っていた方がよいと言われています。
本当であればこのような資金は自己資金である方がよいのですが、手元にない場合は創業資金として銀行から融資を受けることが可能です。
また、創業資金の返済に関しては、事業が安定するまでの間、最大1年程度は元金の返済を据え置くという返済方法を選択することも可能です。
赤字の際
会社の売上が何かしらの原因で赤字になった場合、この赤字が慢性的なものでない限りは銀行は融資によって救済してくれます。
この時には短期で借りても返済していくことは難しいため、長期資金で借りることになります。
例えば、リーマンショック時などの一時的に社会的な不況になった場合などは、1年後には売上が回復すると見込んで、1年分の赤字を埋めるための資金を銀行から長期で借りることができます。
例えば、不況によって売上が激減し、毎月50万円の赤字が生じてしまった場合には50万円を短期で借りるのではなく、50万円×12ヶ月=600万円を長期で借りるというような資金繰りを行うことが一般的です。
その後は業況が回復後に長期で返済していくというような計画になります。
まとめ
運転資金は短期、設備資金は長期というのが原則です。
それぞれ返済すべき原資が異なるためです。
運転資金は未入金の売上金から返済すべきものですし、設備資金は毎月設備が生み出す利益から返済すべきものです。
この原則を間違えてしまうと長短のバランスが崩れて会社の資金繰りは悪化します。
銀行は運転資金でも長期資金の借入を勧めてきますが、運転資金を長期で借りるのは創業時と赤字の時だけで、それ以外はいかに銀行が勧めてきても短期で借りた方がよいでしょう。
タグ:その他金融業者







































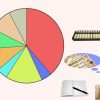














※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。