銀行の儲けは融資だけではない!銀行の儲けの仕組みを徹底解説
銀行はどうやって儲けているのかご存知でしょうか?
「口座を作ってくれ」と銀行は言いますが、口座を作っても我々な何もお金を取られません。
では、なぜ銀行は口座を作ってくれというのか、それは銀行の収益のモデルに影響しています。
この記事は銀行の儲けの仕組みについて徹底解説を行っていきます。
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
銀行の3つの収益源
銀行には大きく分けて3つの収益源があります。
融資だけではなく、銀行が「預金を預けてくれ」とか「口座を作ってくれ」ということには、この3つの収益源が理由になっています。
融資による利息収入
融資によって利息を得るという、銀行にとって最も基本的な収益の方法です。
銀行は預金者から集めた預金を、お金を必要とする人へ貸し出し、社会全体の経済を活性化させるというのが基本的な役目で、これが銀行の本業です。
資産運用
集めた預金を国債などで運用することで収益を得るというのも銀行の収益源です。
融資が伸びずに銀行が本業で儲けることができない場合には、この方法によって銀行はこれまで収益をあげてきましたが、日銀のマイナス金利政策などによって、運用でも収益を上げにくくなっているというのが現状です。
その他
振込などの手数料収入も決して少ない収益ではありません。
また、積立金などの取り崩しなどによって収益を出している銀行もあります。
最近は地方銀行の経営が苦しい苦しいと言われていますが、この方法によって無理やり収益を出して黒字にしている銀行も少なくありません。
銀行の仕入れ
銀行はお金を融資したり、運用したりすることによって収益を得ていると説明しました。
しかし、融資や運用を行うためにはお金が必要です。
このため、銀行にとっての仕入れは「お金を集めること」「お金を調達すること」になります。
預金
銀行の基本的な仕入れの手段は預金です。
銀行は預金者に対して利息を払い、預金を集めて、そのお金を融資などの方法によって運用します。
最近では普通預金の金利は0%ですが、現金を手元に持っているよりも銀行に預けたほうが安心という理由で私たちは銀行に預金をすることが少なくありません。
そのため、最近は仕入先に対して利息を払っていると言うよりも安心や利便性を売っているとも言えるでしょう。
銀行は口座を作ってもらわないことには預金を集めることができないことから、「口座を作ってくれ」と言うのです。
日銀からの借入
銀行は日銀から資金を借りて融資を行うこともあります。
この場合には、日銀へ利息を払わなければならないため、コストがほとんどかからない預金によってお金を預けた方が銀行にとってはコスパが良いことになります。
融資による利息収入
最もポピュラーな銀行の収益源が融資によって利息収入を得るという方法です。
これが銀行の本業ですが、年々銀行は本業によって儲けを得ることが難しくなっています。
銀行の本業による収入
銀行の本業による収入が融資です。
仕入れた預金に利息を上乗せして融資を行います。
預金金利と融資金利の金利差
今や預金金利は0%が当たり前で、預金者も利息収入をあてにしている人はほとんどいません。
融資は預金金利に金利を上乗せして金利を決定しますので、預金金利が0%の現在は、融資の金利もおのずと低くなります。
現在、住宅ローンの金利が1%を切ることが当たり前のようになっていますが、バブル期に住宅ローンを組んだ人は「嘘のように金利が低い」などとよく言います。
20年前は住宅ローンの金利は8%程度というのが一般的でした。
当時は預金の金利が5%程度でしたので、銀行は3%の利ざやを得ることができていましたが、現在は1%弱程度の利ざやしか稼げないことになります。
借りる側にとってはよくても、銀行の儲けはどんどん少なくなっていることが金利1つとっても分かるのではないでしょうか?
本業収入は下がっている
本業の収入である融資による利息収入はどんどん下がっている状況です。
さらに、不景気と企業の内部留保の充実によって、融資量そのものが伸びない状況で、今や地方銀行の半分が本業で赤字と言われています。
そこで、収益力の高い(金利が高い)カードローンの融資を銀行は活発化させており、今や消費者金融よりも多くの金額を融資しています。
しかし、過剰なカードローン融資が社会問題化したため金融庁は銀行のカードローン融資に規制をかけています。
融資量も伸びない、利息も取れないことから、5年先には多くの銀行が生き残れないなどと言われるまで銀行経営は苦しくなっています。
資産運用
集めたお金を運用して収益を得るという方法です。
ただし、銀行は顧客の大切な預金をリスクの高い株式などで運用することはできませんので、運用先は国債か日銀への預金という方法に限られます。
国債購入
銀行は安全な国債を購入して、利息収入を得ることで収益得るという方法でも儲けています。
実際に2011年の銀行全体の国債保有額は150兆円近くにのぼっており、2兆円弱を国債の利回りで稼いだと言われています。
日銀の異次元の金融緩和の影響によって、国債の約4割を日銀が保有するようになったことから、国債運用による銀行の収益も尻窄みとなっているのが現実です。
日銀当座預金に預ける
銀行は顧客からタダ同然で集めた預金を日銀に預けておくことで、日銀から利息を得ることができました。
本業である融資によって運用をしなくても、ただで仕入れたお金を日銀に預けておくだけで利息収入を得ることができていたのです。
本来、企業は無駄な仕入れを行うと、不要な在庫を抱えコストが増大します。
このため、在庫管理の徹底は企業経営の基本中の基本で、在庫管理に頭を悩ましている経営者も少なくありません。
しかし、銀行業務だけは特殊で、預金者からいくら預金を集め不要な在庫を抱えても日銀に預けておくだけで収益を得ることができるという特権的な業種なのです。
ここを問題視した金融庁と日銀がマイナス金利政策を始めたのは記憶に新しいところかと思います。(後述)
マイナス金利の影響
銀行が融資を行う努力をせずに、預金を日銀においておくことで収益を上げている現状を問題視した国は、2016年から日銀当座預金の一部にマイナス金利を導入しました。
これによって、今までは日銀に預けておくだけで利息収入があった銀行は、逆にお金を預けておくと利息を日銀に払わなければならない事態になりました。
つまり、銀行は運用によって儲けることが非常に難しくなったのです。
これによって銀行が本業に本気になり、融資先の開拓や企業の育成を行うことを期待されていますが、現実は融資によっても運用によって収益源を断たれた銀行は今非常に苦しいタイミングに差し掛かっていると言えるでしょう。
その他
そのほかの収益源として、手数料収入や会計上のテクニックによって収益を得るという方法があります。
ここまで述べてきたように、融資や運用によって収益を得ることが難しくなっているため、最近の銀行はこの「その他」の方法によって収益を得ているという側面があります。
手数料収入
振込や出金などの手数料収入も銀行の本業の収入の1つです。
しかし、こちらも最近はフィンテックの登場などによって送金や決済手段が多様化していることから大きな収益は期待できません。
さらに、今後は仮想通貨リップルなどの登場によって国際送金も安価な手数料で行うことができると見込まれることから、銀行の手数料収入はますます厳しくなるでしょう。
会計上のテクニック
本業でも運用でも収益を上げることができない銀行が最近どのようにして収益を上げているかといえば、会計上のテクニックで無理やり黒字にしていることが多くなっています。
具体的に、最近問題視されているのが貸倒引当金の取り崩しです。
貸倒引当金とは、融資先が突然倒産して大きな損失が銀行へ発生しないよう、融資金の一部を費用化して積み立てておくものです。
正常な融資であれば融資金額の5%〜10%の貸倒引当金を計上するのが一般的ですが、リスクが高い融資先に対しては融資金額の50%もの貸倒引当金を計上しなければなりません。
貸倒引当金は融資に対して積み立てを行うものですので、融資金が返ってきたら、貸倒引当金は取り崩します。
リスクの高い融資先に1,000万円の融資を行っていた場合には500万円の貸倒引当金を計上することがあります。
この1,000万円が返済された場合には500万円の貸倒引当金が返ってきますので、500万円は収益になります。
このため、経営が苦しい銀行は収益を得るために無理やりリスクの高い融資先へ貸し剥がしを行い、貸倒引当金と取り崩し益によって収益を得るという事例が最近は珍しくないようです。
◆アスキー公式サイト:「ビジネス:金融庁が地銀の「貸し剥がしで決算“お化粧”」に厳重警告」
まとめ
『絶対に潰れない』と言われてきた銀行という存在も今や昔、銀行は融資、運用、手数料などの収益源がことごとく断たれつつあり、冬の時代を迎えています。
銀行は儲かる業種から儲からない業種となっています。
これまでずっと首位を守ってきた就活生の人気業種ランキングも2018年は4位にまで転落し、内定辞退者の数も急増していると言われています。
銀行はこれまで、銀行だけの収益を考えて、企業を育て地域経済を活性化させるという公共的的指名を忘れてきましたが、今後それができない銀行は生き残れません。
また、金融庁もそのような方針で銀行を指導しています。
今後、生き残る銀行と生き残れない銀行の2つに別れます。
お金を借りるのであれば、将来的に長く取引ができる生き残れる銀行を選択できるよう、自分がお金を借りようとしている銀行の決算状況を確認することも重要なのではないでしょうか?
タグ:その他金融業者


































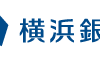












※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。