赤字でも日本政策金融公庫で追加融資は受けられる?
決算書が赤字になっていると、どこからも融資を受けることができないと思っている人は多いと思います。
これは誰しもが持つイメージですが、実は日本政策金融公庫では赤字であっても追加融資を受けることは可能です。
しかし、赤字となっていれば、審査が厳しくなるのは当然のことですので、何の対策もしないで申し込んだとしても融資を受けることはできません。
この記事では、どのような対策を講じると、赤字でも日本政策金融公庫から、追加融資を受けることができるのかを解説していきます。
この記事はこんな人におすすめ
- 赤字で銀行融資が受けられず悩んでいる
- 銀行以外の資金調達方法を知りたい
- 赤字で融資を受ける際のポイントを知りたい
- 執筆者の情報
- 名前:馬沢結愛(30歳)
職歴:平成18年4月より信用金庫勤務
2回目の融資は1回目よりも簡単
日本政策金融公庫から1回目の融資を返済中に、事業の拡大などの理由から2回目の融資が必要となることもあります。
ただし、1回目に融資を受けた時のことを考えると、また多くの書類を提出し、手続きにも時間がかかってしまうのは面倒だと思っている人も多いはずです。
創業期の融資の手続は、初めての起業や融資の申し込みであることも相まって、手続に苦戦した人も多いでしょう。
しかし、日本政策金融公庫で2回目の融資を受ける時は、皆さんが思っているよりも簡単な手続きで借りることができます。
というのも、1回目の融資の時は、日本政策金融公庫に取引先としての情報がない状態で申し込みをします。
会社や事業主の情報がなければ審査のしようがありませんので、それらの情報も含めて日本政策金融公庫に書類を提出しなければならなくなります。
一方、2回目の融資の時は、すでに取引先としての情報がありますので、そういった書類の提出が必要ないため、準備する必要書類が少ないという面では簡単になります。
ただし、確定申告書や財務諸表などは、事業を行うにつれて内容が変更するため、全ての書類が不要になるわけではありません。
また、審査の内容も他の財務諸表などの決算書など、事業実績をもとに行われるため、2回目の方が審査は簡単になるわけではありません。
2回目以降で審査の担当者と仲良くなっているからと言って、簡単に審査通過できるわけではないので気を付けましょう。
赤字でも追加融資は受けられる
近年はアベノミクスの影響もあり、日本経済は年々、上昇傾向にあります。
2016年の中小企業白書によれば、 中小企業の経常利益水準が過去最高を記録したと発表していることからも、これは明白な事実です。
とは言っても、依然、赤字企業が大多数を占めていることには変わりなく、国税庁が2014年に調査した結果では、黒字の法人は全体の33.6%しかなく、残りの66.4%が赤字となっています。
ここで問題となってくるのが資金繰りです。
会社に余剰金等のプールがあれば、当面、赤字をしのぐことはできるでしょうが、そうでなければ早急に資金調達が必要になってきます。
しかし、直近の決算が赤字となれば、金融機関からの借り入れは、当然厳しくなってくるので、慢性的に資金繰りに追われる中小企業経営者ともなれば、どうやって資金調達すればいいのかと頭を悩ませることになるでしょう。
ですが赤字だからという理由だけで、金融機関が融資を突っぱねることはありません。
特に中小企業経営者の資金調達をスムースにすることを、事業理念としている日本政策金融公庫ならば、他の金融機関よりも追加融資を受けられる可能性は高くなってくるでしょう。
追加融資を受けるための絶対条件
しかし、日本政策金融公庫で追加融資を受けるためには、決算書が赤字かどうかよりも大事なことがあります。
それは、延滞することなく返済をしていることです。
延滞をしないことはお金を借りるうえでは当たり前のことですが、赤字企業であれば資金繰りも厳しく、返済ができないところも多いことでしょう。
しかし、延滞は返済能力がないことの証明となるので、延滞をしていないことが追加融資を受けるためにの絶対条件となります。
返済能力なしと判断できるところに、融資してくれる金融機関なんてあるはずはありません。
中小企業の資金調達をスムースにすることを事業理念とする日本政策金融公庫といっても、返済できることが最低限の融資条件となっています。
となれば、赤字でも追加融資可能な日本政策金融公庫でも、融資実行してくれるはずはありませんよね。
昔の事業者は「日本政策金融公庫の返済だけは絶対に遅れない」と言っており、延滞さえしていなければ日本政策金融公庫は支援してくれます。
実際に倒産寸前の企業でも、日本政策金融公庫だけは最後まで支援していたこともありますので、返済はきちんとするように普段から注意するようにしてください。
追加融資は経営改善計画書の出来次第
赤字の状態で日本政策金融公庫に追加融資を申し込む場合には、「経営改善計画書」を提出することになります。
結論から言いますと、この経営改善計画書の出来次第で追加融資を受けることができるかが決まります。
それだけに、経営改善計画書はかなり詳細な内容で根拠のある数値で作成しなければなりません。
改善計画書を作成する際のポイントをまとめると、下記の3つとなります。
- 何が原因で赤字になっているのか(現状分析)
- 今後黒字になっていく見通し(経営戦略)
- 返済していくことができる理由・財源(経営計画)
つまり、この3つにおいて、下記のポイントを説明することになるのです。
- 現状こういう状理由で、経営がくるしくなっています
- しかし、今後はこの戦略を遂行することで、こういった見通しが立ちます
- 具体的にこういった経営計画に基づいて事業展開していこうと考えています
「ですから、そのために追加融資をお願いします。」といった具合です。
これらを日本政策金融公庫に対して、理解してもらうために、十分な説明をしなければなりません。
では、これらポイントについて、それぞれ具体的に解説していくことにしましょう。
何が原因で赤字になっているのか
赤字になる原因はそれぞれの企業によってさまざまな要因があります。
例えば、単純に売上が減少したことによるもの、原材料の仕入れ価格の高騰によるもの、取引先が倒産したことによるものなどがあります。
赤字の原因分析は、経営改善計画書を作成する上で、最初に行わなければならないことであり、経営者自身もきちんと把握していなければなりません。
その理由は明白で、現状分析をしっかりしておかなければ、会社の実態を色濃く反映した、経営改善計画書を作成することができないからです。
現状分析のポイントは下記の6つが挙げられます。
- 創業時から現在までの会社年表を作成する
- 業界において会社がどのような位置づけになっているかを分析
- 過去十年間の実績表を作成し、会社年表と突き合わせる
- 会社の強みと弱み、外部脅威やビジネス機会を多角的に分析する
- 今の状況を引き起こした真の原因を把握し、乗り越えられる可能性を分析
- 現状の経営課題を抽出し、その中で緊急性を要するものを見つけ、改善策を検討
ここがあやふやなものとなれば、日本政策金融公庫を納得させるだけの経営改善計画書を作成することはできません。 経営者だけでなく、スタッフとともに考える必要があるでしょう。
赤字補てん資金ではないことを明確に説明
また日本政策金融公庫だけでなく、一般的に金融機関は赤字補てんのために、追加融資を実行することはありません。
その理由は明快です。
それは赤字補てんのために融資したとしても、その返済原資がないため、回収することができないと判断するからです。
融資によって経営が改善されると確信すれば、その収益によって返済可能となりますが、単なる赤字補てんでは、返済原資を生み出すことはできません。
よって、赤字の会社が追加融資を求めてきた時には、それが赤字補てんのためでないかを慎重に調査します。
そのために必要になってくるのが、経営改善計画書なのです。
決して赤字補てんという後ろ向きなものではなく、経営改善によって売上増加をともなう、前向きなものであることを説明する必要があります。
また赤字が一過性のものでなく、連続した慢性的なものであれば、審査では特に赤字補てんが疑われるでしょう。
この点を踏まえて、そうでないことを納得させるための、経営改善計画書の重要性をよく理解するようにしてください。
今後黒字になっていく見通し
融資をする側にすれば、支援しても黒字にならない企業には貸してはくれません。
よって、経営改善計画書の作成にあたっては、融資を受けることで、「黒字に持っていく状況を作ることができる」という融資の必要性を訴えることが大事です。
その上で、計画書の数値は詳細で根拠のある数値を記載する必要があります。
具体的なポイントを挙げると以下のような内容となります。
- 現実的な売上の推移
- 売上の増加に伴って増加する経費の算出
- 現実的な経費削減内容と効果
これらのうち、売上の推移や経費の削減効果は具体的に作成することができる経営者は多いのですが、売上の増加に伴って増加する経費の算出が甘い人が多いです。
日本政策金融公庫の審査では、むしろこの点を厳しくチェックしていますので、経費に係わる部分はしっかりと時間をかけて考える必要があります。
また、作成に使用した資料は計画書と共に日本政策金融公庫に提出するようにしてください。
根拠となる資料があると計画書の信頼度も高くなります。
返済していくことができる理由・財源
赤字であればどうしても返済能力がないと判断されてしまいますので、それを覆すことができる理由や財源を示す必要があります。
その1つが利益です。
例えば、今後大きな受注がある、数か月後には売掛金が入金される、役員報酬を減額してその分で返済していくなどが挙げられるでしょう。
私も金融機関に勤めていた時は、事業規模に対して役員報酬が多い企業もたくさんありましたので、役員報酬を減額して返済するよう指導したことは何度もあります。
しっかりとした返済財源があれば、日本政策金融公庫としても安心して融資を行うことができるというわけです。
根拠のある資料作りが必須
経営改善計画書は理想や希望ばかりを連ねても説得力がありません。
融資を受けることによって、どのような改善効果が生まれるのかを具体的に説明する必要があります。
その具体性を示すために必要なのが、根拠がある資料作りです。
これは下記の経営改善計画書の定義を見れば明らかでしょう。
会社自社の経営状態を改善する方法について、具体的な数値で計画した書類のこと。
出典:経営改善計画書(日本M&Aセンター)
最低でも下記2つの資料作りは必要になってきます。
- 資金繰り表
- 収支計画表
これまでの実績と今後の資金繰り計画を示す資金繰り表と、今後どのような収支実績が挙げられるかの収支計画表を作成し、改善計画に数値面で具体性を示すのです。
またそれに併せて、日本政策金融公庫では創業資金を借り入れする際に、自己資金の用意や創業計画書の提出が必要になるように、日本政策金融公庫に初めて融資を申し込む際には、下記情報を記入した企業概要書の提出が求められます。
- 企業沿革と経営者の略歴等
- 従業員数
- 資関連企業概要
- 経営者本人の借入状況
- 取り扱っている商品やサービス
特に最後の「取り扱っている商品やサービス」は、会社をアピールする項目となっているので、下記ポイントを添付資料にて詳細に説明することをおすすめします。
- 客単価や受注単価、そして売上の季節変動
- 会社のセールスポイント
- 販売層と販売戦略
- 会社を取り巻く市場環境や競合先
商工会議所や商工会を味方につける
日本政策金融公庫の制度融資の中には「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」という、中小企業経営者におすすめな資金調達方法があります。
商工会議所や商工会で、原則6ヵ月以上の経営指導を受けたところに対し、日本政策金融公庫が無担保・無保証で融資を行う制度です。
経営指導の中でしっかりした経営相談もできるので、赤字による経営改善が必要な企業にもってこいの制度融資と言えるでしょう。
また、マル経融資には東日本大震災や平成28年の熊本地震に関連して、経営改善が必要な小規模企業者が融資を受けられる制度もあります。
申込条件に該当すると、通常の融資額よりも多くの融資額を有利な金利で借りることが可能です。
商工会議所や商工会の影響は非常に強く、推薦を貰うことができれば赤字でも融資を受けられる確率が高くなるので、味方につけて資金調達しやすくしましょう。
マル経融資の内容
そのマル経融資の融資条件は下記の通りです。
| 融資限度額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 返済期間 (うち据置期間) | 運転資金:7年以内(1年以内) 設備資金:10年以内(2年以内) |
| 利 率(年) | 1.21%(特別利率F) |
| 保証人・担保 | 不 要 |
*上記条件は2019年6月現在のものです。
また、融資額限度と返済期間は下記の通り、申込期間が限定されているので、併せて覚えておくようにしてください。
- 融資限度額の取り扱い:2020年3月31日の受付分まで
- 返済期間の取り扱い:2019年3月31日の受付分まで
東日本大震災や平成28年熊本地震に関連した資金の場合には、融資額を別枠で1,000万円多く借りることができ、利率も最大で0.9%優遇されて借りることができます。
しかし、その利率が適用されるのは当初の3年間だけで、4年目以降は通常の特別利率Fの適用となるので注意が必要です。
詳しい融資条件については、下記の日本政策金融公庫HPで確認するようにしてください。
さまざまな情報提供をしてくれる
また中小企業をサポートしてくれるには商工会議所や商工会だけではありません。
商工会議者等では先のマル経融資の他にも、小規模事業者持続化補助金といった経営サポートを盛り込んだ補助金を受けることができますが、中小企業庁でも中小企業の事業者向けに、下記のような経営サポートを行っています。
- 経営革新支援
- 新連携支援
- 再生支援
- 雇用・人材支援
- 取引・官公需支援
- 経営安定支援
- 共済制度
- 小規模企業支援
- ものづくり(サービス含む)中小企業支援
- 技術革新・IT化支援・省エネ対策
- 経営支援体制
- 経営強化法による支援
- 生産性向上特別措置法による支援
上記のように中小企業の抱える問題に応じた経営サポートが用意されており、アドバイス支援だけでなく、下記のようなサポートを行っています。
- 総合支援
- 税制支援
- 補助金
- 助成金
- 資金調達
- 情報提供
- 各種金融支援
必ず各会社に合ったサポートが見つかるので、問題改善を検討しているならば、どのような経営サポートが受けられるのか、検討してみるだけの価値はあります。
興味がある人は下記の中小企業庁HPで確認してみましょう。
参照:経営サポート
公庫が融資したいと思う企業になる
赤字状態での資金調達は企業の存続に係わる重要なことです。
しかし、赤字で融資を受けることがゴールではありません。
最終的に事業を軌道に乗せて、黒字にしなくてはならないからです。
黒字にすることができれば、日本政策金融公庫だけでなく、銀行からも資金調達をしやすくなります。
また、黒字の状態となっていれば、今度は日本政策金融公庫の方から、追加融資の打診が来るようになります。
ここまで来ると日本政策金融公庫での信用は高くなっていますので、審査担当者からの評価も高くなり、簡単に追加融資を受けられるようになるでしょう。
今は赤字かもしれませんが、将来的には自社からではなく、日本政策金融公庫の方から追加融資の連絡が来るような企業へ成長させることを目標にしてください。
そうすることで、会社の存続も図れますし、利益を生み出すことができる体質に、改善することができるでしょう。
日本政策金融公庫は追加融資も積極的
日本政策金融公庫の特徴は、政府系の金融機関だからこそできる低金利な融資を、基本的に無担保・無保証人で受けることができる点です。
そして、銀行ではなかなか融資することが難しい創業資金にも、積極的に融資をしているので、これから事業を営む人にとっても有力な資金調達先である点も見逃せません。
日本政策金融公庫では、新規の借入はもちろんのこと、追加融資にも積極的に融資をしていますので、事業を継続していくうえで長い付き合いとなっている企業も多いです。
しかし、借入していればどんな企業や事業者にも、積極的に追加融資をしているというわけではありません。
追加融資を受けるためには絶対に満たしておかなければならない条件がある他、追加融資を申し込むタイミングも重要となります。
契約後2年~3年が借入のタイミング
事業主の方から、日本政策金融公庫へ追加融資を申し込む場合には、返済が2年~3年程度進んだ時がおすすめな申込タイミングです。
2年から3年くらい確実な返済を継続していると、日本政策金融公庫に対して返済実績を作ることができます。
この返済実績こそが、返済能力があることを示すことになるのです。
この会社なら追加融資しても、遅れることなく、確実にに返済できると信頼されるというわけですね。
また、日本政策金融公庫の方から、追加融資の打診がくるのもこの期間です。
もちろんこれ以上が時間が経過していても、延滞なく返済していれば、追加融資は簡単に受けることができます。
しかし、契約後2年未満は追加融資を申込んでも、審査通過は難しいのが実情です。
これは返済能力の判断材料が揃っていない上、当初の借入時に提出した経営改善計画書の予定通りに、業績が推移していないと判断されることが多いからです。
ただし、取引先の倒産等、予期せぬことが原因であれば、セーフティネットで借り入れできる可能性もあるので、担当者に相談してみることをおすすめします。
借入残高を1/3程度返済した時も借入しやすい
追加融資が受けやすいタイミングは他にもあります。
それは融資残高が1/3程度減った時です。
その理由は返済が進んだ実績と、事業性評価が高くなったことが挙げられます。
日本政策金融公庫で1,200万円の融資を受けたとしましょう。
そのうち400万円を返済して、残高が800万円となると、追加融資を受けやすくなるといった具合です。
また1/3以上、返済が進んでいる場合には、さらに追加融資を受けやすくなります。
逆に残高が1/3まで減っていない場合には、追加融資を受けることは難しくなってくるので注意が必要です。
それでも追加で融資を希望する場合には、資金使途などによっては別枠で融資を受けられる可能性もあるので、こちらも担当者に相談してみるようにしてください。
追加融資は完済後3年以内が望ましい
日本政策金融公庫で最も追加融資が受けやすいタイミングは、完済直後または完済から3年以内です。
借りたお金を延滞することなく完済できたことは、融資側からする優良顧客という評価となり、非常に信用度も高くなります。
よって、この評価が生きている内に、融資を申し込むことで、審査通過確率がグンと高くなってくるのです。
簡単な申込手続きで、追加融資を受けることができるでしょう。
しかし、日本政策金融公庫では完済をしてから3年が経過すると、顧客情報を削除してしまいます。
顧客情報が削除されてしまうと新規申込となるため、前回体験した面倒な申込手続きが必要になるので、この点は覚えておくようにしてください。
本来であれば日本政策金融公庫で借りる場合には多くの書類が必要となります。
これを避けるためには、完済後すぐに資金が必要がなくても、とりあえず借入して優良顧客であり続けるのも1つの手です。
そうしておけば、本当に資金調達が必要となった際にも、日本政策金融公庫が支援してくれます。
信用保証協会を利用して追加融資
借入契約から2年未満である、または借入残高が1/3も減っていないという場合、日本政策金融公庫では追加融資を受けることが難しくなってきます。
その際に検討してもらいたいのが、信用保証協会の保証付融資です。
信用保証協会の保証付融資とは、信用保証協会の保証を受けて銀行から融資を受ける方法で、プロパー融資が受けられない会社でも融資を受けることができます。
また、信用保証協会では、国や地方自治体が実施しているさまざまな制度融資の保証もしているので、ニーズに合った制度融資を利用することができるのも大きな特徴です。
しかし、日本政策金融公庫よりは厳しい審査とは言われますが、追加融資が必要になった際には、ぜひ検討してもらいたい借入方法と言えるでしょう。
利子や保証料の補給が受けられる
また、この信用保証協会と国や地方自治体による生後融資で注目してもらいたいのは、下記の大きなメリットがある点です。
- 借入金利の減率
- 保証料の補てん
支払利息や信用保証協会の保証を受けるために支払う保証料の減額が受けられるのは、利用者にとって大きなメリットとなってくるでしょう。
中には保証料の全額を補給してくれる場合もあるので注目です。
しかし、この補てんは制度融資を提供している国や地方自治体が担っているので、利用する制度融資や、お住まいの地域によって、補てんの有無や割合が異なってきます。
まずは国やお住まいの地域にある地方自治体で、どのような制度融資が提供されているのかを、確認するようにしてください。
まとめ
1期だけの赤字、2期連続赤字など、赤字といってもさまざまな状態があります。
場合によっては債務超過となっている企業もありますが、これまでの返済に延滞がなければ追加融資を受けられる可能性はあります。
しっかりとした経営改善計画書を作成し、審査担当者を納得させれば、融資を受けることもできるでしょう。
もしも自分ではしっかりとした経営改善計画書を作成できない場合には、専門家である税理士や、加入している商工会議所・商工会に相談するのも1つの手です。
そうすれば有益なアドバイスを受けることもできますし、マル経融資を利用して資金調達が行えるかもしれません。
赤字だからといって融資の道が閉ざされたわけではないのです。
今回説明した内容を参考にしてもらい、最善の資金調達の方法を探ってみるようにしてくださいね。
タグ:その他金融業者































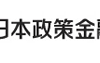













※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。