光熱費の減免制度を集めました!
電気代やガス代、水道代などの光熱費。
電気もガスも水道も、いずれも生きていく上で不可欠なモノです。
本当にお金がないときは料金を支払うことすら難しくなってしまいます。
しかし、条件はあるものの、申請によって光熱費が減免されることがあるのを知っていますか。
国や自治体では経済的に支払が難しい人のために、様々な制度を導入しています。上手く利用すれば、光熱費の支払いに困ることはなくなるでしょう。
今回は光熱費の減免制度を集めました。
利用対象に該当している人はぜひ申請してください。
今回の記事は、以下のような人の役に立ちます。
- 母子家庭や生活保護世帯であり、光熱費の支払いが厳しい
- 光熱費を抑える方法を知りたい
- 光熱費をすぐに工面する方法が気になる
「どうしても支払いが難しい」という場合は、消費者金融カードローンの利用を検討しましょう。
5万円をカードローン最大金利年18.0%で30日間借りた場合、利息は750円以下。さらに無利息サービスがあるカードローンを利用すれば、一定期間利息はかからず、一括返済できれば利息は0円です(SMBCモビットは無利息期間なし)。
以下に今すぐ申し込めるカードローンをまとめたので、まずは公式サイトを確認してみてください。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
生活保護者が利用できる光熱費減免制度
生活保護受給者は、居住する地域に関係なく医療費や国民年金保険料の支払いの免除が受けられます。
しかし、光熱費の減免は自治体によって大きく制度が異なります。
中には補助金の中に母子加算としてすでに含まれており、適用されない場合も。まずはお住いの福祉事務所に相談してみましょう。
光熱費減免制度なしの自治体が多い
基本的には生活保護世帯であっても、光熱費が減免になることはほとんどありません。
減免措置を実施していない地域では、生活保護費の金額にすでに光熱費の料金が含まれているとしています。
そのため生活保護費とは別個に光熱費の補助を行うことは「二重給付」に該当する可能性があるのです。
つまり、生活保護受給を理由に、光熱費の支払い拒否はできません。
水道代をはじめとした公共料金を支払わない場合、しかるべき処罰を受けることになります。
水道料金の基本料金のみ免除する自治体もある
基本的に光熱費の減免は行っていませんが、一部自治体では水道料や下水道代の減免することで支援を行っているところもあります。
全ての自治体が行っているわけではなく、例えば神奈川では生活保護費に含まれていると判断し、廃止されています。
くわしくはお住いの水道局のホームページをチェックするか、直接問い合わせて見て下さい。
生活保護受給者を対象とした水道料金減免は、例えば大阪府枚方市のように、水道使用量に関わらず基本料金のみ免除となるケースが多いです。
また東京都では下水道料金も減免しています。
◆枚方市公式サイト:「水道料金・下水道使用料の基本料金の減免について」
低所得世帯が利用できる光熱費減免制度
生活保護の受給有無に関わらず、世帯所得が一定額以下の場合は光熱費減免制度が利用できる自治体もあります。
ただし、この減免制度も、生活保護者への減免制度と同じく「水道料金」のみとなっています。
例えば、東大阪市では以下の基準を満たす世帯なら、基本水量に対する最低料金の半額と下水道料金の全額が免除されます。
| 世帯人数 | 前々年度の所得合計額 |
|---|---|
| 1人 | 1,250,000円 |
| 2人 | 1,580,000円 |
| 1人増えるごとに | 330,000円加算 |
◆東大阪市公式サイト:「水道料金及び下水道使用料の減免制度に関して」
母子家庭世帯・父子家庭世帯の光熱費減免
母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯も、光熱費減免制度の対象となる自治体は多くあります。
ただし、すべてのひとり親世帯が減免対象になるのではありません。
多くの自治体では児童扶養手当を受給している場合に限り減免措置(基本料金のみの免除であることが多い)を受けられる地域が大半です。
以下はヤフー知恵袋に実際に投稿されていた口コミです。
私のところにもありません。
都内だと区によってすごく優遇されるところもあるらしいですね。
我が家は、半分お風呂は実家で入れさせてもらっていますが、
ほぼ毎日洗濯していて2か月分で5000円弱です。
家族がバラバラに毎日入るようなったら幾らになるのか・・・
恐ろしくて考えたくありませんΣ(T▽T;) ぐわわぁぁ~ん!
児童扶養手当を受給するためには以下の基準を満たさなくてはなりません。
低所得かつひとり親の場合だけ利用できると言い換えることもできます。
| 扶養親族の人数 | 全部支給の所得上限額 | 一部支給の所得上限額 |
|---|---|---|
| 0人 | 19万円 | 192万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 |
※離別した子の親から受け取る養育費は、その80%を所得として加算します。
障害者世帯が利用できる光熱費減免制度
障害者世帯を対象にして、水道料金の減免制度を実施している自治体は多くあります。
免除は等級によって決まり、身体障害の場合は1等~2等級、精神障害では1等級となっている自治体がほとんどです。
等級は障害者手帳で確認できます。
自治体によって違いがあるため、管轄の水道営業所に問い合わせるのが確実です。
こちらも、ひとり親世帯を対象とした減免制度と同じく、基本料金のみ免除されることが一般的です。
災害による被害を受けたときも減免対象に
東京都が、東日本大震災で被災し、避難中の住民に対し水道料金と下水道料金の減免を行っています。
もともとは平成31年3月31日の属する月分まででしたが、平成32年3月31日までに延長されています。
【お知らせ】東日本大震災による避難者の方で、東京都内に避難し居住している方及び避難者の方が同居している世帯を対象に水道料金及び下水道料金の減免措置期間を延長することとしました。詳しくはホームページをご覧ください。 https://t.co/ksxFzqZZGl
— 東京都水道局 (@tocho_suido) March 29, 2019
東京都以外でも、災害によって被害を受けた人を対象に水道料金の減免措置を実施していることもあります。
特定の災害に限定して減免措置が受けられたり、避難所生活をしている場合に限り減免対象に災害の被害に遭った人はお住まいの地域の水道局に問い合わせてて下さい。
電気代とガス代の減免制度はない
一定の条件を満たすと、水道料金の減免措置を受けられることがあります。
しかし、電気代とガス代は地域に関係なく減免措置は実施していません。
これは、水道は「水道局」という自治体の組織が管轄していることが一般的ですが、電気やガスは「民間会社」が管轄していることが多いためです。
民間の場合は、経営ありきとなっているため、簡単に減免は難しいのだと考えられます。
また近年では電力の自由化が進み、各会社ごとに考えが異なる面からも、減免は難しいでしょう。
現在、水道は民営化の動きが出ています。
もし民営化された場合は、減免措置は廃止されてしまうかもしれませんね。
因みに水道が民営化されたら、自治体によって設定されてる生活保護受給者・低所得者等への水道料金一部減免制度も多分なくなるよ。
貧困支援団体はもう少しまともに団結してその辺騒いだ方がいいと思うけどね。#生活保護 #貧困 #水道民営化反対— 尾野里梨@毎日が自由研究 (@onosatori) November 26, 2018
なお、電気代やガス代を滞納したときに起こり得る事柄に関しては、次の記事でまとめています。
母子家庭の平均収入はどのくらい?
離婚をすると親権が母親になることが多いですが、母子家庭は平均的にどの程度生活費がかかるのでしょうか。
ここでは母子家庭の平均収入について見ていきましょう。
母子家庭の平均収入とは
一口に「母子家庭」といっても、こどもの数により生活スタイルは異なります。
そのため今回はこどもの人数を元に、おおよその平均収入を見ていきましょう。
なお養育費は養育費算定表(夫の収入が450万円で仮定)で計算しています。
母親と小学生ひとりの場合
| 給料 | 150,000円 |
|---|---|
| 児童手当 | 10,000円 |
| 児童扶養手当 | 17,000円ほど (前年度の収入により異なります) |
| 養育費 | 30,000円 |
| 合計 | 197,000円 |
ここから必要な生活費も見ていきます。
| 家賃 | 50,000円 |
|---|---|
| 光熱費 | 12,000円 |
| 通信費 | 8,000円 (キッズ携帯も含む) |
| 食費 | 30,000円 |
| 日用品 | 3,000円 |
| 生命保険料 | 3,000円 (掛け捨て) |
| ガソリン代 | 13,000円 |
| 給食費 | 4,500円 |
| 化粧品や美容代など | 3,000円 |
| 衣料費 | 6,000円 |
| 交際費やレジャー | 10,000円 |
| こどもの習い事 | 10,000円 |
| 合計 | 152,500円 |
他にも臨時的な出費として、冠婚葬祭や車検、車のタイヤ代、PTA会費と出費はかさみます。
特に田舎の場合、車の維持費が家計を圧迫することもあるでしょう。
母親と小学生ふたりの場合
| 給料 | 150,000円 |
|---|---|
| 児童手当 | 20,000円 |
| 児童扶養手当 | 34,000円ほど (前年度の収入により異なります) |
| 養育費 | 50,000円 |
| 合計 | 254,000円 |
ここから必要な生活費も見ていきます。
| 家賃 | 60,000円 |
|---|---|
| 光熱費 | 15,000円 |
| 通信費 | 12,000円 (キッズ携帯も含む) |
| 食費 | 40,000円 |
| 日用品 | 5,000円 |
| 生命保険料 | 3,000円 (掛け捨て) |
| ガソリン代 | 13,000円 |
| 給食費 | 9,000円 |
| 化粧品や美容代など | 3,000円 |
| 衣料費 | 10,000円 |
| 交際費やレジャー | 20,000円 |
| こどもの習い事 | 20,000円 |
| 合計 | 210,000円 |
こどもが増えた分手当も増えますが、その代わり光熱費や食費、通信費などが大幅にアップします。
給食費や習い事は倍になります。
他にも臨時出費に備える必要があるでしょう。
母親と小学生3人の場合
| 給料 | 150,000円 |
|---|---|
| 児童手当 | 30,000円 |
| 児童扶養手当 | 51,000円ほど (前年度の収入により異なります) |
| 養育費 | 80,000円 |
| 合計 | 311,000円 |
ここから必要な生活費も見ていきます。
| 家賃 | 80,000円 |
|---|---|
| 光熱費 | 25,000円 |
| 通信費 | 20,000円 (キッズ携帯も含む) |
| 食費 | 70,000円 |
| 日用品 | 10,000円 |
| 生命保険料 | 3,000円 (掛け捨て) |
| ガソリン代 | 13,000円 |
| 給食費 | 13,500円 |
| 化粧品や美容代など | 3,000円 |
| 衣料費 | 13,000円 |
| 交際費やレジャー | 30,000円 |
| こどもの習い事 | 30,000円 |
| 合計 | 310,500円 |
こども3人ともなると、一番上の子は高学年になっており食べ盛りです。
そのため食費が大幅にアップしています。
家もある程度の広さが必要と仮定し、上記のようにしました。
もし養育費を貰っていない場合、困窮する恐れがあるほどギリギリの生活です。
母子家庭になった理由別の平均収入
母子家庭になった理由によっても、収入は大きく異なります。
ここからは、理由別の収入もみていきましょう。
●離婚
母子家庭になった理由でもっとも多く、厚生労働省が平成28年に発表した「ひとり親家庭の現状」によると、全体の80%を占めています。
母子家庭の母親の平均収入は181万円であり、半数以上が非正規で働いているのが現状です。
●死別
平成23年の時点で死別により母子家庭となった割合は7.5%でした。
離婚と比べると、10分の1以下であることがわかります。
死別の場合の平均収入は256万円です。
夫が死亡した場合、遺族年金や生命保険が入ることも多いため、離婚よりは比較的生活は安定することが多いでしょう。
●未婚の母
未婚の母は全体の7.8%で、死別をほぼ同じ割合です。
未婚の母は年収が160万程度と、他の理由に比べて低いのが特徴です。
これは未婚の母は比較的若い母親が多く、十分な仕事をもたずに出産してしまうことが多いためと考えられます。
上記を踏まえると、母子家庭の収入はとても低いことがわかります。
養育費がもらえない場合は、もっと厳しくなるでしょう。
母子家庭の場合知っておきたい節約術
シングルマザーの生活は大変です。
しかし、やりくりの方法によっては、少ないお金でも十分な暮らしができます。
ここでは試して頂きた節約術をご紹介します。
給料が入ったら利用理由ごとに袋分け
生活費は袋分けして管理するのがおすすめです。
給料が入ったら、生活費を銀行から引き出します。
そのままだと何をどこに使ったかわからなくなってしまうことも。
そのため、項目ごとに袋分けし、支出の管理を行いましょう。
項目は主に以下のようなものがあります。
|
|
各項目ごとにあらかじめ予算を決め、ジップロックや茶封筒に仕分けておきます。
袋に入ってい入る金額内でやりくりをすれば、無駄な費用を使うこともありません。
もちろん貯蓄用の口座を作っておき、余った分は口座に戻し、貯蓄にします。
少しでも貯めておくと、いざという時の出費にも慌てません。
クレジットカードでポイントを稼ぐ
クレジットカードを使う=借金というイメージがあるかもしれません。
しかしクレジットカードは計画的に使えば、非常にお得なのです。
クレジットカードは利用履歴に合わせてポイントが貯まります。
貯めたポイントは支払いに充てたり、商品券や豪華賞品に変えることだってできるのです。
支払いをひとつのカードにまとめればポイントも効率よく貯まります。
公共料金や家賃など、月の決まった支払いをカード決済にするだけでも、かなりのポイントが入ってきますよ。
家計簿をつけて無駄を見つけ出す
お金を管理するには、収入と支出を客観的に見直すことが大切です。
家計簿をつけて毎月お金の動きを把握しましょう。
そうすると必要のない出費が見えてきます。
もし家計簿を手書きでつけるのが面倒だと思ったら、家計簿アプリを使ってみるのもおすすめ。
入力をグラフ表示してくれるため、支出の状況が一目瞭然です。
光熱費を少しでもすくなする方法
母子家庭の場合、水道料金が減免される制度がありますが、電気やガスにありません。
そのため少しでも光熱費を抑えたいですよね。
ここでは光熱費を少しでも節約する方法をご紹介します。
お風呂の水は少なめに
半身浴は、体をじんわりと温め、発汗作用もあるため体によい効果が期待できます。
そのためお風呂のお湯は半分でも十分です。
少なめに沸かし、沸いたらすぐに入りましょう。
保温や追い炊きはガスや電気がかかるため、お風呂は早めに入ってしまうのがおすすめです。
また水を満たしたペットボトルを沈め、お湯をかさましするのもよいでしょう。
電力会社の割引を上手に使う
家が東京電力の場合、「でんきの家計簿」で電気の消費量をチェックしてみましょう。
でんきの家計簿では、毎月の使用料や金額はもちろん、使用状況に応じた電力プランも提案してもらえる便利なサービスです。
また電力会社によっては、時間帯によって消費電力が安くなるプランを用意しています。
もしお母さんは昼間仕事、こどもは学校などほとんど家にいない場合は、時間割引のサービスを検討してもよいでしょう。
自炊して食費を低く抑える
普段時間がなく、スーパーの総菜や外食で済ませてはいませんか。
外食は基本的にコストがかかります。
そのためなるべく自炊を心がけましょう。
たとえば、毎日の昼食を外食からお弁当に変えるだけでも月に数万円程度の差が出てきます。
可能な限り自炊をすることで食費を抑えましょう。
1週間の献立をメモして大量買いをする
自炊をしていても、何度もスーパーへ行っていては、無駄なものまで買ってしまいます。
そのため1週間ごとに献立を作り、まとめ買いをするのがおすすめです。
肉や魚は冷凍しておけば日持ちしますし、野菜を下ごしらえし、冷凍してしまうのもおすすめ。
また特売日やポイントが倍になる日にまとめ買いをすれば、さらにお得に買い物ができます。
もちろん買い物に行く日は決めておき、買いだめを行ったら次回まで買い物には一切いきません。
安売りや割引タイムなどを把握する
食費を抑えるためには、食材を安く買うのは必須です。
そのため周辺スーパーが安売りをしている時間帯や、割引が行われる時間帯を把握しておきましょう。
例えば、スーパーの感謝デーを調べる、値引きシールが貼られる時間帯をチェックするなどが挙げられます。
地味な作業ではありますが、月に数千円~数万円程度は差が出てくるでしょう。
母子家庭が利用したい公的扶助や手当
母子家庭の場合、利用できる公的扶助や手当がたくさんあります。
ここでは特にチェックしておきたい補助金についてまとめました。
申請しなければ受けられないものも多いので、該当していると思ったら役所などに聞いてみてくださいね。
遺族年金
大黒柱がなくなってしまった場合、今後の生活が脅かされる恐れがあります。
そんな時、残された家族が一定の基準を満たす場合に、支給されるお金です。
受給資格
|
「子」とは18歳未満の子をいい、高校卒業まで受け取れます。
こどもに障害がある場合は、その子が20歳になるまでです。
こどもの人数によって支給額は異なります。
児童手当
中学生以下のこどもがいる家庭に支給される金額です。支給対象は母子家庭に限りません。
| 子供の年齢 | 月額 (1人あたりの金額) |
|---|---|
| 3歳以下 | 15,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
一定の所得を超えた場合は、一律5,000円で制度を使わないと手当は受けられません。
必ず申請を行いましょう。
くわしくは市役所のこども課などにお問い合わせください。
児童扶養手当
両親の離婚などで母子家庭となってしまった場合に、こどもの成長を支援するために支給されるお金です。
●支給対象
18歳までのこども(障害がある場合は20歳)
支給額は所得やこどもの数によって違います。
保育料の減免
保育料は収入によって決定されます。
そのため一定の収入に満たない母子家庭は減免の対象になります。
2019年10月より保育無償化が施行されましたが、住民税非課税世帯は0歳児から無償になります。
母子家庭の人も経済状況によっては当てはまるかもしれませんので、一度確認してみてください。
児童育成手当
離婚や死亡、教育放棄などで両親のどちらかがいないこどもに支給されます。
他の手当てを違うところは、親でなくとも養育している保護者であれば支給されることです。
支給額は市区町村によって違いはありますが、おおよそ13,000円ほどとなります。
また所得制限があるため注意が必要です。
特別児童扶養手当
精神もしくは体に障害のあるこどもに支給されるお金です。
こどもが満20歳未満であれば、養育をしている父母などに支給されます。
受給者や父母の所得が一定金額を超えている場合は、支給されません。
ひとり親家庭の住宅手当
母子家庭で毎月の賃料が10,000円以上である場合に、超えた分を一部支給する制度です。
支給条件
|
支給額は市区町村によって異なりますが、上限が決まっておりおおよそ15,000円程度です。
また生活保護を受けている世帯は利用できません。
ひとり親家族の医療費助成制度
両親の離婚や死別により母子家庭となった場合に、保険証を使って医療機関を受診した際、医療費の一部が援助される制度です。
補助額は所得によって違ってきますので、詳しくは市役所に確認するのが確実です。
また以下の人は利用できません。
|
|
国民年金・国民健康保険の免除
収入の減少や失業などで年金や国民健康保険料を納めるのが難しい場合、一部もしくは全額免除が受けられます。
免除金額については審査によって決定しますので、一概にはいえません。また10年以内であれば、追納も可能です。
交通機関の割引
児童扶養手当や生活保護を受けている場合、交通機関を割引価格で利用できます。
例えば東京の場合は以下の通りです。
●JR通勤定期券の割引
通勤にJRを使っている場合、定期券が3割引きで購入できます。
●都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーなど一部を除く)の無料乗車券がもらえます。
減免制度が利用できない人はどうやって払う?
お住まいの自治体に光熱費の減免制度があったとしても、利用できるのは「生活保護世帯」や「低所得世帯」「ひとり親世帯」「障害者世帯」「被災者世帯」に限定されます。
どの世帯にも該当しない場合、あるいはこれらの世帯に該当しているけれどもお住まいの自治体では減免制度を実施していない場合は、次の方法で光熱費を支払いましょう。
収入を増やして光熱費を払う
ガス代・電気代・水道代を全部合わせても、一般的な家庭なら使い過ぎ内限り2万円~3万円もあれば十分でしょう。
週末にアルバイトをしたり副業をしたりすることで、毎月の収入を2~3万円増やしてみるのはいかがでしょうか。
無理なく月収を2万円アップさせる方法を次の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
■月15万円,20万円稼ぐ、作る方法【ネット副業の体験レポあり】
不要品を売って光熱費を払う
どの家庭でも不要品はあります。
手元の不用品は、誰かにとって必要なものかもしれません。
そのため使っていないモノを売って、お金に換えるのはいかがでしょうか。
今ではフリマサイトやオークションなどで簡単に出品ができます。
処分する前に売り出してみると、思わぬ臨時収入になるかも。
ただし、家にあるモノは限られていますので、不要品を売って光熱費を稼ぐのは数ヶ月が限界だと考えられます。
また、ネットで売る場合はすぐに売れるとは限らないので、即金を望むならリサイクルショップがおすすめです。
家のゴミがお宝に!?意外と高く売れるものについては、以下のページを参考にしてください。
生活福祉資金貸付制度を利用する
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に該当すれば、お住まいの地域に関係なく「生活福祉資金貸付制度」を利用できます。
「生活福祉資金貸付制度」では資金を年利0~1.5%の超低金利で借りられます。
該当しそうな人は、近くの福祉協議会事務所にでかけて相談してみましょう。
民間の金融機関で借りる
生活福祉資金貸付制度が利用できない場合は、銀行や消費者金融などの民間金融機関のカードローン等を活用して、光熱費を一時的に借りるのはいかがでしょうか。
ただし公的貸付制度と比べると金利が高く設定されていますので、最小限のお金だけを借りて、最速で返済するようにしてくださいね。
カード会社によっては契約から一定期間は無利息のキャンペーンを行っています。
短期間の借り入れであれば、うまく利用してみましょう。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
養育費をあきらめないで!
母子家庭で父親がいる場合、養育費がもらえます。
しかし正しく請求しないと、せっかくの権利を活かせないかもしれません。
ここでは養育費の貰い方についても詳しく解説します。
離婚した場合のもらい方
離婚の場合は、離婚前か離婚後に相手に電話などで支払ってもらえるように請求しましょう。
もし支払いの意思を見せない場合は、裁判所に「養育費調停」を申し立てたほうが早いです。
また離婚に強い弁護士も探しておきましょう。
養育費調停では家庭裁判所で、相手も含めて話し合いの場を設けます。
調停委員が間に入り、相手の説得も行ってくれますので、話がスムーズに進みやすいです。
それでも話がまとまらなければ、「審判」に進み、裁判所に支払うよう命令を下してもらうこともできます。
未婚の場合のもらい方
未婚のまま出産をし、シングルマザーとなった場合、まずは相手に「認知」をさせ自分のこどもであることを認識させなければなりません。
相手が認知に応じない場合は、「認知調停」に進みます。
認知調停で相手が納得すればよいですが、頑なに拒否する場合はさらに「認知訴訟」を起こし、争う必要があるのです。
認知訴訟ではDNA鑑定を行い、父子関係を確定します。そのうえで認知させ、養育費を請求します。
相手が頑なに支払いを拒む場合は、「養育費調停」へと進み、家庭裁判所で争うことになります。
まずは水道局に問い合わせよう!
光熱費の減免措置は、水道料金に限って可能です。
お住まいの自治体でどのような減免制度を実施しているかお知りになりたい人は、水道メーターの検針票に記載されている水道局の電話番号に問い合わせてみましょう。
条件が合えば、月々の水道料金が安くなるかもしれませんよ。
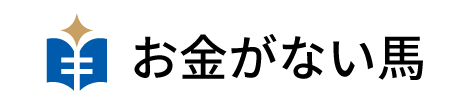























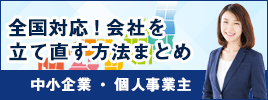

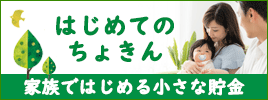


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。