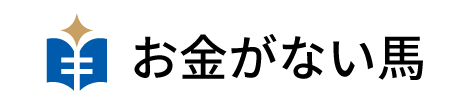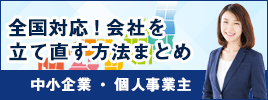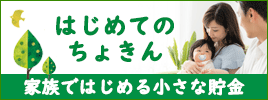マイナンバーで滞納がバレる?住民税・保険料・年金、奨学金は?
2015年から始まったマイナンバー制度。
税金や社会保障といった行政関係の情報や所得情報などを、個人ごとに割り当てられた番号紐付け、管理しようという試みです。
2018年からは銀行口座への紐付けも開始される予定です。
行政の効率化や社会保障の充実を目的にマイナンバーが導入されましたが、一方で税金の滞納がバレやすくなるという声も。
どういうことなのか、解説していきたいと思います。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
マイナンバーで税金滞納がバレる?
マイナンバー制度導入の目的の一つに、「公平・公正な社会の実現」というものがあります。
所得に関する情報と、税制や社会保障を結びつけることで、それぞれの所得状況に合った行政サービスを受けさせるとともに、不当な負担な免れを防ぐというものです。
低所得の人には、税金を下げたり、生活保護などの社会保障を提供してあげないといけません。
そのためには所得状況と、税金をどう支払っているのか、社会保障はしっかり受けられているのかのを把握する必要があります。
こうして、保険や税金の支払い状況に関してマイナンバーで紐付けられることになりました。
以前はバラバラだったものが、「マイナンバー」の一つで管理できるようになり、管理がしやすくなりました。
そのため、マイナンバーで支払状況を見れば、どの税金をどれくらい滞納しているかが一目でわかってしまいます。
「マイナンバー制度で滞納がバレる」というのは、こういうことを言っているのです。
実際の取り立て強化までは言えない
とはいえ、実際に取り立てが厳しくなるのかどうかはわかりません。
ないものから取り立てるわけにもいきませんし、そもそもの傾向として、近年の税金の取り立ては厳し目です。
マイナンバーの導入によって管理されやすくなったことは事実です。
ですが、それが直接の原因となって、取り立てが強まるかどうかまではわからない、と言えるでしょう。
マイナンバー制度の利点
このようなマイナンバー制度ですが、他にもどんなメリットがあるのでしょうか。
また、導入によるデメリットはないのでしょうか。
マイナンバー制度のメリット
メリットとしては、個人情報のやりとりの手間が省けることです。
それにより、人件費などのコスト削減や人的なミスを防ぐことができます。
2007年、国民年金の情報漏えいが大きな問題となりましたが、これは人的な情報管理によるミスが原因とされています。
それまでマイナンバー制度の導入については検討されてきましたが、この問題が起こったことで、本格的に導入に向けて動き出した、という背景があります。
マイナンバー制度のデメリット
デメリットとしてあげられるのは、個人のプライバシーに関わる情報ですので、漏えい時のダメージが大きいということです。
マイナンバーをハッキングされて中の情報を見られようものなら、以下の様な重大情報が漏えいしてしまいます。
- 名前、住所、電話番号
- 勤務先、学校名
- 通院歴、投薬歴
- 税金の納付状況 など
そのため、国はマイナンバーの情報管理を徹底しています。
税金滞納が会社にバレる?
これまでマイナンバー制度の導入により、税金の滞納が「国」にバレるかどうかについて解説しました。
次は、「会社」にバレるかどうかについて見てみましょう。
マイナンバーを会社やアルバイト先に提出したと思いますが、もし自分が税金を滞納してしまった場合、会社にその情報は伝わってしまうのでしょうか。
結論から言うと、会社に伝わることはありません。
マイナンバーは「国」が個人の情報を管理・特定するための番号です。
会社がマイナンバーを使って個人情報を見ることはできないようになっていますので、安心してください。
滞納が会社にバレる場合
税金や滞納したことが会社にバレるケースとしては、差し押さえになった場合が考えられます。
差し押さえになると、給料も差し押さえ対象に入り、対象者の財産を調べる財産調査の対象になります。
その場合、財産調査をしたいという旨が会社に伝わり、それでバレてしまいます。
借金の滞納なら個人再生で会社にバレる
個人再生とは、債務整理の一種です。
借金が何百万と積もりに積もって返済できなくなったとき、裁判所の力を借りて、借金をいくらか減額し、残りを分割で払っていく債務整理です。
個人再生には様々な書類の用意が必要ですが、その際に退職金見込額証明書の発行が必要になり、その事由を述べる際に会社にバレてしまいます。
また、会社から借入がある人も、借金を減らしてもらう際に個人再生をする旨が伝わります。
税金・借金の滞納が理由でクビになる?
もし滞納が会社にバレてしまった場合、最も怖いのは、それが理由でクビになってしまうのかということでしょう。
しかし、それは解雇権の濫用に当たりますので、クビになることはありません。ご安心下さい。
奨学金滞納も厳格化?
奨学金におけるマイナンバー導入が平成29年から開始されました。
それに伴い、「所得関連返済」というものが利用できるようになりました。
それまで奨学金の毎年の返済額は、所得額に関わらず一定でした。
所得額に関わらず一定というのは、低所得の人であればあるほど負担は大きくなるということです。
これを改善し、所得に応じて毎年の返済額が変わる返済の仕組みが「所得関連返済」です。
これも所得情報と奨学金の情報が紐付けられるマイナンバーがあって実現できたことの一つです。
同時に徴収強化説も
同時に、税金同様、滞納状況が管理しやすくなるという面もあります。
平成27年度末の時点で、164,635人の人が滞納しています。
年々減ってきているものの、奨学金の返済に苦労している人はまだまだ多いというのが現状です。
その人達からの徴収を強化するため、と言えなくもないですが、実際に取り立てが厳しくなるのかについては、導入されたばかりというのもあり、まだわかりません。
まとめ
マイナンバーの導入による税金や奨学金の滞納について見てきました。
納付状況の管理はされやすくなり、強化されることが考えられますが、実際に取り立てが厳しくなるのかはわかりません。
マイナンバー導入以前からのそもそもの傾向として徴収は強化されていますし、お金がない人から無理に取り立てるわけにもいきません。
とはいえ、納税は国民の義務ですし、奨学金も借りたお金はきちんと返さなくてはいけません。
税金は役所に行けば、分割の相談にも応じてもらえますし、所得に応じて減額・免除の申請もできます。