【何もしたくない】お金がない時に無気力になる5つの理由~うつ病かも~
お金がないのに元気はつらつという人は、あまりいません。
基本、お金がないと無気力になってしまいますよね。
では、なぜお金がないと無気力になってしまうのでしょうか。
貧乏が無気力を呼ぶ理由と解決策を見ていきましょう。
「今すぐお金が欲しい」という場合は、消費者金融カードローンがおすすめです。
5万円をカードローン最大金利年18.0%で30日間借りた場合、利息は750円以下。さらに大手カードローンには無利息期間が存在するため、一定期間であれば利息0円で利用できます(SMBCモビットは無利息期間なし)。
以下公式サイトをよく確認して申し込みましょう。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
- 1 何もしたくないと思う原因は?
- 2 何もしたくない日におすすめの過ごしかた
- 3 どうしても働かなければいけない時の対処法10選
- 4 無気力のときにしてはいけないこと
- 5 無気力に陥りやすい人の特徴
- 6 無気力状態から脱出する5つの方法
- 7 お金がないと無気力になる5つの理由
- 8 何もしたくないことが多いのは普通?
- 9 もしかして鬱病?病院に行く前に
- 10 うつ病になると金欠になる場合がある
- 11 うつ病で休職するメリットは?
- 12 うつ病で休職するデメリット
- 13 うつ病で休職する方法は?
- 14 休職した後にするべきことは?
- 15 うつ病になってお金に困らないための公的支援
- 16 うつ病でお金を借りる方法
- 17 うつ病になると金欠になりやすい理由は?
- 18 日本のうつ病の現状
- 19 うつ病で生活費が足らなくなる理由
- 20 債務整理は難しい?
- 21 できることからコツコツと始めよう
- 22 無気力と貧乏は表裏一体
- 23 無気力に関するよくある質問
何もしたくないと思う原因は?
無気力で何もしたくないと思ってしまうことは、誰にだってあります。
そんな風に思ってしまうのは、主に以下のような原因があると考えられます。
疲労がたまっている
我々は毎日仕事や家事など、いろいろな労働・作業をしながら生活しています。
そんな労働や作業を繰り返していると、自然と体に疲労が溜まっていってしまうものです。
疲労が溜まると何をするにも億劫になってしまいますから、本来やらなければならない仕事などに手が付かなくなっても、何らおかしくありません。
特に年齢を重ねると、なかなか疲労が抜けにくくなりますから、常に慢性的に疲れているような状態になってしまいます。
疲れが溜まっているなぁと感じるかたは、まずは体のケアをすることが先決かもしれません。
ストレスがたまっている
疲労が溜まると何も手につかなくなってしまいがちですが、同じことはストレスにも言えます。
現代はストレス社会と言われるだけあって、仕事にしろ私生活にしろ、何かしらどこかしらでストレスを感じている人が大半です。
寝てしまえばストレスがきれいさっぱりなくなるような人もいますが、そうではない人は日々ストレスが少しずつ蓄積されていき、仕事や作業の邪魔をするような状態にまで達してしまっているかもしれません。
溜まった疲れに対処するのと同様に、ストレスに関しても何らかの手段で発散させてあげる必要があります。
作業自体に飽きている
仕事は職種が決まっている限り、行わなければならない作業は自ずと決まってきますし、家事も毎日同じようなことの繰り返しが大半です。
そのため、行わなければならない作業自体に飽きてしまって、無気力になってしまうこともあるでしょう。
自分の好きな曲を流して気分を高揚させながら家事を行ったり、普段のルーティンとは異なる順番で仕事を行うことで脳に刺激を与えたりといった工夫を行うことで、少しでも「飽き」から逃れられるかもしれません。
目の前の作業をそもそもやりたくないと感じている
人は、物事に対して興味を抱いたり関心を持っていたりすると、そのことに対する作業を行うのが苦にならないものです。
しかし逆に、特に興味も関心もなく、そもそもやりたくないと感じている作業の場合は、無気力になってしまう度合いが高まります。
人は誰もが、自分がやりたいと思ったことのみをして生きているわけではなく、生活していくために気乗りのしないことやいやなことをしている人が大半です。
そんな状況であれば、無気力になってしまうのも、ある程度は致し方ないと言えるのかもしれません。
何もしたくない日におすすめの過ごしかた
無気力で何もしたくない日に無理に作業をしようと思っても、そもそもあまり集中できていないため、作業効率が著しく悪くなってしまいます。
何もしたくない日のおすすめの過ごしかたについて、説明します。
一番大事なのは自分を責めないこと
一番大事なことは、「何もできないでいる自分を責めないこと」です。
責任感の強い人であれば、「何もできないでいるなんて自分は何て情けないんだ…」と自責の念を感じてしまってもおかしくありません。
ただ、自分を責めてしまうと、さらなるストレスや自己否定につながってしまい、状況が悪化することこそあれ、状況が改善されることは決してありません。
責任感を持つことは重要ですが、無気力で何もできないときは誰にでもあると、割り切るぐらいの気持ちが重要です。
何もしないことを認める
「何もしないこと」は悪いことのように思われがちですが、決してそんなことはありません。
機械だって車だって家具だって、ずっと休みなしで使われていればどんどん劣化していってしまいますので、定期的なメンテナンスが必要になります。
人間の体も同じで、毎日毎日働き続けていれば、疲労やストレスで普段通りのパフォーマンスを発揮できなくなってしまいます。
そのため、何もしないというのは、「今後も同じパフォーマンスを発揮し続けるために必要なこと」だということを、自分に認めさせなければなりません。
特に成長意識の強い人は、毎日一歩でも前に進んでいなければ納得しないかもしれませんが、立ち止まることが今後の糧になるということを認める勇気も必要です。
どうしても働かなければいけない時の対処法10選
無気力で何もしたくないときは、上述したように実際に何もしないことが大事なことが多いです。
とは言え、社会の一員として生きている以上は、何もしないでは済ませられず、働かなければならないケースも多いでしょう。
どうしても働かなければならない場合の対処法を、以下でお伝えします。
1.スケジュールを調整する
働かなければならない場合でも、まさにその日に仕事を終わらせる必要があるのでなければ、スケジュールを調整して別日に働くようにすることで対処できることもあります。
働きたくないときは働かないのが一番の対処なのですから、どうにかしてスケジュール調整ができないか考えてみましょう。
特に自営業のかたの場合は、こういった調整・融通を行いやすいですね。
2.頭を使わずにできる作業のみに注力する
無気力のときは、頭を使うことが億劫になってしまうので、頭で考えずに淡々とできる作業のみを行うことも有効です。
たとえば、会議で使う資料をパワーポイントにまとめるのは頭を使いますが、資料作成のためにデータを集めたり入力したりするのは、比較的単調な作業と言えます。
「今日は単純作業をまとめて行う日」と割り切って、今後の仕事のための下準備をまとめてしてしまうといいでしょう。
頭を使わないとは言え仕事は行っているわけですから、「今日は何もしていない…」と自分を責めてしまうこともないですね。
3.身体を動かす
体を動かすことで、体と同時に気分もほぐれて、多少なりともやる気が湧いてきます。
体を動かすと聞くと、少しハードルが高いように思われるかもしれませんが、何も本格的な運動をする必要はありません。
ちょっとしたストレッチを行うだけでも、普段とは違うことを行うことで脳に刺激がいくため、効果としては十分です。
ランニング程度の軽い運動であれば、継続的に行うことで健康増進にもつながるので、これを機に何かの運動を趣味として始めてみてはいかがでしょうか。
4.森林浴をする
木々の緑に触れて精神的にリラックスする、いわゆる森林浴は、気分を変えたいときには非常に効果的です。
特に新緑や紅葉の季節に行う森林浴は、気候も相まって、短い時間でも非常にリラックスできます。
都会にお住まいの場合は、なかなか近くに緑がないかもしれませんが、ちょっとした公園にでも緑はあるものです。
時間が取れるのであれば、電車や車で郊外のほうまで少し遠出をして、本格的に森林浴をしてもいいですね。
緑の多いところで散策でもすれば、上述した「体を動かす」の効果も相まって、一気に気持ちを上向かせられるでしょう。
5.短時間でも睡眠をとる
睡眠不足のときは、どうしてもコンディションが悪くなってしまいます。
短時間でもかまわないので一度睡眠を取ることで、体調的にも精神的にも状態が改善されるでしょう。
毎日の睡眠時間をきっちり確保できるようにすることで、疲労やストレスも軽減されやすくなり、無気力になって何も手につかなくなってしまう可能性が、多少なりとも減ります。
睡眠時間を確保して睡眠の質を高めることが、ある意味では根本的な対策につながるとも言えます。
6.温かいお風呂に浸かる
温かいお風呂に浸かってのんびりすればリラックスできるというのは、多くの人が経験的に知っていると思います。
最近では忙しさやライフスタイルの変化から、湯舟には浸からずシャワーで済ませてしまう人も多いですが、無気力でどうしようもないときは、やはり温かいお湯に肩まで浸かるのが効果的です。
単純な疲労回復の効果も重要ですが、温泉の素などを入れれば気分も上がります。
お風呂に入るのを面倒なことだと思わずに、1つのイベントごととしてとらえることで、お風呂に入るのが楽しみになると思いますよ。
7.自分の望みを叶える
仕事をすることは決して楽しいことではない場合が多いので、自分へのご褒美、いわゆるアメとムチの「アメ」がない状態で仕事を頑張ろうと思っても、なかなかしんどいものです。
そこで、何か1つ自分の望みを叶えることを考えましょう。
欲しいカバンを買うのでもいいですし、日帰りで温泉旅行に行くのでもかまいません。
仕事を頑張れば「アメ」が待っているとなれば、仕事に対する気力も湧いてくるでしょう。
どうしてもやる気が出てこない場合は、「アメ」を先にもらってしまうのも1つの手です。
望みを叶えて満足している状態で仕事に向かえば、自然と仕事にも身が入るでしょう。
8.規則正しい生活をおくる
無気力になってしまうのは、日々の生活習慣に原因がある場合もあります。
交代制の勤務など、仕事の都合上仕方ない場合もありますが、不規則な生活を送っているとホルモンバランスが乱れてしまい、やる気が出なかったり体がダルくなったりしてしまいます。
睡眠時間と起床時間をある程度定めて、規則正しい生活を送るようにすることで、無気力になってしまうのを防げることもあるのです。
布団に入ってからもダラダラとスマホを見続けて、気づけば寝落ちしているというような生活の人は、まずは自身の習慣を見直しましょう。
9.親しい友人に悩みを聞いてもらう
悩みがあるからどうにもやる気が起きないという人は、心を許せる親しい友人に悩みを聞いてもらうのも、効果的です。
悩みごとは、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいると、なかなか解消せずにいつまでも心の中にわだかまりとして残り続けます。
自分自身の弱い部分でもあるだけに、人を選ばずに話すことは難しいと思いますので、自分のことを受け止めてくれるであろう親しい友人に話すことで、気持ちも軽くなるものです。
無気力のときは人と接するのも億劫になってしまいがちなので、無理矢理にでも理由を付けて人に会うことで、ふさぎ込んでいる状態から抜け出せるきっかけを作りましょう。
10.無気力な状態が長期で続く場合は医師に相談する
無気力状態から脱却するために、いろいろと試行錯誤することは重要です。
しかし、どれだけいろいろなことを試してみてもどうしてもやる気が出ない、ずっと無気力のままだという場合は、精神的な疾患を疑わなければなりません。
現代社会はストレス社会ということは先ほど少し触れましたが、ストレスのせいでメンタル面にダメージを負ってしまう人は年々増えてきており、あなたがメンタル的にやられていないとは限らないのです。
精神疾患の可能性がある場合は、医師に相談して適切な対処・処置を行わないと、状況が悪化して仕事を続けられなくなってしまうかもしれません。
無気力だとかやる気が出ないという理由で医師に診てもらうことを、恥ずかしがる人もいるかもしれませんが、立派な「疾患」の可能性があるので、医師の力を借りることは何ら恥ずかしいことではありません。
無気力のときにしてはいけないこと
無気力のときの対処法をお伝えしてきましたが、逆に無気力のときにしてはいけないこともあります。
以下で挙げるようなことをしてしまうと、状態がさらに悪化してしまう可能性が高いので、要注意です。
暴飲暴食を繰り返す
気持ちを前向きにするためには適度な食事が欠かせませんが、暴飲暴食はかえって気持ちを落ち込ませてしまいかねません。
暴飲暴食をすると、当たり前ですが体重が増えます。
多くの人にとって、体重の増加は決してよい変化ではありませんから、増えた体重を見てまた気持ちが落ち込んでしまうのです。
気持ちが落ち込んでいるときは、食べることしか楽しみがないかもしれませんが、暴飲暴食だけは控えなければなりません。
たくさん食べてたくさん飲みたいのであれば、バイキングのような「たくさん食べることがある程度肯定されるところ」で、好きなだけ食べるのがおすすめです。
自分を責める
無気力になって何もやる気が出ないような状態に陥ってしまうのは、外的要因が原因であるケースも多々あります。
しかし一度無気力になってしまうと、「自分がだらしない・情けないからこんな風になってしまうんだ」と自分を責めてしまいがちです。
無気力なときに自分を責めても、事態は決して好ましい方向には進みません。
いっそのこと責任をすべて外部に見出して、「世間が悪い!」と開き直ってしまうほうが、無気力状態から回復するにはいいぐらいです。
普段の生活では、「他責」の考えかたはあまりよしとはされませんが、無気力になってしまった場合に自分の心身を守るためには、逆に他責で考えるようにしましょう。
過度なアルコールの摂取
無気力なときは、お酒に酔って何もかも忘れてしまいたいと感じることも多いでしょう。
確かに適度なアルコールは、気分を高めるためには非常に有効です。
しかし食事同様に、アルコールも過剰に摂取してしまうと、逆効果になってしまいます。
気分が乱高下して落ち着かなくなってしまいますし、酔った頭にはネガティブな思考が浮かびやすくなってしまいます。
「酒は百薬の長だから」なんて屁理屈をこねながら、お酒をどんどん飲みたがる人がいますが、何事もほどほどが大事だということを、しっかり肝に銘じておいてください。
無気力に陥りやすい人の特徴
同じような境遇で同じような仕事をしていても、無気力になってしまう人もいれば、無気力になりにくい人もいます。
無気力に陥りやすい人には、以下で挙げるような特徴があることが多いです。
ストレスをためやすい
過度なストレスを感じると、人は無気力になってしまいやすいですが、ストレスを「感じる」ことと、ストレスを「溜める」ことは別の話です。
ストレスを感じたとしても、それを先々まで引きずらずに解消できてしまう人であれば、瞬間瞬間でストレスによる無気力さを感じるとしても、慢性的に無気力になってしまうことはありません。
対して、ストレスを発散させることが苦手でストレスを溜めこみやすい人は、相対的に無気力になりやすいと言えます。
ストレスを溜めこみやすいという自覚のある人は、少しでもストレスを感じたらできるだけ早くストレスを発散して、自衛することが重要です。
無理をしがち
仕事にしろ家事にしろ、無理をすると疲労もストレスも溜まりやすくなるので、無気力状態に陥ってしまいやすくなります。
特に責任感の強い人や、人に相談するのが苦手な人は、どうしても無理をしてしまいがちなので、無気力状態に陥ってしまいやすいと言えるでしょう。
すべてを自分で抱え込む必要はありませんので、適度に他人に任せつつ自分の負担を減らせるようにすることが重要です。
生活が不規則
規則正しい生活を送ることが、無気力から脱するために重要であるということは、先ほどお伝えしました。
ということは逆に考えれば、生活が不規則な人は無気力状態に陥ってしまいやすいということになります。
起床と就寝の時間さえある程度固まっていれば、生活リズムがそこまで壊れることはないので、何時に寝て何時に起きるかは決めてしまうといいでしょう。
生活が不規則になってきたなぁと感じはじめたら、休みの日などを利用してうまく修正することで、また元通りの生活リズムに戻せます。
無気力状態から脱出する5つの方法
無気力になると、自分の生活だけでなく仕事もおろそかになってしまいますので、ますます貧乏になってしまう可能性が高いと言えます。
お金がない状態から脱却するためにも、無気力状態を脱出し、やる気あふれる人生を取り戻さなくてはなりません。
無気力状態から脱出するための5つの方法を紹介します。
1.考えるよりも行動する
無気力な状態のまま考えると、思考がネガティブなほうへ行ってしまいます。
「あ~、何にもやる気が起きない・・・」と無気力さに身を任せるのではなく、とにかく行動してみてはいかがでしょうか。
仕事をしている人は、いつも以上に積極的に仕事に取り組んでみましょう。
仕事がない人は、ハローワークに出かけて仕事を探してみましょう。
条件に合う仕事がない場合でも、厚生労働省が実施している専門実践教育訓練を利用して無料あるいは一部負担で職業訓練を受けることもできます。
2.太陽に当たる
無気力になると自暴自棄になり、最悪、自殺を考えるようになります。
内閣府の自殺対策推進室資料によりますと、自殺率の高い国は、1位から順にリトアニア、ベラルーシ、ロシア連邦、スロベニア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、日本となっています。
これらの国々のいずれもが赤道から離れた高緯度地域にあり、赤道周辺の国々と比べると日照時間が短い時期が長いことは、決して偶然とは思えませんよね。
健全な精神を保つためにも、積極的に太陽に当たることも重要なことだと言えるのではないでしょうか。
3.いつも会わない人と会ってみる
人と話すことで、ポジティブな気持ちを持てるようになるかもしれません。
できれば、よく会う友人やママ友ではなく、新しい出会いを求めたり普段あまり話さない人と話してみたりすることをお勧めします。
新しい人と話すことで、気分転換になるだけでなく、気持ちに刺激をもらうこともできますよ。
ただし、新しい人と会うからといって、分不相応に高級なお店に出かけるのはNGです。
「散財してしまった・・・」と、後で落ち込むことにもなりかねませんよ。
また、いつも「お金がない」と言っている人間と会うこともNGです。
無気力さが倍増するかもしれませんよ。
4.身だしなみに時間をかける
家で過ごす時間が長い専業主婦も、毎日、家事の繰り返しでは無気力になってしまいます。
お金がないから出かけても楽しくないというのは分かりますが、だからといって掃除の手を抜いたり、料理も適当に済ませたりするなら、ネガティブな気持ちがさらに大きくなってしまいますよね。
自分の気持ちを高めるためにも、朝起きたらすぐにメイクをして、服装もキレイに整え、1日を楽しい気分で過ごせるための準備をしてみるのはいかがでしょうか。
「朝は忙しくてそんな余裕はない」という人は、いつもよりも10分だけ早起きして、身だしなみを整える時間を作りましょう。
自分自身をキレイにすると、その日一日、自信を持ってポジティブに過ごすことができますよ。
5.勉強をする
いつもポジティブな人は、常に新しいことを学んでいます。
興味がある分野の知識を深めたり、新しい資格に挑戦したりと、少しでも余った時間があれば勉強してみるのはいかがでしょうか。
勉強することで自分自身の能力を高めるだけでなく、生きかたも積極的になりますよ。
お金がないと無気力になる5つの理由
お金がないと、次の5つの理由により無気力になってしまいます。
1.金欠によりストレスを感じているから
人間は強いストレスを受けると、これ以上のダメージを心が受けてしまわないように防御態勢に入り、「何もしたくない」「何も感じない」と無気力になってしまいます。
これを医学的には「無気力症候群(アパシー・シンドローム)」と呼びます。
長い受験生活の後に大学に合格した人や長い就活期間の後に就職した人が5月当たりに無気力になる「5月病」も、強いストレスを受けていた反動による症状と考えられますので、無気力症候群の一つです。
同様に、お金がないことで強いストレスを受けている人も、心がこれ以上傷つかないように自然と防御態勢に入り、無気力症候群に罹患しやすくなってしまうのです。
2.お金がなくてしたいことができないから
大きな夢や希望があるにも関わらず、お金がないために実現が不可能だと分かったとき。
期待する気持ちが大きい分、失望も大きくなってしまいます。
そのため、希望や夢などの目標を持つこと自体が無駄だと考えるようになり、希望や夢を持たない状態、つまりは無気力状態になってしまうのです。
たとえば、hCG注射などのいわゆるホルモン注射によって不妊治療を続けていたものの、思うような効果が得られずに医師から体外受精を勧められたとします。
注射による不妊治療は1回1~3万円ほどですが、体外受精は1回20~50万円ほどかかりますので、金銭的には厳しいと判断する人も多いでしょう。
中には金銭的なことを理由に夫に体外受精を反対され、「赤ちゃんが欲しいという夢を描くだけ無駄だった」と妻が無気力になってしまうことも想定されるのです。
3.失敗や失業によりお金を失ったから
事業を興したものの失敗して多額の借金を背負ってしまった。
また、何らかの事情により失業し、無職になってしまった。
これらのように、失敗や失業といった「不成功体験」のためにお金をなくしてしまった場合は少々厄介です。
すでに敗北によって心に大きなダメージを負っていますので、ただ単にお金がない状態の人よりも心の傷が深く、無気力になりやすくなってしまうのです。
事業を立ち上げようと頑張っているときには気力にあふれていたのに、1度の失敗でその後の人生を廃人のように送ってしまう人が少なくないのも、敗北によるダメージが大きすぎるためと考えられるでしょう。
4.お金がないことに束縛されているから
お金がないからと言って、何にもできないわけではありません。
図書館に出かけたりジョギングをしたりと、レジャーを楽しむことだってできます。
しかし、「お金がないと何もできない」という考えに取り憑かれてしまっている人は、お金基準でしか物事を見られなくなってしまっています。
ステキな洋服を見ても「高いんでしょ?」、おいしそうなフルーツを見ても「高いんでしょ?」、新しくできたスポットの話題を聞いても「高いんでしょ?」とお金基準でしか物事を考えられなくなってしまいます。
そのため、生活する気力すら失ってしまい、無気力に日々を送ることになるのです。
お金がないときの楽しみかたについては、次の関連記事をチェックしてみてください。
5.健康状態に問題があるから
お金がないと、つい、健康管理がおろそかになってしまいます。
食事の栄養バランスを考えないようになったり、適度な運動をしなくなったり、起床時間・就寝時間が不規則になったりします。
そのため、健康状態が優れなくなってしまい、体調の悪さから無気力になってしまうこともあるのです。
6.お金に執着する心理の弊害
お金が欲しいと執着しすぎると、さまざまな弊害が現れる可能性があります。
たとえば、もっともよく見られるのがお金以外の価値観を持てなくなるという弊害です。
「新しいケーキ屋さんのイチゴのショートケーキが美味しかったよ」という話を聞いても、「おいしそう!」「どんな味なの?」「わたしも行きたい」といった反応ではなく「いくらなの?」としか答えない人がいます。
また、お店で洋服を選ぶときも、「似合うかどうか」「着る機会は多いか」といった通常の価値基準ではなく、単に「安いかどうか」という基準でしか見られない人もいます。
何もしたくないことが多いのは普通?
朝、目覚めたけれど何もする気が起こらない。
そう言えばお金もないし、なんか生きているのって面倒だなあ・・・。
そんな風に考える前に知っておきたいことと、生活の改善ポイントを紹介します。
誰もが意欲にあふれて目覚めるのではない
テレビドラマを見ていると、ほとんどの主人公が「今日も頑張ろう!」と独り言を言いつつ、大きく伸びをしながらさわやかに目覚めています。
現実には、そんな人、ほとんどいませんよね。
「え、もうこんな時間!」と慌てて目覚めて、朝ご飯を作ったり、会社や学校に行く準備をしたりと、しなくてはいけないことをこなしていきます。
つまり、あなたが意欲にあふれて目覚めていないのは、少しも変わったことではなく、それが普通なのです。
意欲ではなく用事がないことが問題!
先程も述べましたが、ほとんどの人々は、意欲にあふれているために目覚めるのではなく、用事があるために目覚め、朝の業務をこなします。
つまり、あなたが「何もしたくない」と思っていることに問題があるのではなく、朝起きてしなくてはいけない用事がないことが問題なのかもしれないのです。
朝、どうしても意欲が湧かないという人は、しなくてはいけない用事を作ってみるのはいかがでしょうか。
仕事をしていないのなら朝のバイトを入れてみたり、大学や専門学校に行っている人なら朝の授業を選択してみたりといったことができるでしょう。
次の記事では割の良いアルバイトについて紹介していますので、せっかく働くなら効率よく稼ぎたいと考える人はぜひ参考にしてください。
ライフスタイルや睡眠の質に問題があることも
朝に用事を入れてみたけれど、どうしても身体が動かないという人は、生活自体に疲労感・倦怠感の理由が隠れていることがあります。
次のポイントを見直してみるのはいかがでしょうか。
運動量を増やそう
身体を動かし過ぎることも疲労の原因になりますが、身体を動かさなさすぎるのも疲労や倦怠感の原因になります。
意欲が湧かなくても1日に1回は太陽の光を浴びて、ウォーキングやジョギング、水泳等の運動をしてみてください。
食事の質・量を見直そう
ミネラルやビタミン、タンパク質、適度な脂質・糖質をバランスよく摂取していないと、身体は不健康になり、疲れやすくなってしまいます。
また、量(カロリー)は充分に摂取していても不足する栄養素があるなら、脳に充分な栄養が行きわたらず、脳の働きが鈍くなってしまうこともあるでしょう。
あなたの食生活はいかがですか?
栄養バランスの取れた食事を摂っていますか?
一人暮らしの場合、つい主食系の糖質に偏る傾向がありますので、意識的に主食や菓子を減らし、野菜や魚を摂取していくようにしましょう。
睡眠の質も見直そう
また、睡眠も見直す必要があります。
睡眠時間が不足すると疲労や倦怠感の原因になりますが、睡眠時間が多すぎても疲労や倦怠感の原因になってしまいます。
清潔に整えられた寝具で、できるだけ毎日同じ時間に就寝し、同じ時間に目覚める習慣を身につけて下さい。
もしかして鬱病?病院に行く前に
「朝の用事を作ってみたけれど、どうしても身体が動かない」
「食生活も運動、睡眠もすべて改善したけれど、意欲が湧かない」
そのようなかたは、うつ病の可能性があると考えられます。
ですが、「うつ病かも」と精神科に行く前に、次のことを考慮してから行動するようにしてください。
1.うつ病は誰でも成り得る
うつ病は身体の病気とは異なり、精神的な病気です。
身体の病気は数字で見える基準(血糖値が126mg/dl以上であることや尿タンパクが30mg/dl以上等)で診断可能なことが多いです。
しかし、精神的な病気はそのような数値で見える基準がないことが多いため、医師によって診断基準が大きく異なることがあります。
現在、日本では精神的な症状の分類と診断をDSM-IV(アメリカの精神医学会による分類法)に因っていることが多いのですが、DSM-IVではうつ病の診断基準を次のように規定しています。
- 抑うつ症状もしくは興味や喜びの消失が見られること。
- 1に加えて、食欲の減退あるいは増加、不眠あるいは睡眠過多、精神運動性の焦燥あるいは沈滞、疲れやすいあるいは気力減退、無価値観あるいは過度の罪責感、集中力の減退あるいは決断困難、死についての反復思考あるいは自殺企図のうち5つ以上の状態が見られること。
これらの基準は医師の主観や患者の自己申告によって判断されますので、誰でもうつ病と診断される可能性があると言えるでしょう。
本当は一時的な症状であるにも関わらず、病院で深刻なうつ病と診断され、終わりの見えない薬物治療が始まるということも想定されるのです。
2.病院に行く前に自問したいこと
何も意欲が湧かない人は、次のことを自分自身に尋ねてみてください。
- 意欲が湧かない日もあれば意欲が湧く日もある。
- 仕事が見つからないことや借金を抱えてしまったこと、家族や友人との関係に問題を抱えていること等、何かしらのトラブルを抱えている。
- 身体が太ってきたと感じている。
- 健康上の不安や将来の不安がある。
このうちの1つでも「はい」と答えることができるなら、うつ病を疑う前に、自分自身の問題について熟慮してみるほうが良いかもしれません。
あなたが今抱えている問題が解決されるなら、やる気を取り戻し、生き生きとした人生を送ることができるかもしれませんよ。
ただし、問題解決が現実的に難しい場合や上記の質問のいずれにも「いいえ」と答える場合には、精神科を受診して、医療的な解決を試みることもできるでしょう。
3.うつ病は立派な病気
単に気持ちが優れないというような状態は「うつ病」とは呼びません。
うつ病は健康保険が適用される病気の1つです。
現在、日本ではアメリカ精神医学会が出版しているDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル5版)やDSM-IVの基準で診断することが多いですが、以下の状況がほぼ毎日続いているときにうつ病と判断されます。
- 抑うつ的な気分
- 無気力状態、喜びや興味の喪失
- 食欲や睡眠時間の大幅な増減
- ひどく気分が落ち込む、疲れやすい
- 思考力の低下
- 自分を無価値だと感じる、過剰に罪悪感を覚える
- 同じことを繰り返し考える、自殺について考える
その他にも、不安や絶望感が付きまとう、性欲が落ちることもあります。
また、うつ病には身体的な症状もあります。
上記の心理的な症状以外に体重の増減が激しいときや不眠、呼吸困難、動悸などの症状があるときは、心療内科や精神科で専門的に診察してもらいましょう。
参考:日本うつ病学会治療ガイドライン「Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害2016」
4.日常生活に支障がでる場合もある
うつ病の心身の症状が、社会生活に支障をきたすことも珍しくありません。
睡眠障害や食欲の低下、疲労や倦怠感のほか、発汗、頭痛、関節の痛みなどを伴うことがあるのです。
また、家庭生活がうまく行かずに離婚に進展することもあるでしょう。
ぜひ症状が深刻化する前に病院に行き、適切なカウンセリングや薬物治療などを受けるようにしてください。
5.うつ病になると社会生活に支障が出る
日常生活に支障がでると、今度は社会生活に支障がでることもあります。
会社に行く気力が湧かなかったり、出社しても散漫な仕事をしてしまう傾向があるのです。
また、そのことで上司に叱られたり、人間関係を悪くして、さらにうつ病が悪化するという悪循環を招く場合もあります。
社会生活に支障が出ると、収入源を失うことにもなりかねません。
「最近、少し変だよ」「疲れているんじゃない?」と言われることが増えたら、早めに専門医に相談してください。
うつ病になると金欠になる場合がある
うつ病になると、金欠になる可能性が高まります。
まずは、うつ病になって仕事に影響が出て、収入が減ってしまいます。
さらに、治療にお金と時間がかかることもあり、家計を脅かしかねません。
しかも、うつ病は長期化しやすいため、失職から再就職までの間隔が長くなり、再就職が難しくなってしまいます。
それぞれについて詳しく解説します。
働けない場合がある
うつ病になると働けなくなる可能性があります。
軽度のうつ病であれば、うまく症状と付き合いながら仕事を続けることはできますが、重度のうつ病になると仕事ができなくなることがあるのです。
治療にお金と時間がかかる
うつ病の治療にはお金と時間がかかります。
治療にかかる費用は、カウンセリングルームや医療機関ごとに異なりますし、完治するまでの期間によっても異なりますので一概にいえませんが、長引けば長引くほど治療費はかさみます。
うつ病は治療を受ければすぐに治るというものではなく、時間をかけて治して行くものなので、お金と時間がかかることは覚悟しなければなりません。
再就職が難しい
うつ病で失職してしまうと再就職が困難です。
もちろん、絶対に不可能というわけではありませんが、そもそも再就職の活動に対する意欲も低下している状態ですし、ストレスフリーの仕事を探さなければならないので、選択肢も少なくなってしまいます。
しかも、失職期間が長ければ長いほど再就職には不利になりますし、面接官に「前の仕事を辞めてから随分経つようですが、何をしていたのですか?」と質問されるのは間違いないでしょう。
うつ病に理解のある面接官なら良いのですが、「また長期間休職されても困る」と考えて不採用と判断する面接官も少なくありません。
実際に、うつ病発症後は非正規の仕事しか得られていないという人も多いのです。
うつ病で休職するメリットは?
一旦、仕事から離れてしまうことには勇気が要ります。
今まで築き上げてきたキャリアが途絶えるだけでなく、再度、今の位置に戻れるのかという不安もつきまといます。
また、収入が減ってしまうのも休職をためらう理由になるでしょう。
しかし、キャリアや収入を度外視しても、休職にはメリットがあるのです。
復帰できる可能性がある
自分から休職すると、うつ病が治ったら復帰できる可能性があります。
反対にうつ病であることを黙っていて、あなたが病気で調子が悪いのではなく、人間的に問題があったと周囲からみなされていたとしましょう。
「社員の和を乱す」「会社に不利益をもたらす」などの理由で解雇されてしまうと、たとえ治療ののちにうつ病が治ったとしても復帰は難しくなるでしょう。
うつ病で仕事を続けるのが難しいと思ったときは、思い切って休職を願い出るのも1つの方法ではあるのです。
心身ともに休める
理想を言えば、いつもと同じように通勤しながら治療するのが一番です。
しかし、通勤と通院を同時進行すると健康なとき以上に忙しくなりますから、心身ともに疲れ果て、完治するまでに通常以上に時間がかかってしまいます。
一度、休職してうつ病の治療だけに専念することも、長い人生においては重要なことと言えるでしょう。
うつ病で休職するデメリット
うつ病は決して「気のせい」ではありません。
治療が必要な病気ですから、休職して治療に専念するのは当然なことと言えます。
しかしながら、休職すると会社の評価に響いてしまうというデメリットがあります。
デメリットについてもしっかりと考慮してから、休職届を提出してください。
会社の評価に影響する
会社ではさまざまな観点から社員の評価をつけていきます。
評価の中には「有休以外の休みが多くないこと」や「参加したプロジェクト」「成果」などもありますが、まとまって数ヶ月~数年休んでしまうと、いずれの評価もネガティブになってしまいます。
同期と比べて明らかに昇進が遅くなったり、閑職に移動させられたりすることもあるでしょう。
うつ病で休職する方法は?
うつ病の治療を優先するなら、仕事を休職するのが最善の策です。
治療に専念することで罹患期間を短縮することも可能ですし、職場に迷惑をかけることも避けられます。
仕事と治療の両立が難しく感じたら、次の手順で休職しましょう。
休職の手順
まずは心療内科や精神科などの外部の病院で、疾病名と治療期間を記した診断書を発行してもらいます。
次に診断書を上司に見せ、休職する必要があることを説明しましょう。
あくまでも「休職を願い出る」わけですから、仕事に支障を与えて申し訳ないという態度を示してください。
また、職場によっては産業医の診断や人事部との面談が必要になることや、「休職ではなく退職するほうが良いのでは?」と勧められることもあります。
しかし、大抵の会社の就業規則では病気を理由に解雇することは認められていませんから、退職したくない場合は安易に会社側の提案に乗らないようにしましょう。
万が一、解雇かどうかで揉めたときのために、書類はすべて保管し、必要ならば会社側の許可を得てから話し合いを音声レコーダーで録音しておきましょう。
休職した後にするべきことは?
すべての病気がそうであるように、うつ病も「一定期間治療すれば絶対に完治できる」とは言い切れません。
数ヶ月治療に勤しむことで寛解することもあれば、状態がまったく変わらないこと、反対に症状が一層深刻になってしまうこともあるでしょう。
治療の結果、うつ病の症状が見られなくなった場合、あるいは社会生活を送りながら治療できると主治医が判断した場合は、復職手続きをしてください。
復職手続きをする
医師の診断書を元に休職が決定した場合は、復職の際も医師の診断書が必要になります。
かかりつけの病院やクリニックに行き、病気が治ったこと、あるいは社会生活に支障を与えないほどにうつ病が治癒できていることを書面に記してもらいましょう。
診断書を手に入れたら、直属の上司に電話をかけて復職したい旨を伝えます。
上司は面接日を指定してくれますので、診断書を持って面接に向かいましょう。
面接では「本当に業務に差し支えないのか」という点を重点的に尋ねられますので、答えに詰まらないように何を話すか準備しておくと良いですね。
また、治癒状況によっては数ヶ月間の「お試し期間」が設けられることもあります。
いきなり全時間勤務に復帰するのではなく、勤務時間が短縮されて様子を見つつ、元の働きかたに戻れるケースもあるのです。
退職の手続きをする
治療が思うように進まず、休職時に設定した期間が終了しても職場に復帰できなさそうなときは、退職の手続きに進むという選択肢も検討してみましょう。
もちろん、退職は休職者の自由意思で決定されなくてはなりません。
「これ以上は職場に迷惑をかけたくない」「休職期限を定められていると、焦ってしまって治療に専念できない」と判断するときだけ退職願を出すようにしてください。
うつ病の原因が勤務先にある(過重労働やセクハラ、パワハラなど)ときや休職者本人が同意していないのに勝手に退職扱いにされたときは、不当解雇と判断できます。
労働組合に加入しているときは労働組合に相談し、加入していないときは不当解雇を専門に扱う法律事務所に相談してください。
未払いの残業代の請求
過重労働が原因でうつ病を発症し、休職していた場合は、未清算の残業代が残っている可能性があります。
労働基準法の第115条では残業代の請求は2年まで(退職金の請求は5年まで)しか遡れないと記されていますので、消滅時効が成立する前に請求したということを書面に残しておきましょう。
うつ病になってお金に困らないための公的支援
うつ病になったら無理をせずに休養を取ることが重要です。
休職できるなら休職を、できないのであれば退職して、しっかりと治すことをおすすめします。
しかし、休職も退職も収入が減ったりあるいは途絶えたりすることになるため、お金に関する不安が生じてしまい、逆説的にうつ病の症状を悪化させてしまう可能性もあるのです。
じっくりと安心して休養するためには、お金に関する不安を解消してから休職や退職する必要があるでしょう。
日本には、病気が原因で働けなくなった人に対する公的支援制度がいくつかあります。
うつ病時に利用できる12の制度を紹介しますので、利用条件に合致する場合は申請してみましょう。
1.有給休暇
うつ病で会社を休まざるを得ない状況になったら、最初は「有休制度」を利用するようにして下さい。
有休制度は正社員だけが活用できる制度ではなく、アルバイトなどの非正規雇用のかたでも、一定の条件を満たせば有給休暇の取得は可能です。
雇用形態に関わらず6ヶ月以上連続して勤務し、全労働日の8割以上出金しているなら、最低でも10日の有給休暇を取得できると労働基準法第39条では定められています。
最低有給休暇は勤続年数が増えるにつれ最大20日間まで増え、さらに1年前の有給も取得せずに残っている場合は、そのまま繰り越すことも可能です。
2.傷病手当
うつ病の治療は長期にわたるケースがほとんどですから、有給休暇だけではカバーできない場合もあります。
有給休暇だけでは治療が完了しない場合は、健康保険組合から支給される「傷病手当金」の申請をするようにして下さい。
傷病手当金は、業務上の理由で仕事を休んでいること、連続する3日間を含み4日以上休んでいること、会社から給与の支給がないこと等の条件が整えば、最長1年半の間給料の約2/3が健康保険組合から支給されます。
もちろん、うつ病で休養が必要な場合も利用できます。
健康保険組合が定めたフォームで申請しますので、かかりつけ医に診断書を作成してもらう前に「傷病手当金の申請をする」ということを伝えておきましょう。
傷病手当金が発生する期間
なお傷病手当の支給を受けることができるのは、給与が支払われない期間に対してとなっています。
そのため有給休暇を取得している期間は、正規の給与が支払われますので傷病手当金は支給されません。
有給休暇を使い果たした後もなお休養が必要な場合に、傷病手当の申請をしましょう。
また、傷病手当受給中に退職したとしても、傷病手当の給付は停止されません。
最低限の生活費が確保できるので、お金の心配をせずにしっかりと休養できるでしょう。
3.労災認定
仕事が原因でうつ病になったことが明らかな場合、労災認定を申請できます。
労災認定を受けることができれば、給与の8割のお金を受け取ることができます。
この金額は傷病手当で受け取る金額よりも多くなりますので、労災に該当する場合は以下の所定の書類を使って申請してください。
労災認定には半年程度かかる
ただし、傷病手当金の申請とは異なり、労災認定には時間がかかります。
申請後、順調にいっても半年程度の期間が必要で、1年以上かかる場合もあります。
さらに、仕事や職場がうつ病の原因となっていることを証明することは難しく、うつ病で労災認定されるのは4割程度であるのが現実です。
労災認定されるまでお金は支給されませんので、同時に傷病手当も申請しておくとよいでしょう。
労災が認定されれば返還しなければいけませんが、収入が途絶えてしまうことによる不安を減らすことはできるでしょう。
4.失業保険
仕事を辞める2年間に12ヶ月以上勤務していることが条件となりますが、うつ病が原因で退職した場合、病状が回復して働ける状態になれば、失業保険(雇用保険の基本給付)を受け取ることができます。
失業保険は働ける状態にあり、働く意志を持っている人に対してお金を支給する制度です。
したがってうつ病で休養するために退職した場合にすぐに失業保険を受け取ることはできませんが、再び働ける状態になったときに、お金を心配せず就職活動ができます。
なお、失業保険は受給できる期間が決まっています。
休養が必要で、退職後すぐに就職活動ができない場合は、ハローワークに申請して受給期間の延長を申請することも可能です。
5.自立支援医療制度
お金を受け取ることができる制度ではありませんが、うつ病で通院している人にとって、自立支援医療制度は有益な制度です。
この制度は、長期間治療が必要な人が申請することによって、医療費の負担を3割から1割に軽減してもらえる制度です。
もちろん、うつ病の治療でも利用できます。
うつ病の治療は長期間にわたり、治療費や薬代を含めてかなりの医療費が必要となります。
自立支援医療制度を活用すると1ヶ月あたりの上限金額が設定されるため、上限額以上の負担はなくなり、医療費が多ければ多いほど役立つ制度になっています。
入院費や保険適用外の治療については自立支援医療制度の対象外となりますが、通院で治療をしている場合には適用されます。
かかりつけ医に自立支援医療制度を利用したいと告げ、診断書を受け取って、住んでいる自治体の窓口に提出してください。
6.医療費控除
医療費が高額である場合には医療費控除を受けることができます。
確定申告が必要ですが、医療費にかかった分を所得控除額に含めることができますので、見逃さずに申請してください。
1年間の医療費実費が10万円以上のケースで還付が行われ、入院費や治療費のほか、検査や薬代、通院のための交通費、鍼灸師の施術費などにも適用されます。
7.高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の上限を超える費用に対して払い戻しを受けることが可能な制度です。
上限金額は収入や年齢で異なりますが、健康保険や国民健康保険の被保険者であれば受けることができるため、予想外に医療費がかかっても安心して受診できます。
8.生活保護
資産もなく、働くこともできず、誰からもお金を借りることもできない困窮状態であれば、生活保護の受給を検討してみましょう。
生活保護は最低限度の生活を保障してくれる制度で、必要なお金を支援してくれます。
ただし、受給条件は厳しいため、誰もが簡単に受けられるわけではありません。
どうしようもない場合の最終手段と考えましょう。
9.障害年金
初診日が国民年金加入期間中あるいは20歳未満、60~64歳で、法令によって定められた障害等級の1級か2級と判断されると、障害基礎年金が受給できます。
うつ病も精神障害として障害基礎年金の受給対象となりますので、障害等級が認定されたときは申請してください。
1級と診断されたときは年間974,125円(平成30年4月以降)に子供がいる場合は子供の人数による加算分、2級と診断されたときは年間779,300円に子供による加算分が支給されます。
初診日が厚生年金加入期間中で障害等級の1級・2級・3級のいずれかと判断されると、障害厚生年金が受給できます。
受給額は報酬比例の年金額によって異なりますので、年金事務所で相談してください。
10.特別障害者手当
心身に重度の障害があると判断されるときは、国から特別障害者手当を受給できます。
本人と配偶者もしくは扶養義務者の収入による所得制限はありますが、承認されると月に26,940円(平成30年4月以降)を受給できます。
うつ病の症状が深刻なときは、お住まいの市区町村役場の窓口で特別障害者手当について相談してください。
11.特別児童扶養手当
20歳未満で心身に重度の障害があると判断されたときは、国から特別児童扶養手当を受給できます。
本人と配偶者もしくは扶養義務者の収入による所得制限はありますが、承認されると1級は月に51,700円、2級は月に34,430円(平成30年4月以降)、障害認定された人を養育・監護している父母に支給されます。
該当するかたは、お住まいの市区町村役場の窓口で申請してください。
12.扶養共済制度
「障害者扶養共済制度」とは、障害のある子の保護者が毎月掛け金を納めると、保護者が亡くなった後もしくは保護者自身が重度障害になった後に、障害のある子供が一生涯年金を受け取ることができる制度です。
保護者の年齢によって掛け金が変わりますが、月々9,300円~と手軽に利用でき、毎月2万円(1口2万円、2口4万円)を受け取れます。
誰しも親は子供の将来が不安になりますが、子供に障害がある場合は不安はさらに強くなるものです。
経済的な不安を少しでも解消するために、親が子供のために加入できる公的共済制度を活用してください。
うつ病でお金を借りる方法

12の公的支援制度を紹介してまいりましたが、いずれの制度も、申し込んですぐにお金を受け取れるわけではありません。
長い場合ではお金を受け取るまでに1年ほどかかることもありますので、受給されるまでの期間、生活が厳しくなることもあるでしょう。
また、うつ病になったときでも、まとまった資金が必要になることがあります。
自動車や住宅の修理代金や子供の進学など、健康なときと同じようにお金を必要とするイベントは起こるのです。
うつ病になってからお金が足りなくなったときに利用できる借り入れ方法をいくつか紹介します。
1.親類からお金を借りる
手っ取り早いのは両親や兄弟、親類などから事情を説明してお金を借りる方法です。
うつ病で働くことができずお金が必要だということをきちんと話せば、親類ならばお金を貸してくれる可能性は高いでしょう。
さらに、親や親せきにお金を借りる場合には、利子が不要になったり、病状が回復するまで返済を待ってくれたりする可能性もあります。
格好悪いと感じるかもしれませんが、病気で休養が必要な状態なのですから、まずは親類に頼ってみることをおすすめします。
ただし、年間110万円を超えるお金を受け取ると贈与税の対象となりますので、金額によっては親類からお金を受け取るときも利息を設定するようにしてください。
2.生活福祉資金
公的な貸付金制度を利用すれば、年間0~1.5%の超低金利でお金を借りることができます。
たとえば生活再建までに必要な資金や住宅を借りる費用、子供の進学や就学の費用なども、上限はあるものの低金利で借りられます。
ただし、公的資金ですので手続きや審査に2~3週間ほどかかり、今すぐ必要なときには利用できません。
1週間以内に資金が必要なときは、生活福祉資金の「緊急小口資金」に申し込んでください。
上限は10万円と少額ですが、最短5営業日、原則無利息でお金を借りることができますよ。
3.カードローンの利用
うつ病で働けない状態でも、カードローンなどを利用してお金を借りることができます。
ただし、消費者金融カードローンは原則として「安定した収入がある人」のみ利用できますので、勤務先を休職する前に申し込むようにしてください。
当然のことですが、お金は借りたら返さなくてはいけません。
審査に通って借りられるからといって多額を借りるのではなく、本当に必要な金額かつ本当に返済できる金額だけを借りてください。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
4.生活保護の申請
様々な方法を使ってもお金が準備できない、また借りることができないのであれば、生活保護を申請することも検討してみましょう。
ただし、生活保護は確実に受け取ることができるものではありません。
申請が通るには、非常に厳しい条件を満たさなければいけません。
生活保護は、最終の手段として考えておきましょう。
5.失業中の借金返済はどうなる?
もちろん、失業したからと言って借金の返済義務はなくなりません。
返済が長引くと利息が増えてますます大変になりますので、預貯金や財産があるときは一括で返済することを検討してみましょう。
預貯金や財産がなく、毎月の収入では返済が難しいときは、自己破産も視野に入れてください。
自己破産というと「人生の終わり」と大袈裟に感じる人もいますが、実は法律で認められた「人生の再生方法」なのです。
自己破産をすると財産を失うことにはなりますが借金の返済義務からも解放されますので、毎月返済に追われる生活から解放されます。
個人でも自己破産手続きはできますが、難しそうだと感じるときは債務整理を専門とする法律事務所で相談してください。
うつ病になると金欠になりやすい理由は?
うつ病はつらい病気です。
前向きに人生をとらえることができなくなるだけでなく、不眠や体重の過度の増減、身体の痛みやだるさといった不快症状にも悩まされます。
しかも、うつ病になると金銭的にも困窮しやすくなります。
うつ病になると金欠になりやすくなる理由について見ていきましょう。
働けなくなるから
うつ病の症状が深刻になると、社会生活が難しくなり、勤務できなくなります。
仕事をしないと当然給与はなくなりますので、当然金欠になってしまいますよね。
しばらくの間なら、有給休暇を利用して何とか乗り切ることもできるでしょう。
しかし、有給休暇も無限に利用できるわけではありませんし、人によってはすでにある程度有給休暇を消化してしまっておりあまり日数が残っていないという場合もあるでしょう。
通院や入院によりお金がかかるから
うつ病にかかってしまった場合、治療のために通院する必要がありますし、症状が重い場合には入院の必要性が出てくることもあります。
収入が減っている状態で、普通の生活費に加えて医療費もかさむことになりますので、金欠に陥るのも当然ですよね。
短期間で治療を終えることができればいいのですが、うつ病の治療は長期化する傾向にありますので、その間の医療費負担は家計にとってなかなかの重荷になってしまいます。
ストレス発散で散財してしまう人も
うつ病を治すためには、余分なストレスを溜めないことが重要であることは間違いありません。
しかし、ストレス発散のために趣味などに没頭して散財してしまうと、より一層金欠になってしまいます。
趣味が買い物だからということで買い物ばかりするようになってしまうと、どれだけお金があっても足りないどころか、買い物依存症という新たな病気の引き金になってしまうことも考えられます。
線引きが難しいところではありますが、趣味に使うお金も「ほどほど」のところで止めるようにすることが重要となるでしょう。
ストレス発散がストレス因?
ストレスという言葉が日常的に使われるようになった現在、「ストレス=悪いもの」という図式ができあがっています。
そのため、少しでもストレスが溜まらないように「ストレスを発散すること」は必要なこと、あるいは良いことと考えている人も少なくありません。
もちろん、過度に押さえつけられた状況にいる人(たとえば厳しい寮生活で24時間プライバシーがないなど)が、たまの休みに外出して普段はできないようなことをすることは適切なストレスコントロール法と言えます。
しかし、高額なものを購入したり大声で人を罵倒したり等の間違った方法でストレスを発散すると、ストレスがさらに増大してしまいます。
また、ストレスはかならずしも発散することで減少するわけではないということを覚えておきましょう。
大切なのは「ストレスコントロール」、つまり、ストレスがある状況でもストレスだと感じないようにすることなのです。
日本のうつ病の現状
うつ病は、決して珍しい病気ではありません。
WHO(世界保健機構)によりますと、世界には3億人以上ものうつ病患者が存在し、年間80万人以上の人がうつ病のために自殺しています。
日本では約112万人のうつ病患者がいるとされています。
その他にも強迫性障害や双極性障害(躁鬱病)、パニック障害、全般性不安障害、統合失調症などのさまざまな疾患を含めると、精神疾患を抱えている人は非常に多いと言えるでしょう。
◆ 厚生労働省「2017年世界保健デーのテーマはうつ病です」
生きづらさを感じている人は多い
生きづらさを感じているのは、精神疾患を抱えている人だけではありません。
先天的な脳疾患である発達障害も、生きづらいと感じやすい障害です。
大人になってから発達障害が見つかることもありますし、うつ病などの後天的な疾患はいつ罹患するかも分かりません。
すべての人が「うつ病」や「生きづらさ」を抱える可能性があるわけです。
周囲に手を差し伸べるべき人がいるときには手を差し伸べ、本記事でも紹介した公的支援制度を利用するように勧め、困窮状態から脱出できるように取り組んでいきましょう。
自殺対策も必要
うつ病は症状が深刻化すると自殺につながることがあります。
世界では毎年約80万人がうつ病で自殺していますが、日本でもうつ病で自殺する人は大勢います。
たとえば2009年の自殺者は32,845名ですが、そのうち、原因が特定できた人のうち6,949名がうつ病を患っていました。
うつ病であるのに診断されていない人や原因が特定できなかった人も含めると、自殺をする人のうちのかなりの人がうつ病と関係があることが分かります。
つまり、うつ病が深刻化しないうちに通院して適切な治療を受けることが、自殺対策にもなるのです。
◆ 厚生労働省「自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて」
うつ病で生活費が足らなくなる理由
うつ病になると収入減と医療費増のダブルパンチを受け、経済的に困窮することがあります。
通常ならば、収入減と医療費増が分かっているなら、家計を引き締めて節約に励まなくてはいけません。
しかしながら、うつ病のときは「無気力」に身体が支配されてしまい、健康なとき以上に生活費が増えてしまうことがあるのです。
うつ病の典型的な症状「無気力」
無気力に襲われると、自分の仕事に責任が持てなくなり、仕事を休みがちになることがあります。
そのため、休職していなくても就労時間が減り、減収してしまいます。
また、食事を作る気力もなくなり、外食やケータリングを頻繁に利用するために食費が増えたり、洗濯や掃除も外注するようになって家計がさらに厳しくなることもあるでしょう。
再就職に対して意欲が持てなくなる
失業保険(雇用保険の基本給)も傷病手当金も受給期間は決まっていますので、本来ならば受給期間中に再就職を決め、収入源を確保しておきたいものです。
もちろん、うつ病は病気ですから、適切に治療すれば治癒して日常生活に戻ることは可能です。
しかし、うつ病によって長期にわたって無気力感に支配されてしまうと、再就職に対する意欲が持てなくなり、いつまで経っても失職状態が続くことあります。
そのため、他の疾患と比べても経済的に困窮しやすいという側面があるのです。
債務整理は難しい?
うつ病になると収入が減り、医療費が増え、しかも、無気力感にさいなまれるために生活費が増えます。
そのような状態で借金まで抱えてしまうと、生活に行き詰まり、さらに悩みが深くなり、うつ病の症状悪化にもつながります。
先に、借金を合法的に減らす方法として「自己破産」を紹介しましたが、実は借金を減らす方法は自己破産だけではありません。
合法的に借金を減らす方法を総称して「債務整理」と呼びますが、その中のいくつかを紹介しますので、最適な方法で借金を減らしてください。
任意整理
任意整理とは、それぞれの借金の返済額や今後の金利を見直して、返済しやすくする債務整理の方法です。
裁判所を通さなくても手続きができるため、債務整理の中ではもっとも簡便な方法とされています。
しかしながら、収入がない人や3年以内に全額を返済できる見込みがない人は利用できませんので、現在、うつ病のために休職している人には不適切な方法です。
個人再生
個人再生とは、借金の返済を原則5分の1に減らす債務整理の方法です。
裁判所を通す必要はありますが、借金の負担が大きく減りますので、総借金額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)のかたは申請してみてはいかがでしょうか。
ただし、個人再生も収入がない人や減額した借金を完済する見込みがない人は利用できませんので、現時点で休職している人には不適切な方法と言えます。
自己破産
債務整理の中で唯一整理後の返済がすべて免除されるのが、自己破産です。
返済する必要がありませんから、現時点で休職している人も利用できます。
どうしても返済できない人や返済の見込みが立たない人、借金がうつ病の原因になっている人は、債務整理を専門とする弁護士に相談して、自己破産を検討してみましょう。
できることからコツコツと始めよう
あなたの無気力の原因が「お金」にある場合、ぼんやりと「何もしたくない」と時間を過ごすのではなく、少しでもお金を稼ぐことで無気力を撃退できます。
健康面で言うなら、外に出て働くのが一番良いのですが、どうしても外に出られないときは、自宅で収入を得る方法を検討して見ましょう。
スマホだけでもお金を稼げる
世の中、うつ状態になっている人は珍しくありません。
ブログであなたの気持ちを発信するなら、アクセスが増え、アフィリエイト収入やアドセンス収入を期待できるかもしれません。
また、小遣いサイト(ポイントサイト)等を活用すれば、1ヶ月に数万円の収入が入ってくることもあります。
家から一歩も出ずに稼ぎたい
スマホやインターネットを使わなくても、家から一歩も出ずに収入減を確保する方法はあります。
シール貼りや通信教育の採点等、地道に続けられる仕事もたくさんあります。
無気力と貧乏は表裏一体
親からの遺産で一生困らずに生活していける一部の人を除き、ほとんどの人は、無気力になってしまうと収入が下がり、貧乏になってしまいます。
お金がないと無気力になりますが、反対に、無気力になるとお金もなくなってしまうのです。
今以上お金のない生活を続けないためにも、無気力を排除し、ポジティブに生きていきたいものですね。
無気力に関するよくある質問
お金とうつ病は切っても切れない関係にあります。
うつ病で仕事を失った人によくある質問とその答えをまとめました。
Q.1.再就職までに、どれくらいかかるの?
個人差がありますので、一概にどの程度で再就職ができるかは明言できません。
しかし、再就職までの期間が空けば空くほど再就職は難しくなりますので、急かすわけではありませんが、できるだけ早く再就職のための行動をするようにしてください。
再就職に向けての活動が始まると、「頑張ろう」「お金を稼ごう」という気持ちが生まれ、うつ病の状態も良くなる可能性があります。
また、ハローワークに通うことで失業保険も受給できるようになりますので、金銭的な支えも生まれます。
再就職に向けた活動をしても、どうしても希望の仕事や正社員の職が見つからないこともあるでしょう。
そのときは、職種や勤務形態にこだわらずに、「非正規でも仕事をすること」にこだわり、新たな職場を得るようにしてください。
Q.2.社会復帰のためにできることは?
うつ病で一定期間社会とのつながりを絶ってしまうと、社会復帰することが怖く感じることでしょう。
しかし、怖がっていてはいつまで経っても社会生活を取り戻せません。
少しでも早く社会復帰ができるよう、次の事柄を心がけてください。
1.規則正しい日常生活を送る。
2.週に5日以上は30分以上の運動をする。
3.栄養バランスに気を配る。
4.1日に1回は外出する。
5.1日に1回は誰かと話す。
Q.3.高齢者のうつ病は入院しか改善方法が無いの?
高齢者だからといって、かならずしも入院しなくてはいけないわけではありません。
ただし、うつ病の治療には薬物治療と環境治療、カウンセリング等の精神的治療が必要になりますので、独居のかたは投薬管理が難しく、治療継続が困難になりやすいため、入院を勧められることが多いのも事実です。
家族が支援できるときは家族と一緒に暮らしながらうつ病の治療が可能ですので、まずはお住まいの市区町村の介護保険課に相談し、ケアマネジャーを紹介してもらって治療計画を立てていきましょう。
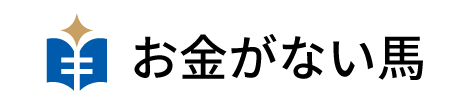



























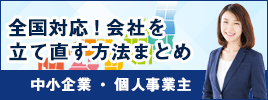

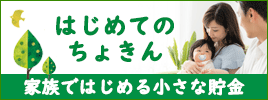


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。