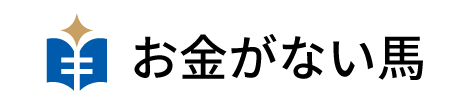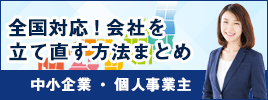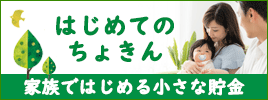社会保険料の分割は可能?滞納時の対処法
会社が払わなければならない費用の1つに、社会保険料があります。
毎月訪れる支払い、経営状況がよくないと、どうしても支払いが億劫になってしまいますね。
社会保険料の納付は義務付けられていて、例え赤字でも納付しないといけないことが定められています。
社会保険料を滞納してしまった時は、分割納付はできるのでしょうか。
また、社会保険料滞納後に起こる督促や差し押さえ、そのリスクについても解説していきます。
この記事はこのような方におすすめです。
- 社会保険料は分納できるのか知りたい
- 社会保険料を滞納すると、どうなるのかを知りたい
- 社会保険料の滞納で起こりうるデメリットを知りたい
「どうしても支払いが難しい」といった場合、カードローンを一時的に利用する人も多くいます。
5万円をカードローンの最大金利年18.0%で30日間借入した場合をシミュレーションすると、利息は750円未満です。また、無利息サービスを利用すれば一定期間利息0円なので、ちょっと借りてすぐに完済すれば無駄な出費も防げます(SMBCモビットは無利息サービスなし)。
まずは以下から公式サイトをチェックしてみてください。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
社会保険料とは?
それではまずは本題に入る前の基礎知識として、社会保険料について、簡単に説明しておきます。
会社の代表取締役やや社長にとって、義務化されているとはいえ、会社が負担する社員の社会保険料の支払いは、頭の痛いところでしょう。
特に中小企業の経営者ともなれば、他にも法人税や地方税といった、税金の納付もあるため、支払いが財務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
しかも、賃金を抑えるために雇った外国人労働者に対しても、在留資格を持つ長期滞在者の場合は、社会保険への加入が義務付けられているので、社会保険料の負担から逃げることはできません。
会社に求められる労務管理の観点からも、雇用者を守るために、必要最低限の保障と言っても過言ではないのです。
社会保険は大きく分けると、下記の5つに分類されます。
|
|
しかも、平成28年度から下記のように、社会保険料の適用変更があったため、雇用者はより働きやすい環境で働くことができるよになりました。
これら社会保険の保険料は事業主が一部負担することとなるため、確実に支払っていくためにも、雇用人数に応じた社会保険料負担額がいくらになるのかを、事業計画書等に盛り込んでおく必要があります。
- 所定労働時間が20時間以上(週単位)
- 月の賃金が88,000円以上
- 1年以上の雇用継続見込
ですが事業主にとっては、支払い負担が増えることへの懸念がぬぐえない事態であることに違いはありません。
よって、会社経営に当たっては、この雇用者に対する社会保険料負担も、重要なポイントとなってくるのです。
社会保険料の計算方法
社会保険料は事業主が算出する必要はありません。
日本年金機構などが保険料を算出して、納付額として通知されます。
しかし、日本年金機構での保険料の算出には、計算根拠となる「算定基礎届」を毎年、提出する義務が事業主に課せられています。
算定基礎届は4月から6月の報酬月額を記載したものです。
報酬月額は給与明細に記載されている、支給されるものすべてが含まれ、下記のものが該当します。
|
|
この3か月分の報酬月額平均を元に、等級が決められ、等級ごとに決められた「標準報酬月額」に保険料率を掛けて保険料が求められます。
社会保険料の分割納付について
社会保険料を滞納した場合、納付先から督促が来るようになります。
中小企業の中には社会保険料が支払えないというところも多く見受けられ、会社規模が小さいほど、その傾向は大きくなっています。
売上が上がっておらず、収益が少ないため、社会保険料の負担が、会社の財務内容を圧迫しているというわけです。
社会保険料の負担は大企業よりも、小規模事業所の方が負担割合が大きいことも、この状況にさらに追い打ちをかけている原因と言えるでしょう。
その状況を鑑み、近年は納税緩和措置として、一括で社会保険料を払えない場合は、分割での納付が認められるケースが多くなっています。
どうやれば分納に応じてもらえるのか。
ここでは社会保険料の分割納付について説明していくことにします。
滞納時の未納分は分割で支払う
分割の可否に統一的な基準はありませんが、それぞれの事業の実情・状況にあわせて分割に対応してくれます。
社会保険料を支払えず、滞納している場合は、年金事務所に行って、払えなかった理由と経営状態の実情を正直に伝えましょう。
しかし、相談に行ったからといっても、必ず分割納付に応じてくれるわけではありません。
「払えませんから、分割にしてください。」だけでは、分割に応じてくれることはないでしょう。
ポイントを抑えた交渉が必要になってくるのです。
それでは、どんな点にポイントを置けばいいのか、次はそのポイントについて説明していくことにします。
分割相談の際のポイント
ポイントは、「必ず支払おうとしている」という意思を見せることです。
ただでさえ滞納しているのですから、分割対応しても、本当に支払えるのかを、相手は疑ってきます。
まずは支払う意思があることを理解してもらえるよう、誠意ある態度で交渉に臨むようにしてください。
また分割納付が認められると、納付計画書の提出が求められます。
その計画通りに払えなければ即差し押さえになっても仕方ない状況ですので、確実に払えるよう、現実的な計画案を作って相談に行きましょう。
基本的には、毎月の保険料に未納分を上乗せする形で支払いを進めていくことが多いようです。
また、延滞金も一緒に払う必要があります。
分割の際の注意点
注意点は、保険料の支払いの際、決して個人が保証人なってはならない、ということです。
会社が不渡りを出して倒産してしまうと、会社は存在しなくなるので、支払いができません。
その場合、保証人に支払いが回ってくるため、その個人が支払いをする義務を負ってしまいます。
延滞金
正式な納付期限に間に合わなかった場合は、延滞金が発生します。
延滞金は日割りで計算されますが、利率は年利で表示されます。
延滞金の利率は、「最初の3ヶ月」と「3ヶ月を超えた場合」で分かれており、「特例基準割合」というもの次第で利率が年ごとに異なります。
「特例基準割合」とは、日本銀行が定める基準で、前年の銀行取引の際の利息を参考に決定されます。
延滞金の割合は、以下の通りに決まります。
| 期間 | 延滞金の割合 | 平成29年度の例 |
|---|---|---|
| 最初の3ヶ月 | 「特例基準割合」+1% (合計最大7.3%まで) | 2.7% |
| 3ヶ月を超えた場合 | 「特例基準割合」+7.3% (合計最大14.6%まで) | 9.0% |
滞納前にできること
この記事をご覧になっているのが滞納前の場合、対策がありますのでご紹介します
会社が労働者のために払わなければならない税金関連はいくつかありますが、その中の「健康保険」と「厚生年金」から脱退してしまうという方法です。
そんなことが可能なのかという話ですが、「会社が休業して社員が全員辞めることになった」という理由で脱退届を出すのです。
保険事務所からすれば、お金を払わないで保険を使われるより、脱退してくれた方が良いので、すんなり受け入れられます。
脱退した場合、従業員の人たちは各自で国民健康保険に入ってもらうことになります。
ですから、社員の人たちにはしっかりと話して、経営が上向いたときには必ずもう一度社保に入り直すことを伝えることです。
もしすでに滞納があった場合は、滞納分が消えるわけではありませんが、以降の支払いはなくなります。
ただし、「労災保険」と「雇用保険」に関しては最低限確保しておきましょう。
かなりグレーゾーン的な方法になってしまいますので、利用の際は注意の上、自己責任でお願いします。
産休や育休をしている従業員は免除
健康保険に関して、もし社員で産休や育休を取得して休んでいる人は、保険料が免除されます。
届出が必要ですので、忘れずにしておきましょう。
この期間は保険が使えなくなるのではなく、きちんと加入期間として扱われますので、ご安心下さい。
社会保険の滞納について
事業主の中には、「支払う資金がないんだから仕方ない。」そう考えて、社会保険の支払いを滞納している人も少なくないでしょう。
これは金融機関かからの借金ではない、国に支払う保険料だから、放っておいても大丈夫だろうという、甘い考えが影響してのことだと思います。
しかし、社会保険保険料を滞納し続けると、最終的には大変な目に遭うことになるのです。
ここでは事業主に、甘い考えを吸ってもらうためにも、社会保険料の滞納がどのようなデメリットを生むのかを、説明していくことにします。
滞納のデメリット
まず滞納した社会保険料の支払いから、逃れることはできません。
会社が存続する限り、延々と滞納分の支払いが求められます。
ここで一番注意しなければならないのは、度重なる督促にも応じず、社会保険料を滞納し続けた場合の年金事務所の対応です。
年金事務者は支払う意思がないと判断すると、会社の財産を差し押さえにかかります。
差し押さえについては、この後の章から詳しく説明していくので、ここではこれ以上触れませんが、最終的には差し押さえ処分が下されることは覚えておきましょう。
また、もう1つ押さえておいてもらいたいのが、社会保険料を延滞すると、延滞金が発生する点です。
納付期限から、納付期日の前日までの、日数に応じた延滞金が加算されます。
これは本来なら支払う必要のないお金です。
余分な支払いを増やさないためにも、できるならば社会保険料の滞納は避けたいところですね。
督促から差し押さえまでの流れと期間
社会保険料の納付期限は毎月末で、毎月20日頃に告知書が年金事務所から送られてきます。
納付できなかった場合は納付期限の翌日から延滞金が発生し、期限を過ぎてから一週間程度で督促状が届きます。
督促状や電話での納付特例が行われている時点で、年金事務所への相談など、何らかの行動を起こせれば良いのですが、もしそのまま放置してしまった場合はどうなるのでしょうか?
そうです。
先ほど話した、国税徴収法に基づく、差し押さえ処分への段階を上ることになります。
しかし、すぐに差し押さえが実行されるわけではありません。
ここでは社会保険料の滞納から、差し押さえが実行されるまでの、流れについて説明していくことにします。
財産調査
督促状が到着してから10日ほどたつと、差し押さえられる財産がないか調査が始まります。
これを「財務調査」といい、2段階にわけられます。
最初は任意調査とも呼ばれ、会社や経営者や関係者の自宅に調査が入り、財産の様子が調べられます。
この際、財産に関する様々な質問(所持している不動産はあるのか、債権の様子についてなど)をされますが、意図的に財産を隠蔽したり虚偽申告をしてはなりません。
立派な違法行為になり、刑罰の対象になります。
この調査だけで十分でない場合、さらに調査は続きますが、この次は強制捜査です。
会社や関係者の住居に立ち入り、完全に財産の有無を調べつくされてしまいます。拒否権はありません。
差し押さえ
このように財産の様子を丸裸にされた後、充当できそうな財産があれば、差し押さえになります。
多くの場合、対象になるのは、銀行の預金や不動産、有価証券、保険金などです。
差し押さえになることのデメリット
社会保険料を払えないと一大事になることはわかりました。
ですが、会社は社会保険料だけを払っているわけではありません。
他にも銀行への支払だったり、他の税金の支払いだったりをしているので、経営が苦しいときにはどうしても優先順位を付けざるをえない時がありますよね。
ここでは社会保険料を滞納し、差し押さえになった場合に、発生しうるデメリットについて検証していきたいと思います。
銀行からの信用を一瞬で失う
差し押さえが実行されると、まず最初に差し押さえられるのが預貯金です。
会社名義の預金口座が凍結され、預金残高が滞納額に充当されます。
そうなると、取引銀行に差し押さえになった事実が知れ渡ってしまいますよね。
差し押さえが銀行にバレるのは、会社にとっては大打撃です。
その銀行からの信用は0になったと行っても過言ではありません。
今後の融資にも支障が出るでしょうし、現在受けている融資についても、条件変更が求められる可能性も考えられます。
どちらにしても、必要な運転資金を銀行から調達できなくなる可能性があるため、今後の会社運営にも大きな影響が出てくることは必至でしょう。
税関係は即差し押さえになる可能性
銀行から借入金は、延滞した場合でも少し猶予してくれたり、相談に応じてくれることが多くあります。
また、差し押さえになるまで、一旦裁判所からの許可を得ないといけないので、少し時間がかかるのが一般的です。
それに比べると、税金関連は国税徴収法によって、税務署に自力執行権が認められています。
つまり、支払いが認められないと判断した場合は、裁判所からの許可なく、自力で差し押さえまで持っていけるのです。
よって、即差し押さえになる可能性があります。
助成金の申請ができなくなる可能性
企業にとって公的機関などからの助成金はありがたいものですよね。
ですが、社会保険料の滞納によって助成金の申請ができなくなることがあります。
助成金の申請の条件の多くに、「過去◯年間、社会保険料の滞納がないこと」という項目があるからです。
既に助成金をもらっている場合や、助成金が欲しい場合は、こちらの面に関しても検討しておきましょう。
金利は少し安いけれど・・・
銀行借入を滞納した場合、遅延損害金の多くの場合は年14.6%です。
社会保険料の延滞金も最大14.6%、3ヶ月を超えても平均すると9.0%前後が多いですから、金利に関してだけ比較すれば少し安いかもしれません。
ですが、以上のように様々な理由・リスクが生じます。
その多くは、将来の経営に大きな不利益になるものです。
不利益を被らないためにも、社会保険料の滞納はなんとしても避けなければなりません。
社会保険料滞納の現実
これほど厳しい滞納処分の背景には、社会保険料滞納の実情が影響しています。
数年前まで滞納事業者数は増加傾向にあって、平成23年度には186,805件もの事業所が、社会保険料の滞納をしていました。
それにより、滞納処分の迅速化を進め、分割対応にのるなど納付指導を強化した結果、平成28年度には134,940事業所にまで減少したのです。
この対応で注目してもらいたいのが、差し押さえ事業所数です。
平成28年度の差し押さえ事業所数は25,174事業所で、ここ3年間で最多となっています。
日本年金機構の業務実績報告書には、「滞納困難な申し出があった場合は、経営状況や将来の見通しを丁寧に聞き取り」「きめ細やかな指導を行うこと」が明記されています。
しかし、見逃してはならないのは、滞納処分など徴収対策を徹底することも記載されている点です。
社会保険料滞納による差し押さえは、かなり厳しく行われているというのが実情といったところでしょう。
ですが分割の相談にも応じてもらいやすくなっているのも事実です。
払えない時は一人で抱え込まず相談にいきましょう。
Q&A
それでは社会保険料の滞納で、よくある質問を挙げて、回答しておきましょう。
年金事務所に相談に行くようににしてください。
しかし、ファクタリングに用いる売掛金や受取手形は、差し押さえの対象となります。
差し押さえが決定してからファクタリングを行えば、所得隠しとして問題になりますが、督促状が届いた時点ならば問題はないでしょう。
条件のいい金融機関でファクタリングし、それを滞納分の支払いに充てるのもおすすめです。
まとめ
ここまで社会保険料滞納について書いてきました。
近年は滞納処分も厳格化されており、差し押さえになる可能性は十分あります。
ですので、払えなかった時は年金事務所に相談しに行き、分割の申し出をしましょう。
きちんとこちらの状況を伝えた上で、しっかり払う意思を伝えれば、十分に可能です。
同時に、健康保険や厚生年金を脱退する場合は、従業員の人に対しても、しっかりと説明をしましょう。
大事なのは一人で抱え込まないことです。
誠実さと真摯な態度で対応しましょう。