就業規則の見直しポイント
就業規則の意義を理解する
就業規則は、従業員との間の労働契約の一種です。
つまり、就業規則に記載した事柄は、基本的に従業員との約束事であると理解をしなければなりません。
よく、就業規則は会社のルールであり、自分の考えを好きに書き込んでいいと思っている経営者の方がおられます。
もちろん、それはそれでよいのですが、労働契約である以上、一度書き込んでしまうと労働者に不利な方向には、非常に変更しづらくなるという事実をしっかりと押さえて下さい。
できれば労働条件に関する条文については、その水準はできるだけ低いところからスタートをした方がベターです。
またあまり深く考察をしないで、インターネットからそのままひな形をダウンロードして使用している会社も見受けられますが、そうすると自分の会社には噛み合わず思わぬ落とし穴に出くわすこともあります。
以上のことを踏まえて頂き、この機に自社の就業規則を是非見つめ直していただくことをお勧め致します。
それでは、就業規則を見直しする際に、「もしそうなっていなかったら是非、この際に修正して頂きたい」ポイント、見直しの着眼点について、いくつか具体例を挙げていきたいと思います。
総則関連の見直しポイント
パートタイマー等について適用除外としていない
中小企業では、正社員用の就業規則が1つあるだけで、パートタイマーやアルバイトを実際に雇っていても、パートタイマー用、アルバイト用の就業規則を別に設けているところは少ないのではないでしょうか。
ただ、そうした内容のままにしておくと、パートタイマーから、「自分も就業規則に出ている(正社員用に設けた)労働条件が適用されるはずだ」と主張され、正社員と同じ扱いにしなければならなくなる可能性が出てきます。
もしパート社員がいる場合には、「パートタイマーについては本規則を適用せず、個別に締結した労働契約書の規定に従う」という文言を挿入してリスクヘッジをしておくべきでしょう。
試用期間の位置づけが不明確
試用期間は、採用した者が会社に適応することができるか否かを見極めるためのものですので、不適格者については、退社をしてもらう可能性を踏まえておく必要があります。
そのためには、試用期間中に不適格と判断した場合には解雇する旨と解雇事由について記載しておかなければなりませんが、よくこの表現が洩れている就業規則を見かけます。
この表現が無いと試用期間中の解雇はできません。
また、試用期間中観察し、やや疑問が残るのでもう少し観察を続けたいということがあるかもしれません。
こうした場合には、試用期間の「延長の可能性」についても、就業規則に盛り込んでおいた方が便利です。
入社に際して必要書類の提出期限を規定していない
入社時に提出させる必要書類については、たいていの就業規則に記載されていますが、この書類の提出期限が規定されていないものをよく見かけます。
必要書類なのに提出が遅れると手続きに支障を来たすことになります。
こうしたトラブルを防ぐために、例えば「上記の書類は入社日までに提出しない場合には、雇用の打切りをすることがある」などの文言を条文内に記載しておきます。
また、当該新入社員には予め通知書などで同様の内容を伝えておくようにします。
労働時間関連の見直しポイント
記載がないとシフト勤務や残業をさせられない
始業時刻と終業時刻については「業務の都合により変更することができる」旨を必ず記載しておきます。
もしこれがないと、例えば勤務時間を午前9時から午後6時と規定したら、それ以外の時間帯(たとえば午前10時から午後7時のシフト勤務)での労働は一切認められないこととなってしまいます。
また、時間外労働に関する条文も必ず記載してください。
時間外労働をさせるには36協定だけを締結すれば良いと思っている経営者がいますが、就業規則に時間外労働をさせることができる根拠を設ける必要があります。
これがないと時間外労働をさせることができなくなりますので、ご注意下さい。
服務規律規定に不備がある場合
服務規律は、社内において従業員に守らせるルールです。
このルールについても、できるだけ具体的に、かつ洩れなく記載をしておいた方が、いざというときに役立ちます。
会社の損害をできるだけ出さないという観点で、必ず入れておきたい服務規律事項として競業避止義務があります。
競業避止義務とは、従業員が退職した後の一定期間、競合他社への就職を禁止し、顧客情報の持ち出しや知的財産権の侵害を防ぎます。
これに違反し会社が損害を受けたら、損害賠償や退職金返還を求めていくべきものですが、就業規則にその記載がないと、こうした損害賠償や退職金返還請求を行っていくことができません。
また守秘義務についても、同様の理由から必ず記載をしておくべきです。
懲戒事由規定に不備がある場合
前項と同様のことは、懲戒に関する規定における懲戒事由にもいえることです。
これは刑法における罪刑法定主義を準用するものであり、どんな事由、つまり罪に対してのものかを明確にしなければ、懲戒することはできないことになっています。
できるだけ具体的に懲戒事由は列挙しておきたいところです。
特に懲戒解雇事由は、社会人として死刑宣告をするようなものですので、なぜ懲戒解雇なのかの根拠をしっかりと定め、一点の曇りもない状態としておくことが、リスクを最小限にしていきます。
まとめ
ここでは、良く見かける就業規則の落とし穴についていくつかの例をご紹介致しましたが、本項で言及した内容を意識してご自分の会社の就業規則を読み返すと、多分気になる点はまだ他にもでてくるのではないかと思います。
就業規則は、正しい認識で作成すれば経営にとって大きな武器にもなりますが、作り方を間違えると、とんでもない爆弾を抱えるものにもなりかねない性質をもっています。
是非これを機会に貴社の就業規則の内容を洗い直して頂き、リスクヘッジの効いたものに改めて頂きたいと思います。

社労士事務所 早稲田労務経営所長
池内 恵介
特定社会保険労務士、中小企業診断士、人事コンサルタント。
早大法学部卒業後、㈱三越に入社、企業内労組の幹部役員経験も含め人事・労務畑中心のキャリアを積み、三越の4回に亘る人事賃金制度改正などにも実務担当として関わる。
三越退職後、マーケティングコンサルティング会社取締役、セガ・サミーグループの関連メーカー総務人事部長などを勤めた後、独立。
人的リストラ対策を含めた労務問題への対応を大企業、中小企業双方のキャリアの中で数多く手がけてきたことを強みとする。
著書には「中小企業のための人事労務ハンドブック(同文館出版)」「人件費適正化マニュアル(すばる舎リンケージ)」等がある。
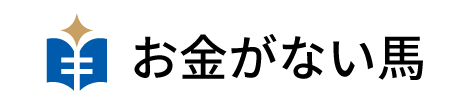






















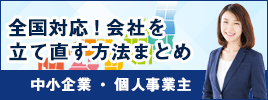

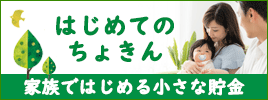


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。