パート社員と社会保険
非正規社員が増えています
パートタイマーや派遣社員等の非正規社員が増えていると言われてから久しくなります。
総務省の「労働力調査」によると、平成元年に817万人、働いている人全体の19.1%であった非正規社員は平成30年には2,120万人、全体に占める割合は37.9%に上昇しました。
実に4割近くが非正規社員となっています。
既に正規社員、非正規社員と区別することに意味がない状況になっています。
この背景には、会社の事情、働く人の事情による種々の要因が絡んでいます。
(1)会社の事情
① 国際的な競争激化を背景に人件費の抑制
② 景気の先行き不透明を背景に雇用調整が容易
③ 機械化、マニュアル化が進み、熟練度を必要としない
④ 女性、高齢者の採用増
⑤ 能力のある派遣社員の利用
(2)働く人の事情
① 正規社員の門戸が狭く、仕方なく
② 育児や家事と両立を図り、好きな時間だけ働きたい
③ 会社に拘束されず、好きな仕事を選びたい
④ 社会経験を得るため
⑤ 自分の能力を活かしたい
⑥ 家計の補助やお小遣いのため
働く人の事情の②~⑥のケースでは、低賃金や社会保険・雇用保険への加入はあまり問題になりませんが、①のケースは別です。
ディップ総合研究所が2019年3月に実施したインターネット調査によると、正社員として働きたいと回答した有期雇用契約社員は実に約6割に上ります。
その理由は、①雇用の安定、将来の安心(66.7%)、②給与のアップ(62.4%)、福利厚生の充実(39.0%)となっています。
好むと好まざるにかかわらず非正規社員として働かざるを得ない状況があるので、将来のことも含めて、非正規社員として働くときの雇用条件を考えることは非常に意味あることになります。
非正規社員とは
既に非正規社員の割合が4割近くを占めている現状で、正規社員、非正規社員と区別することに意味がないことは上に書きました。
ここでは、話を進めるに当たって社員の分類と本稿での定義を次のようにしておきます。
(1)勤務時間による分類
① フルタイム社員:その事業所において所定労働時間が最も長い雇用形態の社員
② パートタイム社員:勤務時間がフルタイム社員より短く、週20時間以上の社員
③ アルバイト社員:勤務時間が週20時間未満の社員
(2)雇用主による分類
① 直接雇用社員:雇用主と勤務先が同一の会社で働く社員
② 派遣社員:雇用主と勤務先が同一でない会社で働く社員
(3)雇用期間による分類
① 無期雇用社員:期間の定めのない雇用契約で勤務している社員
② 有期雇用社員:期間の定めのある雇用契約で勤務している社員
正規社員の定義は法令で規定されておりません。
通常はフルタイムで直接雇用かつ無期雇用されている社員が正規社員、それ以外が非正規社員です。
単にパートタイム社員と言うだけでは、無期と有期雇用契約がありますし、派遣社員にもフルタームとパートタイム社員がいます。
本稿では、社会保険、雇用保険を論じますのでパートタイム社員とアルバイト社員に焦点を当てます。
社会保険
加入要件
社会保険とは健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称ですが、ここでは狭義の健康保険、介護保険、厚生年金保険を社会保険とします。
社会保険に加入する要件は、1ヶ月の勤務日数と所定勤務時間が正規社員の4分の3以上あることです。
事業所での正規社員の勤務日が月~金曜日までの週5日、一日8時間であれば、月の所定勤務日数は概ね21日、所定労働時間は168時間務前後です。
すると、パートタイム社員の勤務日数が月に16日以上、かつ1ヶ月の労働時間が126時間以上で社会保険に加入するのが原則です。
ところが昨今の雇用形態の多様化を受けて、所定勤務時間と勤務日数が正規社員の4分の3未満であっても社会保険の加入できる2つの道が拓かれました。
特定適用事業所
全社の社員数(社会保険の被保険者数)が500名以上の会社は、特定適用事業所となります。
特定適用事業所に勤めているパートタイム社員は、所定勤務時間と勤務日数が正規社員の4分の3未満であっても
① 週の所定労働時間が20時間以上ある
② 月の給与が88,000円以上ある
③ 雇用期間が1年以上見込まれている
の条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。
任意特定適用事業所
全社の社員数が500名に満たない会社であっても、社員の代表者または過半数の同意があれば、任意特定適用事業所になれます。
任意特定適用事業所に勤めているパートタイム社員は、特定適用事業所のときと同じ条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。
任意と言っても社員の都合で加入・不加入を選択することができるわけではありません。
社会保険のメリット
これはパートタイム社員に限ったものではありませんが、社会保険に加入するメリットは多くあります。
主なメリットを次に示します。
保険料
社会保険に加入していないパートタイム社員は扶養されていない限り国民健康保険、20歳から60歳までは国民年金保険に加入しなければなりません。
国民健康保険料も国民年金保険料も全額が本人負担です。
これに対して、社会保険では保険料は会社と折半です。
更に、配偶者や子供を扶養していても被扶養者のための保険料の負担増はありません。無料です。
配偶者は、国民年金保険の第3号被保険者として保険料の負担なしに65歳以降に老齢基礎年金を受けることができます。
傷病手当金
不幸にして病気や怪我で働けなくなることは生身の人間ですからあり得ます。
病気や怪我で仕事を休み給与が支給されなくなったときは健康保険から傷病手当金が支給されます。
支給額は概ね給与の3分の2、支給期間は1年と6ヶ月です。
働けなくても収入があることは助かります。
障害年金
1年と6ヶ月間の傷病手当金の受給期間を過ぎても病や怪我が癒えない、あるいは障害が残ってしまったときには厚生年金保険から障害年金を受けることができます。
国民年金保険にも障害年金制度はありますが、障害の程度は1級、2級しかなく受給要件は厳しいものです。
厚生年金保険ではもう少し軽い障害でも受給できる3級が設定されていますので、受給要件が緩くなります。
障害年金は、障害の程度が変わらない限り支給されます。
出産手当
出産したときは1児当たり420,000円の出産育児一時金が支給されます。
また、出産のために仕事を休み給与が支払われないときは、出産手当金が支払われます。
出産手当金の額は概ね給与額の3分の2です。
出産予定日前42日(6週間)から出産後56日(8週間)が出産手当金の対象期間です。
埋葬料
縁起でもありませんが、本人が死亡したときは家族に50,000円の埋葬料が支給されます。
被扶養者が死亡したときも家族埋葬料として50,000円が支給されます。
雇用保険
加入要件
週の所定労働時間が原則として20時間以上のときが加入できる要件の一つです。
パートタイム社員やアルバイト社員は、勤めている間に徐々に勤務時間が長くなることがあります。
アルバイトとして1日5~7時間、週に2~4日の条件で入社したときは週の所定労働時間が平均で20時間に満たないため雇用保険に加入することができません。
ところが、働いている間に、実質的に一日の所定労働時間が7時間以上になることがあります。
こうなると週の所定労働時間は平均21時間以上となり雇用保険の加入要件を満たすことになります。
ところが明示的な雇用条件の変更でないために雇用保険の加入手続きをしないで時が経過することがしばしば起こります。
繰り返しますが、雇用保険の加入要件の原則は週の所定労働時間が20時間以上であることです。
所定労働時間ですから、雇用条件で時間が定められていることが原則です。
が、実質の労働時間が週20時間を満たしていれば雇用保険に加入できることが実務で認められています。
更に実質的に週20時間以上働いているときは、最長2年間に限り遡って加入することが可能です。
会社に事情を話し、実質的に週20時間以上の勤務時間になった時点での雇用契約書の交付を受けて、加入手続きをとることが実務で行われています。
会社が、遡っての加入を認めないときはハローワークの職権で加入する手段も残されています。
雇用保険のメリット
これもパートタイム社員に限ったものではありませんが、雇用保険に加入するメリットは多くあります。
主なメリットを次に示します。
失業給付
雇用保険の主な目的は失業したときに次の仕事に就くまでの給付いわゆる失業給付です。
失業給付を受けるためには、単に雇用保険に加入しているだけではなく、つぎの要件があります。
① 原則は、辞めた日から遡って24ヶ月間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること
② 解雇や倒産等のために予期していない退職となったときは、辞めた日から遡って12ヶ月間に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あること
11日以上勤務した日には有給休暇の取得日が含まれます。
正確には「給与の支払い基礎日数」が11日以上です。
月給者は通常はこの要件を満たしますが、パートタイム社員は時給であったり日給であったりすることが多いので、この要件が壁になることがあります。
例えば、1日8時間、週2~3日の勤務では、週平均所定勤務時間が20時間となり雇用保険の加入要件を満たします。
ところが、カレンダーによっては皆勤しても10日しか勤務できない月があります。
欠勤や休日が加わると勤務日はさらに減ります。
勤務日数が11日に達しない月は、月数に数えませんので1年以上勤務していても受給要件を満たさないことが起き、実際に受給できない事態が発生します。
給付額は、退職前6ヶ月の給与平均の45%~80%です。
給与が少なかった方の率が高くなります。
支給期間は、雇用保険に加入している期間や年齢により、90日~330日になります。
育児・介護休業手当
在職者にも雇用保険のメリットがあります。
育児や介護に際しては育児・介護休業法で休業を取得することは法律で認められていますが、給与の保証はありません。
雇用保険では育児や介護で休業する社員に手当を給付する制度があります。
支給期間は、育児・介護休業法で定められた育児休業であれば最長2年間、介護休業であれば最長93日間となります。
支給要件は、休業に入った日を退職した日と読み替えて失業給付と同じ要件が課せられています。
高年齢雇用継続給付
60歳のときに比べて給与が75%以下に社員には65歳に達するまで給与の最大15%が支給される制度です。
次の支給要件があります。
① 60歳時点で雇用保険の加入期間が5年以上ある
② 60歳以降に失業給付を受けていない
給付を受けるには会社または本人のハローワークへの申請が必要です。
教育訓練給付
在職中または退職後にキャリアアップを目指して教育訓練を受講し終了したときに受講料の20%(上限10万円)が教育訓練給付金として支給されます。
次の支給要件があります。
① 在職中の方は訓練開始時に雇用保険の加入期間が1年以上の空白がなく3年以上
退職者は、退職日以前に雇用保険の加入期間が1年以上の空白がなく3年以上あり、退職日から1年以内
② 受講する教育訓練は厚生大臣の指定するもの
教育訓練には更に受講料の50%(一年間の上限40万円、総支給上限120万円)の専門実践教育訓練給付金制度があります。
まとめ
パートタイム社員、アルバイト社員の中には今の手取り額を減らさないために社会保険や雇用保険に加入することを嫌う人もいるようです。
しかしながら、上で見たように、社会保険や雇用保険のメリットは多くありデメリットを差し引いても余りあります。
要件を満たせば強制加入ですので加入・不加入を選ぶことはできませんが、可能であれば加入のできる雇用条件を選ぶことが得策です。
昨今、人手不足が顕著になってきました。売り手市場です。
安易に転職を勧めるものではありませんが、社会保険や雇用保険に加入していない方は、これからは今の会社での雇用条件を向上させるか、転職により社会保険・雇用保険に加入する選択肢を視野に入れておくことも必要でしょう。

社会保険労務士
丸山峰雄
化学・製薬兼業会社の工場、研究所、本社勤務を経て、平成20年に丸山事務所を開設しました。
開設後、春日部労働基準監督署において総合労働相談員、36協定指導員として9年間勤務し、その間に年間数百件の相談を受けました。
-保有資格-
・特定社会保険労務士
・中小企業診断士
・労働安全コンサルタント
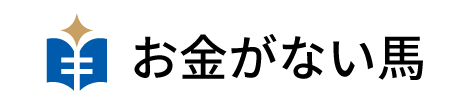























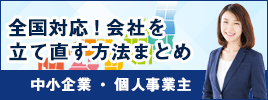

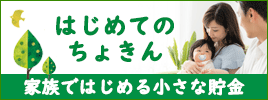


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。