人生100年時代―老後に必要とする生活費は?
最近至る所で“人生100年時代”の言葉を聞きます。
平均寿命が延びる中、老後にいったいいくら必要になるのでしょうか。
記事の目次
退職時期は物価上昇率と貯蓄額で決まる
現在の物価上昇率はおおよそ1.0%(2018年データ)となっています。
現在の生活費を支払うために、将来掛かるであろう費用は下記のとおりです。

物価がどこまで上昇するか未知数ではありますが、今後人口が減少するにつれ大量生産から多品種少量生産へシフトしていくことが考えられます。
多品種少量生産は大量生産より一つ当たりのコストが割高になります。
また、今後人口に対する生産年齢人口がさらに低下していきます。
ある程度歯止めがきくまでの期間、需要に対し供給が不足し、モノの価格が高騰する可能性があります。
当然ながら労働力の不足により、ある程度の賃金の上昇による人件費高騰も見込まれます。
基本的に物価は上昇を続けるとみて問題ないでしょう。
人生100年時代に懸念されること
年金額の減少に伴う貯蓄からの持出増加
- 現在のマクロ経済スライド率と今後の見通し
(2019年度年金受取額は-0.3%、2018年は-0.2%の経済スライド導入)
下記条件の下で試算した結果、厚生年金加入者の家計からの持出額は下図のとおりとなります。 - マクロ経済スライド率は-0.2%/年
- 物価上昇率は1.0%

現在、手厚いと言われている厚生年金でも、受給者の貯蓄持出は26千円/月発生しています。
注目すべきなのは、40年後、物価上昇とマクロ経済スライドによる年金額の減少により、貯蓄からの持ち出し額が年間80万円近くになること。
個人の負担が決して軽くはないことが分かります。
介護期間の長期化と物価上昇
平均寿命が延びるにつれて健康寿命が延び、介護期間が縮まっているわけではありません。
また、一人当たりの介護費用が圧縮されているわけでもありません。
ひとりあたりの介護にかかる個人負担額は下記のとおりです。
- 在宅介護・・・5万円程度 /月
- 施設介護・・・18~20万円/月(入居一時金を除く)
介護保険の支給を受けても、なぜここまで個人負担が発生してしまうのでしょうか。
それは、介護保険が在宅介護を前提として組まれた保険であり、居住費、食費、雑費などは介護保険の適用対象外で、全額自己負担となるからです。
現在の施設利用者の平均支出19.2万/月を基準に算出すると、それぞれの年齢ごとの必要額は下記のとおりとなります。

現在50歳の方で60歳で退職なさるサラリーマンの方は、60歳から100歳までのあいだに、7000万円近く支出がある計算になります。
60歳で退職しても家計がもつのか、それともそれ以降も働く必要があるのかを十分検討し、退職時期を決定するのが大切であると言えそうです。
また、これからの世代の年金負担が増え続けるのは必然です。
これからの世代、自分の子供からの援助を過度に期待しないようにしましょう。
老後費用を賄うために
下記の資産運用をしましょう。
定期預金
短期間のキャンペーン利率に踊らされるのはやめましょう。
金利が低いため利息は付き辛いですが、普通預金よりはましです。
元本も保証され利息も普通預金より高いため、定期預金を資産運用の一部に組み込むメリットは高いでしょう。
デメリットとしては、元本が保証される半面、インフレに非常に弱く、価値が目減りする可能性があります。
定期預金の比率は全額ではなく一部にし、資産の形成のためにほかの手段も取り入れていきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは長期型投資信託です。
利率が高い半面、途中解約ができなかったり株式市場の暴落により損失を被る可能性があります。
必ず定期預金と並行し、リスク分散をしましょう。
また基本的に、運用手数料が発生します。
コストとリターンを計算し、期待したリターンが得られるか確認しましょう。
資金に余裕がある場合は下記の運用も取り入れていきましょう
投資信託
中長期が望ましいでしょう。
投資信託のなかでもハイリスクとローリスクを分散して購入しましょう。
買い場が分からない場合、積立投信なども活用できるかもしれません。
株式
短期での売買は安定した運用に不向きです。
中期程度の運用にしましょう。
最初から値上がり益を狙いに行くのはやめましょう。
自分の周りにある企業で株主優待があり、かつ落ち目でない企業を探しましょう。
配当金のほかに株主優待などで還元され、家計に余裕ができます。
債券
債権の代表としては国債や社債などが挙げられます。
定期預金よりも利回りが高いことも多く、運用に適しているでしょう。
ただし企業の倒産などにより債務不履行に陥り、投資額を回収できなくなる場合もあります。
株式よりは安定していますが、そのようなリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
貴金属
代表的なものとして、プラチナ・金・銀などが挙げられます。
これらは金利等がつかないため、資産を増加させるというよりは安定資産としてポートフォリオに組み込むのがよいでしょう。
不動産
これから人口減少にあたり、トータルで見ると不動産需要は低下していくものと思われます。
不動産の購入等で資産運用なさる場合、立地条件などを十分に調べ、慎重に検討が必要かもしれません。
まとめ
いったん退職してしまうと、再就職は難しくなるかもしれません。
現在の生活費を計算し、多少の物価上昇に備えられるように資金に余裕を持ちましょう。
また、介護期間にかかる費用も侮れません。
早いうちから資産運用などを行なって自分の老後に備えましょう。

ファイナンシャルプランナー
安彦 志俊
2014年ファイナンシャルプランナー(AFP)取得。
“人生を楽しむために、お金の使い方を考える”をモットーに、家計の見えない無駄を抑えつつ、生活を楽しむ余裕を持てるような提案を行なう。経済・金融の知識や投資経験を生かしながらの資金設計やバランスシートの作成・提案には定評がある。
“プライバシー重視コース”も用意し、氏名・住所を開示せず、メール・データ送信のみで相談できるシステムも完備。たくさんの個人情報を扱うにあたり、システムの充実により情報漏洩への不安払拭に努める。
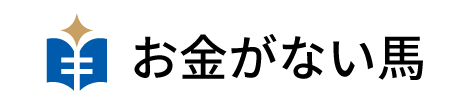























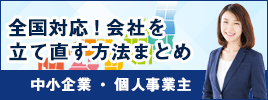

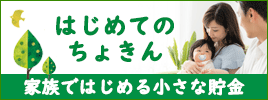


※₁お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。