子供が税金を払わない、親への影響はあるの?
一緒に住んでいる子供が税金の滞納をしている、その支払い義務は親にも及ぶのだろうか。
個人に課せられる税金は下記のように少なくないので、もしそうなら呑気に構えているわけにはいきませんよね。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 自動車税
基本的に親族へ税金支払い義務が及ぶことはないので、親が子供の税金不払いを心配する必要はないでしょう。
しかし、相続税と贈与税は話が違ってきます。
そこで今回は、どのようなケースで親へ子供の税金支払い義務が発生するのか、その場合の対処法と併せて詳しく説明していきます。
即日OK!審査通る?カードローン
| カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
|---|---|---|
 アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
 プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
 SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
親に支払い義務が発生するケース
国民が国に対して支払い義務を負うものには税金をはじめとして、下記のようなものが挙げられます。
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
このうち国民年金保険料に関しては子供が不払いのままだと、同居している親族に支払い義務が課せられることになります。
これは同居している親または配偶者に連帯納付義務が課せられているからです。
しかし、個人が支払う一般的な税金には、この連帯納付義務が課せられていないため、子供が税金を払わないからといって、親に支払い義務が生じることはありません。
基本的に親が子供の税金未納に頭を悩まされることはないでしょう。
ですが相続税と贈与税には連帯納付義務が課せられています。
このケースにおいては親が子供の税金未納に対して、支払い義務が課せられるケースも出てくるのです。
知っているかたも少ない連帯納付義務
連帯保証人という言葉はよく耳にするでしょうが、それに似た連帯納付義務という言葉は知らないというかたも少なくないでしょう。
連帯納付義務は税金支払いにおける連帯保証人のようなもので、誰かの税金不払いに対して、誰かが支払い義務を負うことを指します。
よって、連帯納付義務を課せられたかたは、その対象者が税金を未納した場合、その税金を支払わなければなりません。
税金で連帯納付義務が課せられているのは相続税と贈与税となりますが、その連帯納付義務を課せられるのは、下記のように違ってきます。
- 相続税 相続人全員がお互いにその義務を負う
- 贈与税 あげた側がもらった側に対してその義務を負う
子供が親より先に死んで、子供の財産を相続するというケースも考えられますが、この定義からすれば親が子供の税金支払いの連帯納付義務を負うのは、親が子供に贈与した際に支払い義務が発生する贈与税が大半となってくるでしょう。
親が子供へ贈与して、子供が贈与税の支払いを怠れば、親が代わりに贈与税の支払う羽目になるといった具合です。
贈与した上、税金の支払い義務まで背負わされるなんて、なんだか納得いかないところですが、この点はよく覚えておいてください。
財産の差し押さえを喰うのは誰?
税金を滞納すると最悪の場合、財産が差し押さえされることになります。
差し押さえまでの流れは下記のとおりです。
|
親に督促状が届いた時に支払いが済ませられれば、財産の差し押さえは行われませんが、親が支払い拒否をすれば財産の差し押さえが実行されることになります。
そしてここで気になってくるのが、誰の財産が差し押さえられるのかという点です。
子供が贈与税を支払わないからといって、いきなり親の財産が差し押さえられたのでは、たまったものではありませんよね。
しかし、安心してください。
差し押さえが行われるのは、本来の納税者である子供からです。
いきなり親の財産が差し押さえられることはありません。
よって、子供のいい加減さを正してやるためにも、敢えて支払いを拒否するというのもありでしょう。
ですが子供に差し押さえする財産がない場合や、換金しづらい不動産しかない時には、親へ財産の差し押さえが実行されることになるので注意が必要です。
子供に差し押さえできる財産なしと国税庁が判断すれば、手痛い目に遭うことになるので、支払い拒否をする際には子供の財産事情を確認しておくようにしましょう。
差し押さえは勤務先にも影響が!
また差し押さえとなる際、最もその対象とされやすいのが給与です。
役所が勤務先に下記情報の照会書類を送付し、調査後に勤務先が役所に給与を直接支払うといった流れになります。
- 給与額
- 給与支払日
そしてここで押さえておいて欲しいのは給与が差し押さえられるだけでなく、勤務先に税金滞納が知られてしまうという点です。
自分が税金滞納したわけでもないのに、勤務先にはあたかも当人が税金滞納したかのように思われてしまいます。
これは勤務先からの評価にも影響することになるので、よく覚えておいて欲しいポイントとなってくるでしょう。
差し押さえされる給与額は?
差し押さえとなって最も気になるのが、差し押さえされる額面です。
「給与全額が差し押さえられるのでは?」と心配されるかたもいるでしょうが、差し押さえできる額は国税徴収法第76条第1項で、給与の差押え禁止の範囲及び金額が規定されています。
下記条件に基づいて、差し押さえ可能額が決定されるのです。
| 1号 | 所得税の額 |
|---|---|
| 2号 | 住民税の額 |
| 3号 | 社会保険料の額 |
| 4号 | 最低生活費 |
| 5号 | 体面維持費 |
それでは実際に総支給額480,000円の場合、どれくらいの差し押さえが可能となってくるのかを試算してみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1号:所得税の額 | 17,000円 |
| 2号:住民税の額 | 25,000円 |
| 3号:社会保険料の額 | 43,000円 |
| 4号:最低生活費 | 235,000円 |
| 5号:体面維持費 | 32,000円 |
| 合計 | 352,000円 |
上記額面が差し押さえが禁止されているので、差し押さえが可能になるのは下記金額となります。
480,000円 - 352,000円 = 128,000円
給与差押となれば未納額が完済されるまで、上記計算によって給与の一部が税金支払いに充てられます。
ここで注意してもらいたいのは、支払いは個人ではなく勤務先の事務方が毎月対応することになり、勤務先にも過分な事務対応が強いられることになる点です。
勤務先からは決していい顔はされないことは、簡単に予測がつきますよね。
差し押さえは個人だけでなく、勤務先へも迷惑をかけてしまうことになることを、よく覚えておきましょう。
差し押さえを避けるには
税金滞納による差し押さえは法律に基づいて行われるため、実行段階に入ってしまえば避けることはできません。
差し押さえとなるのは、督促状を出しても支払いに応じないと判断された場合のみですから、差し押さえを避けるためには、実行が決定される前に自らの対応が必要になってきます。
放っておけばどうにかなるという問題ではないため、差し押さえを避けたいのであればこの点をよく理解して、これから説明する対応策を検討するようにしてください。
差し押えとなる前に相談
差し押さえとならないようにまず行って欲しいのが、役所への相談です。
支払えない現状を相談すれば、下記の様な対応を取ってくれる可能性も出てきます。
- 分納
- 減額
- 免除
先ほど差し押さえられる給与額でも説明しましたが、差し押さえという強制執行においても、一度に全ての未納額の差し押さえがされるわけではありません。
生活していく上で最低限必要となる額は、差し押さえすることが法律で禁止されているからです。
よって、支払う余裕がないとか、一度に支払えないといった事情があれば、役所も柔軟な対応を見せてくれます。
何度も言うようですが税金未納で最もやってはならないのは、支払督促を放ったらかしにすることです。
この点を肝に銘じて、まずは支払い相談をしてみるようにしましょう。
差し押さえを停止してもらう
また下記法律にはある一定条件に該当すれば、差し押さえを停止できる旨が規定されています。
- 地方税法第15条の7第1項第2号
- 国税徴収法第152条第2項等
その一定条件は「滞納処分が生活を著しく窮迫させる恐れがある時」とされており、これに該当すれば差し押さえ処分の停止を受けることができるのです。
しかし、この差し押さえ処分の停止を受ける場合には、実際に差し押さえにより条件に該当する事実を証明しなければならないので、闇雲に窮状を訴えただけでは停止処分となることはありません。
税金滞納している事情は個人によって違ってくるので、どのような書類を用意すればいいかは、個人によって様々です。
証明できるものがなくては、徴税担当者が停止にしたくてもすることができません。
まずはどのような状況なのかを職員に相談し、どんな書類が必要になるのかを聞いてみるよにしてください。
支払いたくても支払われないという場合には、しっかりとした事前準備を怠らないようにしましょう。
死んだ両親が滞納した税金は誰が支払うの?
ここまで説明してきたように、子供が税金を支払わないことで親に影響を及ぼすのは、大抵の場合は子供に贈与税の未納がある時です。
しかし、このケースでは贈与する財産があるくらいですから、未納による財産差し押さえとなる最悪のケースは避けることができるでしょう。
むしろ税金未納の影響を考えなければならないのは、親よりも親の遺産を相続する子供の方です。
両親が亡くなったあとに固定資産税や地方税等の滞納があったという話は珍しいものではありません。
年金生活のため生活するのにカツカツで、税金を支払う余裕がなかったというケースは少なくないからです。
こういったケースでは親の遺産を相続する子供には、親の未納となっている税金支払いの義務が課せられることになります。
よって、親からの相続を控えている子供は、相続に関する注意点はしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
相続人に支払い義務が・・・
恐らく相続と聞けば大抵の人は土地建物や預貯金、有価証券といった財産相続を思い浮かべるのではないでしょうか。
テレビドラマなどでも親の財産相続で、いくら相続するか兄弟同士がいがみ合うシーンが度々見られますよね。
しかし、相続するのはこういった有益となるプラスの財産相続だけではありません。
相続人にはプラスの財産だけでなく、下記のようなマイナス財産の相続義務も課せられることになるのです。
|
よって、子供が親の遺産を相続する際に未納の税金があれば、その税金支払いの義務は相続人となる子供に引き継がれることになります。
親が死んで相続財産を有効活用しようと思っていたのに、未納の税金や借金の返済に追われて散々な目にあったという話も珍しくありません。
何度も言いますが相続にはマイナス財産も含まれます。
「まさか親にこんな負の遺産があるなんて知らなかった」というケースも少なくないので、普段から親の財政事情がどうなっているのかを、しっかり把握しておくようにしましょう。
支払いを回避するには?
親のマイナス財産の支払いを回避したい。
相続する財産がマイナスにしかならない場合には、みなさんそういう気持ちになることでしょう。
ですが安心してください。
そういったケースで親のマイナス財産の支払いから、逃れる手立てはちゃんと用意されています。
その方法が下記の2つです。
- 相続放棄
- 限定承認
相続する財産事情に応じてどちらかの対応を取れば、親のマイナス財産の支払いから逃れることができるでしょう。
それでは最後にこれら2つの回避策について簡単に説明していきます。
相続放棄
まずは1つ目の相続放棄です。
これはその名のとおり、親の財産全ての相続を放棄する手段となります。
財産を相続しても、債務しかないといった場合には、有効な手立てとなってくるでしょう。
しかし、相続放棄は親の死亡を知った時点から、3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをする必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認とみなされ、二度と相続放棄をすることはできません。
相続放棄するかしないかを決めるためにも、親が死んだ際には相続される財産がどうなっているのかを、早急に明確化することが必要不可欠です。
プラスの財産だけで負の財産なんてあるはずはないと決め込んでいると、蓋を開ければ債務だらけで、その支払いから逃れることができなくなったということにもなりかねません。
相続人となるかたは、迅速な対応を心掛けるようにしてください。
また相続放棄で誤解のないようによく理解して欲しいのが、相続放棄ができる期間の開始期日です。
開始期日は親が死んだ日ではありません。
親が死んだことを子供が知った日が開始期日となります。
死亡してもそのことを知らなかった場合には、知った日が1年後であったとしても、その日が開始期日です。
これは誤解されているかたも多いので、しっかりと覚えておくようにしましょう。
限定承認
次は2つ目の限定承認です。
この限定承認は相続財産のプラスマイナスがどうなるかわからない場合に、利用してもらいたい手段となってきます。
プラス財産に相当するマイナス財産だけを相続するという便利な手立てです。
遺産総額がどれだけあって、借金がどれだけあるのかわからない。
一緒に住んでいないため、親の懐事情を把握していないという子供も多いことでしょう。
しかし、この限定承認を利用すれば、あとで遺産総額を上回る借金があったとしても、借金すべての支払い義務から逃れることが可能です。
調べた結果、遺産総額が1,000万円で、借金が2,000万円あったとしましょう。
この限定承認を利用すれば借金の返済義務を負うのは、遺産総額分の1,000万円だけで、残りの1,000万円の借金は返済する必要がありません。
また、これも相続放棄と同様に、親が死亡したことを知った日を開始期日として、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければ、二度と限定承認をすることはできないので、この点も併せて覚えておくようにしてください。
そしてこの限定承認で押さえておいて欲しいのが、相続時に発生する「みなし譲渡所得課税」です。
これは被相続人に財産譲渡したことで課せられる税金で、その支払い義務は相続人に発生します。
この税金支払いもマイナス財産に含まれるので、この税金分も忘れないようしっかりと計算に入れるようにしてください。
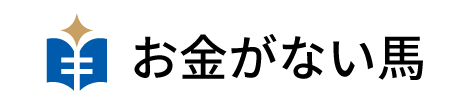

























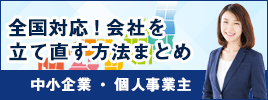

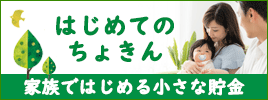


※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。