法人成りで借入金を引き継ぐときの議事録の書き方は?
個人事業主として始めた事業を節税や事業拡大のために、法人の設立をすることがありますが、これを法人成りといいます。
そして、経営者は法人成りをするときに、「現状の借入金はどうするか」「議事録をどう書くの?」など疑問に思うことがあるようです。
そこで、法人成りするときのよくある疑問について簡単に解説します。
法人成りとは
法人成りとは、既に開業している個人事業主が法人として事業をすることであり、一から事業を始めるときに法人をつくる新規法人設立とは異なります。
法人成りには以下のメリットやデメリットがありますのでおさらいしましょう。
法人成りのメリット
法人成りの最大のメリットは、節税になるということです。
個人の所得税率は最大45%で、法人税率は25~35%ですので、黒字の多い個人事業主は法人成りをするだけで税率が下がります。
また、所得税は収益と税率が比例する累進課税ですので、法人からの役員報酬を社長や親族へ所得分散をすることで節税効果がさらに上がります。
さらに消費税についてもメリットがあり、既に消費税を支払っている個人事業主は、法人成りすることで人格が変わるため、新たに2年間の免税期間をとることができます。
そのほか、法人では役員退職金や生命保険などの、個人事業主では使えない経費もありますので、法人成りによる節税効果は大きいと言えるでしょう。
法人成りのデメリット
法人成りのデメリットとしては、まず赤字でも税金を払わないといけない点があります。
個人事業主は、赤字でしたら所得税がかかりませんが、法人では赤字でも6万円~8万円程度の均等割りという住民税のような税金を支払わなければなりません。
また、法人は社会保険の加入義務があるため、これまで国民年金と健康保険に加入していた個人事業主は保険料が上がる可能性がありますので注意しましょう。
設立の流れ・資産の引継ぎ方法
法人成りには様々なメリットがあるという話をしましたが、個人から法人に資産や負債を引き継ぐ必要があり、この方法を間違えるとメリットを上回る税金を支払いかねません。
そこで、引継ぎのポイントを、資産や負債ごとにまとめましたので確認しましょう。
売掛金・貸付金・買掛金
個人事業主のときに残っている売掛金や買掛金、また貸付金は名義変更をせずにそのままにしておきましょう。
理由はこれらを名義変更すると、契約変更の手間が増えるだけでなく、貸付金に対する受取利息が法人の利益となって税金が高くなるからです。
棚卸資産
棚卸資産は個人から法人への売買契約か、お金の移動がない現物出資という方法で移転することができます。
ただし、いずれの場合でも資産の時価を計算する手間がかかりますので、棚卸資産はなるべく個人保有の状態で売り切ることをおすすめします。
固定資産
建物や機械、又は備品といった固定資産は減価償却費という経費になりますので、個人から法人へ売買するか現物出資をするとメリットが大きくなると考えられます。
また、個人から法人へと賃貸契約を結ぶことで、個人の売却益や法人の不動産取得税等を押さえることもできますが、この方法は、個人側で不動産収入の所得税がかかりますので注意しましょう。
借入金
借入金は、支払利息を法人の経費にできるため、名義変更することをおすすめします。
ただし、借入金の名義変更は債権者である銀行の承諾が必要であるため、新たに法人名義での審査が必要になります。
また、担保付の借入であれば担保価値を見直すため、不足があれば銀行から追加の担保を依頼されるケースもありますので注意しましょう。
債務引継ぎはできる?
個人事業主が法人成りするときに、債権や債務を譲渡又は売却することで、法人へ移転することが可能です。
しかし、債権や債務の内容によっては、賃貸をしたり、そもそも移転しない方が得なケースもあったりしますので、そのポイントについて確認してみましょう。
譲渡(売却)の注意点は?
個人から法人へ資産を譲渡又は売却をするときは、時価額を計算する必要があるほか、時価額次第では売却をする個人側で所得税が高くなることと、以下の点に注意しましょう。
譲渡価額や消費税に注意
法人成りで個人側に譲渡益が発生する場合、個人事業主が消費税の課税事業者であれば、所得税だけでなく消費税もかかってきます。
したがって、個人が消費税の免税になるタイミングで譲渡できるかどうか、必ず顧問税理士に確認するようにしましょう。
新会社に借入金を引き継がせられる?
個人事業主の借入金は、法人成りによって新会社に引き継がせることが可能です。
ただし、銀行審査が新たに必要になる点と、有担保の借入でしたら追加担保を求められる可能性もある点に注意しましょう。
賃貸の場合の注意点は?
個人の資産を法人に賃貸することで、個人の譲渡益を抑えることができます。
ただし、賃貸契約を結ぶと個人側で毎年確定申告と納税が必要になることと、不適切な賃貸金額は法人側の経費として税務署に否認されますので注意しましょう。
個人・法人の会計処理時の注意点
個人から債権債務を法人に移す会計処理として、借入金と貸付金の勘定を使う方法と、事業主と資本金の勘定を使う方法があります。
このふたつの方法では後者の方が節税効果が高いのですが、適正な金額以上は否認されますので顧問税理士にどちらがいいのか確認することをおすすめします。
建物だけを売却
土地付き建物を個人から法人へ移転するときは、建物だけを売却すると節税効果が高いケースがあります。
理由は、土地は原則経費にならないため、個人のまま保有して法人へ賃貸することで、法人の経費にできるからです。
この方法は個人側で不動産収入の確定申告をする必要がありますが、個人の所得税より法人側での節税効果の方が高くなるケースが多いので是非覚えておきましょう。
土地の無償返還は届出書が必要
法人成りのときに、土地の名義を個人、建物の名義を法人にすることでメリットがあるという話をしましたが、この場合は法人が個人に権利金を支払わなければなりません。
しかし法人が、建物を利用した後は無償で個人に返すという無償返還の届出書を出すと、権利金が不要になるだけでなく、土地の評価が8割になって固定資産税を節税できますので覚えておきましょう。
法人成り後に生じた不動産所得はどうする?
個人が法人に土地を賃貸する場合は、不動産所得の確定申告をする必要があります。
一般的に法人の賃借料による節税額の方が、個人の不動産所得税より大きくなります。
そのため、なるべく大きな金額で賃貸借したいところですが、過度な金額は税務署に否認されますので注意しましょう。
法人成りをするときの個人の確定申告
個人事業時から働いている人に退職金は?
個人事業のときから働いている人が、法人成りをして新しく設立した法人に引き続き勤務する場合には法人成りしたあとに退職をすると退職金をもらうことができます。
その計算は個人事業主として、働いていた期間を含めて計算することになります。
ここで注意をすることは、退職金の計算時に個人事業のときからの通算年数で計算することを退職金規程などに明記しておきましょう。
ただし、個人事業の期間に対する退職金分は、法人の損金に含めることができませんので注意が必要です。
必要経費は支払いが発生したタイミングで、通常は会計処理すればよいのですが、法人成りをしたあとには個人事業としては廃業してしまってますので退職金の支払いが発生しません。
あとで経費として落とせないという状況になってしまわないように、個人事業としての最終年度で行う確定申告のときには、法人の事業税を計算して退職金を未払計上にしておくことを忘れないでください。
一括償却資産は必要経費算入をする
事業で使用していた固定資産を、法人成りをしたあとに引継ぎをする場合は、一般的に個人事業主から法人に譲渡したものとして処理します。
譲渡をするため売却益にはなりませんので、個人事業の事業所得とはせずに譲渡所得として処理します。
ただし、一括償却資産として法人成りしたあとに、引継ぎをする場合には注意が必要です。
該当する資産を取得した価格のうち、必要経費に含まれていない部分を個人事業の最終年度には必要経費として全額を計上して処理しなければいけません。
もし、一括償却資産を譲渡したときに、利益が出た場合には雑収入として処理しましょう。
なお、譲渡する資産の価格は時価となり、一般的に売買価格の70%以上が目安になっています。
借入金などの債務・未収入金などの債権の処理
法人成りをするときに、「借入金」「買掛金」などの債務や、「未収入金」「売掛金」などの債権は、必ずしも法人に引継ぎをする必要はありません。
もし、法人に引継ぎをする場合は、法人成りをする前日時点の帳簿価格で引継ぎをすることになります。
また、引継ぎをする場合は全てか、一部のみの継ぎをするのかを選ぶことができます。
法人成りの引継ぎ時の基本的な注意点
法人成りをすると消費税の納税義務が発生する?
消費税の納税義務があるかないかの判定は、事業者単位で行われます。
このため、6月など1年の途中に、個人事業主が法人成りをしたときには、個人事業と法人とそれぞれ分けて判定することになります。
資本金が1000万円未満の場合には、事業年度2期間は消費税の納税義務が免除されます。
この制度を上手に活用するには、法人成りをするときに決算期をしっかりと考える必要があります。
消費税の納税義務が免除されるのは、2年間ではなく「事業年度2期間」です。
法人として設立登記した日(会社設立の日)から決算期末までが、初年度の事業年度となります。
このため、会社設立から最初の事業年度が長ければ長いほど、消費税の納税義務の免除期間が長くなります。
例えば、会社設立が9月1日の場合、決算期末を8月とすると、まるまる1年が事業年度の初年度となります。
1円資本金の本当の意味
現在は、法人設立における最低資本制度は廃止されていて、資本金が1円でも法人設立が可能となっています。
しかし、資本金が少ないということは、社会的信用を得にくい可能性があります。
特に金融機関からの融資では、資本金を上限とした借入金しか受けられない可能性があります。
法人成りをして金融機関からの融資を検討している場合には、資本金についても十分に検討する必要があります。
また、資本金が少ない場合には決算で損失を計上すると、債務超過になる可能性があります。
法人として債務超過になることことは、デメリットだらけでメリットは全くありません。
1円資本金の法人が現実的に機能するは、個人を取引先とした事業である場合や、現金を中心に事業を行っている場合になります。
また、法人化することによって、世間の信用力をあげたいときにもいいでしょう。
類似商号規制はなくなった?
法人成りをするとき、個人事業で使用していた屋号をそのまま法人の商号にしたいと思う人が多いでしょう。
現在、類似商号規制はなくなり、同じ市区町村内でも同じ商号で法人登記することが可能になりました。
しかし、これはあくまで同一の商号や、類似の商号でも法人登記が可能になったというだけです。
たとえ同じ商号だったとしても、看板やロゴなどが既に法人登記されている商号に似ていた場合には、不正競争防止法に抵触する恐れがあります。
最悪の場合、企業名の使用差止めや、損害賠償などの請求を受ける恐れがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、法人登記しようとする商号が、既に使われていないかなどをしっかりと調べましょう。
所轄する法務局で情報を取得できますので、是非活用するとよいでしょう。
株式会社でも取締役はひとりでいいの?
条件を満たせば取締役ひとりでも、株式会社を設立できるようになりました。
なお、取締役がひとりで株式会社を設立できる条件は、株式の全てを譲渡制限付き株式とすることです。
譲渡制限付き株式とは、株主総会で承認を得ない限り、他人に持ち株を譲渡できない制限がある株式です。
取締役をひとりで法人成りをするときには、会社の定款に全ての株式が譲渡制限付き株式だということを記載しなければいけません。
少人数で株式会社を設立できるということは、法人成りをするのにメリットがあります。
役員の人数に制限がないので、個人事業主がひとりで取締役になるのも、配偶者とふたりで取締役になるのもよいでしょう。
免責的債務引受けによる法人成りをするには?
債務引受けすることを決める議事録の書き方
金融機関からの借入金など個人事業主として負っていた債務を、法人成りをして債務の引継ぎをするときに免責的債務引受けをしたいという経営者がいます。
免責的債務引受けを決めるためには、代表取締役が利益相反の取引になりますので、取締役会設置会社であれば取締役会の承認が必要です。
また、取締役会非設置株式会社であれば、株主総会の承認が必要となります。
ここでだいじなことですが、承認が得られたエビデンスとして、議事録を残すことが重要になります。
金融機関からの借入金がある場合には、議事録の写しを求められるからです。
詳細については、金融機関に相談することをおすすめします。
なお、債務引受けを決める議事録には、次の事項を必ず記載するようにしましょう。
- 取締役会又は株主総会の開催日、出席者
- 引継ぎする債務の概要(債権者、金額など)
- 法人として債務引受けを承認したこと
- 関係者の署名と押印
さらに、関係者の印鑑証明を添付することや、元々の契約書等のコピーと議事録を貼り付けて割り印をしておくこともおすすめです。
法人化するための手続き
現在、法人成りをすると、株式会社、合同会社、合資会社を設立することができます。
いずれも特徴がありますが、資本金1円で会社設立ができるため、個人事業主から株式会社を設立するケースが多いようです。
株式会社を設立する手続きとして、「会社概要の検討・決定」「法人の実印作成と印鑑証明書の取得」「定款の作成」「設立総会の開催」「定款の認証」「出資金の払込み」「登記書類の作成」「登記申請書類の提出」などを順にする必要があります。
これに加え、並行して個人事業の廃業手続き、資産・債権の引継ぎ、名義変更などを行わなければいけません。
抜けなく行うには時間にゆとりを持って、専門家と相談をしながら行うといいでしょう。
まとめ
法人成りは、個人事業主として取り組んだ事業が、成功した結果といえるでしょう。しかし、法人成りをするときに、様々な疑問を出てくるかと思います。
そこで、多少のお金や時間はかかりますが、しっかりと専門家に相談をして、スムーズに法人化をすすめることをおすすめします。
また、併せて銀行にも相談をすると、法人成りも円滑にすすむのではないでしょうか。
タグ:その他金融業者



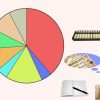



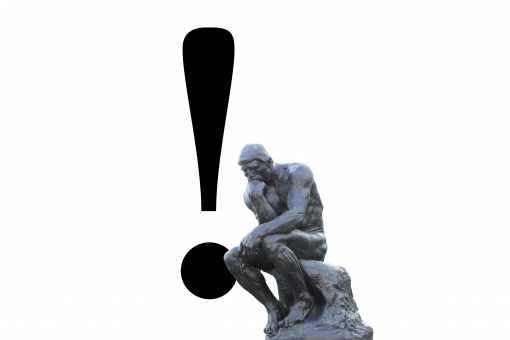















































※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。